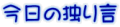■【若狹の生意気言ってすみません!】9 令和の米騒動・郵政民営化と小泉さん、◎◎省がバック?財政の偉人について
■【若狹の生意気言ってすみません!】9 令和の米騒動・郵政民営化と小泉さん、◎◎省がバック?財政の偉人について


■ 筆者挨拶
特定非営利活動法人「日本経営士協会」首都圏支部の経営士 若狹晃司です。
当ブログに、私の経営士として日常考えたこと、感じていることをラフなスタイルで掲載させて頂きます。「生意気なヤツ!」と言われるのを覚悟で出来る限り本音のお話をしていますので、よろしくお願いします。
■【若狹の生意気言ってすみません!】 No.9
~~~ 令和の米騒動・郵政民営化と小泉さん、◎◎省がバック?財政の偉人について ~~~
酷暑猛暑続きで私は体の調整が上手くいかずバテバテになっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。この猛暑のあおりを受けて新米が市中に出てきましたが、ブランド米の値段はやはり昨年より高くなっています。私も消費者の一人として見ますと、最寄りのスーパーに輸入米や備蓄米が常時入荷している様子はなく、多少値が下がったけどそれほどでもないなというのが実感です。今年の一部地域の水不足・南九州の線状降水帯の被害を考えると、新米が出たらコメの値が下がるという予想をしていた専門家は何を見ているのだろうと疑問に感じます。農林水産省ですら、日本人が古来より主食としている「米」の需給についての国家の調査が杜撰なまま放置していた以上、専門家・コンサルが間違うのも仕方がないことだと思います。
ただ、小泉進次郎農林大臣による備蓄米の放出や輸入米の増加等から感じる印象は、今から24年前の「自民党をぶっ壊す!」で有名な進次郎氏の父・小泉純一郎総理大臣を思い出します。純一郎氏は「郵政民営化」に力を入れましたが、進次郎氏も農林水産行政をぶっ壊す!とは言っていませんがそのくらいのインパクトがあります。これからの流れとしては、米の行政に留まらず、JA(農協)の改革、そのバックにいる農林中金(最近1.8兆円の巨額赤字)を含めて何か動きがあるのではと個人的には感じております。単刀直入に言えば、親の真似をしているんじゃないかな、このパターンで総理大臣になりたいのかな、色々破壊するんじゃなかろうかと心配しています。
ゆうちょ銀行・かんぽ生命は日本でもトップの金融機関です。また、農林中金も同じく巨額資金を運用する日本を代表する金融機関の一つです。その資金を狙っているのは言うまでもなく、欧米の運用会社です。「ぶっ壊す!」論理の裏には、金融マーケットの攻防があるのでしょう。そのまた裏は何があるのか?という疑問も沸いてきます。これだけは言えることですが、金融資産の運用を手掛ける会社というのは、庶民の皆様に「資金の運用で儲けて戴く」のが目的ではなく、「自らの会社が儲ける」のが目的で日本の金融マーケットの門戸を開放する様、求めています。金融マーケットの解放は内閣府傘下の金融庁が所管する話ですが、実の所は財務省だと思います(当たらずとも遠からず)。国の資金の一切を取り仕切りたい財務省としては、抜群の資金力がある旧郵政省のゆうちょ銀行・かんぽ生命を影響下に置きたいと考えるのも無理は無いことです。同様に、農林水産省で巨額の資金力がある農林中金も強い影響下に置きたいことでしょう。あまり言うと「陰謀論」と馬鹿にされますのでこの辺で深入りするのは止めておきます。
一見、ゆうびん貯金の話であったり、お米の話であったりしますが、それが全てでは無く必ず裏側もあると考えるのがベターではないでしょうか。世界で金融を牛耳っている欧米投資家・投資運用機関から見えている日本国というのは、悪い表現をすれば「日本は欧米のATMである。奪ってやる!」と思われていることでしょう。多分、草刈り場かも。もうそろそろ、日本の政治家や国家公務員のエリート層も「日本国としての国益」を物事の基準として意識してもらいたいと思います。国益についての議論もエリート官僚に任せっきりではなく、21世紀のこの混沌とした時代だからこそ、有意の議員や国民から活発に発信して欲しいと願っております。
前貢からの続きで、◎◎省がらみの話題です。消費税減税や所得税の非課税限度、社会保険料負担の程度、ガソリン税等に関して、減税か補助金かまた今後どうあるべきかなどが争点となり、参議院選挙が行われました。特に消費税は当初より社会保障費の特定財源にはなっておらず、一般財源となっているにも関わらず、少子高齢化社会を支える重要財源として消費税減税政策は暴論極まり無い!として自民党の重鎮や◎◎省から猛烈に批判されて来ました。
将来に亘り消費税を増税しない分、国債発行によって穴埋めをして、財政規律が緩いまま国債発行をし続けると、将来の孫・曾孫世代に巨額の国債返済の「ツケ」を回すことになり、これこそ国民として許されることではないと政府財務省も国会議員もマスメディアも報道します。
となると、国民は何を感じるでしょうか。このままの状況が続くとしても、子供・孫・曾孫を「国債の借金地獄」に突き落とすのは間違い無いことと感じるのではないでしょうか。だったら、「子供を産まない!」という選択肢を選んでもおかしくはないと私は思います。子供がいない以上、「ツケを回すことは一切ないよ!」と言い切れます。結婚しない、子供を産まない、現に日本国民にそうなっています。そうさせているのは誰ですか?子孫がいなければツケを回せませんよ!どうしますか?この◎◎省の論理って、最初から破綻してませんか?
そもそも国家財政がひっ迫しているのであれば、増税だけでいつまで凌げるでしょうか?実現性が高く、抜本的な財政改革を計画し、実行するのが本当の国家エリートの使命ではないでしょうか。江戸時代、藩財政を改革した上杉鷹山が財政改革の偉人として有名ですが、私の郷里の岡山県にも財政改革・藩政改革の偉人(江戸時代末期)がおります。
その偉人は、備中松山藩(現岡山県高梁市)の藩士で儒家の山田方谷です。陽明学の佐藤一斎に学び、同門下生の佐久間象山の二人を「佐門の二傑」と言われています。山田方谷の藩財政・藩行政改革は次の7項目です。
1.上下節約(最低レベルの生活費で上の者も凌いで資金を捻出)、2.負債整理(債権者にリスケ要請等)、3.産業振興(備中鍬の開発と販売、銘菓ゆべし販売)、4.藩札刷新(藩札を貨幣と交換し、回収藩札を公開焼却)、5.教育改革(学問所、教諭所、藩校有終館、家塾牛麗舎、等の設置)、6.民生刷新(賄賂賭博禁止、災害備蓄「貯倉」設置、
交通網整備、目安箱など)、7.軍政改革(洋式砲術導入、農兵隊を創設し、長州「騎兵隊」はこれをモデルとした)。
佐久間象山―吉田松陰―幕末維新の偉人という流れを言う人が多いですが、岡山県にも優秀な人物はおります。なぜ評価されないのか?それは日本の明治以降の政治は薩長が中心となっているからです。でも、長州よりも先に凄い改革を成し遂げております。
翻って今日の我が国を振り返りますと、国家財政が厳しく国債発行は駄目!と◎◎省はいうけれど、ではこの国を実現可能な抜本改革をなぜしようとしないのか不思議に思えます。日本銀行と交渉して、日本国債の60年償還ルールを100―200年償還ルールに変えたり、特別会計改革および国家外郭団体の整理廃止売却、公務員―民間の相互交流、国家事業(役人仕事ではない事業性によるエネルギー確保)、国公私大学統廃合、軍事大学・大学院増設、などなど今日でも実行できることが多いと個人的には考えます。
横道にそれますが、大学の話です。日本の最高学府と言われる何某国立大学の大学院留学生比率は30%強、その60%強が中国国籍とAIの検索でデータが出てきました(このデータが完全に正しいとは思えませんが何某民放TVでもかなり多いと報道されています)。国家の大学なのに、国民を優先せずに国際化という言い訳の下で留学生を受け入れ過ぎるという日本の有様、どうなんでしょう?国際化?中国化?どうなっているのでしょうか。
話を戻します。日本国が、その国の機関である日本銀行から金を借りるという理屈。その理屈の為に、国家財政は厳しいという論理。異様な世界としか私には感じられません。日本円(日本の通貨)で日本国が日本国の日本銀行(通貨発行機関)から借り入れして、なんで国家が破綻するのか?私は理解できません。私は頭が悪いので、ごめんなさい、上手く説明できません。国家がその下部国家機関から金を借りてという仕組みは変です。連結ベースで考えれば、同じでは?下部国家機関が通貨発行が出来る機関であることを考えれば余計に変です。通貨発行益というものすらあるのに。◎◎省の論理が絶対正しいとどうやったら証明できるのかわかりません。
幕末・維新の偉人達がもし今の時代に存在したならば、現在のような政策を取り続けたりはしないと思います。消費者物価指数は上がり続け、実質賃金指数は下がり続け、いまだデフレ進行中なのに、どこかのお役人は「デフレから脱却し始めた」と仰せです。日経新聞をはじめ大手マスメディアも同じような論調が続いていました。何かおかしな世の中になっていませんか?と小言を言いたいです。すみません。
今回も支離滅裂の話が満載になってしまいました。ここまでお読み戴き、心より感謝申し上げます。来月も頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。