■【ナレーション付き映像で見るカシャリ!ひとり旅】福島県郡山市 隈上苑 平安時代創建古寺如宝寺の日本庭園
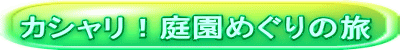
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間に旅をしたのか、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
旅のテーマは寺社や庭園めぐりです。
日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。
下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。
■ 【ナレーション付き映像で見るカシャリ!ひとり旅】福島県郡山市如宝寺・隈上苑ミニ 平安時代創建の歴史ある福島県郡山市の如宝寺にある池泉廻遊式庭園「隈上苑」
「高嶽山如宝寺(如寳寺)」は、郡山の中心市街地にある、創建は平安時代(802)と伝わる真言宗寺院です。
一万坪という広い境内を持ち、敷地内には日本庭園・隈上苑があります。
如宝寺の仁王門や山門の手前に位置し、道路に面しているという珍しい形式です。一段高いところに立つ如宝寺の伽藍を借景とした池泉廻遊式庭園です。
「ミニ」は、特定のテーマだけに絞り込んで、コンパクトにまとめた短編映像です。統合版を別途再編集し、お届けしていますので、そちらも併せてご覧下さると幸いです。
高嶽山如寳寺は、福島県郡山市に所在する、大日如来をご本尊とし、真言宗豊山派長谷寺(奈良県桜井市)をご本山としています。
郡山の中心市街地にあり、一万坪という広い境内を持つ寺院です。如宝寺庭園“隈上苑”という池泉廻遊式庭園もあります。それほど遠くない、市の中央高台に位置しています。近くには、日本の歴史公園100選に選ばれている「麓山公園」や「21世紀記念公園 麓山の杜」もあります。
明治時代の戊辰戦争の戦火によって主な建造物の多くを焼失してしまいました。住職を務めた鈴木信教は、子女の養育や学校教育、地域の開発などに尽力した名僧として知られ、境内にある墓は福島県指定史跡に指定されています。
隣接する2階建ての書院は国登録有形文化財で、元は明治天皇行在所として白河に作られた建物をその後移築されたものです。2階建てという外見からもお寺らしくない建物です。
境内には、「国宝殿」があります。
仁王門は、文化財指定はされていませんが、江戸時代より残る、境内で最も古い建造物です。
境内には、七堂伽羅の荘厳な建造物群が配されています。そのほか、平安朝時代の古瓦、鎌倉時代の古碑、明治の先覚者位碑などが保存され、千余年もの年月を数える由緒ある寺院です。
当寺の縁起は大同二年(西暦807年)、この地を治めていた虎丸長者がはるばる京に上り時の帝・平城天皇に拝謁を賜った際、馬頭観音像を郷土住民の守護仏として下賜されたことに始まります。
長者は守り本尊として現在地に観音堂を建立し、現在の郡山市中町に庵を結び、徳望が高かった笹久根上人を招いて荘厳な開眼供養をあげました。上人は本尊大日如来を奉じて庵室を観音堂境内に移し、“如寳寺”と称して観世音を守護したと伝えられています。
大本堂・光明殿・観音堂
如宝寺隈上苑
如宝寺の日本庭園は、「隈上苑」といい、郡山駅から徒歩で10数分の所に位置しています。郡山の日本庭園のひとつである「麓山の杜」からは、徒歩5~6分の距離です。
如宝寺は、平安時代に創建されましたが、池泉回遊式庭園「隈上苑」の開園は記録にはありません。
昭和の初めには、「隈上苑」が存在することは解っているそうですので、開園は、昭和の初めか、それ以前と推定できます。
池泉には中島が作られています。両側に石橋がかけられていて、直線状に配置されています。
隈上苑は、それほど大きな庭園とはいえませんが、ずっしりとした石橋の奥に、滝石組を組むなど、作庭者の奥行きを感じられます。
滝石組は、枯滝石組ですが、池泉には水が張られています。
滝水が伝う水落石(みずおちいし)は、2段組です。そこに青石が使われていますので、水の流れが表現されていることが解ります。
隈上苑では、橋添石と池泉に立つ池中立石の配置が見事といえます。
映像で視るカシャリひとり旅
如宝寺と池泉廻遊式庭園「隈上苑」

ユーチューブで視る 【カシャリ!庭園めぐりの旅】
写真集は、下記URLよりご覧いただくことができます。
静止画: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmeisho.htm
映像: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
【 注 】 映像集と庭園めぐりは、重複した映像が含まれています



































































































































































































