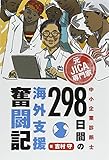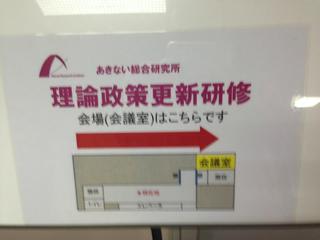|
決済インフラ入門 |
| クリエーター情報なし | |
| 東洋経済新報社 |
中小企業大学校の虎の門セミナー、今回で3回連続聴講している。今回は「フィンテックと中小企業」、最近フィンテックという言葉をよく聞くが、内容がわからないため勉強に来たものだ。

講師は、宿輪先生、上記の書籍を書かれている。銀行マンから大学の先生になった方だ。冒頭、予定にはない「トランポノミクス」の話。旬なのだろう。経済にプラス面のキーワードは、法人税減税、経済成長4%、インフラ投資1兆ドル、マイナス面は、財政悪化、金利上昇、ドル高、反グローバルなどだ。しかし、公約通りやるかまだ分からない。
フィンテックとは、金融ファイナンスと技術テクノロジーの合成語だ。フィンテックの分野としては金融サービス、付加価値サービス、仮想通貨だそうだ。有名なものにペイパルがある。そうかあれがフィンテックか。
直接我々に関係するのは、決済が再来年には24時間制になるという。そんなに必要もないと思うがまあ・・それにDesaiサービスと言って、売掛金も電子化されると、この債権を担保に融資ができるようになるそうだ。これはかなり大きい。
最後は時間があったため、何人もの質問に答えていた。会場の質問は、質問者だけでなく、全員が聞いていていて、そのやり取りが、かなり参考になる。そんな意味で多くの質問に答えると参加者の満足度は高いだろう。
話は違うが、私が現役時代に最も多くの質問に答えたのは、1時間近くだ。中国上海で日中ガス技術セミナーのときだ。一通り講義を終えた後の質問タイム、一人が二つも三つも質問する。順番がもう回ってこないと思って質問が長い。通訳を介していたが、合計1時間近く質疑応答に費やした。
ガス工場の白い霧の写真を見せられて、これは何だ、というが、私の専門ではないため、すぐはわからない、時間をくれ、と日本に電話して聞いた。やがて日本の担当者が捕まって、内容がわかり、会場で解答した。あとの懇親会であれは良かったと評価を戴いた。
そんなことで、質疑応答は、セミナーの重要な時間なのである。










 20ほどの研究会がプレゼン
20ほどの研究会がプレゼン 人財研の幹事と応援メンバー
人財研の幹事と応援メンバー


 研修資料の表紙
研修資料の表紙 研修資料:女性の活躍
研修資料:女性の活躍 研修資料:診断事例
研修資料:診断事例