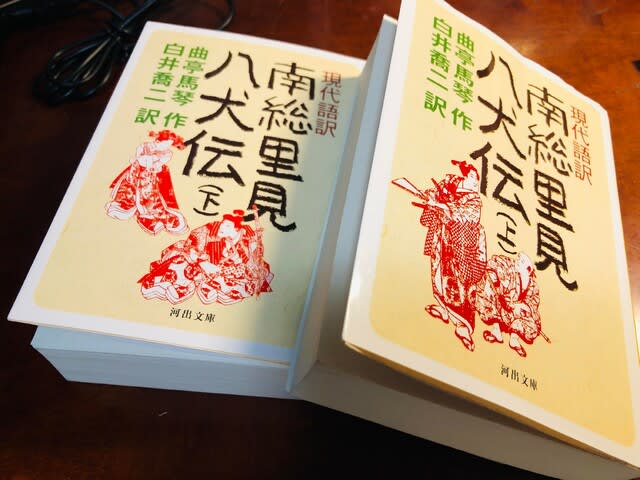「天皇の国史」を読んだ。著者は竹田恒泰氏、明治天皇の玄孫(やしゃご)だ。虎ノ門ニュースの月木に時々出演しているので、私は、少しだけ知ってる。ラーメン屋でデジタル通貨も発行している作家、マルチタレントだ。皇室記事は耳を傾けるものがあるし、検定不合格な歴史の教科書を書いてることも知ってる。
この本、本文は650頁、分厚い。石器時代(岩宿時代以前)から令和時代まで、天皇を中心に日本の歴史が書かれている。日本と他国との違いは、間違いなく天皇陛下が日本のシンボルであること。この本の内容はキチンとしてふざけた内容ではない。よくここまで書けたもんだと感心する。そして内容も面白い、つまらないという章はないので、次の章もその次の章も読みたくなる本だ。
自分の知らなかったことを幾つか書き留める。まず、石器時代の日本人、DNAまで遡って日本人の先祖を探している。さらに、鎌倉時代に御成敗式目というのがある。この中に、土地の取得時効の考え方が入った。御成敗式目の名称は知ってはいたが、この時代に時効ができたとはねえ。
建武の中興時代、伊勢神宮の式年遷宮、20年に一度神宮を建て替えるものだ。これに使う木材は、神宮の森から伐採する。そしてその木材は、樹齢4百年のものが必要で、現在でも年間2万本のヒノキが植えられているそうだ。4百年先に使う木材を営々と植林している。すごい歴史だ。
もう一つ、太平洋戦争時の大本営発表。軍に都合のいいことを選んで誇張して発表し、都合の悪いことは発表しない。今でも、偏った発表を「それは大本営発表だな」ということがある。それで思い当たることがある。
11月に行われた米国大統領選挙だ。米国も日本も大手マスコミは、バイデンが勝ったことにしているが、実はまだ決まっていない。選挙不正が多く、裁判で不正の証拠も数多く出ている。米国の大統領選挙に中国も関与しているようだ。私は保守系のユーチューブを欠かさず見てるから、知っている。なんせ、選挙人の名簿より、投票数の方が多いところがある。投票率100%以上だ。これを民主党の州政府が有効としてしまっている。郵便投票が原因のようだが、ひどい話だ。
1月6日に大統領を決める上下院が開かれるが、まだどうなるかわからない。ドミニオン(選挙用のコンピュータ)はじめ民主党の不正がまかり通ったら、民主主義はもうおしまいだと思っている。
さらにフェイスブックなど米国のSNSは、選挙の不正に関する記事や選挙不正の証拠などは規制している。私も投稿したが友人には広がらないように制限されている。何かキーワードが引っ掛かって制限されているようだ。ムチャクチャだな。
1月6日の連邦議会は、ペンス副大統領が主役になるが、バイデン、トランプ、どっちに転んでもアメリカは暴動が起きる可能性がある。アメリカのスーパーは生活必需品は買いだめで売り切れ、銃やその弾が品切れになってる。いざというときは軍が出動するかも入れない。こんな情報は、大手マスコミは報道しない、いやバイデンに不都合な情報は、わざと報道しない「大本営発表」なのだ。1月6日、米国のことながら、どうなるか心配だ。