月曜日に東京商工会議所でBCPシンポジウムがあった。事業継続管理者の准主任管理者を受講した関係で、お誘いのメールが来たため、出席。皇居前の東京商工会議所ホールにて。200人の席に500人の申し込みがあったそうだ。中小企業の経営者が対象だ。
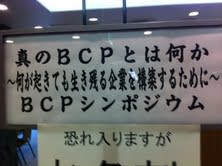
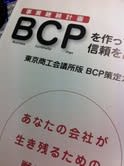
冒頭、事業継続管理機構の細坪事務局長から基調講演。事務局長が盛んに言っていたのは、BCPは防災とは違う、というここと。准主任管理者の研修でもよく言っていたことである。しかし、聴衆に理解できたかどうか。
次は、東商モデルの第1号のイッツコミュニケーション株の講演。さらに気仙沼のケーブルテレビ会社の被災から復旧まで。そして青森県の試験状況と来て、最後はパネルディスカッション。私は途中で退席した。退席中、テレビ東京のワルドビジネスサテライトが取材。一応答えたが、月曜夜の番組では、別のコンサルタントがしゃべっていた。残念!!
それと同封物に、「東京商工会議所のBCP策定ガイド」があた。内容を見たが、これはよくできている。使えそうだ。機会があったらコンサルで使ってみよう。
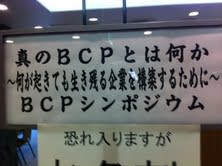
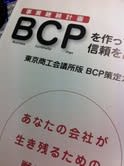
冒頭、事業継続管理機構の細坪事務局長から基調講演。事務局長が盛んに言っていたのは、BCPは防災とは違う、というここと。准主任管理者の研修でもよく言っていたことである。しかし、聴衆に理解できたかどうか。
次は、東商モデルの第1号のイッツコミュニケーション株の講演。さらに気仙沼のケーブルテレビ会社の被災から復旧まで。そして青森県の試験状況と来て、最後はパネルディスカッション。私は途中で退席した。退席中、テレビ東京のワルドビジネスサテライトが取材。一応答えたが、月曜夜の番組では、別のコンサルタントがしゃべっていた。残念!!
それと同封物に、「東京商工会議所のBCP策定ガイド」があた。内容を見たが、これはよくできている。使えそうだ。機会があったらコンサルで使ってみよう。


















 BCPの事業継続管理者という資格を私は持っている。この団体主催で毎年「首都圏危機管理セミナー」が開催される。昨日は終日そのセミナー、今年は「想定外への挑戦、首都圏M9」というテーマであった。首都圏の地震ではM9は想定外の大きさである。これに対応できるか考えようというもの。
BCPの事業継続管理者という資格を私は持っている。この団体主催で毎年「首都圏危機管理セミナー」が開催される。昨日は終日そのセミナー、今年は「想定外への挑戦、首都圏M9」というテーマであった。首都圏の地震ではM9は想定外の大きさである。これに対応できるか考えようというもの。








