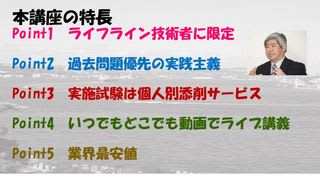最近のこんなニュースから。韓国のピョンチャンオリンピックの準備が遅れている。なんでもジャンプ台が検査不合格になって、大幅な手直しが必要という。そして遅れ気味の工事をオリンピックに間に合わせるには、さらにコストがかかるという。
文章は正確ではないが、こんな意味の記事だったと思う。さて、ものつくりには、三大管理というのがある。コスト管理(原価管理)、工程管理、品質管理の3つである。そしてこの3つは各々関連がある。
検査不合格の施設を改修するのは、コストをかけて品質を上げるもので、コストと品質は正比例の関係だ。また、工程と品質の関係も、急いで作るとやっつけ仕事になり品質は落ち、ゆっくり作ると丁寧な仕事で、品質は良くなる。これもすぐわかる。
問題は、工程とコストの関係だ。一般に、工程を遅くすると、コストはかかる。期間が長いため、固定費がかかるためだ。そして工程を早くすると、一定の速度までは、コストはだんだん安くなる。ところが、急ぎ過ぎると、工程間がバッティングしたり、調整したり、さらには時間外の賃金が必要になったりして、逆にコストがかかる。つまり、経済速度というのがある。先の韓国の記事は、経験的にわかっている人が書いた、あるいはわかっている人から聞いたことを書いたものだろう。
さて、このコスト・工程・品質の関係を一般化すると下図のようになる。これは実は土木施工管理技士の問題なのである。資格試験も時には役立つこともあるね。