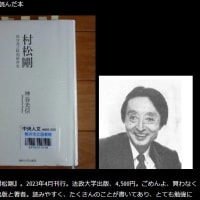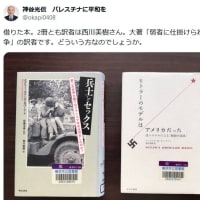1853年6月25日に米国の新聞「ニューヨーク・デイリー・トリビューン」に掲載されたカール・マルクスの新聞記事「イギリスのインド支配」の和訳(鈴木正四 訳)全文をコピペする。なお、英語の原文はネットですぐ見られる(The British rule in India)。
載せる理由やこの論文についてはここに書くと予断を与えるので、末に書きたい。ここでは簡単にすませる。
■ 今日でブログ15年。愚ブログも今日で15年。初記事で、「昔、マルクスの『イギリスのインド支配』という記事を読んだことがあった」と書いた。その「イギリスのインド支配」の全文。
■ この「イギリスのインド支配」は”西欧のもっとも露骨で恥知らずな植民地主義者の文章” [1] 的なものである。つまりは、スキャンダラスな文章ということ。 [1] 西川長夫、『国境の越え方』, 1992年
なお、この全文のうちスキャンダラスなくだりを別途ダイジェスト版として後日載せる。
マルクス
イギリスのインド支配
「ニューヨーク・デイリー・トリビューン」
一八五三年六月二十五日付、第三八〇四号
ロンドン、一八五三年六月十日、金曜日
ヴィーンからの電報によれば、ヴィーンでは、トルコ、サルデーニャ、スイスの問題の討論が平和的に解決されるのは確かだと考えられているとのことである。
昨晩、下院ではインド問題の討論が、いつものようにだれた調子でつづけられた。ブラケット氏は、サー・チャールズ・ウッドとサー・J・ホッグの陳述には楽天的にすぎる嘘という特徴があると非難した。内閣と理事会の多くの代弁者たちが、この非難を最大限に反駁した。型のようにヒューム氏が要約して、内閣に法案の撤回を求めた。討論は延期された。
ヒンドゥスタンは、アジア的な規模でのイタリアのようなものである。アルプスのかわりにヒマラヤがあり、ロンバルディア平野の代わりに平野があり、アペニン山脈の代わりにデカン高原があり、シチリア島の代わりセイロン島がある。土地からの生産物が種類にとみ、政治の構造がばらばらであるのも同一である。イタリアがしばしば征服者の剣によってさまざまな国家団体に凝縮させられたように、われわれはヒンドゥスタンが、回教徒やムガル人やイギリス人の圧迫のもとにおかれた場合を除いて、多くの独立した、あい争う国家に分かれ、その数は町の数、いや村の数とさえ等しいほどであることを知っている。けれども、社会的見地からみれば、ヒンドゥスタンは東洋のイタリアではなくて、東洋のアイルランドである。そしてこのイタリアとアイルランドとの奇妙な結合、官能の世界と苦難の世界との奇妙な結合を、ヒンドゥスタンの宗教の古い伝統があらかじめ示している。この宗教は、肉欲的歓喜の宗教であると同時に難行的禁欲の宗教であり、性器[リンガ]崇拝の宗教であると同時にジャガナートの宗教(121)であり、行者の宗教であると同時舞妓[バヤデール]の宗教である。
私はヒンドゥスタンに黄金時代があったと信じる人たちの意見にくみするものではないが、だからといってサー・チャールズ・ウッドのようにクリー・カーンの権威をかりて自分の意見を裏づけようとも思わない。ただ、たとえばアウラングズィーブ**の時代をとってみればいい。あるいは北にムガル人が現われ、南にポルトガル人が現われた時代でもいい。あるいは回教徒が侵入し、南インドでは七王国分立の状態にあった時代(122)でもいい。さらにさかのぼりたければ、ブラーフマン(バラモン)自身の示す神話的な年代記をとって見ればいい。ブラーフマンは、インドの苦難が、キリスト教徒の説く創世よりももっとまえにさせ始まったとしているのである。
**ムガル王朝第六代の王(在位1658-1707年)
しかしながら、すこしも疑いのないことは、イギリス人がヒンドゥスタンに与えた苦難が、ヒンドゥスタンがこれまで嘗めなければあらゆる苦難と根本的に違い、はるかに強烈なものであることである。私が言っているのは、イギリス東インド会社がアジアの専制主義の上につぎ木したヨーロッパの専制主義が、サルセット寺院(123)の人を驚かす異様な仏像のどれよりも、奇怪な結びつきを示しているということではない。これはイギリスの植民地支配の模倣にすぎないのであって、それも、イギリス東インド会社の活動の特徴をみるには、まえのオランダ東インド会社について、イギリスのジャヴァ総督サー・スタムフオード・ラッフルズが言った次のことばを、文字どおりくりかえせば十分なほどである。
「オランダ会社は、利欲一点ばりで動いており、領民にたいして、西インド諸島の農園主が昔その農場の奴隷の集団に示したほどの関心や顧慮をもはらっていない。西インド諸島の農園主が人間財産を手にいれるのに金を出したのに、オランダ会社はそうしていないからである。オランダ会社は、これまであった専制主義の全機構をつかって、人民から貢納と労働とを最大限に一片残らずしぼりとった。こうして、まえからの気まぐれでなかば野蛮な政府が、政治家のあらゆる巧みな手口と商人のあらゆる排他的な利己心で運用されて、さらにひどい害悪を示すことになった。」
内乱、侵入、革命、征服、飢饉、それらがあいついでヒンドゥスタンに及ぼした作用が、どんなに奇妙なほど複雑で、急速で、破壊的であるように見えても、それらはすべてヒンドゥスタンの表面にふれただけであった。ところがイギリスは、インド社会の骨組み全体をうちこわしてしまい、それが再建されるきざしはまだすこしも現われていないのである。このようにインド人が古い世界をなくして、しかも新しい世界を得ていないため、インド人の現在の苦難は一種独特の憂鬱さをおびているのであり、またこの点でイギリス支配下のヒンドゥスタンは、この地の古来の伝統のすべて、過去の歴史全体から、隔てられているのである。
アジアでは、一般に、太古以来、三つの政府部門しかなかった。財務省すなわち国内略奪者、軍事省すなわち国外略奪者、最後に公共事業省である。天候と地形上の条件、とくにサハラからアラビア、ペルシア、インド、タタールを経て、アジア最高の高原にまでひろがっている広大な砂漠地帯のために、運河と用水とによる人工灌漑が、東洋農場の基礎となった。エジプトとインドと同様、メソポタミア、ペルシアその他でも、洪水を利用して土地を肥沃にし、高い水位を利用して灌漑水路に水をそそいだ。このように水を節約して共同につかわなけければならない根本的な必要から、西洋では、フランドルやイタリアの例のように、私的経営が自発的な連合を結ぶのが促進されたが、東洋では文明があまりにも低く、また地域があまいに広大で、自発的な連合を生みださなかったため、とうぜん集中的にはたらく政府権力が介入することになった。ここからして、一つの経済的機能、すなわち公共事業をおこなうという機能が、あらゆるアジアの政府に帰した。このように土壌を人為的に肥沃化するのに中央政府にたより、灌漑や排水を怠るとすぐだめになってしまうしくみからして、パルミラやペトラ、あるいはイエメンの廃墟、さらにはエジプト、ペルシア、ヒンドゥスタンの広大な諸地方のように、まえにはみごとに耕されていた地域が、まるごと、いま不毛の荒地になっているという奇妙な事実がはじめて説明できるし、また、国土を荒らす戦争が一回あっただけで、何世紀となく無人の地となり、その文明もいっさい無に帰してしまうという理由も説明できる。
さて、東インドのイギリス人は、前任者から財務省と軍事省はひきついだが、公共事業省のほうはまったくおろそかにした。そこからして、農業は衰退した。イギリス流の自由競争、自由放任 (124) [kaissez-faire, laissez-aller] の原則ではいとめない農業なのである。しかしアジアの諸帝国では、農業がある政府のもとでは衰退するが、他の政府のもとでは復活するのを、われわれはよくみなれている。ヨーロッパでは収穫が天気のよしあしで変わるように、アジアでは収穫が政府のよしあしで決まるのある。だから、農業を圧迫したり、おろそかにしたことは、悪いことではあるが、もしそれが格段に重要な一つの事情、全アジア世界の年代記にはじめて現われた一つの事情をともなわなかったら、侵入者のイギリス人がインド会社に致命的打撃を与えたものとみなすことは、不可能であったろう。インドではこれまでどんなに政治の姿が変わったようにみえても、その社会的条件は、最古の時代から変わることなく一九世紀の最初の一〇年代にまでおよんだ。無数の紡績工と敷布工とを規則ただしくつくりだす手織機と紡車とは、この社会の構造の枢軸であった。はるか昔からヨーロッパは、このインド人の勤労によるみごとな織物を受け取ってきたものである。その代わりとしてヨーロッパは貴金属を送って、インドの金細工に原料を提供してきた。この金細工師はインド社会には不可欠の人間である。というのは、インド社会が装飾品を好むことはたいへんなもので、ほとんどはだしで歩きまわる最下層の階級でさえ、金の耳輪を一対と首飾りになにかの金の細工品をつけているのが普通なくらいである。指輪や足の指輪もひろくつかわれてきた。女や子供がしばしば金や銀のずっしりした腕輪や足輪をつけていたし、家のなかには金銀の神像が見られた。このインドの手織機をうちこわし、紡車を破壊したのは、侵入したイギリス人であった。イギリスはまずインド綿製品をヨーロッパ市場から駆逐した。つづいて撚糸をヒンドゥスタンにもちこみ、ついにはこの木綿の母国そのものに綿製品を氾濫させた。一八一八年から一八三六年までに、イギリスのインドへのモスリンの輸出は、一八二四年には一〇〇万ヤードたらずであったが、一八三七年には六四〇〇万ヤードをこえた。しかし同時に、ダガー(インドの綿業都市)の人口は一五万人から二万人に減った。だが、このように織物製品で有名なインドの諸都市が衰退したことも、けっして、いちばん悪い結果ではなかった。イギリスの蒸気力と科学とが、ヒンドゥスタンの全土にわたって、農業と手工業との結合をくつがえしてしまったのである。
これらの二つの事情― 一方ではインド人が、東洋のすべての国民と同じく、大公共事業の世話という農業および商業の第一条件を中央政府にまかせたこと、他方ではインド人が国中にちらばっていて、農業と手工業との家内的結合によって小さな中心をかたちづくっていたこと―これらの二つの事情は遠い昔から、独特な性質をもった一つの社会制度―いわゆる村落制度を生み出していた。この制度の特殊な性格については、インド問題にかんするイギリス下院の古い公式報告のなかにある次の記述から察することができよう。
「村は、地理的にみれば、数百か数千エーカーの耕地と荒地からなる一地域であり、政治的にみれば、自治体か町村に似ている。その役員と吏員とは、正常ならば、次の種類のものから編成されている。ポタイルすなわち住民の長、彼は村の事務を一般に主宰し、住民の争いを解決し、警察事務にあたり、村内の租税の徴収という任務を果たす。この徴税の任務は、彼が個人的影響力をもち、人民の事情や業務をこまかく知っているので、もっとも適任なのである。カルナムは耕作の記帳をし、耕作に関係あるすべてのことを記録する。タリアとトティ、前者の任務は、犯罪や不法行為についての情報を集めること、村から村へと旅する人を護衛、保護することであり、後者の職分は、もっと村に直接かぎられているようで、とりわけ作物をまもったり、その計量をたすけることにある。貯水池と用水路の管理人は、農業用の水を分配する。ブラーフマン、村の礼拝をおこなう。学校教師、村の子に砂の上で読み書きを教えているのがみうけられる。暦をつかさどるブラーフマン、すなわち占星師など。このような役員と吏員とで村の管理機構を編成しているのが普通である。しかし、この国のある地方では、これがもっと小規模で、上記のいくつかの任務や職能を一人の人間が兼ねているし、反対に他の地方ではそれがまえにあげた人間の数よりも多い。こういう単純なかたちの自治体政府のもとに、この国の住民は太古このかた暮らしてきているのである。村の境界はめったに変わらなかった。村そのものは戦争や飢饉や病気で時にそこなわれ、荒廃しさえしたけれども、同じ名称、同じ境界、同じ利害、いや同じ家族までが、幾世紀となくつづいてきたのである。住民は王国が瓦解しようと分裂しようと気にかけなかった。村がそこなわれないかぎり、住民は、村がどの権力のもとに移されようが、どの支配者に属そうがかまわなかった。村の内部の経済は、変わることなく残っている。ポタイルは依然として住民の長であり、依然として小裁判官ないし治安判事として、また村の徴税人ないし小作料徴収人として行動しているのである。」
これらの小さな固定したかたちの社会組織は、イギリスの徴税官やイギリスの兵士の野獣のような干渉のためというよりも、イギリスの蒸気力やイギリスの自由貿易の作用によって、大部分解体されたし、消滅しつつある。これらの家族共同体は家内工業に基礎をおいていた。すなわち、手織り、手紡ぎ、手耕農業の独特な組合せが、これらの共同体に自給自足の力を与えていたのだが、それに基礎をおいていたのである。イギリスの干渉は、紡績工をランカシアに、敷布工をベンガルにとわけへだてたり、あるいはインド人の紡績工と敷布工とを共に一掃したりして、この小さな半野蛮、半文明の共同体の経済的基礎を爆破して共同体を解体させ、じつは唯一の社会革命を生みだしたのである。
ところで、この無数な家父長的で無害な社会組織が解体され、各構成単位に分解され、苦難の海になげおとされ、その各成員が古代そのままの形態の文明と伝来の生活手段とを同時に失うのをみることは、人間感情にとって胸いたむものではあるにはちがいないけれども、われわれは、これらの牧歌的な村落共同体がたとえ無害にみえようとも、それがつねに東洋専制政治の強固な基礎となってきたこと、またそれが人間精神を迷信の無抵抗な道具にし、伝統的な規則な奴隷とし、人間精神からすべての雄大さと歴史的精力を奪ったことを、忘れてはならない。みすぼらしいいくらかの土地にとらわれ、いくつ帝国が滅びても、度をこえた残虐行為がおかされても、いくつもの大都市の全住民が虐殺されるということが起こっても、平然とこれらを傍観して、自然現象にたいするほどの関心しかよせず、みずからも、目をつけられたら最後、まちがいなく侵略者の無力な餌となった、このような野蛮な利己主義を忘れてはならない。この人間的尊厳を知らない、停滞した、十年一日のような生活、この受動的な生き方が、他方では対照的に、乱暴で、盲目的で、とどまるところを知らない破壊力をよびおこし、ヒンドゥスタンでは殺人をさえ宗教上の祭式にしたことを、忘れてはならない。これらの小さな共同体がカーストの差別や奴隷制という汚点をもっていたこと、これらの共同体が人間を環境の支配者にたかめるのではなくて人間を外的環境に隷属させたこと、これらの共同体がみずから発展してゆく社会状況を、けっして変化しない自然の運命に変え、こうして人間性を失わせる自然崇拝、それも自然の支配者である人間が猿のハヌマンや牝牛のサッパラにひざまずいて礼拝する事実に示されるほど堕落した自然崇拝を、もたらしたことを忘れてはならない。
なるほどイギリスがヒンドゥスタンに社会革命をひきおこした動機は、もっともいやしい利益だけであり、その利益を達成する仕方もばかげたものであった。しかし、それが問題なのではない。問題は、人類がその使命を果たすのに、アジアの社会状態の根本的な革命なしにそれができるのかということである。できないとすれば、イギリスがおかした罪がどんなものであるにせよ、イギリスはこの革命をもたらすことによって、無意識に歴史の道具の役割を果たしたのである。
だから、古代世界がくずれおちる情景が、われわれの個人的感情にはどんなに悲痛であるとしても、歴史の立場からすれば、われわれはゲーテとともに、次のように叫ぶ権利を持っている。
「この苦しみがわれらの快楽をますからには、
どうしてわれらの心を苦しめよう。
ティームールの支配も、
無数の命を滅ぼしたではなかったか?」
[“Sollte diese Qual uns qualen,
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timurs Herrschaft aufgezehrt?”]
* ゲーテ『西東詩集』所収「ティームールの書」中の「ズライカに」から。
(121) リンガの宗教(性器崇拝)―シヴァ神の礼拝。南インドのリンガ宗派(「リンガ」―男性器―はシヴァの表象)のあいだにとくにひろまっていった。ヒンドゥー教の一宗派で、カーストの差別を認めず、断食、いけにえ、巡礼を拒否している。
ジャガナート(ジャガナウト)―ヒンドゥー教の主神のひとりであるシヴァ神の化身の一つ。ジャガナートの礼拝は、特別壮麗な儀式とはなはだしい狂信とを特徴としている。この狂信は、信者がみずから去勢し、いけにえとなることに現れていた。大祭日には、信者は、ヴィシェヌ‐ジャガナートの神像をのせた山車の轍の下に身を投げた。
(122) ムガル―トルコ系の征服者で、十六世紀初頭に中央アジア東部からインドに侵入し、一五二六年にインド北部大ムガル帝国(この帝国を支配した王朝は大ムガル朝とよばれた)を創立した。同時代に人々は、ムガル帝国の創立者たちを、チンギス・カーン時代のモンゴールの征服者の直接の子孫と見なしていた。「ムガル」という名まえもここから出てきた。ムガル帝国は、十七世紀中葉にインドの大部分とアフガニスタンの一部を征服してから、とくに強大になった。農民蜂起、回教徒の征服者にたいするインド諸民族の反抗の増大、たえまない内訌、封建的な分離主義的傾向の増大、これらはムガル帝国の崩壊をもたらし、十八世紀の前半には同帝国は事実上存在することをやめた。
七王国分立―七つの独立の部分に分裂した国のこと(たとえば、六世紀から八世紀のアングロサクソン時代の古代イングランド)。ここでは、マルクスはこの表現を類推的に、回教徒の征服依然のデカン(インド中部および南部)の封建的割拠状態をさすのに使っている。
(123) ボンベイ地方のサルセット島は、一〇九の仏教洞窟寺院の存在で有名である。
(124) 自由放任― マンチェスター学派、すなわち自由貿易の自由主義的な経済原則。彼らは、自由貿易と、経済問題への国家の介入とを主張していた。
コピペ元; 大月書店、マルクス=エンゲルス全集 第9巻、1962年、「イギリスのインド支配」、鈴木正四 訳。なお、鈴木正四のwiki。
マルクスに「イギリスのインド支配」という文章がある。1853年6月25日に米国のニューヨーク・デイリー・トリビューンという新聞に寄稿したものだ。この1853年6月というのは、マシュー・ペリー率いる米国東インド艦隊が、琉球経由で、浦賀に来た頃。
文明的に遅れたインドはイギリスに破壊されれることによってより文明的な社会になれるといったこの西欧自己中心主義的思想について、日本では結構昔から一般書において紹介されている。
おいらの知る限り、例えば、岩波新書では2冊ある。蝋山芳郎、『インド・パキスタン現代史』(1967年)、遠山茂樹、『明治維新と現代』(1968年)。しかし、これらの本において、マルクスがイギリスの帝国主義を歴史的必然として肯定することには言及していないし、マルクスを非難することもしていない。
学術的にはマルクスのインド論は「アジア的生産様式」論争として研究されてきた。例えば、おいらは、小谷汪之、『マルクスとアジア』(1979年)(Amazon)をみたことがある。小谷汪之もマルクスを帝国主義者よばわりしていない。
一方、このマルクスの「イギリスのインド支配」が、より盛んに、日本で言及されるようになったのは、1990年代以降で、その理由はE. W. サイードの『オリエンタリズム』(1978年、邦訳1986年)のせいである。そのE. W. サイードの『オリエンタリズム』で「イギリスのインド支配」のマルクスの言説をロマン主義的オリエンタリズムと解釈している。サイードがこの「イギリスのインド支配」を有名にした。こういうわけで、現在、マルクスの「イギリスのインド支配」の全文を知りたい人というのは、サイードの引用文献として全文を確かめたい人だと思われる。
例えば、サイード経由のマルクス、「イギリスのインド支配」への言及として、柄谷行人の次の発言がある(【共同討議】伝統・国家・資本主【共同討議】伝統・国家・資本主義、 西部邁、福田和也、浅田彰、柄谷行人、「批評空間 II-16」1998);
柄谷 (前略)確かに、現在は、アメリカが規制緩和・自由化を要求して、世界中に圧力をかけている。しかし、その場合、アメリカがどうこうやっているとか言っても仕方がない。例えば、イギリスがインドを植民地にしたことについて、マルクスはやむをえないと言う。サイードはマルクスよ、お前もか、と怒っているけれど(笑)。
浅田 資本主義は世界を呑み込んでいくけれども、それに伴って「資本の文明化作用」も働くことになる。これがマルクスの弁証法でしょう。ある段階でイギリスがその先端を担ったけれど、後には没落した。今の段階ではアメリカがその先端を担っているけれど、後でどうなるかわからない。ともあれ、で問題は資本主義であって、イギリスやアメリカではない、と。
柄谷 そうですね。そこにどうしようもなく旧来の共同体を変えてしまう力が働いているわけで、それが貨幣経済です。(以下、略)
資本による伝統的社会の破壊は必然的なものとみる立場だ。この思想的立場だとアメリカによるヴィエトナム戦争は肯定されることになる。
一方、サイード経由のマルクス、「イギリスのインド支配」をおかずにして、文明論に言及しているのが、西川長夫。西川長夫、『国境の越え方』, 1992年。
西川は、マルクスのインド一連のインド論について、「マルクスの署名がなければ、われわれ読者は、西欧のもっとも露骨で恥知らずな植民地主義者の文章だと思うだろう」と云う。しかし、「もちろんマルクスは植民地支配を擁護しているのではなく、歴史的事実と歴史的必然について述べているのである」と云う。イギリス帝国主義、あるいは資本主義が他文明を征服することが歴史的必然であると判断するのは帝国主義のイデオロギーである。
そして、西川は云う;「それに、このようにテクストの一部を抜き出してそれが全体の論調であるかのような論じ方をしてはならないだろう」。
なので、マルクスの「イギリスのインド支配」の全文をコピペして見られるようにした。