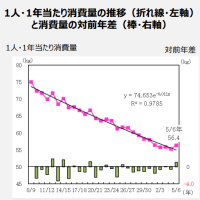私のXに、ビックりするようなポストとリツイートがあった。
ビックリする内容とは、筑波大学で「文系学部の統廃合」が、行われるという内容だった。
日本労働評議会NEWS:筑波大学で人文、比較文化、日本語・日本文化の3学部廃止方針・・・
タイトルが長いので、省略をさせていただいたのだが、あまりにも驚く内容だった。
その理由のいくつかを上げてみたい。
1.筑波大学の前身は「東京教育大学」を中心につくられた、総合大学。
学校教育のプロを養成するために大学だったのだ。
確かに、筑波大学のスポーツ科学出身のスポーツ選手は、数多くいらっしゃるし、日本代表として活躍されていた方々も少なくない。
しかし、プロのスポーツ選手を養成する大学ではなく、あくまでも「スポーツ教育」ができる人材を教育することを目的としているのだ。
そう考えると、「教育」の基本中の基本である、「母語=日本語」を蔑ろにして、満足な教育者が育成できるのか?という、疑問だ。
確かに、学部の廃止なので「日本語・日本文化」を教える教員を養成しないだけ、ととらえることもできるが、大学の姿勢として
「母語を大事にしない」という、考えが見て取れるし、そのような印象を与えている。
2.政府方針で理工系、医薬系を充実させる、ということのようだが、昨今の政治家や官僚の言葉遣いを見聞きして感じることは、今回筑波大学
が廃止を決めた人文系、比較文化、日本語・日本文化を理解していないのでは?ということを多々感じる。
これらの学問は、実利的ではないかもしれないが、これから先AIが企業の中心となって仕事を進めていく中で、唯一(と言ってもよいと思う)
AIが太刀打ちできない「教養」と呼ばれる分野でもある。
データの解析などは、AIの方が遥かに早く正確に処理できるだろう。
しかし、そのデータを何に使うのか?何のために必要なのか?という「発想」の部分では、「教養」となるモノが必要なのだ。
もちろん、グローバルコミュニケーションという視点でも、「相手の文化を理解し、敬意を払うコミュニケーション力」は、これらの人文系、
比較文化などを学ぶことで身につく部分が大きい。
それらを教育として教える人財は、これからのAI社会にとっては一番必要な人財なのでは?
3.論文作成力の低下を招く危険性
ここ数年だろうか?日本の大学発の論文が世界から認められにくくなってきているのでは?という、気がしている。
特に、これまで日本が得意とされてきた「理工、医薬系の基礎研究」が、減ってきているような印象がある。
もちろん、これは私の印象なので、現実は違うのかもしれないのだが、これらの研究論文をつくる力が衰えている、とすれば、やはり問題
なのだと思う。
論文の執筆は、その分野に精通しているだけで書き上げることができない。
重要なことは「伝える」ということなのだ。
その基礎となるのが、やはり母語=日本語の力、ということになる。
確かに、少子化の中若い人達が、世界で活躍するためには新しい学術領域での教育の充実は不可欠だろう。
だからと言って、母語である日本語や多様な文化に対する教育を怠ることは、世界で活躍する為の人財の芽を摘み取るようなものなのでは?
目先の手っ取り早い方法で、人財が育つわけではない。
特定の教育に力を入れ、基本となる学問を教える人財を蔑ろにすることこそ、国力を低下させる愚策だと思うのだ。
最新の画像[もっと見る]