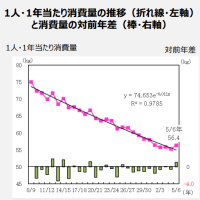今朝、FMを聞いていたら、驚くニュースがあった。
讀賣新聞:全国学力テスト 中学国語「記述式」の正答率25%台、3割近くが無解答の問題も…4月の全国学力テスト
選択式や短い言葉や漢字を問う内容に関しては50%以上の正答率であったことから、「言葉の意味が分からない」とか「漢字が分からない」という訳ではなさそうだ。
文章を書くことや、論理的な文章の組み立てができない、ということになると思う。
そしてこの「文章を書く・(思考の)論理的組み立てをする」ということは、ビジネスで一番求められる力でもある。
確かに、文章を書くことが苦手、という方は少なくない。
「少なくない」というよりも、「多い」と言ってしまった方が良いかもしれない。
何故多くの人が「文章を書く」ことに対して、苦手意識があるのか?ということを考える必要があると思う。
「文章を書く」ということは、ある種の「表現力」を問われる部分でもある。
「自分が、〇〇と思いました」ということを書けても、その理由が書けなくては説得力(=論理的思考の始り)は無い。
説得力というよりも、伝える力といった方がわかりやすいかもしれない。
「伝える力」に一番必要なことは何か?と考えると、「想像する力」ということになると思う。
「伝える相手のことを想像し、言葉を選び、文章を組み立てる」という、様々な能力を総動員させる必要がある。
成績の良かったテスト内容は、どちらかと言えば機械的に当てはめることができる「作業」と、言えるかもしれない。
それに対して「記述式」は、上述した通り「伝えるためには、何が必要なのか?しかも受け手となる相手に、的確に伝える必要がある」と、考えることになる。
最近「自分が分かっているのだから、相手もわかっている」という前提で、書かれた文を読むことがある。
そのような文を読むたびに「私はあなた(=文を書いて人)じゃないから、分からない」と、感じるのだ。
このような状況は「言葉の祖語」が生まれ、共通に理解にたどり着くまでが大変だ。
伝言ゲームで「A」と伝えたはずが、最後の人に伝わる頃には「Z」になっていたりするのは、「A」と聞いた人(=受け手)が、「A」の情報に自分がイメージしているBという情報を加えてしまうからだ。
伝える人が多くなればなるほど、伝わってきた情報+その言葉から自分がイメージするモノを加える、という作業が繰り返されることによって、最終的には「Z」になってしまうのだ。
伝言ゲームの面白さは、そのように「伝える」中で情報が変わり、全く別ものになってしまう、ということを実感しながら楽しむものだが、ビジネスの場面では、そのような事は許されない。
その為に必要な力が「相手に伝えるための想像力+表現力+論理的思考」ということになるのだ。
個人的には、中学生の頃からそのような練習に取り組めば、問題は無いと思っている。
ただ、このテスト結果を見て感じるのは「タイパ」や「合理性」という言葉によって、基本的な「創造力・表現力・論理的思考」のトレーニングがおざなりになってしまっているのでは?という懸念だ。
何故なら、「記述式」で必要な力というのは、とても効率が悪く、短時間で身につくものではないからだ。
そう考えると、大量の問題を短時間で解く為の力ばかりに目を向けてきた結果なのでは?という気もしている。
最新の画像[もっと見る]