
19世紀後半にニューヨークで活躍した二人の女流記者の話。
一人はエリザベス・ビスランド、もう一人はネリー・ブライ。ネリー・ブライはペンネーム(19世紀アメリカの作曲家フォスターの曲のタイトルからとった)で、本名はエリザベスなので、これは「二人のエリザベス」の話でもある。
ビスランドは、南部ルイジアナ州に生まれる。10代の少女は、詩を書いてニューオリンズ(ジャズで有名な街)の新聞社に送り、それがクリスマスの日に掲載された。少女は、それが家族や友人に知られたら恥ずかしいと思い、何マイルも歩いて隣町まで行き、投稿を続けた。
ビスランドが18歳の時、ニューオリンズの別の新聞『アイテム』誌に載ったある小説をビスランドは読み、なぜかそれを書いた作者に会いたくなった。彼女は持ち前の行動力を発揮して、ミシシッピーの田舎町からニューオリンズまで出て行き、その小説の作者を訪問する。 小説のタイトルは『死者の愛』、作者はラフカディオ・ハーンであった。ハーンはビスランドより、11歳年上である。二人は友人関係となる。
やがて彼女は、ニューオリンズに出て、ずっと投稿をしていた新聞社の社員となり、記事を書くようになる。 (その後、ハーンも同じ新聞社で働くことなり、二人は同僚になる。)
その後、ビスランドはさらなる飛翔をせんとニューヨークに出る。美人で優雅、若く社交的なビスランドの周囲にはたくさんの人が集まった。記者としての収入もかなりのものになっていった。(後を追うように、やがてハーンもニューヨークへ出てゆく。)
1889年11月14日、いつものよう目覚め優雅な朝をすごしていたビスランドのもとに、「すぐに出社されたし」と会社から伝言が来る。彼女が出社すると、『コスモポリタン・マガジン』編集長が彼女に「今すぐ、世界一周の旅に出よ」という。
エッ、世界一周!? なぜ…??
これはネリー・ブライの挑戦だった。ブライ25歳、ビスランド28歳。
どちらが早く世界一周できるか、勝負だ、というわけである。
ジュール・ベルヌが『八十日間世界一周』を書いたのは1873年。これは大ヒットとなり、日本でも1878年に翻訳されている。
エジプトのスエズ運河が開通したのは1869年である。これによって、「世界一周」がかなりラクになった。 世界地図を見れば一目瞭然、ヨーロッパからアジアへ行くのに、アフリカをまわらなくていいのだ。
「80日で世界一周できるはずだ」という主人公に対し、「無理だ、できるもんか」という意見多数。「では、やってみせよう」ということで、主人公フィリアス・フォッグ(イギリス人)はロンドンを出発した____というのが、ジュール・ベルヌ『八十日間世界一周』のストーリーである。主人公フォッグは、ロンドンからスエズ運河を通過し、インドへ。インドでは、花嫁となる美女を見つけ、途中様々な困難に会いながら、シンガポール、香港、日本(横浜)、アメリカ、と渡って、ついに世界一周を達成。ピッタリ80日であった。
ただし、これは小説である。この小説が出て、16年経っている。鉄道・船舶はより便利に発達している。たとえば、カナダのモントリオールとバンクーバーを結ぶカナダ太平洋鉄道はその3年前に開通した。
それなら、1889年の現在、実際には何日で世界一周が可能なのか?
これはネリー・ブライの考えた企画だった。
ネリー・ブライは、「女闘士」のような記者だった。
ピッツバーグですでに活躍していたブライは、23歳のとき自信満々でニューヨークに移る。が、思ったよりも現実は厳しく、おまけにブライは全財産を盗まれてしまう。だが、そこでへなへなと座り込んでしまうような女ではなかった。
ネリー・ブライは新聞社「ニューヨーク・ザ・ワールド」に面会を申し込む。受付で3時間粘り、根負けした社員がとうとう社長室に案内した。彼女は自分の企画を6通り用意していた。
そのうちの1つが採用された。 『ブラックウェルズ島の精神病院潜入レポート』であった。 悪名高き精神病院に患者のふりをして一週間潜入するという企画である。 そしてこの記事が大成功、彼女はニューヨークで有名な女性記者となった。その後もブライは次々に企画を打ち出した。
「世界一周早まわり競争」、これに成功すればだれもが知っているスター記者になるだろう。
ビスランドには分のわるい戦いだった。ブライのほうは自分で企画したのだから、十分準備をして出発しただろう。ビスランドは突然、知らされた。しかしネリー・ブライは11月14日のこの日、すでにニューヨークを発っていた。
「嫌です。」と、いったんはビスランドは断った。これに敗れれば「敗者」のレッテルが貼られてしまうではないか。 しかし、編集長の説得に押し切られ、とうとうビスランドは「勝負」を受けた。
ビスランドは、ブライの挑発に乗ったのだ。 それなら、すぐに出発せねばならない。やる以上は、勝たねば。
ビスランドは、ニューヨークをその日のうちに汽車に乗り、サンフランシスコに向かった。サンフランシスコから、汽船ホワイト・スター号に乗り、太平洋を渡り、日本へ向かった。 ジュール・ベルヌの小説とは逆の、西まわりである。
ビスランドが突然にニューヨークから消え、日本へ行った__。
そのニュースを聞いて意外なほど動揺したのが、ラフカディオ・ハーンである。
〔たまに逢うだけですが、とても嬉しい気持ちで訪問の時を待ち望んでいたことを申し上げなければなりません。その訪問のおかげで、巨大な鉄の嵐の吹きまくる世界を、そして、その中のあなた以外のすべてを忘れることができました。あなたは私のためにうっとりするような日溜りを作ってくれたのです。〕
(ラフカディオ・ハーンのビスランド宛の手紙)
ビスランドはニューヨークを去ったとはいえ、3ヶ月後には帰ってくる。それなのに、ハーンは、滑稽なほど、感傷的になっている。 それに、ハーンとビスランドは恋仲ではなかったのだが…。 たぶん、ハーンは、人一倍落ち込みやすい性格なのだ。 「巨大な鉄の嵐の吹きまくる世界を」とニューヨークを表しているように、彼は大都会ニューヨークが好きではなかったのだ。
ニューヨークは湧いた。 ネリー・ブライとエリザベス・ビスランド__二人の世界一周早まわり競争。 どっちが先にニューヨークに帰ってくるか__。
なにしろラジオも映画もまだない時代である。新聞・雑誌の記事は、市民の主要な娯楽でもあった。 二人は、映画のヒロインのようなものである。「地球」がその劇場だ。
ブライの後ろ楯は新聞社『ニューヨーク・ザ・ワールド』である。旅先から送るブライの記事が、新聞紙面を飾った。
ビスランドはその点でも不利であった。彼女の『コスモポリタン』誌は、月刊誌なのである。
エリザベス・ビスランドが、日本・横浜の地を踏んだのは1889年(明治22年)12月8日である。夏目漱石と正岡子規がまだ学生で、寄席の話などしていたころである。
〔(果物は)すべてが輝くように清潔で優美でそして美味しそうだ。人々もまた楽しくてお喋りだ。子供たちはのびのびと遊び、優しく微笑むような月光の下で、この土地はとても楽しいから、なにか提灯のお祭りでもしているのかと思ってしまう。〕
外国人向けの観光ツアーで、一日、横浜と東京を楽しんだビスランドは、翌日、香港行きの汽船に乗った。
香港、シンガポール、セイロン、アデン…
一人はエリザベス・ビスランド、もう一人はネリー・ブライ。ネリー・ブライはペンネーム(19世紀アメリカの作曲家フォスターの曲のタイトルからとった)で、本名はエリザベスなので、これは「二人のエリザベス」の話でもある。
ビスランドは、南部ルイジアナ州に生まれる。10代の少女は、詩を書いてニューオリンズ(ジャズで有名な街)の新聞社に送り、それがクリスマスの日に掲載された。少女は、それが家族や友人に知られたら恥ずかしいと思い、何マイルも歩いて隣町まで行き、投稿を続けた。
ビスランドが18歳の時、ニューオリンズの別の新聞『アイテム』誌に載ったある小説をビスランドは読み、なぜかそれを書いた作者に会いたくなった。彼女は持ち前の行動力を発揮して、ミシシッピーの田舎町からニューオリンズまで出て行き、その小説の作者を訪問する。 小説のタイトルは『死者の愛』、作者はラフカディオ・ハーンであった。ハーンはビスランドより、11歳年上である。二人は友人関係となる。
やがて彼女は、ニューオリンズに出て、ずっと投稿をしていた新聞社の社員となり、記事を書くようになる。 (その後、ハーンも同じ新聞社で働くことなり、二人は同僚になる。)
その後、ビスランドはさらなる飛翔をせんとニューヨークに出る。美人で優雅、若く社交的なビスランドの周囲にはたくさんの人が集まった。記者としての収入もかなりのものになっていった。(後を追うように、やがてハーンもニューヨークへ出てゆく。)
1889年11月14日、いつものよう目覚め優雅な朝をすごしていたビスランドのもとに、「すぐに出社されたし」と会社から伝言が来る。彼女が出社すると、『コスモポリタン・マガジン』編集長が彼女に「今すぐ、世界一周の旅に出よ」という。
エッ、世界一周!? なぜ…??
これはネリー・ブライの挑戦だった。ブライ25歳、ビスランド28歳。
どちらが早く世界一周できるか、勝負だ、というわけである。
ジュール・ベルヌが『八十日間世界一周』を書いたのは1873年。これは大ヒットとなり、日本でも1878年に翻訳されている。
エジプトのスエズ運河が開通したのは1869年である。これによって、「世界一周」がかなりラクになった。 世界地図を見れば一目瞭然、ヨーロッパからアジアへ行くのに、アフリカをまわらなくていいのだ。
「80日で世界一周できるはずだ」という主人公に対し、「無理だ、できるもんか」という意見多数。「では、やってみせよう」ということで、主人公フィリアス・フォッグ(イギリス人)はロンドンを出発した____というのが、ジュール・ベルヌ『八十日間世界一周』のストーリーである。主人公フォッグは、ロンドンからスエズ運河を通過し、インドへ。インドでは、花嫁となる美女を見つけ、途中様々な困難に会いながら、シンガポール、香港、日本(横浜)、アメリカ、と渡って、ついに世界一周を達成。ピッタリ80日であった。
ただし、これは小説である。この小説が出て、16年経っている。鉄道・船舶はより便利に発達している。たとえば、カナダのモントリオールとバンクーバーを結ぶカナダ太平洋鉄道はその3年前に開通した。
それなら、1889年の現在、実際には何日で世界一周が可能なのか?
これはネリー・ブライの考えた企画だった。
ネリー・ブライは、「女闘士」のような記者だった。
ピッツバーグですでに活躍していたブライは、23歳のとき自信満々でニューヨークに移る。が、思ったよりも現実は厳しく、おまけにブライは全財産を盗まれてしまう。だが、そこでへなへなと座り込んでしまうような女ではなかった。
ネリー・ブライは新聞社「ニューヨーク・ザ・ワールド」に面会を申し込む。受付で3時間粘り、根負けした社員がとうとう社長室に案内した。彼女は自分の企画を6通り用意していた。
そのうちの1つが採用された。 『ブラックウェルズ島の精神病院潜入レポート』であった。 悪名高き精神病院に患者のふりをして一週間潜入するという企画である。 そしてこの記事が大成功、彼女はニューヨークで有名な女性記者となった。その後もブライは次々に企画を打ち出した。
「世界一周早まわり競争」、これに成功すればだれもが知っているスター記者になるだろう。
ビスランドには分のわるい戦いだった。ブライのほうは自分で企画したのだから、十分準備をして出発しただろう。ビスランドは突然、知らされた。しかしネリー・ブライは11月14日のこの日、すでにニューヨークを発っていた。
「嫌です。」と、いったんはビスランドは断った。これに敗れれば「敗者」のレッテルが貼られてしまうではないか。 しかし、編集長の説得に押し切られ、とうとうビスランドは「勝負」を受けた。
ビスランドは、ブライの挑発に乗ったのだ。 それなら、すぐに出発せねばならない。やる以上は、勝たねば。
ビスランドは、ニューヨークをその日のうちに汽車に乗り、サンフランシスコに向かった。サンフランシスコから、汽船ホワイト・スター号に乗り、太平洋を渡り、日本へ向かった。 ジュール・ベルヌの小説とは逆の、西まわりである。
ビスランドが突然にニューヨークから消え、日本へ行った__。
そのニュースを聞いて意外なほど動揺したのが、ラフカディオ・ハーンである。
〔たまに逢うだけですが、とても嬉しい気持ちで訪問の時を待ち望んでいたことを申し上げなければなりません。その訪問のおかげで、巨大な鉄の嵐の吹きまくる世界を、そして、その中のあなた以外のすべてを忘れることができました。あなたは私のためにうっとりするような日溜りを作ってくれたのです。〕
(ラフカディオ・ハーンのビスランド宛の手紙)
ビスランドはニューヨークを去ったとはいえ、3ヶ月後には帰ってくる。それなのに、ハーンは、滑稽なほど、感傷的になっている。 それに、ハーンとビスランドは恋仲ではなかったのだが…。 たぶん、ハーンは、人一倍落ち込みやすい性格なのだ。 「巨大な鉄の嵐の吹きまくる世界を」とニューヨークを表しているように、彼は大都会ニューヨークが好きではなかったのだ。
ニューヨークは湧いた。 ネリー・ブライとエリザベス・ビスランド__二人の世界一周早まわり競争。 どっちが先にニューヨークに帰ってくるか__。
なにしろラジオも映画もまだない時代である。新聞・雑誌の記事は、市民の主要な娯楽でもあった。 二人は、映画のヒロインのようなものである。「地球」がその劇場だ。
ブライの後ろ楯は新聞社『ニューヨーク・ザ・ワールド』である。旅先から送るブライの記事が、新聞紙面を飾った。
ビスランドはその点でも不利であった。彼女の『コスモポリタン』誌は、月刊誌なのである。
エリザベス・ビスランドが、日本・横浜の地を踏んだのは1889年(明治22年)12月8日である。夏目漱石と正岡子規がまだ学生で、寄席の話などしていたころである。
〔(果物は)すべてが輝くように清潔で優美でそして美味しそうだ。人々もまた楽しくてお喋りだ。子供たちはのびのびと遊び、優しく微笑むような月光の下で、この土地はとても楽しいから、なにか提灯のお祭りでもしているのかと思ってしまう。〕
外国人向けの観光ツアーで、一日、横浜と東京を楽しんだビスランドは、翌日、香港行きの汽船に乗った。
香港、シンガポール、セイロン、アデン…










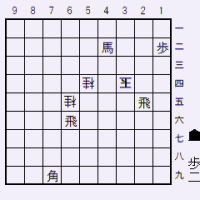
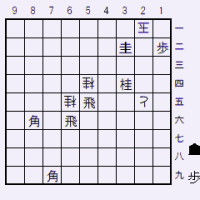
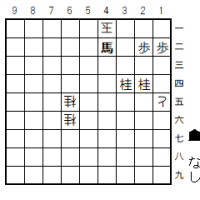
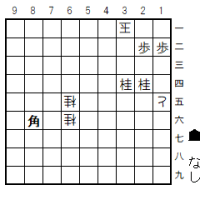
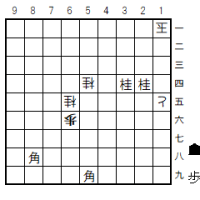
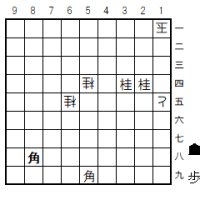
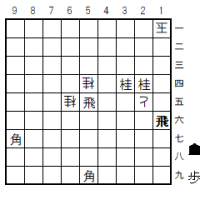
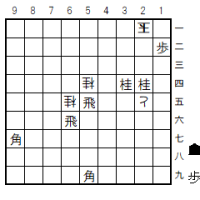
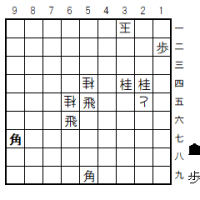
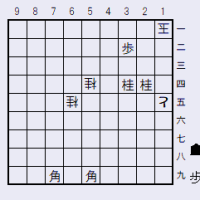






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます