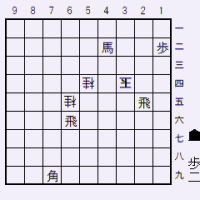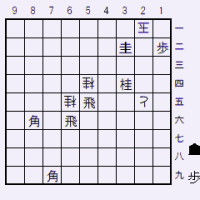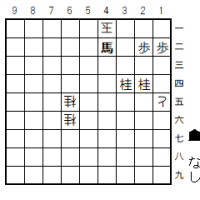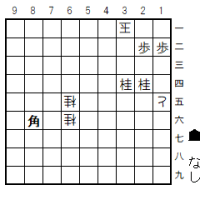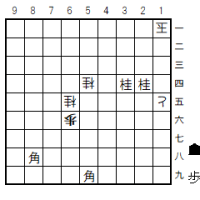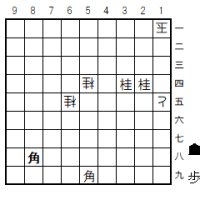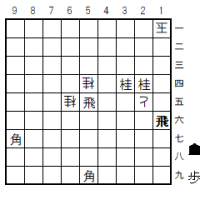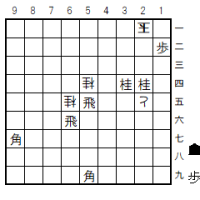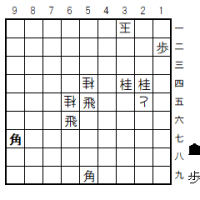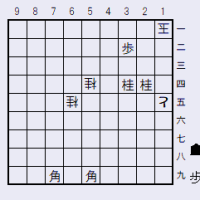エジソンが白熱電球を発明したとき、管の中は真空だった。 フィラメントには苦心の末日本の竹を使ったことが知られている。しかしその電球は、現代の基準からすればすぐに切れやすく(一日もたなかったとか)、まだ実用的でなかったようだ。今は改良されて、タングステンのフィラメントに、真空ではなく、「アルゴン」が入っているようである。
アルゴン、Ar、原子番号18、不活性気体…
「アルゴン」という気体は、「怠け者」という意味で、1894年に発見された。発見者はイギリスのレイリー卿とラムゼー卿である。
これを彼らが発表した時、他の研究者達はそれを信じようとしなかった。空気(大気)の研究はすでにその100年も前にされつくされたと思っていたし、メンデレーエフの周期表の「空席」に、その新発見の空気「アルゴン」のすわる座席はなかったからだ。 (原子量の並びから、ClとKの間になるが、そこに「座席」はなかった。)
「未知の気体」なんて、まだあったのか!?
アルゴンは、不活性元素である。働かない元素…つまり、化学反応をしない‘無口なおとなしい’元素であり、だから誰も気づかなかったのである。アルゴンは大気中に1パーセント存在する。アルゴンだけでなく、「不活性元素」はまだあった。ヘリウム、ネオン、キセノン、ラドン…、それらをすべて科学者たちは、まとめて見逃してきたのだった。
だから、アルゴンの発見は、大発見!なのだった。この功績により、レイリー卿はノーベル物理学賞を、ラムゼー卿はノーベル化学賞を1904年に受賞している。
「空気を調べてごらんよ」
キャベンディッシュ研究所の妖精が、レイリー卿に、そうささやいたのだろうか。
僕はそんなことを思ってしまうのだ。
1879年J・C・マックスウェルの死によって、第2代キャベンディッシュ研究所所長に就任したのがレイリー卿である。 レイリー卿は物理学においてそれまでも十分な実績を残している。たとえば、「レイリー散乱」とよばれる式があって、それによって、空の色がなぜ青いかという証明もできるのだという。夕焼けが赤いということも。 また、熱力学にも、地震学にも、「レイリー」と名の付く式があるようだ。
キャベンディッシュ所長を5年間務めた後、その地位を若く優秀なJ・J・トムソンにゆずったレイリー卿は、その後ロンドンの教授などを勤めた後、自分の研究のための時間を持てるようになった。 そこでレイリー卿は、前から気になっていた問題に着手しはじめた。
それが「空気」の問題である。
「空気」について、その正体が盛んに分析・研究されるようになったのは、18世紀後半である。ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明、水素・酸素・二酸化炭素・窒素の発見…。調子に乗って「水素」入りの気球を造って大爆発が起きたり…ということもあった。
その結果、自然界の「空気」には、酸素が(体積で)21パーセント、残り79パーセントは窒素だということになった。それを長い間だれも疑うことはなかった。(100年の間、だれも!) およそ100年ほど経って、ただ一人、レイリー卿が、「もう一度よく調べてみよう」と思ったのだ。
そうしてレイリー卿は、慎重にその気体の質量を調べる実験を行った。
「空気」から、酸素、炭酸ガス、水分を完全に取り除く…すると残りは「窒素」(空気窒素という)になる。この質量と体積を計る。
一方、アンモニアから「窒素」をつくる方法があって、それでつくった「窒素」(化学窒素という)の質量・体積を計る。
するとなぜだろう、「空気窒素」と「化学窒素」はわずかに質量がちがうのだ? 両者は、同じ窒素ではないということか…?
レイリー卿はその結果を学会で発表した。 「まことに不可解である。みなさんの御意見をうかがいたい。」と。
するとそれに興味を示したのがラムゼー卿だった。 ラムゼーは、私もそれについて研究したいと申し出た。 (イギリスは紳士の国だ。つまりラムゼーは、私も同じ研究をしてもよいかと許可を求めたのである。) それで二人は、お互いに独自にこの研究をして、意見交換をしようということになった。
二人が考えたのは、「空気窒素」には、「なにか別のもの」が含まれているのではないかということだ。 それなら、「空気窒素」から、「窒素」をすべて取り去れば、その「なにか」が残ることになる。
問題は、取り除く、その方法だ。
ラムゼー卿は、マグネシウムに窒素を吸収させるというやりかたで、そのための装置を何度も改良し、そしてついに「なにか」を掴んだのだった。ラムゼーは残った気体を調べてみた。質量を計り、放電管に入れてスペクトルを調べる…。
これはまったく「未知の気体」であった。
ラムゼーはレイリーに連絡を取った。すると驚いたことに、レイリー卿も、ほぼ同時に(なんというすてきな偶然だろう!)、その「未知の気体」の分離と分析を終えたところであった。
その新しく発見した気体、「空気」の中にこっそりと1パーセント含まれていて、だれにも見つからずに隠れていたその気体に、「アルゴン」と名前をつけ、二人の科学者は連名でそれを発表した。 その発表は驚きを持って受け止められ、はじめは誰も信じようとしなかった。 実験ミスではないのか、と。 しかし物理学者クルックスがその「アルゴン」を調べたスペクトルを発表すると、もう反対者も黙る以外になくなった。 だれも気づかなかった「不活性気体」、それは確かに存在するのだと。 「メンデレ-エフの周期表」は修正され、新たな「座席」が1列まるごと追加されることとなった。
(クルックスは、「クルックス管」の発明で知られている。その「クルックス管」が、その後のドイツでのX線の発見や、トムソンの電子の発見に繋がることになる。)
レイリー卿が、「空気窒素」から「窒素」を取り除いた方法は、ラムゼー卿とは違う方法であった。
彼の方法は、「空気窒素」に適量の酸素をまぜ、そこに電気の火花を放電することで、「窒素」を二酸化窒素としてアルカリ水に吸収させるというやりかたであった。
二人が、この「アルゴンの発見」によって、それぞれノーベル賞に輝いたことはすでに述べたとおりである。
ラムゼー卿は、その後も助手とともにこうした研究を重ねた。 まだあるぞ、と思ったのである。アルゴンの中に、まだ未知の「不活性元素」があるのではないかと。 そして、科学史にさらに重要な貢献をすることになる。 化学の歴史にとり残されていた「未知の不活性元素」を次々と発見し「周期表」の空席を埋めたのである。 ヘリウム、クリプトン、キセノン、ネオン…
大阪の初代通天閣(現代のは2代目)は1912年に建築されたようだが、あの通天閣を象徴するネオンサインも、ラムゼー(とトラバース)によるネオンの発見(1898年)に由来するというわけ。 ネオン(Ne)は「新しい」という意味である。
さて、化学のお勉強でおなかいっぱい…な感じだが、「アルゴンの発見」についてもう一つ話が残っているので、おつきあいを願いたい。
以前に、マックスウェルの書いた『ヘンリー・キャベンディッシュ電気論文集』(1879年)のことにふれた。 そして、アルゴンの発見からさらに年月が過ぎた1920年頃、ヘンリー・キャベンディッシュの残された「ノート」についての未整理だった内容がまとめられ明らかになった。 そこには、「空気」についての、驚くべき内容が。
まさか…
そう、まさか…まさか… なのである!
ヘンリー・キャベンディッシュは、すでに18世紀に、「空気」の中に、酸素、窒素以外の「何か別の気体」が1パーセント存在することを、実験により、ただ一人、知っていたのである!!
その実験の方法は、レイリー卿がやったものと同じ方法であった。 電気火花を放電させてアルカリ水に二酸化窒素として吸収させるというやりかたで…。 その時代は、まだ発電機も電池も発明されていないから、静電気をびん(ライデンびん)に貯めたものを使って。
究極の「理系男子」とは、きっとヘンリー・キャベンディッシュのことであろう。
アルゴン、Ar、原子番号18、不活性気体…
「アルゴン」という気体は、「怠け者」という意味で、1894年に発見された。発見者はイギリスのレイリー卿とラムゼー卿である。
これを彼らが発表した時、他の研究者達はそれを信じようとしなかった。空気(大気)の研究はすでにその100年も前にされつくされたと思っていたし、メンデレーエフの周期表の「空席」に、その新発見の空気「アルゴン」のすわる座席はなかったからだ。 (原子量の並びから、ClとKの間になるが、そこに「座席」はなかった。)
「未知の気体」なんて、まだあったのか!?
アルゴンは、不活性元素である。働かない元素…つまり、化学反応をしない‘無口なおとなしい’元素であり、だから誰も気づかなかったのである。アルゴンは大気中に1パーセント存在する。アルゴンだけでなく、「不活性元素」はまだあった。ヘリウム、ネオン、キセノン、ラドン…、それらをすべて科学者たちは、まとめて見逃してきたのだった。
だから、アルゴンの発見は、大発見!なのだった。この功績により、レイリー卿はノーベル物理学賞を、ラムゼー卿はノーベル化学賞を1904年に受賞している。
「空気を調べてごらんよ」
キャベンディッシュ研究所の妖精が、レイリー卿に、そうささやいたのだろうか。
僕はそんなことを思ってしまうのだ。
1879年J・C・マックスウェルの死によって、第2代キャベンディッシュ研究所所長に就任したのがレイリー卿である。 レイリー卿は物理学においてそれまでも十分な実績を残している。たとえば、「レイリー散乱」とよばれる式があって、それによって、空の色がなぜ青いかという証明もできるのだという。夕焼けが赤いということも。 また、熱力学にも、地震学にも、「レイリー」と名の付く式があるようだ。
キャベンディッシュ所長を5年間務めた後、その地位を若く優秀なJ・J・トムソンにゆずったレイリー卿は、その後ロンドンの教授などを勤めた後、自分の研究のための時間を持てるようになった。 そこでレイリー卿は、前から気になっていた問題に着手しはじめた。
それが「空気」の問題である。
「空気」について、その正体が盛んに分析・研究されるようになったのは、18世紀後半である。ジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明、水素・酸素・二酸化炭素・窒素の発見…。調子に乗って「水素」入りの気球を造って大爆発が起きたり…ということもあった。
その結果、自然界の「空気」には、酸素が(体積で)21パーセント、残り79パーセントは窒素だということになった。それを長い間だれも疑うことはなかった。(100年の間、だれも!) およそ100年ほど経って、ただ一人、レイリー卿が、「もう一度よく調べてみよう」と思ったのだ。
そうしてレイリー卿は、慎重にその気体の質量を調べる実験を行った。
「空気」から、酸素、炭酸ガス、水分を完全に取り除く…すると残りは「窒素」(空気窒素という)になる。この質量と体積を計る。
一方、アンモニアから「窒素」をつくる方法があって、それでつくった「窒素」(化学窒素という)の質量・体積を計る。
するとなぜだろう、「空気窒素」と「化学窒素」はわずかに質量がちがうのだ? 両者は、同じ窒素ではないということか…?
レイリー卿はその結果を学会で発表した。 「まことに不可解である。みなさんの御意見をうかがいたい。」と。
するとそれに興味を示したのがラムゼー卿だった。 ラムゼーは、私もそれについて研究したいと申し出た。 (イギリスは紳士の国だ。つまりラムゼーは、私も同じ研究をしてもよいかと許可を求めたのである。) それで二人は、お互いに独自にこの研究をして、意見交換をしようということになった。
二人が考えたのは、「空気窒素」には、「なにか別のもの」が含まれているのではないかということだ。 それなら、「空気窒素」から、「窒素」をすべて取り去れば、その「なにか」が残ることになる。
問題は、取り除く、その方法だ。
ラムゼー卿は、マグネシウムに窒素を吸収させるというやりかたで、そのための装置を何度も改良し、そしてついに「なにか」を掴んだのだった。ラムゼーは残った気体を調べてみた。質量を計り、放電管に入れてスペクトルを調べる…。
これはまったく「未知の気体」であった。
ラムゼーはレイリーに連絡を取った。すると驚いたことに、レイリー卿も、ほぼ同時に(なんというすてきな偶然だろう!)、その「未知の気体」の分離と分析を終えたところであった。
その新しく発見した気体、「空気」の中にこっそりと1パーセント含まれていて、だれにも見つからずに隠れていたその気体に、「アルゴン」と名前をつけ、二人の科学者は連名でそれを発表した。 その発表は驚きを持って受け止められ、はじめは誰も信じようとしなかった。 実験ミスではないのか、と。 しかし物理学者クルックスがその「アルゴン」を調べたスペクトルを発表すると、もう反対者も黙る以外になくなった。 だれも気づかなかった「不活性気体」、それは確かに存在するのだと。 「メンデレ-エフの周期表」は修正され、新たな「座席」が1列まるごと追加されることとなった。
(クルックスは、「クルックス管」の発明で知られている。その「クルックス管」が、その後のドイツでのX線の発見や、トムソンの電子の発見に繋がることになる。)
レイリー卿が、「空気窒素」から「窒素」を取り除いた方法は、ラムゼー卿とは違う方法であった。
彼の方法は、「空気窒素」に適量の酸素をまぜ、そこに電気の火花を放電することで、「窒素」を二酸化窒素としてアルカリ水に吸収させるというやりかたであった。
二人が、この「アルゴンの発見」によって、それぞれノーベル賞に輝いたことはすでに述べたとおりである。
ラムゼー卿は、その後も助手とともにこうした研究を重ねた。 まだあるぞ、と思ったのである。アルゴンの中に、まだ未知の「不活性元素」があるのではないかと。 そして、科学史にさらに重要な貢献をすることになる。 化学の歴史にとり残されていた「未知の不活性元素」を次々と発見し「周期表」の空席を埋めたのである。 ヘリウム、クリプトン、キセノン、ネオン…
大阪の初代通天閣(現代のは2代目)は1912年に建築されたようだが、あの通天閣を象徴するネオンサインも、ラムゼー(とトラバース)によるネオンの発見(1898年)に由来するというわけ。 ネオン(Ne)は「新しい」という意味である。
さて、化学のお勉強でおなかいっぱい…な感じだが、「アルゴンの発見」についてもう一つ話が残っているので、おつきあいを願いたい。
以前に、マックスウェルの書いた『ヘンリー・キャベンディッシュ電気論文集』(1879年)のことにふれた。 そして、アルゴンの発見からさらに年月が過ぎた1920年頃、ヘンリー・キャベンディッシュの残された「ノート」についての未整理だった内容がまとめられ明らかになった。 そこには、「空気」についての、驚くべき内容が。
まさか…
そう、まさか…まさか… なのである!
ヘンリー・キャベンディッシュは、すでに18世紀に、「空気」の中に、酸素、窒素以外の「何か別の気体」が1パーセント存在することを、実験により、ただ一人、知っていたのである!!
その実験の方法は、レイリー卿がやったものと同じ方法であった。 電気火花を放電させてアルカリ水に二酸化窒素として吸収させるというやりかたで…。 その時代は、まだ発電機も電池も発明されていないから、静電気をびん(ライデンびん)に貯めたものを使って。
究極の「理系男子」とは、きっとヘンリー・キャベンディッシュのことであろう。