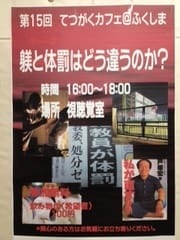昨日、初のてつがくカフェ@御倉邸の開催でした。
雰囲気のよい日本家屋と庭園に22名の方にお越しいただき、「何のために勉強するのか?」というテーマで話し合いが始められました。




「私は教員ですが、何のために勉強するのかという問いを生徒から受けることはよくあります。こういう問いは勉強に対するモチベーションの低い生徒から出されることが多いと思います。これはモチベーションの問題ではないでしょうか。」
「たしかにこの問いはやってもできない子たち、学校教育の目指す将来像と異なった子どもたちから発せられるように思います。でもそういう子たちも、例えばパソコンがよくできたり、車についてめちゃくちゃ詳しかったりして、自分なりの将来を築いていくことができます。学校とは別の路線があるのだから、勉強なんかできなくてもいいんじゃないでしょうか。」
「今日は学校の先生が何人かおられるようなのでお聞きしたいのですが、学校教員としては生徒にどうなってほしいと考えているのでしょうか。」
「私は教員で今日の問いも20人に聞かれたら20通り、いろいろな答え方があるのですが、今の質問に答えるなら、ちゃんとした大人になってほしいということでしょうか。一人一人が自分の人生を送れるようになってほしいと思っています。」
「『ちゃんとした』 って言っちゃうとある一定の枠があるように聞こえてあまり好きではありませんが、いろいろな路線、判断できるいろいろなモデルを学び、たくさんのモデルから自分の道を選べるようになるのが学ぶ意味ではないでしょうか。」
「私も学校現場に勤めていましたが、生徒には自分の選択肢を広げるためにとりあえずやっとけと言います。勉強は学校で強制されるという意味がある。それに対して学ぶというのは、目的や好奇心、自分の欲求、本能として学ぶという意味でしょう。生まれてしまった以上、人生の目的を考えると自殺してしまう人もいるように、何で学ぶのかと考えるとそれには答えがなく困ってしまうのではないでしょうか。あえて答えるならば、知りたいという好奇心が学びの根本にあると思います。」
ファシリテーター:「今回は学校教育に焦点を当てて考えたいので、あえて学びとは区別して「勉強」をテーマにしました。」
「ある先生から聞いた話ですが、病院の中にある院内学校の子どもたちは長く生きられないことを運命づけられていて、本人たちもそれは覚悟しているにもかかわらず、その子たちが一生懸命勉強するそうですす。その子たちは自分の将来が短いとわかっているに関わらず、一生懸命していると聞くと、どこか将来のために勉強をするというのとは違うのではないかと感じます。」
「学ぶと勉強は対立させなくてもいいのではないでしょうか。勉強はその時が楽しいということがあります。知らないことを知る、できないことができるようになるというのはとても面白い経験です。けれど、自分の子どもが小学校に入学したときに、自分が子どもの頃に習った学習内容とほとんど同じだったことにショックを受けました。それで、これくらいなら私でも教えられると思い、子どもたちには学校に行きたくなかったらいかなくていいよと言ったことがあります。福島に来た頃はシュタイナー教育やモンテッソーリ教育を知り、そちらに行かせたいとも考えたこともあるが、とにかく学校での学習内容の変わらなさにショックを受けたことがあります。」
「高校に勤務していますが、私は勉強しなくてもいいと思います。何で勉強を始めるのかというと勉強をしなさいと言うのは、まず親から言われるからだと思います。高校で進路を決めるときに、親は子どもの選択し拡げておいてあげたいという思いでそういうのだろうけれど、子どもにしてみれば親のために勉強しているという場合も多いのではないでしょうか。」
「塾講師をしていた時に勉強にそう感じたことがあります。子供たちは塾に勉強しに来ているのではなく、友達に会いに来ているのですね。教えていて感じたのは、小さいころは目をキラキラさせて勉強している子供たちが、年とともに目の輝きを失って勉強しているなということでした。」
「私は学校教育を終えてそんなに時間は経っていませんが、社会人になって強制して勉強する必要がなくなったけれど、だからといって勉強していないわけではありません。営業をやっている中で、学校では習わない知識が必要になります。いまは営業先の相手を知るために勉強するという意味になっています。もちろんその根底には生活のためにという目的はあるけれど、将来のためとか資格を取りたいという勉強ではないし、楽しい気持ちで勉強しているわけではありません。」
「そもそも勉強が何を指しているのかわかっていないのだけれど、何のために勉強するのかという問いは、何のために生きるのかという問いと同じくらい答えがない問いではないでしょうか。勉強も日々生きていく中で困難にぶつかって解決していることそのものが学ぶのであって、困難にぶつかってもどうでもいいというのは生きていないのと同じことだと思います。あえて答えるとすれば生きるために勉強するということになると思います。」
「カフェ冒頭で挙げられた「生徒にどういう人間になってほしいのか」という問いに関して、教師という立場で考えると、卒業生に会ったときに死んでいたり犯罪を犯していない限りOKだという自分がいます。とすると、生きているだけでOK だとすれば学校で教えることってほとんどないのではないかと思います。」
「それってニートの場合はどうなの?」
「本人が幸せだと思っていればいいのかなぁ…。まぁ、自立して生活できていないことには一概にOKとはいえないけれど…」
「埼玉で高校の教員しています。就職してもほとんどの卒業生がすぐに仕事を辞めてしまうような学校に勤めています。九九ができない子どもも大勢います。その中で知りたいという欲求があるからこそ勉強の教え甲斐もあるのですが、ただそれが自立につながるかと言うとよくわからないところがあります。教え子が就職できたと聴けば嬉しいと思うし。ただ、納税とか社会的な義務を果たしてもらえる人になってもらえればいいかな。最終的には自己実現かなと思うのですが。」
「私がいる職場も同じような学校です。最初の勉強のモチベーションは低いのだけれど、その子に合った勉強を教えると大学に行ってみたいとか、就職したいという子どもが出てきます。だから、その子にあった時間や速度があるので、それをうまくやれればその人なりの生き方が見つかるのだろうし、その時にはよかったねといえるのかな。でもニートの子に対してはどう言うのかと問われるとドキっとします。」
「中学校3年生の時に「死ぬ間際にあると仮定して、どんな人生だったか」というテーマで作文を書けと言う課題があったのですが、その時に思ったのが最終的にニートであろうが何だろうが、最期の瞬間にに「いい人生だった」と思えれば、それでいいのではないかと思うのです。娘が高校を選ぶとき実力以下の高校に進学したいといった、親心で自分の学力に合ったところに行ったらと勧めると、娘はその学校で思いっきり高校生活を送りたいと言い、卒業した時によかったと言いました。多分、めいいっぱい騒いだり、さぼったり、地べたに座り込んだりしてもいいのだ、と自分を解放するエネルギーを同級生からもらって、落ちこぼれという感覚もなくイキイキと通学できたことはよかったなと思いました。」
ファシリテーター:「これまでの議論をふり返ると、皆さんの話は「学ぶ」ということと「勉強」が重なっているところがあります。いったん、「勉強」を学校の教育課程で教科に分かれてやるものだと規定してみると議論が整理できるのではないでしょうか。」
「このテーマを提案させてもらった者です。自分の息子が高校1年生の段階で文系理系を分けられることにびっくりして、数学も理科も勉強しないことで一人前の人間になれるのかなという心配があったことがきっかけで提案させていただきました。息子の通う学校は音楽科と普通科に分かれているのですが、校長先生は入学当初から「〇〇大学には何人入った」等の話しかしません。私はすべての教科を勉強することが学びだと思っているのだけれど、ほんとうに子供が息つく間もなく勉強しろという学校の在り方に驚いたし、そのような中で文系理系に分けられて勉強する教科が偏ってしまっていいのかと疑問に思います。音楽も数学も文学もすべてが融合してこそ学びだと思うのですが。」
「中学高校は主要5教科と技能4教科に分かれていたり、その「主要」という言い方がどうかと思うですが、さらに高校の体育教員はその専門競技しか知らない人が多く、それってどうなのかと思っていたことがあります。」
「私は理系文系と分けることには肯定的です。生きるために勉強するという方がいましたが、今は社会が複雑すぎてその分野を自分で選んでいくことが必然になってくると思う。もっと文系理系がフレキシブルに交流することは必要だけれど、基本的に専門分野に細分化せざるを得ないのではないでしょうか。」
「でも、将来を考えさせるという点では、高校1年生の段階で選ばせることは早いのではないでしょうか。色々な可能性を早い段階で切ってしまうのはもったいない気がします。その先に柔軟性がある制度があればいいんだけれど、日本は社会的に整備されていないのではないでしょうか。」
「高校教員です。まさに1年生の段階で文系理系を分けている側です。たしかに自分で選択することを先延ばしにすることも大切ですが、意外と人間は「お前は何だ」と選択を迫られることで、はじめて人生が決まりだすという側面があるのではないでしょうか。」
「高校1年生で文系理系に分けられる問題以前に、高校入試段階で工業高校や商業高校などの選択する問題をどう考えますか?つまり、中学生の段階で自分の専門性を選択させられる子どもたちがいるわけですが、その子たちが主体的に専門性を選んでいるとは言えないでしょう。ドイツなんてもっと早い段階で人生の階級や階層の選択が迫られますし。どの専門性を選ぶのかという時期の決定は、実はその社会がどのようなしくみを選択するのかという議論と関係していると思います。」
「これまでの議論では、学校の勉強に関して知識理解の話が多い気がするけれど、文科省だって知識理解だけが学習ではないとも言っています。とはいえ、いくらそういうふうに親方日の丸の方がそう叫んでも、最終的に現場では知識理解に比重が置かれています。人の評価の仕方が変わっていかないと根本的には難しいのかなと思いました。」
「僕もそれはずっと感じていたことです。進学校の勉強は先送りの勉強だと思っていて、とにかく思考力とか何かというのは大学でやればいいから、とりあえず大学受験に合格させることが勉強の目標になってしまう。そもそも実際に思考力を問うテストなんて、相当作るのが難しい。だから、客観的に測定できるセンター試験が重視されるわけだけれど、それによって学びと勉強のかい離が大きくなっている気がします。」
「勉強って、やはり外から強制されてするものだと思います。僕は剣道をずっとやってきたから、無味乾燥な基本練習をなぜしなければならないのかなんて、本人はわけわかっていないにもかかわらずそれを強制されて練習するわけです。すると、後々それがとても大切なことだと気づかされます。勉強も本来そういう側面があって、本人はなぜ勉強しなければならないのかなんて意味を知る必要がないと思います。が、しかし、事受験勉強になると鬼のような宿題と授業時間を強制されて考える間もなく疲弊している進学校の生徒の話を聞くと、それが剣道でいう基礎練習の意味とは異なっている気がします。本来、勉強だって大学に入ってから必要な基礎知識を身に着けるという意味があったはずだと思いますが、高校時代に勉強したことが意味をもつ経験がない点が最大の問題ではないでしょうか。」
「勉強がすぐに役に立つというのは無意味だけれど、それが自分の人生にどのような意味を持つのかという出会わせ方は大事だと思います。その出会わせ方が決定的になさすぎるのが問題でしょう。」
「財界や体制側にとって、国民に思考力をつけてもらっては困るという側面があるのではないでしょうか。経済優先によって教育のことがなおざりにされていることが根本問題ではないでしょうか。」
「それの意見には修正が必要です。実は、財界もまたグローバル化の中で勝ち残らなければならないから、思考力をつけてもらうことを求めているところがあるからです。ただし、それはダブルスタンダードで、その力をつけてもらう層は全体のごくわずかでよくて、残りの大多数は非正規雇用のように落ちこぼれが必要だと考えているところがあります。」
「わずかのエリート層を強化しようという、その発想は高度経済成長期の頃からマンパワーポリシーとして掲げられていますね。つまり、企業や政府側が求める思考力と、人生をよく生きるという意味での思考力というのは意味がまったく異なるわけですが、前者の方ばかりが社会的には強調されるのは当たり前と言えば当たりませですが、それを必要とする相はごくわずかでしょう。それに関して、底辺校に勤務していた時に同僚に、自分で考える力をつけさせるために授業を工夫していると、社会に適応するだけで精いっぱいの子どもにとってそれは無意味どころか、彼らを不幸にするだけじゃないかと指摘されたことがあります。そのことは今でも考え続けて授業づくりをしているわけですが。」
「たしかに考える強制から降りる自由は必要でしょう。そうであるにもかかわらず、自分で考えることで批判的に物事を考えたりできる人間を育てたいという理想は持ち続けたいと思っています。」
「個人的には革命は起こらない方がいいなと思っていながら、革命が必要だと思える人も必要だと思っています。適応させる躾のような教育も大事だけれど、幅は広い方がいいのかなと思います。個人的に数学は苦手でしたが、『博士の愛した数式』を読んだときには数学はやるべきだと思いました。理系の教え子にも、ボタンを押してミサイルで人を殺してしまうということをどう考えられるのかという人になってもらいたいし。その意味で、とにかく色々な知識にふれて幅を広げるという意味での学校の勉強は必要だと思います。」
「山で生きていける力があり生物として生きることができれば勉強しなくてもよいと思いますが、この社会で生きていくしかないのであれば、その社会のシステムで生きていく勉強をせざるを得ないでしょう。大学受験はその点で生きる力を身につけるということになるのではないでしょうか。」
「幅があった方がいいというのはその通りだと思うし、武道の修練で意味が分からずに基本練習をするということもその通りだと思いました。ただ、大人になって何に役に立つかという説明がない中で無意味にやらされるから、生徒は「なんで勉強するの?」という問いが立ち上がってしまうのだと思います。「いまはわからないと思うけれど将来意味が分かる」という言い方では、生徒はやはり納得しないものです。その点で、やはり「なぜ勉強するのか」という答えは現場の教師としては欲しいところです。説得に成功することはほとんどないのですが。」
「大学受験の勉強って、大学に入ってから消耗するだけの勉強になっていないでしょうか。学生の姿を見ているととにかく疲れ切って、学ぼうとする余力も残されていない感じがします。そんなに疲れ切っていても、おそらく受験生に勉強は必要だと答えるのだと思いますが、どこか違和感があります。」
「それは社会に言わされているのではないでしょうか?」
「勉強はしたくないけれど、高卒の資格必要だからと答えている高校生は多いですし、大学受験勉強もそのレベルでいわされていると言えば言わされているかもしれません。」
「80歳ですが、勉強するということよりも今は学びたいと思うことが多く、あまりそれは線引きできないと思います。いまは法律をとにかく勉強したいと思っているのだけれど、日本の教育制度は社会人になってから勉強できる環境がなさ過ぎます。なぜ勉強したいのと聞かれれば、学ぶ「まねぶ」であり、子どもの頃はこれを学ばなければならないという理屈はなかったけれど、自然の中で遊ぶしかなかった子供のころの経験が今の判断力や思考力の基礎になっていると、いまになってその時の遊びで学んだことが生きているような気がしています。親から勉強させられたという気がするけれど、それ以前に勉強したくても学校に行けなかった、選択すらできなかった時代があったということを知ってほしいと思います。親の手伝いしかさせられなかった時代があったということを。今に政治的無関心は勉強することと背中合わせではないか。幅をもつということはハンドルの遊びと共通する。関心をもち勉強することが必要だと思います。」
今回は教育関係者の参加と発言が多かったですが、この議論はさらに深められそうですね。
また次回、大勢の方々にご参加いただけることを楽しみにしております。
雰囲気のよい日本家屋と庭園に22名の方にお越しいただき、「何のために勉強するのか?」というテーマで話し合いが始められました。




「私は教員ですが、何のために勉強するのかという問いを生徒から受けることはよくあります。こういう問いは勉強に対するモチベーションの低い生徒から出されることが多いと思います。これはモチベーションの問題ではないでしょうか。」
「たしかにこの問いはやってもできない子たち、学校教育の目指す将来像と異なった子どもたちから発せられるように思います。でもそういう子たちも、例えばパソコンがよくできたり、車についてめちゃくちゃ詳しかったりして、自分なりの将来を築いていくことができます。学校とは別の路線があるのだから、勉強なんかできなくてもいいんじゃないでしょうか。」
「今日は学校の先生が何人かおられるようなのでお聞きしたいのですが、学校教員としては生徒にどうなってほしいと考えているのでしょうか。」
「私は教員で今日の問いも20人に聞かれたら20通り、いろいろな答え方があるのですが、今の質問に答えるなら、ちゃんとした大人になってほしいということでしょうか。一人一人が自分の人生を送れるようになってほしいと思っています。」
「『ちゃんとした』 って言っちゃうとある一定の枠があるように聞こえてあまり好きではありませんが、いろいろな路線、判断できるいろいろなモデルを学び、たくさんのモデルから自分の道を選べるようになるのが学ぶ意味ではないでしょうか。」
「私も学校現場に勤めていましたが、生徒には自分の選択肢を広げるためにとりあえずやっとけと言います。勉強は学校で強制されるという意味がある。それに対して学ぶというのは、目的や好奇心、自分の欲求、本能として学ぶという意味でしょう。生まれてしまった以上、人生の目的を考えると自殺してしまう人もいるように、何で学ぶのかと考えるとそれには答えがなく困ってしまうのではないでしょうか。あえて答えるならば、知りたいという好奇心が学びの根本にあると思います。」
ファシリテーター:「今回は学校教育に焦点を当てて考えたいので、あえて学びとは区別して「勉強」をテーマにしました。」
「ある先生から聞いた話ですが、病院の中にある院内学校の子どもたちは長く生きられないことを運命づけられていて、本人たちもそれは覚悟しているにもかかわらず、その子たちが一生懸命勉強するそうですす。その子たちは自分の将来が短いとわかっているに関わらず、一生懸命していると聞くと、どこか将来のために勉強をするというのとは違うのではないかと感じます。」
「学ぶと勉強は対立させなくてもいいのではないでしょうか。勉強はその時が楽しいということがあります。知らないことを知る、できないことができるようになるというのはとても面白い経験です。けれど、自分の子どもが小学校に入学したときに、自分が子どもの頃に習った学習内容とほとんど同じだったことにショックを受けました。それで、これくらいなら私でも教えられると思い、子どもたちには学校に行きたくなかったらいかなくていいよと言ったことがあります。福島に来た頃はシュタイナー教育やモンテッソーリ教育を知り、そちらに行かせたいとも考えたこともあるが、とにかく学校での学習内容の変わらなさにショックを受けたことがあります。」
「高校に勤務していますが、私は勉強しなくてもいいと思います。何で勉強を始めるのかというと勉強をしなさいと言うのは、まず親から言われるからだと思います。高校で進路を決めるときに、親は子どもの選択し拡げておいてあげたいという思いでそういうのだろうけれど、子どもにしてみれば親のために勉強しているという場合も多いのではないでしょうか。」
「塾講師をしていた時に勉強にそう感じたことがあります。子供たちは塾に勉強しに来ているのではなく、友達に会いに来ているのですね。教えていて感じたのは、小さいころは目をキラキラさせて勉強している子供たちが、年とともに目の輝きを失って勉強しているなということでした。」
「私は学校教育を終えてそんなに時間は経っていませんが、社会人になって強制して勉強する必要がなくなったけれど、だからといって勉強していないわけではありません。営業をやっている中で、学校では習わない知識が必要になります。いまは営業先の相手を知るために勉強するという意味になっています。もちろんその根底には生活のためにという目的はあるけれど、将来のためとか資格を取りたいという勉強ではないし、楽しい気持ちで勉強しているわけではありません。」
「そもそも勉強が何を指しているのかわかっていないのだけれど、何のために勉強するのかという問いは、何のために生きるのかという問いと同じくらい答えがない問いではないでしょうか。勉強も日々生きていく中で困難にぶつかって解決していることそのものが学ぶのであって、困難にぶつかってもどうでもいいというのは生きていないのと同じことだと思います。あえて答えるとすれば生きるために勉強するということになると思います。」
「カフェ冒頭で挙げられた「生徒にどういう人間になってほしいのか」という問いに関して、教師という立場で考えると、卒業生に会ったときに死んでいたり犯罪を犯していない限りOKだという自分がいます。とすると、生きているだけでOK だとすれば学校で教えることってほとんどないのではないかと思います。」
「それってニートの場合はどうなの?」
「本人が幸せだと思っていればいいのかなぁ…。まぁ、自立して生活できていないことには一概にOKとはいえないけれど…」
「埼玉で高校の教員しています。就職してもほとんどの卒業生がすぐに仕事を辞めてしまうような学校に勤めています。九九ができない子どもも大勢います。その中で知りたいという欲求があるからこそ勉強の教え甲斐もあるのですが、ただそれが自立につながるかと言うとよくわからないところがあります。教え子が就職できたと聴けば嬉しいと思うし。ただ、納税とか社会的な義務を果たしてもらえる人になってもらえればいいかな。最終的には自己実現かなと思うのですが。」
「私がいる職場も同じような学校です。最初の勉強のモチベーションは低いのだけれど、その子に合った勉強を教えると大学に行ってみたいとか、就職したいという子どもが出てきます。だから、その子にあった時間や速度があるので、それをうまくやれればその人なりの生き方が見つかるのだろうし、その時にはよかったねといえるのかな。でもニートの子に対してはどう言うのかと問われるとドキっとします。」
「中学校3年生の時に「死ぬ間際にあると仮定して、どんな人生だったか」というテーマで作文を書けと言う課題があったのですが、その時に思ったのが最終的にニートであろうが何だろうが、最期の瞬間にに「いい人生だった」と思えれば、それでいいのではないかと思うのです。娘が高校を選ぶとき実力以下の高校に進学したいといった、親心で自分の学力に合ったところに行ったらと勧めると、娘はその学校で思いっきり高校生活を送りたいと言い、卒業した時によかったと言いました。多分、めいいっぱい騒いだり、さぼったり、地べたに座り込んだりしてもいいのだ、と自分を解放するエネルギーを同級生からもらって、落ちこぼれという感覚もなくイキイキと通学できたことはよかったなと思いました。」
ファシリテーター:「これまでの議論をふり返ると、皆さんの話は「学ぶ」ということと「勉強」が重なっているところがあります。いったん、「勉強」を学校の教育課程で教科に分かれてやるものだと規定してみると議論が整理できるのではないでしょうか。」
「このテーマを提案させてもらった者です。自分の息子が高校1年生の段階で文系理系を分けられることにびっくりして、数学も理科も勉強しないことで一人前の人間になれるのかなという心配があったことがきっかけで提案させていただきました。息子の通う学校は音楽科と普通科に分かれているのですが、校長先生は入学当初から「〇〇大学には何人入った」等の話しかしません。私はすべての教科を勉強することが学びだと思っているのだけれど、ほんとうに子供が息つく間もなく勉強しろという学校の在り方に驚いたし、そのような中で文系理系に分けられて勉強する教科が偏ってしまっていいのかと疑問に思います。音楽も数学も文学もすべてが融合してこそ学びだと思うのですが。」
「中学高校は主要5教科と技能4教科に分かれていたり、その「主要」という言い方がどうかと思うですが、さらに高校の体育教員はその専門競技しか知らない人が多く、それってどうなのかと思っていたことがあります。」
「私は理系文系と分けることには肯定的です。生きるために勉強するという方がいましたが、今は社会が複雑すぎてその分野を自分で選んでいくことが必然になってくると思う。もっと文系理系がフレキシブルに交流することは必要だけれど、基本的に専門分野に細分化せざるを得ないのではないでしょうか。」
「でも、将来を考えさせるという点では、高校1年生の段階で選ばせることは早いのではないでしょうか。色々な可能性を早い段階で切ってしまうのはもったいない気がします。その先に柔軟性がある制度があればいいんだけれど、日本は社会的に整備されていないのではないでしょうか。」
「高校教員です。まさに1年生の段階で文系理系を分けている側です。たしかに自分で選択することを先延ばしにすることも大切ですが、意外と人間は「お前は何だ」と選択を迫られることで、はじめて人生が決まりだすという側面があるのではないでしょうか。」
「高校1年生で文系理系に分けられる問題以前に、高校入試段階で工業高校や商業高校などの選択する問題をどう考えますか?つまり、中学生の段階で自分の専門性を選択させられる子どもたちがいるわけですが、その子たちが主体的に専門性を選んでいるとは言えないでしょう。ドイツなんてもっと早い段階で人生の階級や階層の選択が迫られますし。どの専門性を選ぶのかという時期の決定は、実はその社会がどのようなしくみを選択するのかという議論と関係していると思います。」
「これまでの議論では、学校の勉強に関して知識理解の話が多い気がするけれど、文科省だって知識理解だけが学習ではないとも言っています。とはいえ、いくらそういうふうに親方日の丸の方がそう叫んでも、最終的に現場では知識理解に比重が置かれています。人の評価の仕方が変わっていかないと根本的には難しいのかなと思いました。」
「僕もそれはずっと感じていたことです。進学校の勉強は先送りの勉強だと思っていて、とにかく思考力とか何かというのは大学でやればいいから、とりあえず大学受験に合格させることが勉強の目標になってしまう。そもそも実際に思考力を問うテストなんて、相当作るのが難しい。だから、客観的に測定できるセンター試験が重視されるわけだけれど、それによって学びと勉強のかい離が大きくなっている気がします。」
「勉強って、やはり外から強制されてするものだと思います。僕は剣道をずっとやってきたから、無味乾燥な基本練習をなぜしなければならないのかなんて、本人はわけわかっていないにもかかわらずそれを強制されて練習するわけです。すると、後々それがとても大切なことだと気づかされます。勉強も本来そういう側面があって、本人はなぜ勉強しなければならないのかなんて意味を知る必要がないと思います。が、しかし、事受験勉強になると鬼のような宿題と授業時間を強制されて考える間もなく疲弊している進学校の生徒の話を聞くと、それが剣道でいう基礎練習の意味とは異なっている気がします。本来、勉強だって大学に入ってから必要な基礎知識を身に着けるという意味があったはずだと思いますが、高校時代に勉強したことが意味をもつ経験がない点が最大の問題ではないでしょうか。」
「勉強がすぐに役に立つというのは無意味だけれど、それが自分の人生にどのような意味を持つのかという出会わせ方は大事だと思います。その出会わせ方が決定的になさすぎるのが問題でしょう。」
「財界や体制側にとって、国民に思考力をつけてもらっては困るという側面があるのではないでしょうか。経済優先によって教育のことがなおざりにされていることが根本問題ではないでしょうか。」
「それの意見には修正が必要です。実は、財界もまたグローバル化の中で勝ち残らなければならないから、思考力をつけてもらうことを求めているところがあるからです。ただし、それはダブルスタンダードで、その力をつけてもらう層は全体のごくわずかでよくて、残りの大多数は非正規雇用のように落ちこぼれが必要だと考えているところがあります。」
「わずかのエリート層を強化しようという、その発想は高度経済成長期の頃からマンパワーポリシーとして掲げられていますね。つまり、企業や政府側が求める思考力と、人生をよく生きるという意味での思考力というのは意味がまったく異なるわけですが、前者の方ばかりが社会的には強調されるのは当たり前と言えば当たりませですが、それを必要とする相はごくわずかでしょう。それに関して、底辺校に勤務していた時に同僚に、自分で考える力をつけさせるために授業を工夫していると、社会に適応するだけで精いっぱいの子どもにとってそれは無意味どころか、彼らを不幸にするだけじゃないかと指摘されたことがあります。そのことは今でも考え続けて授業づくりをしているわけですが。」
「たしかに考える強制から降りる自由は必要でしょう。そうであるにもかかわらず、自分で考えることで批判的に物事を考えたりできる人間を育てたいという理想は持ち続けたいと思っています。」
「個人的には革命は起こらない方がいいなと思っていながら、革命が必要だと思える人も必要だと思っています。適応させる躾のような教育も大事だけれど、幅は広い方がいいのかなと思います。個人的に数学は苦手でしたが、『博士の愛した数式』を読んだときには数学はやるべきだと思いました。理系の教え子にも、ボタンを押してミサイルで人を殺してしまうということをどう考えられるのかという人になってもらいたいし。その意味で、とにかく色々な知識にふれて幅を広げるという意味での学校の勉強は必要だと思います。」
「山で生きていける力があり生物として生きることができれば勉強しなくてもよいと思いますが、この社会で生きていくしかないのであれば、その社会のシステムで生きていく勉強をせざるを得ないでしょう。大学受験はその点で生きる力を身につけるということになるのではないでしょうか。」
「幅があった方がいいというのはその通りだと思うし、武道の修練で意味が分からずに基本練習をするということもその通りだと思いました。ただ、大人になって何に役に立つかという説明がない中で無意味にやらされるから、生徒は「なんで勉強するの?」という問いが立ち上がってしまうのだと思います。「いまはわからないと思うけれど将来意味が分かる」という言い方では、生徒はやはり納得しないものです。その点で、やはり「なぜ勉強するのか」という答えは現場の教師としては欲しいところです。説得に成功することはほとんどないのですが。」
「大学受験の勉強って、大学に入ってから消耗するだけの勉強になっていないでしょうか。学生の姿を見ているととにかく疲れ切って、学ぼうとする余力も残されていない感じがします。そんなに疲れ切っていても、おそらく受験生に勉強は必要だと答えるのだと思いますが、どこか違和感があります。」
「それは社会に言わされているのではないでしょうか?」
「勉強はしたくないけれど、高卒の資格必要だからと答えている高校生は多いですし、大学受験勉強もそのレベルでいわされていると言えば言わされているかもしれません。」
「80歳ですが、勉強するということよりも今は学びたいと思うことが多く、あまりそれは線引きできないと思います。いまは法律をとにかく勉強したいと思っているのだけれど、日本の教育制度は社会人になってから勉強できる環境がなさ過ぎます。なぜ勉強したいのと聞かれれば、学ぶ「まねぶ」であり、子どもの頃はこれを学ばなければならないという理屈はなかったけれど、自然の中で遊ぶしかなかった子供のころの経験が今の判断力や思考力の基礎になっていると、いまになってその時の遊びで学んだことが生きているような気がしています。親から勉強させられたという気がするけれど、それ以前に勉強したくても学校に行けなかった、選択すらできなかった時代があったということを知ってほしいと思います。親の手伝いしかさせられなかった時代があったということを。今に政治的無関心は勉強することと背中合わせではないか。幅をもつということはハンドルの遊びと共通する。関心をもち勉強することが必要だと思います。」
今回は教育関係者の参加と発言が多かったですが、この議論はさらに深められそうですね。
また次回、大勢の方々にご参加いただけることを楽しみにしております。