

第17回てつがくカフェ@ふくしまは、昨日アオウゼにて19名の参加者により開催されました。
今回は「脳死は人の死か?」というテーマで行われましたが、内容的にもかなり医学専門的な知識が必要とされましたので、まず冒頭で世話人の小野原から脳死-臓器移植に関する歴史や医学的、法律的情報について簡単な解説をさせていただきました。
これまでのてつがくカフェのテーマと比べても、やはり今回はかなり専門知識を前提にしないと議論がしにくかったため、おのずと小野原への質疑応答の時間も増えました。
とはいえ、議論は生死をめぐって活発に展開されました。
まずは、参加者の「何をもって死としてきたのだろう」という問いかけから始められます。
従来、死は心臓停止、瞳孔散大、自発呼吸停止によって医学的な判断でもって判定されてきました。
しかし、その医学的な基準ですら実はかなり主観的なものだったのではないかとの意見が出されます。
というのも、脳死の判定基準は国によってバラバラであり、国際的にも統一された基準がないからです。
したがって、ここいう「主観的」とは客観的な科学的基準というのではなく、社会的文化的な枠組みで決定される相対的なものではないかという意味においてのことでしょう。
日本では脳死判定の方法は厚生省基準(竹内基準)でもって行われますが、深昏睡、自発呼吸の停止、瞳孔散大、脳幹反射の消失、平坦脳波の確認後、6時間後に再検査することで不可逆的であるかどうかを調べますが、この「6時間」という時間も世界的に見ると日本が最短時間だということです。
もちろん、この「6時間」という基準も様々な症例をもとに医学的な決定がなされたのでしょうが、それが国ごとに異なるという意味においては、やはり「主観性」を免れないといえるかもしれません。
さらに、死を認定するという要素には、家族の感じ方も重要ではないかとの意見も出されました。
脳死は人工呼吸器をはずさない限り体温もあり、汗すらかき、見た目には死んでいないと感じるとも言われます。
そのような一見して死とは受け取れない脳死状態を、家族が割り切れるかという問題です。
すると、家族や身近な友人という立場によって死の認定は変わるということになります。
しかし、死に対する医学的判定以外にこうした文化的な要素を重視していくと、ミイラ化しても「その人は生きている」と家族が言い続ける限り死とは認められないのか、という問題が生じます。
この場合、通常は遺体遺棄罪で罰せられるでしょう。
脳死に関していえば、脳死状態で生まれてきた子どもを生命維持装置で心肺機能を維持していけば、身長も髪の毛も爪も伸び、身体的な成長がはっきり確認されますし、日本では実際にこうしたケースも存在します。
そうした成長が確認できれば、ますます死を受容することなど難しくなるのではないでしょうか。
ここには死の受容について家族の生に対する執着や感情の割り切れなさという問題が指摘されます。
なるほど、死を受容する理論は誰しも一応は持ちうるものです。
たとえば、輪廻転生や来世という宗教思想はそれに応えるものでしょう。
この死後の物語化を通じて私たちは死に対する不安を払拭しようとするものですが、そうはいっても目の前で家族がまさに死なんとする場において、その理論と感情との鬩ぎ合いが存在するというわけです。
この意見を発言された方によれば、肉体は滅びても精神は永遠になくならないというのは宗教思想として存在しており、その理屈から言えば、ミイラ化した身体をなお生きていると認めるのは、即身仏にも見られる考え方ではないかといいます。
これらの意見を踏まえれば、家族あるいは宗教的立場からみて死の到達点は様々であり、決定的な死の地点などないのかもしれません。
それに対して客観的なデータを下にして判定されていると考えられてきた医学的死においても、脳死という段階にあっては、実は国ごとに異なるということからしても、どうも脳死における死を決定することは困難ではないかという視点が浮き彫りにされました。
とはいえ、そもそも従来、死の判定はそれほど難しいものではなかったでしょう。
これほど死の基準が混乱し始めた背景には、飛躍的な医療技術の進歩があることは否めません。
すると、「人間は永久に死ねない存在になるのではないか」という不安も提起されました。
ips細胞の進歩は、ひょっとすると無限に人間のサイボーグ化を実現化し、永遠の生命を実現するかもしれない。
SF的な発想かもしれませんが、しかし現実は数十年前の夢を実現してしまっています。
この創造も夢想とは言い切れないでしょう。
すると、どこかで死はどこで決めるかというタイミングを、自分で決める必要のある時代が来るのではないか(あるいはすでに来ているのかもしれません)。
その意味でもやはり社会的な死の基準を確定する必要はあるのではないかという意見も出されます。
たとえば、過激な意見ですが、それは人間100歳になったら死とする基準を法的に定めるなどの例などが挙げられました。
ただし、そこにはすべての人が永遠の生命を手に入れられるわけではなく、富める人間は臓器交換が自由にできるかもしれないけれど、貧しいものには金銭的に不可能であるという点で、生命の長短に貧富の格差が生じる問題を指摘する声も上がります。
いずれにせよ、議論では脳死の話題から死の不確定性の時代に入ったことが共有されました。
このことは一方で人間として生きるとは何かが問われる必要があります。
ある参加者によれば「幸せに生きているかどうか」が、人の生死の区分としてありうるのではないかと言います。
これはQOL(Quality Of Life)、つまり生命(生活、人生)の質という概念と密接です。
脳死状態が人間として生きるに値すると言えるかどうか。
これは「脳だけ生きていれば人間として生きているといえるのか?」という問いを生じさせました。
脳だけ生きていればということは、すなわちその人の記憶であり意識が存在することを意味しますが、それはその人のアイデンティティが存在するということに他なりません。
すると、その脳が外部情報を受信し、自分の意思を発信することが可能であれば、脳以外の身体がなくともその人は生きているということができるのではないか。
実際、、筋萎縮性の難病患者がアイコンタクトで意思表示が可能な機器も存在します。
将来的には脳波をキャッチするだけでそれが可能になる時代が来ることもありうるでしょう。
いやそうはいっても、人間は心と身体を切り離して存在することはできないのではないかという意見も出されます。
精神にのみ人間の存在の在り処を求めることは、いわゆる西洋的な心身二言論ともいえますが、これに対して身体にその人の存在を与えるという文化は、日本特有の文化といえるかもしれません。
その点で、脳死者の臓器が他者へ移植されることで、家族は本人が被移植者の中で生きていると思えるという話は、このことと無関係ではないでしょう
あるいは、脳死だけをもって人の死と判定するのではなく、やはり死の判定基準には心臓死も含むべきだという意見も出されます。
もちろん、脳死者の生命維持装置を外せば自ずと心臓は停止することになるわけでしょう。
しかし、その意見のように心臓死を重視する背景には、実は心臓のように自律神経によって自発的に生命維持の機能を司るということは、まさに生命が生へ向かって生を欲すことをもって、生は存在するという思想があるように思われました。
いわば、意識を超えてその人を生に向かわせる意志のようなものが、生の根源として重要なのではないかというものです。
倫理学的にいえばシュヴァイツァーや、あるいはショーペンハウアーの意志論の文脈に属す意見でしょう。
すると、脳死は人の死だというのは、単に意識や記憶、アイデンティティが存在しなくなるからだというわけではなく、自発的な生命機能が失われるという点が重要であることが確認されます。
その点で、意識は回復する可能性がほとんどない植物状態の患者を死とは認めないのも理解できるでしょう(植物状態の患者は自発呼吸などの機能は失われません)。
とはいえ、いずれにせよ脳死が生命維持装置によって身体機能を維持しているという点では、「周囲に生かされている」ことになります。
言い換えれば、
それを死と受け入れられない家族にとっては、生命維持装置を外すということは、脳死者本人を死に至らしめる決定権を与えられていると錯覚してもおかしくはないでしょう。
中には、家族の死は家族で決めてあげたいという意見も上げられましたが、そのプレッシャーや罪悪感に耐えられるほどの人はどれだけいるのでしょうか。
すると、やはり死の定義は社会的に決められなければならないものだという意見が出されます。
容易に死を受容できない脳死者の遺族にとって区切りを受けさせられるものは、やはり社会的な死の判定であるということになります。
それは、たとえ医学的科学的であろうと、死とは常に社会学的なものではなかったかという意見も上げられました。
脳死の受容の仕方は既に見たとおり、立場や国によってさえも様々なものです。
そうであるからこそ、その判定は法律でつけられるべきだというわけです。
そもそも死は法律で判定されるものではなかったし、それは医師による判定に任されていたものですが、日本では「和田移植事件」以来の医療不信がこうした法的判定の必然性を招いたという話題にも触れられました。
今回のテーマは「脳死は人の死か?」というものでしたが、議論を振り返ってみると、死の判定と受容、あるいは人間的な生についての議論が大半を占めたように思われます。
脳死そのものが生まれた背景には、繰り返すように医療技術の進歩がありますが、これだけ死の判定が複雑になってしまったのは同時に、現代社会に生きる人々が「自然な死」を迎えられなくなっている事態を示しています。
その点で自然な死とは何か、果たしてありうるのか別の機会に話し合ってみたいと思いました。
さて、次回は8月24日(土)にサイトウ洋食店にて、初の試みである「哲学書deカフェ」を企画します。
これは哲学書を読みあうことで対話を試みるカフェです。
一冊の本を読んできて語り合う本deカフェは、既に5回開催していますが、それとは別にあえて本格的な哲学書をてつがくカフェで扱ってみようという実験的な試みです。
課題図書は、ルネ・デカルトの『省察』第1章・第2章です。
今回の脳死の問題とも関係する一冊ですし、哲学書とはいえ、わりと読みやすい文体ですし、相変わらず専門的な哲学議論を交わすことを目指すわけではないので、多くの方々にお気軽にご参加いただければ幸いです。










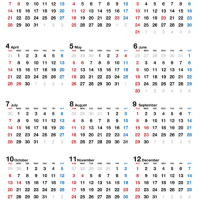









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます