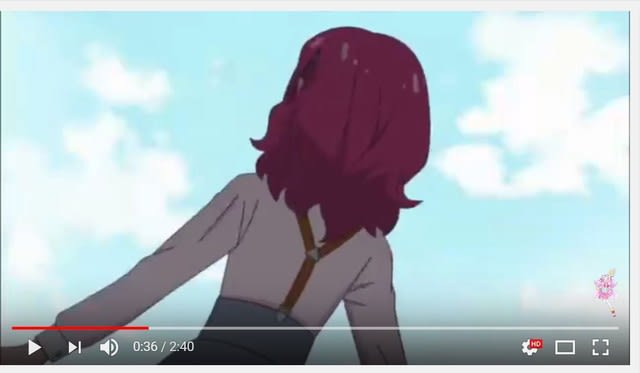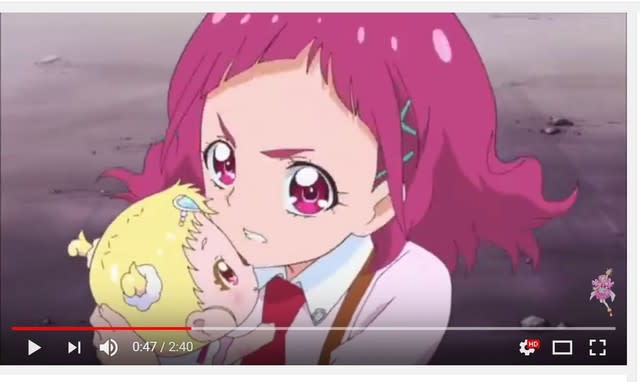最終話、ビデオに録ったのを2回見たけど、難しかったね。タイム・パラドックスにパラレルワールドでしょう。まあ、この両者はたいていセットになってるもんだけど。ああいうの苦手でねえ……。とくに本作のばあい、作り手(坪田文さん)がどこまできちんと設計図を引いているのか判然としなくて、よけいにモヤモヤしたですよ。
ぼくが理解したかぎりでは、「ルールーたちが帰っていった未来」と「成長したはな社長たちの迎えた未来」とは別個のものですね。うん。さすがにそこは間違いないでしょう。
でもって、
①あの荒野みたいなところ(例の黄色い花だけは咲いてたようですが)をひとり彷徨っていたジョージ・クライと、
②はな社長の出産シーンで、タワーの上にいたハリー(人間態)と、あとあの人、キュアトゥモローさんでしたっけ、はぐたんの成長した姿、というか元に戻った姿の女性、
この3人は、少なくとも、「成長したはな社長たちのいる2030年現在」には居ないんですよね。
まず、ジョージ・クライのいる時間軸というか世界線というか、それがいつなのか、どこなのか、これがどうにもわからない。「ルールーたちが帰っていった未来」と見ていいんかい?と。それだったら、「止まっていた時間が動き出した」んだから、そっちの未来も変わったってことになるしね。
キュアトゥモローと人間態ハリーがいるのは、たぶん、はな社長たちのいる2030年の延長線上だと思う。キュアトゥモローは、成長したはぐたん、本名はぐみさんのことだから、やっぱり、はな社長の娘さんだった。でも、でもですよ、その人がプリキュアさんになって戦ってるっていうんなら、結局それって、未来は暗いんだぞってことになりませんかね。違うのかな。
そのばあい、そもそもキュアトゥモローさん、誰と戦ってるんですかね。もし敵がいるとしたら、ジョージ・クライ以外には考えにくいけど。
はなの出産を見舞うべく、はなの両親と共に(黄色い花の束をもって)病院に向かっていた青年(?)は若き日のジョージ・クライ(ほかに本名があるのかもしれないけど)でしょう。つまり、はなのパートナーは大方の予想どおりジョージ氏だった。
けど、だったらトゥモローさん、実父と戦ってた/戦うわけですよね。なんで?
そもそも、「ルールーたちが帰っていった未来(ないし世界)」と「成長したはな社長たちの迎えた未来(ないし世界)」とは、一体どの時点で分岐したんだろうか。
第1話の冒頭、「はなが自分で前髪を切った」時にもう分岐してたって話をネットで見たんですよね。47話か48話かその前だったか忘れたけど、ジョージ社長が(おそらく夭折した)パートナーであるはなの写真(遺影)を見ていて、その写真のはな(成長した姿)は、ふつうの前髪だったんで。
それでもって、この1年かけてずっとやってきたストーリーがあって、この最終話で2030年になって、その2030年はずいぶん楽しそうに、希望に満ちて描かれてたけど、でもその時間軸の延長線上にキュアトゥモローさんがいるのであれば(しかもそれで実父と戦ってるのであれば)、そういうの一切合切、「何だったの?」ってことになっちゃわないですか。違うのかな。違うとは思いたいけど。
だったら、あそこでキュアトゥモローさんがプリキュアのコスチュームじゃなく、なんか私服で描かれてたならよかったのかな? だけどそれでは絵にならんしな。誰この子? みたいなことにもなりかねんしな。それならあれか、べつに戦ってるわけじゃないけど、もう世界は平和なんだけど、たんにビジュアル的な配慮でプリキュアさんの衣装になってただけか。そう考えればよろしいか?
いや、ほんとに難しいなこれ。
あと、なんか『ドラえもん』の都市伝説版・最終話(本物かと見まがうようなオマージュ作品あり)みたいなことになってたえみる、ルールー、トラウムさん側のエピソードもね……。これもまた、(ドラえもんと同じく)考えだしたらタイム・パラドックスの泥沼で、もうアタマが痛くてムリですね。
ほんとは『HUGっと!プリキュア』全体の総括をするつもりだったんだけど、最終話があまりに難しすぎて、だめですね。理解できないのに総括はできません。ただ、こうやって理詰めで考えるのではなく、情動だけで見ているぶんには、それなりに泣けて、心もあたたまる良い最終話でした。
いちおう、メモとして、ぼくが本作をみて思い浮かべた先行作品をリストアップします。
まず過去のプリキュアシリーズ。これは言わずもがな。
ほかに、
『風の谷のナウシカ』(アニメ版ではなく原作のほう)
『新世紀エヴァンゲリオン』
『時をかける少女』(2006年度のアニメ版。思えばあれもマッドハウス制作だったなあ)
『アトム・ザ・ビギニング』
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
『ドラえもん のび太と鉄人兵団』などなど。
とにかく、よかれあしかれボリューム満点の作品でした。はっきり言えば、盛りすぎ。それは間違いないですね。
追記) 3日経ってから思いついたけど、①彷徨っているジョージ・クライ、②タワーの上にいる人間態ハリーとキュアトゥモロー、この3人が「ルールーたちが帰っていった未来(世界)」にいる、という可能性はありますね。そう考えればいちばん整合性がとれるかもしれない。ただ、46話からもう一度ちゃんと見返さないと確かなことはいえない。しばらくは暇がないのでムリだけど、できればもう少し詰めたいとこですね。
ぼくが理解したかぎりでは、「ルールーたちが帰っていった未来」と「成長したはな社長たちの迎えた未来」とは別個のものですね。うん。さすがにそこは間違いないでしょう。
でもって、
①あの荒野みたいなところ(例の黄色い花だけは咲いてたようですが)をひとり彷徨っていたジョージ・クライと、
②はな社長の出産シーンで、タワーの上にいたハリー(人間態)と、あとあの人、キュアトゥモローさんでしたっけ、はぐたんの成長した姿、というか元に戻った姿の女性、
この3人は、少なくとも、「成長したはな社長たちのいる2030年現在」には居ないんですよね。
まず、ジョージ・クライのいる時間軸というか世界線というか、それがいつなのか、どこなのか、これがどうにもわからない。「ルールーたちが帰っていった未来」と見ていいんかい?と。それだったら、「止まっていた時間が動き出した」んだから、そっちの未来も変わったってことになるしね。
キュアトゥモローと人間態ハリーがいるのは、たぶん、はな社長たちのいる2030年の延長線上だと思う。キュアトゥモローは、成長したはぐたん、本名はぐみさんのことだから、やっぱり、はな社長の娘さんだった。でも、でもですよ、その人がプリキュアさんになって戦ってるっていうんなら、結局それって、未来は暗いんだぞってことになりませんかね。違うのかな。
そのばあい、そもそもキュアトゥモローさん、誰と戦ってるんですかね。もし敵がいるとしたら、ジョージ・クライ以外には考えにくいけど。
はなの出産を見舞うべく、はなの両親と共に(黄色い花の束をもって)病院に向かっていた青年(?)は若き日のジョージ・クライ(ほかに本名があるのかもしれないけど)でしょう。つまり、はなのパートナーは大方の予想どおりジョージ氏だった。
けど、だったらトゥモローさん、実父と戦ってた/戦うわけですよね。なんで?
そもそも、「ルールーたちが帰っていった未来(ないし世界)」と「成長したはな社長たちの迎えた未来(ないし世界)」とは、一体どの時点で分岐したんだろうか。
第1話の冒頭、「はなが自分で前髪を切った」時にもう分岐してたって話をネットで見たんですよね。47話か48話かその前だったか忘れたけど、ジョージ社長が(おそらく夭折した)パートナーであるはなの写真(遺影)を見ていて、その写真のはな(成長した姿)は、ふつうの前髪だったんで。
それでもって、この1年かけてずっとやってきたストーリーがあって、この最終話で2030年になって、その2030年はずいぶん楽しそうに、希望に満ちて描かれてたけど、でもその時間軸の延長線上にキュアトゥモローさんがいるのであれば(しかもそれで実父と戦ってるのであれば)、そういうの一切合切、「何だったの?」ってことになっちゃわないですか。違うのかな。違うとは思いたいけど。
だったら、あそこでキュアトゥモローさんがプリキュアのコスチュームじゃなく、なんか私服で描かれてたならよかったのかな? だけどそれでは絵にならんしな。誰この子? みたいなことにもなりかねんしな。それならあれか、べつに戦ってるわけじゃないけど、もう世界は平和なんだけど、たんにビジュアル的な配慮でプリキュアさんの衣装になってただけか。そう考えればよろしいか?
いや、ほんとに難しいなこれ。
あと、なんか『ドラえもん』の都市伝説版・最終話(本物かと見まがうようなオマージュ作品あり)みたいなことになってたえみる、ルールー、トラウムさん側のエピソードもね……。これもまた、(ドラえもんと同じく)考えだしたらタイム・パラドックスの泥沼で、もうアタマが痛くてムリですね。
ほんとは『HUGっと!プリキュア』全体の総括をするつもりだったんだけど、最終話があまりに難しすぎて、だめですね。理解できないのに総括はできません。ただ、こうやって理詰めで考えるのではなく、情動だけで見ているぶんには、それなりに泣けて、心もあたたまる良い最終話でした。
いちおう、メモとして、ぼくが本作をみて思い浮かべた先行作品をリストアップします。
まず過去のプリキュアシリーズ。これは言わずもがな。
ほかに、
『風の谷のナウシカ』(アニメ版ではなく原作のほう)
『新世紀エヴァンゲリオン』
『時をかける少女』(2006年度のアニメ版。思えばあれもマッドハウス制作だったなあ)
『アトム・ザ・ビギニング』
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
『ドラえもん のび太と鉄人兵団』などなど。
とにかく、よかれあしかれボリューム満点の作品でした。はっきり言えば、盛りすぎ。それは間違いないですね。
追記) 3日経ってから思いついたけど、①彷徨っているジョージ・クライ、②タワーの上にいる人間態ハリーとキュアトゥモロー、この3人が「ルールーたちが帰っていった未来(世界)」にいる、という可能性はありますね。そう考えればいちばん整合性がとれるかもしれない。ただ、46話からもう一度ちゃんと見返さないと確かなことはいえない。しばらくは暇がないのでムリだけど、できればもう少し詰めたいとこですね。