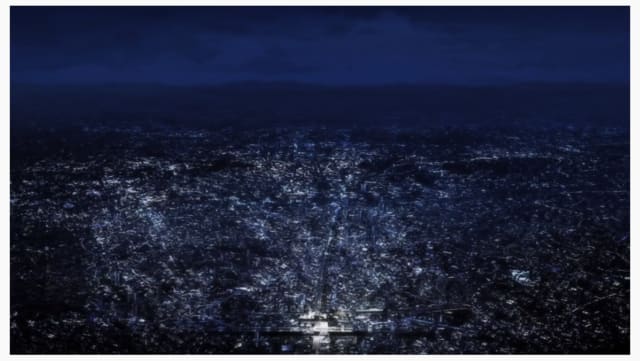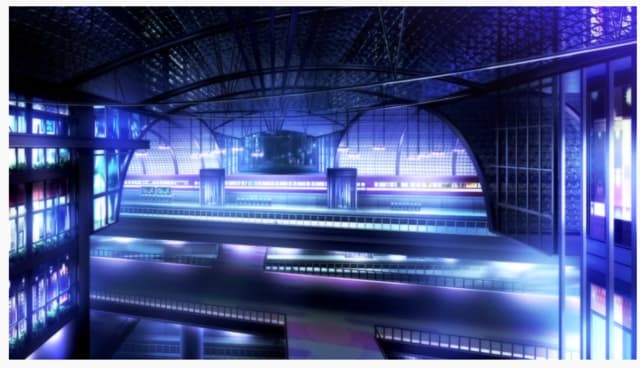何だかんだで、歴代シリーズの系譜まで絡めて「スタプリ」全体の紹介をしてしまった。この手の話は作品をよく見ている層には面倒くさがられるだけだし、見てない層にはまったくもってどうでもいいし、書いても何の得にもならないのだが、やるからにはきちんとやらねば気のすまぬ性分だから仕方がない。日本語を解する人の中には、「誰もが知ってる手近な素材を片っ端からどんどん使って物語の成熟の過程を考察する。」というぼくの趣旨を理解してくれる方も百人くらいはいるだろう。ネットの上に置かれていれば、いつの日か、何かのきっかけでそんな人たちの目にふれて刺激を与え、ひいては日本文化の質的向上に寄与する可能性も皆無とはいえまい。そう信じて続けましょう。
今回は余談。「スタプリ」には好感をもっているけれど、ひとつ苦言を呈するのを忘れていた。異星人初のプリキュア・キュアミルキーとなったララの名乗り、「天にあまねくミルキーウェイ! キュアミルキー!」についてだ。この「あまねく」は誤用なのである。

じつはこの誤用には先蹤(せんしょう)があって、2016年の『魔法つかいプリキュア!』でも、3人めのプリキュアとなるキュアフェリーチェが「あまねく生命(いのち)に祝福を! キュアフェリーチェ!」との名乗りを上げていた。

2度まで重なるからには単なるミスではなく、スタッフのあいだに勘違いが行きわたってるのであろう。「あまねく」は、「遍く・普く・洽く」と書いて、「広々と。すべてにわたって」という意味の「副詞」なのである。これをあたかも「動詞」のように使っているから誤用なのだ。
動詞は「歩く。運ぶ。移す」のようにU音で終わる。「ひしめく」という似た意味の動詞があるせいで、「あまねく」も動詞と錯覚されやすいのだが、そうではない。たとえば「星々が夜空にあまねく。」なんて使い方はできない。副詞はそれ単独で「状態」をあらわす述語にはなりえないので、主語「星々」を受けることはできないのである。この場合だと、たとえば「星々が夜空いっぱいに広がっている。」とか「星々が夜空に満ち満ちている。」と言うべきところだ。
「星々が夜空にあまねく。」という文章については、さほど文法に詳しくなくても多くの人が違和感をおぼえるだろうが、しかし「夜空にあまねく星々」だったら良いんじゃないの、と感じる人はいるかもしれない。「あまねく」が名詞「星々」を修飾している格好で、これは「天にあまねくミルキーウェイ」「あまねく生命に祝福を」と同じことである。
だけどこれらも文法としては間違っている。なぜなら、副詞は名詞(ミルキーウェイや生命)を修飾できないからだ。副詞が修飾できるのは、動詞、形容詞、そして同じ副詞の3種だけである。どうしても名詞に懸けたいならば、村上春樹の『風の歌を聴け』の中の有名な一節、語り手の「僕」がミシュレの『魔女』からの引用として述べる「わたしの正義はあまりにあまねきため、というところがなんともいえず良い。」のように、「あまねき」と活用しなきゃいけない。
(ちなみはこれは魔女裁判官の台詞で、「自分の正義は絶対である。」という絶大な、より正しくは傲慢な自信を示している。この信念に基づいて、かつて数多くの無実の女性が命を散らしたのだった)。
今たまたま法華経の(漢訳からの)日本語訳を読んでいるので、そこから「あまねく」の正しい用例を引こう。
「(釈尊は)光を放って、東方にある無数の諸仏の世界をあまねく照らされました。」
「願わくは、此の功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道を成ぜん。」
「十方界には形(かたち)分け衆生(しゅじょう)あまねく導きて……。」
このとおり、「照らす」「及ぼす」「導く」と、みな動詞に係っている(2番目の文は「一切に」という副詞に係ってるとも見えるが、ふつうは動詞に係るものとして取る)。
むろん、「照らす光」「及ぼす功徳」「(衆生を)導く仏」というように、動詞はあたかも形容詞のように名詞を修飾することができる。しかし、これらは述語として文末に置かれる時と一見同じ形をしているが、文法的には「連体形」といって、活用変化をしている扱いなのだ。
だから「あまねくミルキーウェイ」「あまねく生命」という名乗りを決めたスタッフは、やはり「あまねく」を動詞と錯覚していることになる。
子供向けファンタジーアニメの言葉遣いに目くじらを立てるな、という意見もあろうが、子供向けだからこそ、内容はもちろん、日本語にも気を使ってもらいたいとぼく個人は思う。ただ、ネットの上ではもっともっと汚らしくて出鱈目な日本語が蔓延しているんだから、ここだけを突っついてもしょうがないなあというムナシサはある。
それに、正直なところをいうと、「あまねくミルキーウェイ」「あまねく生命」とやるのは、文字として読めば気になるが、耳で聴く分にはそれほど不愉快ではない。語感はそれほど悪くない。「言葉は世につれ」というやつで、いまプリキュアを見ている世代が大人になる時分には、案外「あまねく」がほんとに動詞として扱われるようになっちまうのかもしれない。
補足01) このあと思いついたのだが、上記のプリキュアさん2人の名乗りも、「天にあまねく(広がる)ミルキーウェイ」「(世界に)あまねく(満ちる)生命に祝福を」というように、いくつかの語句が略されてると解釈すれば筋が通らぬこともない。さりとて、苦しいことに変わりはないから、やはり「天にあまねきミルキーウェイ」「あまねき生命に祝福を」と、正しく連体形にしておくべきところだろう。
補足02) このあとたまたまgyaoで『宇宙戦艦ヤマト2199』を観たところ(全編通して観たわけではない)、スターシャさんが「あまねく星々、その知的生命体の救済、それがイスカンダルの進む道。」てなことを言っていた。この作品がテレビ放映されたのは2013(平成25)年。なるほど。どうやらこのあたりが誤用の元凶であったか。
さらに補足) ララはひかるのパートナーだから、多くの点で対になっている(ストッキングとか)。この名乗りにしてももちろんそうで、ひかるの「宇宙(そら)に輝くキラキラ星!」と対句を成すものとして、ララの名乗り「天にあまねくミルキーウェイ!」がある。どうしても「輝く」と韻を踏ませたかったわけだ。コメント欄でぼくは「天を綾なすミルキーウェイ!」にしたらよかったと書いたけれども、「~を綾なす」ではきれいに韻を踏まない。そうなると、コメント欄にてakiさんが提唱しておられる「天をつらぬくミルキーウェイ!」のほうがいいか……。ただ、格助詞が「~に」ではなく「~を」になってしまうのと、「天の川が天を貫く」という語感が、いまひとつぼくには馴染めない。いちばん手頃な「きらめく」は、「き~ら~めく~ ほ~し~のちからで~」と、歌詞のほうで使っちゃってるしなあ……。というわけで思いついたのが「たなびく」。夜空を雄大に流れる天の川の感じをうまく捉まえている……のではないか。「天にたなびくミルキーウェイ!」でどうでしょう。「七夕」と音が通じているのもミソである。