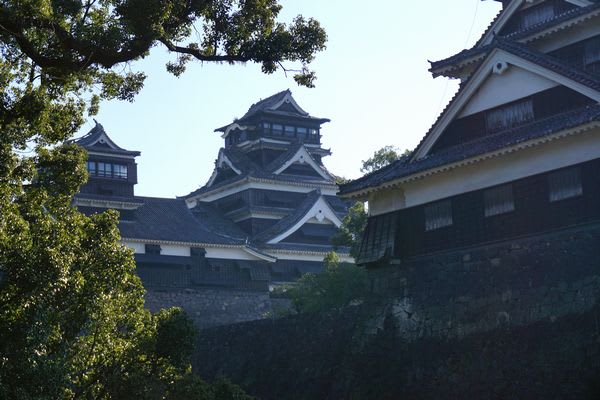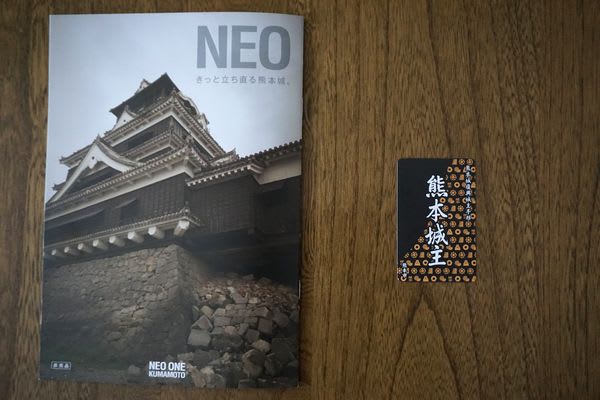昨年に引き続いて、冬ぼたんを見に筥崎宮の花庭園に行ってきました。しめやかに咲くぼたんを囲む藁帽子(わらぼっち)は、訪れる人に冬ならではの風情を感じさせます。

昭和62年4月に開園した神苑花庭園は、地下鉄筥崎宮前駅のすぐそば。筥崎宮の参道沿い、二之鳥居と三之鳥居のあいだにある入り口には、「冬ぼたん」の幟がハタハタと風に揺れていました。

入り口を入ると、藁でくるまれ和傘をさしかけられた冬ぼたんがお出迎え。

昨日はあいにくの曇り空で、寒い一日でしたが、ぼたんの花は藁ぼっちに守られて、健気に大輪の花を咲かせていました。



花庭園では、約20種200株の可憐なぼたんを見ることができます。


春を告げる福寿草も、土の中から顔を出していました。

花庭園は、園内をぐるりと巡る回遊式庭園。私たちは冬ぼたんの時期しか訪れたことはありませんが、四季折々の花々を楽しめるそうです。

光沢があって綺麗・・・・・。

つぼみから大きく開いたものまで、色も形もさまざまです。

梅の花が、早くも開き始めていました。

つぼみも、ふっくらと膨らんできています。

後ろ姿も可愛らしかったです~♪

よく剪定され見事な枝ぶりの紅梅。こちらも、いくつか花が開いていました。

園内を歩いていると、真冬だというのに、さまざまな花々を見ることができます。これはレウィシアという花で、北米ロッキー山脈が原産地だそうです。

均整のとれた可愛らしい花びら。険しい山岳地で見るレウィシアは、なお一層可憐でしょうね。

この時期に、あやめが見られるとは思いませんでした (^-^)ゞ

ラッパ水仙も、かなり早咲きですね。

まん丸のつぼみが可愛らしい花かんざし。今にも、はちきれそうに膨らんでいました。

昨年に続いて、園内のフレンチレストラン、迎賓館で食事をと思っていたのですが、残念ながら、昨日は貸切となっていたので、向かいの宮カフェでカレーとグラタンを頂きました (^-^)ゞ


ランチのあとは、筥崎八幡宮とも言われ、宇佐八幡、石清水八幡とともに日本三大八幡宮に数えられる筥崎宮に参拝。筥崎宮には、応神天皇(八幡大神)、神功皇后(応神天皇の母君)、玉依姫命(たまよりひめのみこと:神武天皇の母君)が祀られています。

16世紀末、小早川隆景が建立した楼門は、国指定の重要文化財。掲げられた「敵国降伏」の扁額は、蒙古襲来により炎上した社殿の再興にあたって、時の亀山上皇が納められた事跡を拡大したものと、筥崎宮の公式HPに記されています。

昨年ここに、「**.**(タイム)を切って、リオデジャネイロ・オリンピックに出場できますように」と書かれた絵馬がありました。その願い叶って、昨夏、晴れの舞台に立てていたらいいなぁと思います。

藁ぼっちと冬ぼたん。ここ筥崎宮花庭園や門司の白野江植物公園で何度も見ていますが、今年の冬ぼたんは、例年以上に綺麗に咲いていたような気がします。早咲きの梅や花かんざしもとっても可愛らしく、いい時に行けてよかったです (^-^)ゞ


昭和62年4月に開園した神苑花庭園は、地下鉄筥崎宮前駅のすぐそば。筥崎宮の参道沿い、二之鳥居と三之鳥居のあいだにある入り口には、「冬ぼたん」の幟がハタハタと風に揺れていました。

入り口を入ると、藁でくるまれ和傘をさしかけられた冬ぼたんがお出迎え。

昨日はあいにくの曇り空で、寒い一日でしたが、ぼたんの花は藁ぼっちに守られて、健気に大輪の花を咲かせていました。



花庭園では、約20種200株の可憐なぼたんを見ることができます。


春を告げる福寿草も、土の中から顔を出していました。

花庭園は、園内をぐるりと巡る回遊式庭園。私たちは冬ぼたんの時期しか訪れたことはありませんが、四季折々の花々を楽しめるそうです。

光沢があって綺麗・・・・・。

つぼみから大きく開いたものまで、色も形もさまざまです。

梅の花が、早くも開き始めていました。

つぼみも、ふっくらと膨らんできています。

後ろ姿も可愛らしかったです~♪

よく剪定され見事な枝ぶりの紅梅。こちらも、いくつか花が開いていました。

園内を歩いていると、真冬だというのに、さまざまな花々を見ることができます。これはレウィシアという花で、北米ロッキー山脈が原産地だそうです。

均整のとれた可愛らしい花びら。険しい山岳地で見るレウィシアは、なお一層可憐でしょうね。

この時期に、あやめが見られるとは思いませんでした (^-^)ゞ

ラッパ水仙も、かなり早咲きですね。

まん丸のつぼみが可愛らしい花かんざし。今にも、はちきれそうに膨らんでいました。

昨年に続いて、園内のフレンチレストラン、迎賓館で食事をと思っていたのですが、残念ながら、昨日は貸切となっていたので、向かいの宮カフェでカレーとグラタンを頂きました (^-^)ゞ


ランチのあとは、筥崎八幡宮とも言われ、宇佐八幡、石清水八幡とともに日本三大八幡宮に数えられる筥崎宮に参拝。筥崎宮には、応神天皇(八幡大神)、神功皇后(応神天皇の母君)、玉依姫命(たまよりひめのみこと:神武天皇の母君)が祀られています。

16世紀末、小早川隆景が建立した楼門は、国指定の重要文化財。掲げられた「敵国降伏」の扁額は、蒙古襲来により炎上した社殿の再興にあたって、時の亀山上皇が納められた事跡を拡大したものと、筥崎宮の公式HPに記されています。

昨年ここに、「**.**(タイム)を切って、リオデジャネイロ・オリンピックに出場できますように」と書かれた絵馬がありました。その願い叶って、昨夏、晴れの舞台に立てていたらいいなぁと思います。

藁ぼっちと冬ぼたん。ここ筥崎宮花庭園や門司の白野江植物公園で何度も見ていますが、今年の冬ぼたんは、例年以上に綺麗に咲いていたような気がします。早咲きの梅や花かんざしもとっても可愛らしく、いい時に行けてよかったです (^-^)ゞ