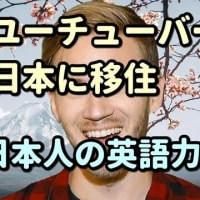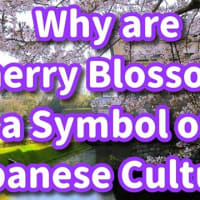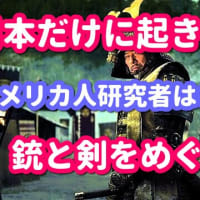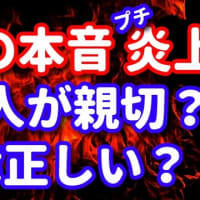◆『日本のアニメは何がすごいのか 世界が惹かれた理由(祥伝社新書) 』
』
この本では日本のアニメのユニークさを、①ロボット・アニメ、②スポ根アニメ、③魔法少女アニメ、④ヤングアダルト向けアニメという視点から捉えていた。私の関心は、これらが日本の伝統とどのように関わるかだった。今回は、その③と④について見ていこう。
③魔法少女アニメ‥‥母性社会日本
欧米では、「日本アニメでは女の子がヒーローとして活躍する作品が多いのか」と質問される場合が多いという。しかし逆に、欧米ではなぜそういう作品がほとんどないのだろうか。むしろ私たち自身がそう問うべきかもしれない。欧米の方にこそ、男性と女性の役割の違いに関して、文化的に根深い区別意識があるのではないか。それは、一神教という父性原理の宗教を文化的背景としてもっているということであり、それゆえ女が男のような「ヒーロー」として活躍するという発想が生まれにくいということだろう。
日本の文化的伝統は、そのほぼ対極にある母性原理を基盤とするものだった。このブログの柱である日本文化のユニークさ8項目でいえば、
(2)ユーラシア大陸の父性的な性格の強い文化に対し、縄文時代から現代にいたるまで一貫して母性原理に根ざした社会と文化を存続させてきた。
ということである。
父性原理と母性原理の比較についてはこれまで繰り返し語ってきた。ここではひとつだけ関連記事を紹介しておこう(→マンガ・アニメと中空構造の日本文化)。ここでも語ったように、西洋のような一神教を中心とした文化は、多神教文化に比べて排除性が強い。対立する極のどちらかを中心として堅い統合を目指し、他の極に属するものを排除したり、敵対者と見なす。これが一神教の父性原理だ。一神教は、神の栄光を際立たせるために、敵対する悪魔の存在を構造的に必要とする。唯一の中心と敵対するものという構造は、ユダヤ教(旧約聖書)の神とサタンの関係が典型的だ。絶対的な善と悪との対立が鮮明に打ち出されるのだ。また、父性的なものに対して母性的なものが抑圧され、その抑圧されたものが「魔女」のような形をとって噴出し、さらに「魔女狩り」のような集団殺戮を生む背景となっていった。
ひるがえって日本の場合はどうか。縄文人の信仰や精神生活に深くかかわっていたはずの土偶の大半は女性であり、妊婦であることも多い。土偶の存在は、縄文文化が母性原理に根ざしていたことを示唆する。縄文土偶の女神には、渦が描かれていることが多いが、渦は古代において大いなる母の子宮の象徴で、生み出すことと飲み込むことという母性の二面性をも表す。こうした縄文の伝統は、神々の中心に位置する太陽神・アマテラスや、卑弥呼に象徴されるような巫女=シャーマンが君臨する時代にも受け継がれていった。そして、日本はそういう母性原理的な伝統が、男性原理の宗教によって駆逐されずに、現代まで何らかの形で受け継がれてきたのである。
現代日本のアニメ作品に多くの魔法少女が「ヒーロー」として描かれるのは、むしろ日本の伝統からしてごく自然なことなのである。しかし欧米のファンにとってはそれが新鮮だった。女の子が、男のヒーローのように、しかも魔法を使って大活躍する、それは父性原理の強い欧米では生まれにくい発想だった。神は「父なる神」、つまり男性であり、ヒーローもおのずと男性という発想になる。アメリカのセーラームーンのファンは、自分の国に溢れているありきたりの男性スーパーヒーローとのちがいに惹かれていった。普通の女の子がスーパーヒーローに変身する物語に魅了されたのだ。また、誰か一人を特別扱いしたり悪者にしたりする(善と悪の対立)のではなく、さまざまな要素を絡めて描く複雑なストーリーが絶賛されたのだ。 セーラームーンの魅力は、「戦闘とロマンス、友情と冒険、現代の日常と古代の魔法や精霊とが混在し、並列して描かれている点だ」という。物語と登場人物をさまざまな方向から肉づけすることで、ほかのスーパーヒーローものよりも、「リアル」で感情的にも満足できる、というのだ。
海外でのこうした反応からも、日本の魔法少女アニメがいかにユニークなものだったかがわかるだろう。
④ヤングアダルト向けアニメ‥‥子どもと大人の区別が曖昧な日本
欧米では子ども文化であるマンガ、アニメだが、日本では、はっきりとした区別はなく大人をも含んだ領域としても確立している。マンガ、アニメは、大人が子どもに与えるものではなく、大人をも巻き込んだ独立したカルチャーとしての魅力や深さをもっている。ではなぜ欧米では、マンガ・アニメが子どもに限定されるのか。ここにもキリスト教文化の影響があり、日本はその影響をあまり受けていないという文化的な背景の違いがあるようだ。
欧米では、子供は未完成な人間であって、教え導かなければいけない不完全な存在、洗礼を経て、教育で知性と理性を磨くことで、初めて一人前の「人間」に成るとという子ども観があるようだ。子どもは「人間になる途上の不完全な存在」で、大人とは明確に区別される。一方日本では、もともと子ども文化と大人文化に断絶がなかったからこそ、マンガ・アニメが大人の表現形式にもなり得たのだ。欧米のアニメーションの根底に依然として「アニメーションは子どもが観るもの」という常識があるのとは、まさに対照的だ。
欧米を中心とする世界の常識を唯一無視してきたのが、日本のアニメだった。日本のアニメは、「子どもが観るもの」という常識を無視して、製作者たちがそこで様々な映像表現の可能性をさぐる場となった。その複雑な世界観やストーリー展開の魅力は、アニメーションで育った世界の若者たちに、乾いた砂に水が浸み込むように自然に受け入れられていった。
「子どもが観るもの」には様々な制約がある。その制約がはじめからなければ、マンガ・アニメという表現の場は、逆に限りなく自由な発想と表現の場になる。実写映画は、登場する生身の人間のリアリティに引きずられて発想と表現に自ずと制限がかかる。マンガ・アニメはその制約がなく、想像の世界は無限だ。子どもと大人の領域が融合しているため、エロや暴力の表現が、子供の世界にまで入り込んでいる。これが、批判や拒否の理由とされることもあるが、国際競争力の強さになっている現実もある。
さて、本ブログでは、日本のマンガ・アニメの発信力の理由をこれまで以下の視点から考えてきた。
①生命と無生命、人間と他の生き物を明確に区別しない文化、あの世や異界と自由に交流するアニミズム的、多神教的な文化が現代になお息づき、それが豊かな想像力を刺激し、作品に反映する。
②小さくかわいいもの、子どもらしい純粋無垢さに高い価値を置く「かわいい」文化の独自性。
③子ども文化と大人文化の明確な区別がなく、連続的ないし融合している。
④宗教やイデオロギーによる制約がない自由な発想・表現と相対主義的な価値観。
⑤知的エリートにコントロールされない巨大な庶民階層の価値観が反映される。いかにもヒーローという主人公は少なく、ごく平凡な主人公が、悩んだりり努力したりしながら強く成長していくストーリが多い。
これらは、あくまでも暫定的なものであり、今回の考察を含めて、今後さらに項目や内容は変化していくと思う。いずれにせよ、世界の若者が日本ののポップカルチャー魅せらるのは、その「オリジナリティ」によるのだろう。そして「日本でしか生まれないものを次々に創り出していく」その独創性の背景には、日本独特の文化的背景がある。それをさらに明らかにしていくのが私の課題だ。
《関連記事》
★日本のポップカルチャーの魅力(1)
★日本のポップカルチャーの魅力(2)
★子供観の違いとアニメ
★子どもの楽園(1)
★子どもの楽園(2)
★マンガ・アニメの発信力の理由01
★マンガ・アニメの発信力の理由02
★マンガ・アニメの発信力の理由03
★『菊とポケモン』、クール・ジャパンの本格的な研究書(1) ※1
★『菊とポケモン』、クール・ジャパンの本格的な研究書(2)
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(1) ※2
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(2)
★『国土学再考』、紛争史観と自然災害史観(1)
★『国土学再考』、紛争史観と自然災害史観(2)
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(3)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(1):「かわいい」
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(2)融合
★日本発ポップカルチャーの魅力01:初音ミク
★日本発ポップカルチャーの魅力02:初音ミク(続き)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(3)相対主義
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(4)相対主義(続き)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(5)庶民の力
★マンガ・アニメの発信力:異界の描かれ方
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(1)
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(2)
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(3)
★マンガ・アニメの発信力:セーラームーン(1)
★マンガ・アニメの発信力:セーラームーン(2)
★マンガ・アニメの発信力:「かわいい」文化の威力
この本では日本のアニメのユニークさを、①ロボット・アニメ、②スポ根アニメ、③魔法少女アニメ、④ヤングアダルト向けアニメという視点から捉えていた。私の関心は、これらが日本の伝統とどのように関わるかだった。今回は、その③と④について見ていこう。
③魔法少女アニメ‥‥母性社会日本
欧米では、「日本アニメでは女の子がヒーローとして活躍する作品が多いのか」と質問される場合が多いという。しかし逆に、欧米ではなぜそういう作品がほとんどないのだろうか。むしろ私たち自身がそう問うべきかもしれない。欧米の方にこそ、男性と女性の役割の違いに関して、文化的に根深い区別意識があるのではないか。それは、一神教という父性原理の宗教を文化的背景としてもっているということであり、それゆえ女が男のような「ヒーロー」として活躍するという発想が生まれにくいということだろう。
日本の文化的伝統は、そのほぼ対極にある母性原理を基盤とするものだった。このブログの柱である日本文化のユニークさ8項目でいえば、
(2)ユーラシア大陸の父性的な性格の強い文化に対し、縄文時代から現代にいたるまで一貫して母性原理に根ざした社会と文化を存続させてきた。
ということである。
父性原理と母性原理の比較についてはこれまで繰り返し語ってきた。ここではひとつだけ関連記事を紹介しておこう(→マンガ・アニメと中空構造の日本文化)。ここでも語ったように、西洋のような一神教を中心とした文化は、多神教文化に比べて排除性が強い。対立する極のどちらかを中心として堅い統合を目指し、他の極に属するものを排除したり、敵対者と見なす。これが一神教の父性原理だ。一神教は、神の栄光を際立たせるために、敵対する悪魔の存在を構造的に必要とする。唯一の中心と敵対するものという構造は、ユダヤ教(旧約聖書)の神とサタンの関係が典型的だ。絶対的な善と悪との対立が鮮明に打ち出されるのだ。また、父性的なものに対して母性的なものが抑圧され、その抑圧されたものが「魔女」のような形をとって噴出し、さらに「魔女狩り」のような集団殺戮を生む背景となっていった。
ひるがえって日本の場合はどうか。縄文人の信仰や精神生活に深くかかわっていたはずの土偶の大半は女性であり、妊婦であることも多い。土偶の存在は、縄文文化が母性原理に根ざしていたことを示唆する。縄文土偶の女神には、渦が描かれていることが多いが、渦は古代において大いなる母の子宮の象徴で、生み出すことと飲み込むことという母性の二面性をも表す。こうした縄文の伝統は、神々の中心に位置する太陽神・アマテラスや、卑弥呼に象徴されるような巫女=シャーマンが君臨する時代にも受け継がれていった。そして、日本はそういう母性原理的な伝統が、男性原理の宗教によって駆逐されずに、現代まで何らかの形で受け継がれてきたのである。
現代日本のアニメ作品に多くの魔法少女が「ヒーロー」として描かれるのは、むしろ日本の伝統からしてごく自然なことなのである。しかし欧米のファンにとってはそれが新鮮だった。女の子が、男のヒーローのように、しかも魔法を使って大活躍する、それは父性原理の強い欧米では生まれにくい発想だった。神は「父なる神」、つまり男性であり、ヒーローもおのずと男性という発想になる。アメリカのセーラームーンのファンは、自分の国に溢れているありきたりの男性スーパーヒーローとのちがいに惹かれていった。普通の女の子がスーパーヒーローに変身する物語に魅了されたのだ。また、誰か一人を特別扱いしたり悪者にしたりする(善と悪の対立)のではなく、さまざまな要素を絡めて描く複雑なストーリーが絶賛されたのだ。 セーラームーンの魅力は、「戦闘とロマンス、友情と冒険、現代の日常と古代の魔法や精霊とが混在し、並列して描かれている点だ」という。物語と登場人物をさまざまな方向から肉づけすることで、ほかのスーパーヒーローものよりも、「リアル」で感情的にも満足できる、というのだ。
海外でのこうした反応からも、日本の魔法少女アニメがいかにユニークなものだったかがわかるだろう。
④ヤングアダルト向けアニメ‥‥子どもと大人の区別が曖昧な日本
欧米では子ども文化であるマンガ、アニメだが、日本では、はっきりとした区別はなく大人をも含んだ領域としても確立している。マンガ、アニメは、大人が子どもに与えるものではなく、大人をも巻き込んだ独立したカルチャーとしての魅力や深さをもっている。ではなぜ欧米では、マンガ・アニメが子どもに限定されるのか。ここにもキリスト教文化の影響があり、日本はその影響をあまり受けていないという文化的な背景の違いがあるようだ。
欧米では、子供は未完成な人間であって、教え導かなければいけない不完全な存在、洗礼を経て、教育で知性と理性を磨くことで、初めて一人前の「人間」に成るとという子ども観があるようだ。子どもは「人間になる途上の不完全な存在」で、大人とは明確に区別される。一方日本では、もともと子ども文化と大人文化に断絶がなかったからこそ、マンガ・アニメが大人の表現形式にもなり得たのだ。欧米のアニメーションの根底に依然として「アニメーションは子どもが観るもの」という常識があるのとは、まさに対照的だ。
欧米を中心とする世界の常識を唯一無視してきたのが、日本のアニメだった。日本のアニメは、「子どもが観るもの」という常識を無視して、製作者たちがそこで様々な映像表現の可能性をさぐる場となった。その複雑な世界観やストーリー展開の魅力は、アニメーションで育った世界の若者たちに、乾いた砂に水が浸み込むように自然に受け入れられていった。
「子どもが観るもの」には様々な制約がある。その制約がはじめからなければ、マンガ・アニメという表現の場は、逆に限りなく自由な発想と表現の場になる。実写映画は、登場する生身の人間のリアリティに引きずられて発想と表現に自ずと制限がかかる。マンガ・アニメはその制約がなく、想像の世界は無限だ。子どもと大人の領域が融合しているため、エロや暴力の表現が、子供の世界にまで入り込んでいる。これが、批判や拒否の理由とされることもあるが、国際競争力の強さになっている現実もある。
さて、本ブログでは、日本のマンガ・アニメの発信力の理由をこれまで以下の視点から考えてきた。
①生命と無生命、人間と他の生き物を明確に区別しない文化、あの世や異界と自由に交流するアニミズム的、多神教的な文化が現代になお息づき、それが豊かな想像力を刺激し、作品に反映する。
②小さくかわいいもの、子どもらしい純粋無垢さに高い価値を置く「かわいい」文化の独自性。
③子ども文化と大人文化の明確な区別がなく、連続的ないし融合している。
④宗教やイデオロギーによる制約がない自由な発想・表現と相対主義的な価値観。
⑤知的エリートにコントロールされない巨大な庶民階層の価値観が反映される。いかにもヒーローという主人公は少なく、ごく平凡な主人公が、悩んだりり努力したりしながら強く成長していくストーリが多い。
これらは、あくまでも暫定的なものであり、今回の考察を含めて、今後さらに項目や内容は変化していくと思う。いずれにせよ、世界の若者が日本ののポップカルチャー魅せらるのは、その「オリジナリティ」によるのだろう。そして「日本でしか生まれないものを次々に創り出していく」その独創性の背景には、日本独特の文化的背景がある。それをさらに明らかにしていくのが私の課題だ。
《関連記事》
★日本のポップカルチャーの魅力(1)
★日本のポップカルチャーの魅力(2)
★子供観の違いとアニメ
★子どもの楽園(1)
★子どもの楽園(2)
★マンガ・アニメの発信力の理由01
★マンガ・アニメの発信力の理由02
★マンガ・アニメの発信力の理由03
★『菊とポケモン』、クール・ジャパンの本格的な研究書(1) ※1
★『菊とポケモン』、クール・ジャパンの本格的な研究書(2)
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(1) ※2
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(2)
★『国土学再考』、紛争史観と自然災害史観(1)
★『国土学再考』、紛争史観と自然災害史観(2)
★『「かわいい」論』、かわいいと平和の関係(3)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(1):「かわいい」
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(2)融合
★日本発ポップカルチャーの魅力01:初音ミク
★日本発ポップカルチャーの魅力02:初音ミク(続き)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(3)相対主義
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(4)相対主義(続き)
★マンガ・アニメの発信力と日本文化(5)庶民の力
★マンガ・アニメの発信力:異界の描かれ方
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(1)
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(2)
★マンガ・アニメの発信力:BLEACH―ブリーチ―(3)
★マンガ・アニメの発信力:セーラームーン(1)
★マンガ・アニメの発信力:セーラームーン(2)
★マンガ・アニメの発信力:「かわいい」文化の威力