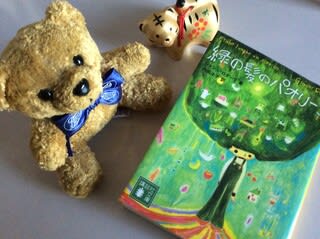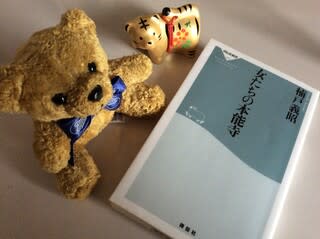「こんにちわッ、テディちゃでス!
まだまだァ、わだいィ~ふッとうちゅうゥ!」
「がるる!ぐるる~!」(←訳:虎です!だよね~!)
こんにちは、ネーさです。
放送から一日経ったので、もう喋ってもいいわよね。
まさかの“光秀生存?説”で幕を閉じた
大河ドラマ『麒麟がくる』……
アタマの中が歴史ネタで満杯の本日は、
読書タイムも歴史モノでゆきましょう。
さあ、こちらを、どうぞ~♪

―― 古生物学者、妖怪を掘る ――
著者は荻野慎諧(おぎの・しんかい)さん、
2018年7月に発行されました。
『鵺の正体、鬼の真実』と
副題が付されています。
「こせいぶつゥ、ッていうとォ~…?」
「ぐるるがるるるる?」(←訳:化石の研究者さん?)
ええ、そうです、
著者・荻野さんの専門は、
肉食の哺乳類化石。
クマやイヌ、
イタチなどの祖先の分類・記載や、
それら化石種の分布、
地域ごとの種の文化・拡散を
研究テーマとしています。
「なのにィ~、ようかいィ??」
「がるぐるるる!」(←訳:接点なさそう!)
古生物学と、妖怪。
まったく関連なさそうですけれども、
荻野さんは考えました。
《古生物学的視点で、
古い文献に記載されている
不思議な生物や怪異の記録を読み解くと、
いろいろおもしろいことが見えてくる》
つまり、
化石を発掘するように、
古文献を《掘る》ことで
妖怪や怪異の正体に近づこう!と。
「たとえばァ~…」
「ぐるる!」(←訳:鬼とか!)
本文の、
第一章『古生物学者、妖怪を見なおしてみる』
第二章『古文書の《異獣・異類》と古生物』
第三章『妖怪考古学って役に立つの?』
のうち、
《鬼》について考察されているのは、
第一章、ですね。
《鬼》を“ツノを有する生物“として
解釈してみると、
けっこうたくさんいるんです。
シカ、ウシ、ヒツジ、サイなどの哺乳類。
カブトムシ、クワガタなどの昆虫。
↑これらツノを持つ生物に
共通している特徴は……
植物食。
肉食ではなくて、
草や、樹液がゴハンなのです。
「えええッ??」
「がるるぅ?」(←訳:非肉食ぅ?)
鬼は植物食?
ヒトを喰らう魔物ではない?
実に魅力的な疑問を掲げつつ、
荻野さんはさらなる逆転の発想を
私たち読み手に突きつけます。
第二章で考察されているのは、
《鵺(ぬえ)》。
『古事記』『万葉集』
『源平盛衰記』や『平家物語』等に登場する、
顔がサルで胴がタヌキで
四肢はトラで尻尾がヘビで……
という怪生物の、まことの名は。
レッサーパンダ?
「ええええええェッ!」
「ぐるぅ!!」(←訳:うそぉ!!)
なぜまたレッサーパンダ?
動物園のアイドルが?
驚くより先に動揺してしまいましたが、
読み進んでゆくにつれ、
どんどん引き込まれてゆきます。
平安時代の日本にレッサーパンダは……
いたのかしら?
いてもいいわよね?
「ますますゥ、ふかまるゥ!」
「がるるぐる!」(←訳:混乱と疑問!)
昔むかしの日本を騒がせた
《彼ら》の素性と素顔とは。
一見奇妙な、
しかし、説得力ありまくり!な
古生物学×妖怪検証の新科学、
歴史好きな活字マニアさんにも
理系好きな方々にもおすすめですよ。
書店さんで、図書館で、
ぜひ、探してみてくださいね~♪
まだまだァ、わだいィ~ふッとうちゅうゥ!」
「がるる!ぐるる~!」(←訳:虎です!だよね~!)
こんにちは、ネーさです。
放送から一日経ったので、もう喋ってもいいわよね。
まさかの“光秀生存?説”で幕を閉じた
大河ドラマ『麒麟がくる』……
アタマの中が歴史ネタで満杯の本日は、
読書タイムも歴史モノでゆきましょう。
さあ、こちらを、どうぞ~♪

―― 古生物学者、妖怪を掘る ――
著者は荻野慎諧(おぎの・しんかい)さん、
2018年7月に発行されました。
『鵺の正体、鬼の真実』と
副題が付されています。
「こせいぶつゥ、ッていうとォ~…?」
「ぐるるがるるるる?」(←訳:化石の研究者さん?)
ええ、そうです、
著者・荻野さんの専門は、
肉食の哺乳類化石。
クマやイヌ、
イタチなどの祖先の分類・記載や、
それら化石種の分布、
地域ごとの種の文化・拡散を
研究テーマとしています。
「なのにィ~、ようかいィ??」
「がるぐるるる!」(←訳:接点なさそう!)
古生物学と、妖怪。
まったく関連なさそうですけれども、
荻野さんは考えました。
《古生物学的視点で、
古い文献に記載されている
不思議な生物や怪異の記録を読み解くと、
いろいろおもしろいことが見えてくる》
つまり、
化石を発掘するように、
古文献を《掘る》ことで
妖怪や怪異の正体に近づこう!と。
「たとえばァ~…」
「ぐるる!」(←訳:鬼とか!)
本文の、
第一章『古生物学者、妖怪を見なおしてみる』
第二章『古文書の《異獣・異類》と古生物』
第三章『妖怪考古学って役に立つの?』
のうち、
《鬼》について考察されているのは、
第一章、ですね。
《鬼》を“ツノを有する生物“として
解釈してみると、
けっこうたくさんいるんです。
シカ、ウシ、ヒツジ、サイなどの哺乳類。
カブトムシ、クワガタなどの昆虫。
↑これらツノを持つ生物に
共通している特徴は……
植物食。
肉食ではなくて、
草や、樹液がゴハンなのです。
「えええッ??」
「がるるぅ?」(←訳:非肉食ぅ?)
鬼は植物食?
ヒトを喰らう魔物ではない?
実に魅力的な疑問を掲げつつ、
荻野さんはさらなる逆転の発想を
私たち読み手に突きつけます。
第二章で考察されているのは、
《鵺(ぬえ)》。
『古事記』『万葉集』
『源平盛衰記』や『平家物語』等に登場する、
顔がサルで胴がタヌキで
四肢はトラで尻尾がヘビで……
という怪生物の、まことの名は。
レッサーパンダ?
「ええええええェッ!」
「ぐるぅ!!」(←訳:うそぉ!!)
なぜまたレッサーパンダ?
動物園のアイドルが?
驚くより先に動揺してしまいましたが、
読み進んでゆくにつれ、
どんどん引き込まれてゆきます。
平安時代の日本にレッサーパンダは……
いたのかしら?
いてもいいわよね?
「ますますゥ、ふかまるゥ!」
「がるるぐる!」(←訳:混乱と疑問!)
昔むかしの日本を騒がせた
《彼ら》の素性と素顔とは。
一見奇妙な、
しかし、説得力ありまくり!な
古生物学×妖怪検証の新科学、
歴史好きな活字マニアさんにも
理系好きな方々にもおすすめですよ。
書店さんで、図書館で、
ぜひ、探してみてくださいね~♪