「こんにちわッ、テディちゃでス!
……もぐらッ??」
「がるる!ぐるるがる!」(←訳:虎です!モグラだよ!)
こんにちは、ネーさです。
確かにいる、と分かっていても、
実物と出会う機会は滅多にない、という
ヘンテコな生き物――モグラくん。
本日の読書タイムは、
モグラくんたちが橋渡しする
ワールドワイドなノンフィクション作品を、
さあ、どうぞ~♪

―― アラン・オーストンの標本ラベル ――
著者は川田伸一郎(かわだ・しんいちろう)さん、
2020年11月に発行されました。
『幕末から明治、海を渡ったニッポンの動物たち』
と副題が付されています。
国立科学博物館の動物研究部研究主幹さんである
著者・川田さん、
先日は標本をテーマにしたTV番組にも
出演しておられましたね。
「ふァいッ! みましたァでス!」
「ぐるるるがるる!」(←訳:標本の海でした!)
標本製作のスペシャリストでもある川田さんは、
また同時に
《モグラ博士》を自認する
モグラ研究の第一人者さんです。
博士論文の内容は、
世界中のモグラ類の染色体を調査して
種間で比較する、
というものであったほど、
川田さんの関心は、
モグラ、モグラ、モグラ……。
そして、モグラへの関心は、
学位を取得し、
貧乏生活に耐えつつ
研究を続けていた時代も
色褪せはしなかったのですが。
「あるひのォ、ことッ!」
「がるるぐる~!」(←訳:驚きの発見~!)
2004年、11月22日。
川田さんは英国に旅行し、
研究者として
大英自然史博物館を
訪問する機会を得ました。
博物館の哺乳類担当研究者さんに案内され、
スタッフ限定の扉をくぐって、
収蔵庫へ。
さっそくモグラなどの
小型哺乳類標本が入ったキャビネットを開け、
調査を始めてみれば。
「あれれッ??」
「ぐるる~…?」(←訳:これは~…?)
同じだ!
標本ラベルが
森林総合研究所で見たものと同じ!
ええ、
それはちょうど一ヶ月前、
川田さんが目にした
日本のつくば市の、
森林総合研究所の陸生哺乳類の標本、
モグラの仮剥製標本に付いていたものと
同じ書式のラベルが、
そこにあったのです。
「なんでッなんでッ??」
「がるぐぅるるるる?」(←訳:偶然じゃないよね?)
日本と英国に分散する
同一の標本ラベル。
ラベルは古く、
『1839』という西暦年が
記されていました。
この不思議な出来事を解明しようと、
諸々の文献を漁った川田さんは
或る名前に行き着きます。
アラン・オーストンさん。
明治から大正の初期を
横浜で過ごした英国人――
彼こそが、
モグラの標本を英国に送った人物だった?
「ふむむゥ~??」
「ぐるがるぐる!」(←訳:謎が謎を呼ぶ!)
モグラの研究史を語りつつ、
川田さんは
日本の自然史研究の発展の裏側に
どんな人びとの活躍があったのかを
少しずつ、
けれど着実に調査を進め、
明らかにしてゆきます。
「すべてのォ、はじまりィはァ~」
「がるるぐる!」(←訳:モグラから!)
御本の表紙画にも描き込まれている、
掌に乗ってしまうくらいの、
小さなサイズの哺乳類。
モグラくんたちが見せてくれる
夢のようなノンフィクション作品は、
歴史好きな方々、
標本大好きな方々におすすめです。
ぜひ、手に取ってみてくださいね~♪
……もぐらッ??」
「がるる!ぐるるがる!」(←訳:虎です!モグラだよ!)
こんにちは、ネーさです。
確かにいる、と分かっていても、
実物と出会う機会は滅多にない、という
ヘンテコな生き物――モグラくん。
本日の読書タイムは、
モグラくんたちが橋渡しする
ワールドワイドなノンフィクション作品を、
さあ、どうぞ~♪

―― アラン・オーストンの標本ラベル ――
著者は川田伸一郎(かわだ・しんいちろう)さん、
2020年11月に発行されました。
『幕末から明治、海を渡ったニッポンの動物たち』
と副題が付されています。
国立科学博物館の動物研究部研究主幹さんである
著者・川田さん、
先日は標本をテーマにしたTV番組にも
出演しておられましたね。
「ふァいッ! みましたァでス!」
「ぐるるるがるる!」(←訳:標本の海でした!)
標本製作のスペシャリストでもある川田さんは、
また同時に
《モグラ博士》を自認する
モグラ研究の第一人者さんです。
博士論文の内容は、
世界中のモグラ類の染色体を調査して
種間で比較する、
というものであったほど、
川田さんの関心は、
モグラ、モグラ、モグラ……。
そして、モグラへの関心は、
学位を取得し、
貧乏生活に耐えつつ
研究を続けていた時代も
色褪せはしなかったのですが。
「あるひのォ、ことッ!」
「がるるぐる~!」(←訳:驚きの発見~!)
2004年、11月22日。
川田さんは英国に旅行し、
研究者として
大英自然史博物館を
訪問する機会を得ました。
博物館の哺乳類担当研究者さんに案内され、
スタッフ限定の扉をくぐって、
収蔵庫へ。
さっそくモグラなどの
小型哺乳類標本が入ったキャビネットを開け、
調査を始めてみれば。
「あれれッ??」
「ぐるる~…?」(←訳:これは~…?)
同じだ!
標本ラベルが
森林総合研究所で見たものと同じ!
ええ、
それはちょうど一ヶ月前、
川田さんが目にした
日本のつくば市の、
森林総合研究所の陸生哺乳類の標本、
モグラの仮剥製標本に付いていたものと
同じ書式のラベルが、
そこにあったのです。
「なんでッなんでッ??」
「がるぐぅるるるる?」(←訳:偶然じゃないよね?)
日本と英国に分散する
同一の標本ラベル。
ラベルは古く、
『1839』という西暦年が
記されていました。
この不思議な出来事を解明しようと、
諸々の文献を漁った川田さんは
或る名前に行き着きます。
アラン・オーストンさん。
明治から大正の初期を
横浜で過ごした英国人――
彼こそが、
モグラの標本を英国に送った人物だった?
「ふむむゥ~??」
「ぐるがるぐる!」(←訳:謎が謎を呼ぶ!)
モグラの研究史を語りつつ、
川田さんは
日本の自然史研究の発展の裏側に
どんな人びとの活躍があったのかを
少しずつ、
けれど着実に調査を進め、
明らかにしてゆきます。
「すべてのォ、はじまりィはァ~」
「がるるぐる!」(←訳:モグラから!)
御本の表紙画にも描き込まれている、
掌に乗ってしまうくらいの、
小さなサイズの哺乳類。
モグラくんたちが見せてくれる
夢のようなノンフィクション作品は、
歴史好きな方々、
標本大好きな方々におすすめです。
ぜひ、手に取ってみてくださいね~♪



















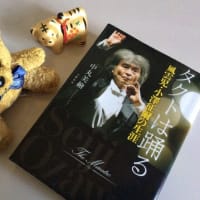





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます