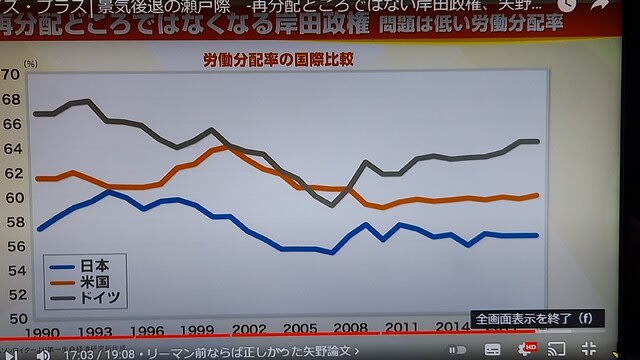2020年6月から職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主の義務となった。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)が労働政策フォーラム(オンライン開催)「職場環境の改善─ハラスメント対策─」を以下のごとく開催するので事業主は必見だ。
職場環境改善のためのハラスメント対策について、組織はどのように取り組むべきか。本フォーラムではJILPTの研究報告や現場での取組に関する報告を踏まえて、ハラスメントの無い職場環境づくりの課題や具体策について議論される。
・日時:2022年2月10日(木曜)~17日(木曜)
【第1部】研究報告・事例報告(オンデマンド配信・約130分)
2月10日(木曜)10時00分~17日(木曜)14時30分
【第2部】パネルディスカッション(ライブ配信)
2月17日(木曜)15時30分~17時00分
・開催方式:オンライン(Zoomウェビナー)
申し込みは