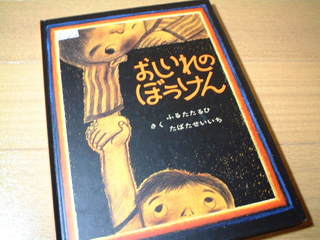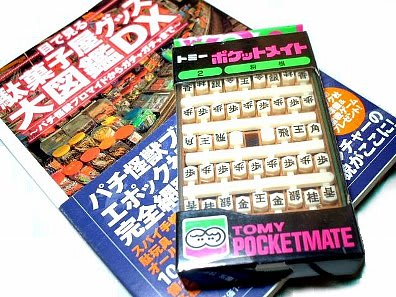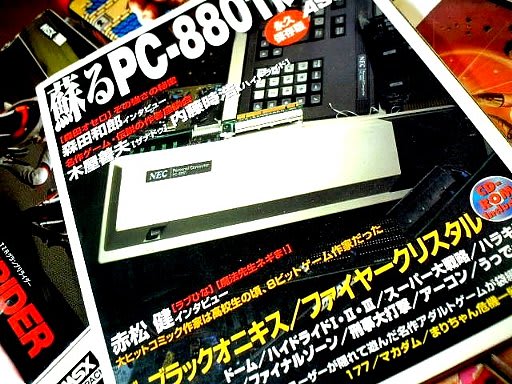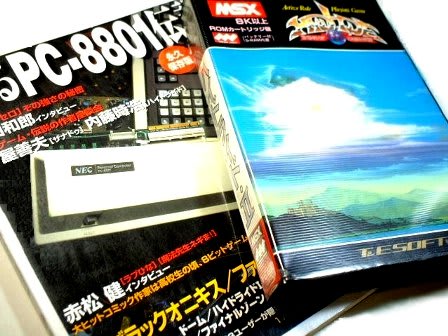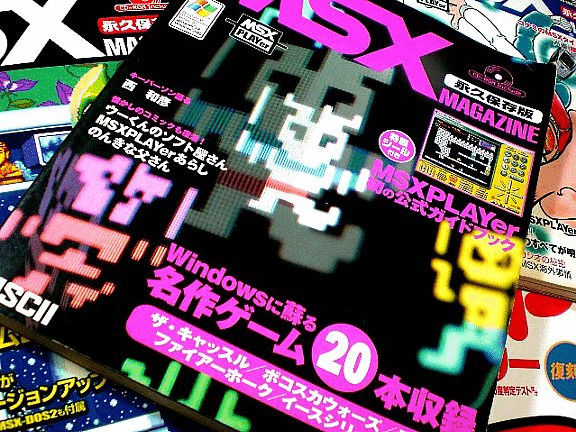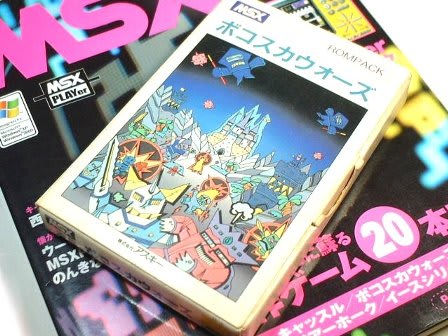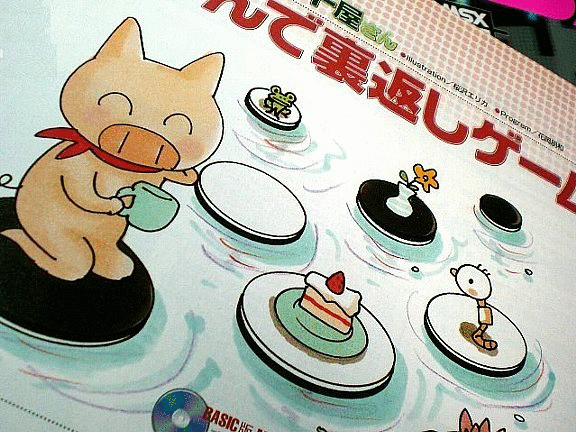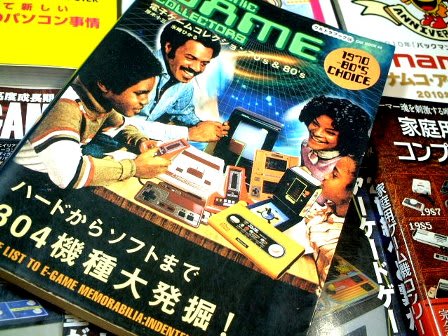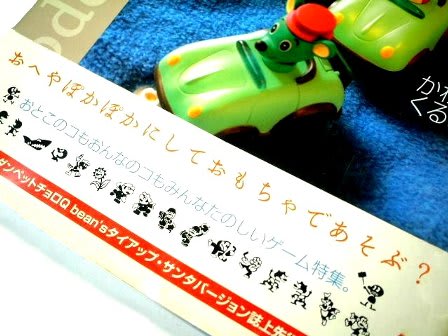『おしいれのぼうけん』は、童心社より1974年に発行された絵本(児童文学書)です。作者は、児童文学作家で評論家の古田足日氏と、画家で絵本作家の田畑精一氏。取材の過程から二人で相互に影響を与え合って成立した作品のため、文ふるたたるひ、絵たばたせいいちではなく、二人の作となっているそうです。ちょっと変則的なネタですが、どのくらいの方がご存知でしょうか。
物語はさくらほいくえんという保育園が舞台。このさくらほいくえんでは、人形劇に登場する『ねずみばあさん』と悪いことをするとお仕置きに入れられてしまう『おしいれ』の2つが、園児達にとってこわいものとなっています。ある日いたずらっこのさとしとあきらが、悪ふざけをして罰としてみずの先生におしいれに閉じ込められてしまいます。2人は、その押入れの中で不思議な冒険を体験することになります。保育園が舞台なのですが、実際は結構文字の多い作品のため(自分で読む場合には)2年生くらいが対象のようです。また絵本とはいっても、鉛筆書きのモノクロのイラストがついており、とても個性的なものになっています。ちなみに私は、これを小学校の時に学校の推薦図書だか、読書感想文かなにかで読んだような記憶があります。ネットでたまたま検索をしていて、世代を超えて現在までずっと読み継がれているベストセラー(ロングセラー)になっているということをはじめて知りました。
このおしいれのぼうけんの公式サイトには、広末涼子さんの毎日新聞のインタビュー記事が掲載されています。またスチャダラパーのアニ氏が、この主人公の少年のモデルという意外な話もあります。作家さんと近所で、遊んでいるところを取材されたのだとか。さくらほいくえんという舞台も(みずのせんせいも)非常にリアリティがあり、こちらもしっかりと取材がなされているのかもしれません。また、おしいれのなかより幻想的な冒険が始まるのですが、ねずみばあさんの追跡を振り切ってトンネルを抜けると突然深夜の高速道路に出る展開など、不思議な現実感もあったりします。そういったところも、世代を超えて今の子供達にも愛読されている理由の一つなのでしょうか。時代が変わっても、人の根本的な部分というのはそれほど変わらないのかもしれませんね。それにしても、吸収力(感受性)の強い子供の頃に読んだ書籍というのは、いつまでも強い印象で残っているものです。
物語はさくらほいくえんという保育園が舞台。このさくらほいくえんでは、人形劇に登場する『ねずみばあさん』と悪いことをするとお仕置きに入れられてしまう『おしいれ』の2つが、園児達にとってこわいものとなっています。ある日いたずらっこのさとしとあきらが、悪ふざけをして罰としてみずの先生におしいれに閉じ込められてしまいます。2人は、その押入れの中で不思議な冒険を体験することになります。保育園が舞台なのですが、実際は結構文字の多い作品のため(自分で読む場合には)2年生くらいが対象のようです。また絵本とはいっても、鉛筆書きのモノクロのイラストがついており、とても個性的なものになっています。ちなみに私は、これを小学校の時に学校の推薦図書だか、読書感想文かなにかで読んだような記憶があります。ネットでたまたま検索をしていて、世代を超えて現在までずっと読み継がれているベストセラー(ロングセラー)になっているということをはじめて知りました。
このおしいれのぼうけんの公式サイトには、広末涼子さんの毎日新聞のインタビュー記事が掲載されています。またスチャダラパーのアニ氏が、この主人公の少年のモデルという意外な話もあります。作家さんと近所で、遊んでいるところを取材されたのだとか。さくらほいくえんという舞台も(みずのせんせいも)非常にリアリティがあり、こちらもしっかりと取材がなされているのかもしれません。また、おしいれのなかより幻想的な冒険が始まるのですが、ねずみばあさんの追跡を振り切ってトンネルを抜けると突然深夜の高速道路に出る展開など、不思議な現実感もあったりします。そういったところも、世代を超えて今の子供達にも愛読されている理由の一つなのでしょうか。時代が変わっても、人の根本的な部分というのはそれほど変わらないのかもしれませんね。それにしても、吸収力(感受性)の強い子供の頃に読んだ書籍というのは、いつまでも強い印象で残っているものです。