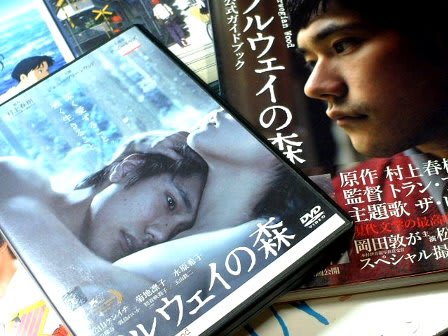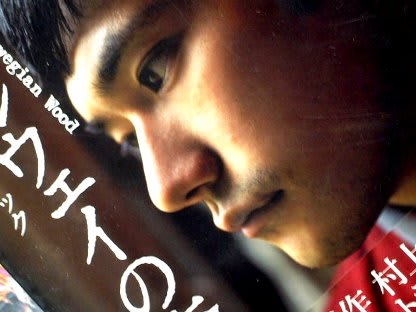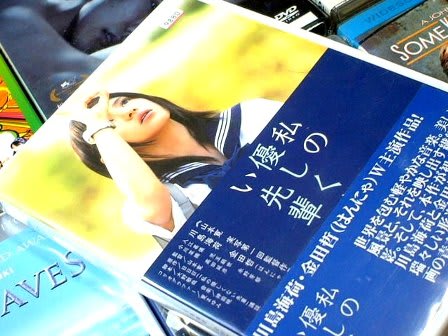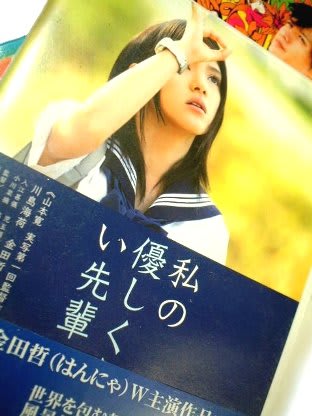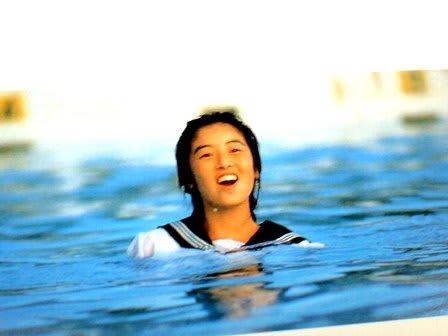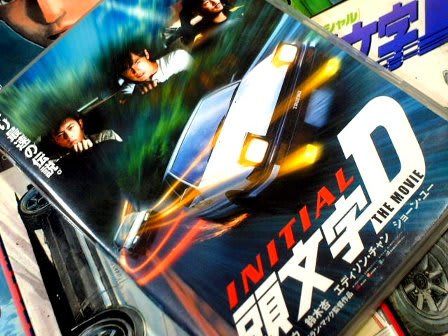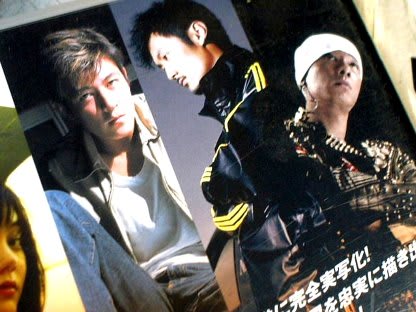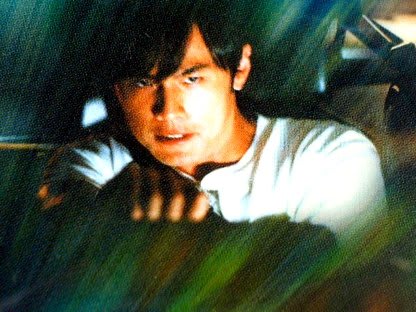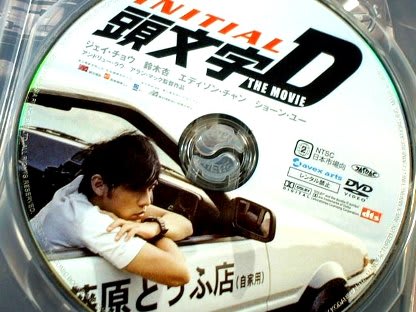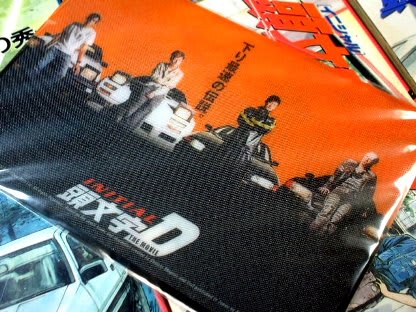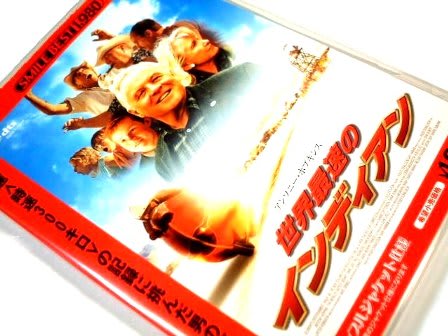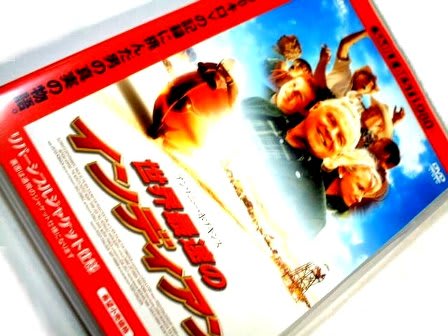スーパーカブ SUPER CUBは、2008年に公開されたアクション映画。スーパーカブ2 SUPER CUB2~激闘編は、同年に公開された続編。

そのタイトル通り、ホンダのスーパーカブ SUPER CUBをメインに据えて、アクション映画に仕立てたという世にも珍しい作品。郵便配達や出前で実用車として使われるスーパーカブにバイクアクションをさせています。主演は、映画版タッチで双子の主人公を演じた斉藤慶太さんと、NHK連続テレビ小説ウェルかめの主演女優にもなった倉科カナさん。主人公にバイクを託す蕎麦屋の主人役に、元一世風靡の小木茂光さんと、主人公行き付けのバイク屋の店主に風間トオルさんなどが出演しています。

主人公の浜田武史は、峠ではバイク最速の男であり、走り屋の仲間内でHAMMEと呼ばれていた。ある日事故を起こしてしまい、免停をくらってバイクを取り上げられてしまう。挙句に学校も中退して、父親の親友である蕎麦屋に面倒をみてもらうことになる。蕎麦屋でのバイト生活を余儀なくされ、バイクにも乗ることを禁じられた主人公だが、ある時店のガレージの片隅で出前用のバイクであるスーパーカブを見つける・・・。

ということで、前半は仲間内で評判の腕利きライダーを、いかにしてカブに乗せて、そのカブの能力(魅力)を引き出すのかという設定に説得力を持たすための物語になっています。後半では、そこにバイク窃盗団が絡み主人公が事件解決をするという展開になりますが、物語自体にはあまり説得力はなく、はっきりとしたチューン描写もないカブでリッターバイクをぶち抜いたりと、わりとなんでもありの話になっています。いかにしてカブにアクションをさせるかというところに力点が置かれており、それ以外のことにはあんまり関心が払われていないようにも。まさにスーパーカブのためだけの映画。

2008年の映画だというのに、峠で最速を競うバイクはなぜかカワサキのZXR250とホンダの88'NSRと、実に20年前のバイクです。若者が夜な夜な峠に集まり、峠道を勝手に封鎖してバトルが行われてます。バイクの走り屋の走りを見るために、女子高生がわざわざ峠にやってくるなど、どこのファンタジーゾーンですかという設定。80年代~90年代頃のバイクブームの頃には、バリバリマシンという峠道での膝すり写真を投稿するための専門誌があったりしましたが、ここだけ時間がその時代に戻っています。ということで、バイクの好きなおやじのためのファンタジーということでよいのだと思います。

続いて続編であるスーパーカブ2 SUPER CUB2~激闘編。前作が劇場公開作品であったのに対して、こちらはオリジナルビデオ(Vシネマ)での展開となりました。

物語は、蕎麦屋の出前を続けている主人公の元にある出前の依頼が入る。それは蕎麦屋の店主の友人のために、東京から山梨県甲府まで出張出前をこなすというもの。無事役目を果たした主人公たちは、その帰りにこの友人よりあるものを託される。それは悪徳警察官の麻薬取引に関する証拠となるものであった・・・。前作では、バイク窃盗団が相手でしたが、今作では国家権力と暴力団。道路封鎖による検問やパトカー、ヘリに追われながらの逃走劇となります。

前作には、バイクを題材とした青春映画の趣もあったのですが、こちらはスケールアップしてカースタントアクションのノリ。さらにロードムービーの要素もある。前作でもストーリーにリアリティがないと感じる部分はあったのですが、こちらでは悪徳警官の協力者として、元白バイ乗りで現在では酪農を営んでいる刺客が登場します。カワサキのモンスターバイクZZRとの対決で、これだけでもありえないのですが、終いにはZZRからミサイルまで発射してくる超展開に。つじつまやリアリティを気にしながら見ていると、ここでずっこけます。ということで、もうリアリティうんぬんいう映画ではありません。

ただストーリーが単純な分、アクション映画としてはこちらの方が楽しめます。スーパーカブでのアクションを見るためのお馬鹿映画として、お気楽に見ればよいのだと思います。

スーパーカブ(カブ)は、1958年から現在に至るまで製造され続けているホンダ製のオートバイ。出前や郵便、新聞の配達など実用車のイメージが強いバイクですが、最初アメリカではレジャーバイクとして売られ、ホンダがアメリカに進出する際の足がかりとなった。ビーチボーイズがリトルホンダというカブの歌を作り、ホンデルズ(The Hondells)がカバーしてビルボード9位にも輝いたほど。最初は、青春の象徴でもあったんですね。その後、北米やヨーロッパでの販売は落ち着きますが 、今度はアジア圏での販売が伸びてゆき、輸送用の機械の一機種としては世界最多量産・販売台数を誇るまでになりました。

バイクブームの頃だと、バリバリ伝説、あいつとララバイ、ふたり鷹、万歳ハイウェイなど、バイクを題材とした作品もある程度あったのですが、90年代以降にはその数も減少。特に、カブや原付などの実用車ともなるとかなり貴重。写真は、西風氏が90年代の終わりにバイク誌に連載したSEX MACHINE。リトルカブやモンキー、ベンリィ、ドリーム50など、原付を題材とした作品。そういった意味では、これもかなり貴重な作品だと思います。

ということで、バイクに興味のない一般の人向けだと星★~★★、バイク好きには星★★★★、カブやモンキーなど原付好きな人には星5つと、見る人を選ぶ作品だと思います。

参考:Wiki スーパーカブ(映画)、ホンダ・カブ、リトルホンダの項