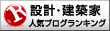人生の潤いを生み出す暮らしの空間を
設計デザインのチカラで・・・・・。

※玄関からリビング空間へ続く間取り動線の改善
よく考えられた家を建てると
暮らしが楽しくなる。
住まいのリノベーション(リフォ―ム)工事が
現場で進んでいる
(仮称)暮らしの自由度を愉しむフレキシブルモダンの家

※キッチン背面のシステム収納(設備建材メーカーTOTO商品提案)
選定提案させていただいた
壁紙(クロス)も貼られた状態で
室内の仕上げがほぼ「見える化」
が出来た状態に。

※間取り改善と空間改善で提案したアイランド設置でのキッチン(設備建材メーカーTOTO商品提案)
インテリアの連動の意味も
分かりやすくなる状態なので
周辺要素と
予め行っている提案と連動した状態で
今後はソファやダイニングテーブル
ウインドートリートメントとなる
カーテンやブラインド類の
採用提案確定等での「インテリアコーディネート」が
メインの提案に移行しますが
前もっての現場監理調整も、
もう少し残っているので・・・・・。
機能だけではなくて
空間構成にきちんと連動する
キッチンや水まわり商品の
提案と選定を行ったうえで
採用にいたりますが、
LDKに設置するキッチンは
見える場所になる場合
特に重要・・・・・。
フォーカルポイントにするのか?
逆に馴染む
商品選定をするべきか?
室内は色と素材感の効能で
雰囲気が決まってきますから。
存在させる意味を
はき違えると機能が良くても
残念なキッチンになりますからね。
それは他の水まわり商品も同じ。
それらを踏まえつつ
空間構成の話し・・・・・。
工事期間中の床養生を
はがす事の出来る状態になれば
提案のうえ採用の
ブラックチェリーフローリングの効能も
空間構成にプラスされますよ。

※LDK空間・壁紙の提案と採用明るさの調整と雰囲気の組み立て
色と素材の効能は
空間構成に重要ですから。
照明器具はそこに連動します。
部屋全体を照らすダウンライトも
ありますが、
部分的に照らすダウンライトも
今回は採用しています。

※壁のセンターを照らすのではなく「ズレ」で陰影と奥行をデザイン
タスク域照明とアンビエント域照明。
両方を兼ね備える
タスクアンビエント照明計画等。
省エネ的にも
照明の役割として
空間領域的にもそれは重要で
タスクアンビエント照明とは、
簡単に言うと、作業(task)領域と
それを取り巻く周辺(ambient)を
ちょうどよく照らす照明のことです。
無駄に全体を均一に照らすのではなく、
必要なところに
必要な明かるさで照らす、
という至ってシンプルな考え方。
これにより無駄な電力を抑えつつ
効率的であり「効果」を得る雰囲気も
生み出す事が可能になりますから。
何よりもそれにより
光の範囲に濃淡が生まれることで
場の持つ雰囲気に奥行きや
立体感が生まれます。
素敵なカフェやレストランを
想像してみてください。
キチンと考えて
デザインにより計算された空間は
店内は薄暗い暖色系の照明(ambient)、
厨房は調理に必要な明るい照明(task)、
テーブルには料理を照らす
ペンダント照明(task)が存在して
そこにほんのりと漂う香り、
背景に流れる心地よい音楽、
そして美味しい料理やお酒が
組み合わさることで「雰囲気」が醸成され、
とてもリラックスできるという体験は
皆さんも感じた事が
あるのでは?。
少し話はそれますが、
谷崎潤一郎の小説「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」には
僕にとって非常に印象的な
一節が登場します。
つまり金蒔絵は明るい所で
一度にパッとその全体を見るものではなく、
暗い所でいろいろの部分が
ときどき少しずつ
底光りするのを見るように
出来ているのであって、
豪華絢爛な模様の大半を
闇に隠してしまっているのが、
言い知れぬ叙情を催すのである。
(中公文庫「陰翳礼讃」P26より引用)
見えるべきもの全てが
一度に見えない方がいい、
という辺りを初めて読んだときは
一瞬ドキッとしましたが、
鈍い光により部分的に見える状態にこそ
趣が生まれるというところには
妙に納得したものです。
光ではなく陰に焦点を当てるという
逆転の発想で生まれる
谷崎潤一郎の美意識には
とてもシビれました。
部屋が明るいと
全てが一度に見えてしまい、
空間が均質になり味気ない。
しかし部屋に適度な闇が潜むことで、
明るさに濃淡が生まれ、そ
こに「言い知れぬ叙情」が
浮かび上がってくる。
そしてこの「言い知れぬ叙情」こそが、
居心地の良さに
密接に関連しているというところ。
以上のような経験から、
僕が照明提案を調整して
プランニングをする際には
明かりと灯りというものを
強く意識するよう心がけていますよ。
建物がどんなに素晴らしくても
明かりと灯りで失敗していたら、
居心地の良さも半減です。
だからそれらを囲う空間に
光の反射や色の濃淡を意識する提案を
カタチにしているんです。
勿論住まい手さんの価値観に応じて。
逆に何の変哲のない部屋でも
明かりで成功していたら、
そこに居心地の良さが生まれます。
20世紀の偉大な建築家
ミースファンデルローエの
より少ないことは、より豊かなこと(Less is more)
のように。
明かりと灯りはそれくらい
無視できない要素。
決して蔑ろにすべきではないと
感じています。
明かりには照明だけではなく、
もちろん外からの光も含まれます。
居心地の感度と部屋構成に
そういうったところ
少し考えてみてください。
住宅計画での思考の範囲は
家の事を考える事も大切にしつつ
暮らし全体に意識を向けて。
ご相談、面談のご希望は
ホームページ「お問い合わせ」から。
Produce Your Dream>>>>>
建て主目線+αの提案・・・・・。
明日の暮らしを設計する
建築と住まいとその暮らしを豊かに
URL(ホームページ)
<<<Yamaguchi Architect Office