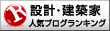自然災害に備える
住まいづくりの基本
奈良という土地で
安心して暮らすために.

※木造住宅新築現場・骨組みの状態
日々、設計という
仕事を通じて
どのような住まいが、
家族の安心と
心地よさを支えるのか
という問いと
向き合っていますが
それらは建物単体で
完結するものでは無くて
敷地や周辺状況にも
大きく左右されるものです。
近年は全国各地で
自然災害が頻発し、
今更ながらですが
「災害に強い家づくり」が
注目されています。
特に奈良県においても、
地震や豪雨など、
過去には大きな被害が
記録された地域が
いくつもあります。
そんな奈良という
風土の中で、
家族と大切な日々を
安心して暮らすために、
どのような
備えができるのかを
テーマに、
自然災害に強い家づくりの基本を
建築家の視点から
少し書いてみたいと思います。
土地選びの第一歩
奈良のハザードマップを読む
既存の建て替えという場合や
リフォームという場合も
ありますが
住まいづくりの
第一歩は、
やはり「土地選び」です。
ここで最も大切なことの
ひとつが、
その土地が自然災害のリスクに
どの程度さらされているかを
知ることです。
特に奈良県内では、
吉野川や大和川流域における
水害のリスクや、
紀伊山地周辺における
土砂災害リスクが
過去の実例からも
知られています。
その判断に欠かせないのが、
各市町村が公表している
ハザードマップの確認です。
これは、
洪水・内水氾濫・土砂災害などの
リスクを地図上に
可視化したもので、
地形や過去の災害履歴から、
色分けされたエリアを
ひと目で確認することが
できます。
たとえば、
奈良市や橿原市、
桜井市の一部では、
古来より湿地帯や
河川が多く存在していたため、
現在でも洪水リスクが
高い区域が
点在しています。
このような場所では、
いくら利便性が高くとも、
災害リスクと
どう向き合うかを
十分に検討する必要が
あります。
土地のご相談をいただいた際は、
ハザードマップなども確認し、
住まい手さんと
一緒にリスクの共有を
行っております。
立地条件の良とさと
安心して暮らせる環境は、
時として
トレードオフになることも
ありますが、
だからこそ納得した選択が
必要になります。
奈良の地盤と地震への備え
奈良県は比較的
地震が少ない地域と
見られることもありますが、
実際には、
過去に大きな被害をもたらした
「南海トラフ巨大地震」の
影響を受ける恐れもあり、
安心はできません。
また、
奈良盆地には堆積層が厚く、
地盤が柔らかい
地域も多いため、
同じ震度の揺れでも
建物への影響が
大きくなりやすい
傾向があります。
そして建築の計画の為にも
地盤の強さや
支持層の深さを
正確に把握することが
不可欠です。
調査の結果、
軟弱地盤であると
判明した場合には、
地盤改良工事等が
必要となります。
工法には表層改良、
柱状改良、
鋼管杭工法などがあり、
内容や規模によって
費用が異なりますが、
一般的に70万〜90万円前後の
費用がかかることが多く、
建物の規模などにもよって
大きく差が出ます。
これは土地購入後の
思わぬ出費として
計画を圧迫する
ケースもあります。
したがって、
土地探しの段階から
ある程度の
改良費用を
住宅の総予算に
含めておくことを
おすすめしております。
地盤の安全性を
無視した住まいづくりは、
例えるなら
柔らかい土の上に
重たい石を乗せる
ようなもので、
非常に危険です。
建物だけでなく、
「その土台となる地盤」こそが、
命を守る最初の要です。
建物構造と耐震設計の考え方
建物の「構造」は、
災害への備えの
中心となる部分です。
日本では主に、
耐震・免震・制震の
3つの技術が存在します。
耐震:揺れに「耐える」
最も基本的な考え方であり、
建物を強く
固くつくることで、
地震の揺れに
耐える構造です。
特に新築住宅においては、
耐震等級3(最高等級)を
目指すことが
安心のひとつの
目安となります。
制震:揺れを「吸収する」
建物内部に
ダンパー(制震装置)を
設けることで、
構造躯体の揺れを抑え、
繰り返す地震に対して
建物の損傷を軽減します。
奈良県のように
比較的静かな
地震環境の地域でも、
今後の南海トラフ地震を
想定すれば、
有効な対策といえます。
免震:揺れを「逃す」
建物と基礎の間に
免震装置を設け、
地面の揺れを
直接建物に
伝えにくくする技術です。
コストはかかりますが、
美術館や病院など、
重要施設で
多く採用されています。
個人住宅においては、
耐震性の確保を
基本としつつ、
必要に応じて
制震技術を取り入れることが、
現実的かつ
バランスの良い選択と
いえるかと思います。
間取りと耐震の関係
美しさと強さの両立・・・。
耐震性の高い家をつくるには、
建物の形状や
間取りのバランスも
非常に重要です。
例えば、
2階建ての住宅では、
1階と2階の
柱や壁の位置が揃っていると、
構造的に力の流れが整い、
地震に強い家となります。
また、
建物の形状が
極端にL字型や
コの字型など不均衡であると、
地震の際に“ねじれ”が生じ、
倒壊リスクが
高まることがあります。
※構造検計算(種類が様々あります)にて
検討する事でリスク回避を設計します。
ただし、
構造の制約ばかりを
優先すると、
「住み心地」や
「デザインの自由度」が
制限されてしまうという
ジレンマが生じますが
設計としては
構造の合理性と
空間の快適性、
その両立を実現することを
念頭に「暮らし」を改善できる
間取りとなるように
意識しています。
最も安全で、
最も美しい空間とは、
見えない部分にも
意味がある空間であると
考えています。
住まい手さん自身の
理想を大切にしながらも、
目には見えない
安全性という価値を
建物の隅々にまで
織り込むこと。
奈良という土地で
「安心」と「快適」を両立する。
奈良県は、
古都としての歴史と
美しい自然に恵まれた、
非常に魅力的な土地です。
一方で、
盆地特有の
夏の暑さ・冬の寒さや、
ゲリラ豪雨の増加、
そして将来的な
南海トラフ地震など、
見えにくい災害リスクも
存在します。
住まいに「安心」と「快適」、
両方をバランス良く
備えることを大切に。
たとえば、
太陽光発電+蓄電池の導入により、
停電時でも
最低限の生活が可能に。
断熱性の高い
外皮設計によって、
猛暑や厳寒に
左右されにくい
住環境を考える事。
通風計画や
自然採光の工夫により、
日々の暮らしに
やさしさと
心地よさを届けること。
これらはすべて、
災害対策と
日常の暮らしを支える
「住まいの力」です。
自然災害は、
誰にとっても
遠い出来事ではありません。
しかし、
そこに過度な不安を抱く
必要もないと考えています。
大切なのは、備えと選択
そして、「納得」です。
この奈良という
穏やかな地で、
何十年先までも
ご家族が笑顔で
過ごせる住まいを、
一緒にかたちにしていきませんか?
やまぐち建築設計室は
その家に暮らす家族の過ごし方を
デザインする設計事務所です。
‐‐----------------------------------------
■やまぐち建築設計室■
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
建築家 山口哲央
https://www.y-kenchiku.jp/
住まいの設計、デザインのご相談は
ホームページのお問合わせから
気軽にご連絡ください
------------‐-----------------------------