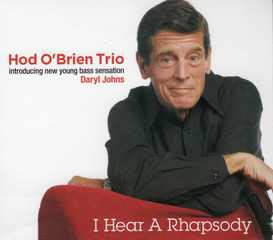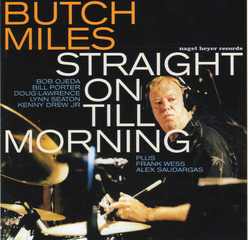Touch Of Love / 宮之上 貴昭 & Jimmy Smith
ライブハウスというと都心にあると思いがちだが、最近では郊外にも多い。自宅の近くにあるライブハウスには一度は行ってみたいと思うが、きっかけがないとなかなか出向く機会がない。先日も書いた気がするが、やはり誰か知っているメンバーが出ている時でないと。
先日、そんなライブハウスにギターの宮之上貴昭が出るというので行ってみた。自宅からは車で10分足らずの武蔵境のフォンタナ。駅からは少し離れているが、同じ町内といっても良い距離だ。今回一緒のメンバーはトロンボーンの駒野逸美。このコンビは以前別の所でも聴いたこともあり、内容も勝手知った演奏だったので初物の楽しみはなかったが。
最初に演奏した曲が、宮ノ上のオリジナルで、ジミースミスと共演したアルバムで演奏したSmokin’ in the rainでスタート。スタンダード中心にジャズの名曲やオリジナルも交えていたが、宮之上の曲はどれも演奏スタイル同様メロディアスでスインギーだ。途中、ボーカルの飛び入りもあったが、持参した譜面も不要と、絶妙の歌伴も聴けて楽しいセッションであった。

この宮之上とジミースミスのアルバムというと宮之上がデビューしてまだ間もない1981年、ジミースミスが来日した時に録音したアルバムだ。ギターとオルガンというと相性がいい組み合わせだが、曲によってはヴァイブやテナーも加わってさらに彩を加えている。
ジミースミスとウェスモンゴメリーというとアルバムDynamic Duoが有名だが、ウェス信奉者の宮之上にとっては、願ったりかなったりの共演で、オリジナルのデュオにどこまで迫れるかといった感じであったろう。
このようなセッションにはエピソードが付き物だが、最近の自身のフェースブックでもその出来事を記事にされていたので、以下に転載させて頂く。
〜〜 以下転載 〜〜
「ジミー・スミスに捧ぐ」
ジャズオルガンの神様ジミー・スミスが亡くなって
今月で8年になるんですね。
わたしが28歳の時にジミー・スミスとのレコーディングが決まり、
彼の来日歓迎パーティがあるとのことで、ディレクターと大阪に飛んだ。
しかし神様はこのパーティで演奏するギャラのトラブルか、
待てども暮らせども会場に来ない。(*_*;
さらに待つこと1時間半。
ようやく会場に現れたジミースミスはものすごく恐い表情。
しかしオルガンに座ると夢にまで描いたジミーサウンド炸裂!!
でも2曲ほど短く弾き切るとすぐにステージを離れて休憩した。
そんな中、今でいうKYなディレクターがジミーに近づいて
「This is Japanese Wes Montgomery,Yoshiaki Miyanoue」
Σ(゜Д゜)
ジミーはわたしに向かってこう言いました
「I like Wes, I love Wes, but I don't like copy!」
ひぇ~~(*_*;
これから一緒にステージに上がるというのに何ということを!!
※当時のわたしは今よりずっとウェス色強烈でした(汗)
ジミーは「You like Wes...hum, You must be know this tune」
そう言っていきなり「Baby it's cold outside」を弾きはじめました。
わたしは初めて演奏する曲でしたけど、
ウェスとジミーのレコードで聴いたことはあります。
テーマでコード進行を頭に叩き込み、
思いっきりウェスのように演奏しました。
だってそれしかできなかったんですから。
演奏途中からジミーの顔は笑顔に変わり、
ステージを終えると熱烈なハグをされました。
(一体ウェスのコピーはDon't like、何だったんでしょう)
〜〜 以上転載終わり〜〜
この頃は、このような来日大物ミュージシャンとの共演アルバムが良く作られたが、若手でも動じることなく素晴らしい演奏が多く残されている。
ここでも二回り近く年上の大先輩であり超有名スターのジミースミスの胸を借りる共演だが、全体は宮之上ペースで、ジミースミスは脇役ゲストといった感じだ。というのも、宮ノ上の物おじしない余裕のプレーは、下積み時代は横田基地のクラブで演奏し、アメリカで武者修行をしてからデビューをしたという経験が生きていたからだと思う。
この手の共演だとスタンダード曲が多いが、ここではSmokin’ in the rainだけでなく宮之上のオリジナル曲が中心。ジミースミスのオルガンだけでなく、ヴァイブとテナーを曲によって適宜加えているが、これも2人の演奏に実によくブレンドされアルバムとしての纏まりもある。
最後は、今回のレコーディングに付き合ってくれたジミーに謝意を表して、ギターとベースで自らのリズムギターをオーバーダビングして「サンキュー・ジミー」で締める。
演奏はジミースミスのオルガンに合わせてブルージーな黒っぽい感じが基本だが、ジャケットの白地のデザインに合わせたような洗練されたサウンドでもある。
昔はこんなデモツールもありました。↓
1. Fried Cornbread
2. Georgia On My Mind
3. Smokin’ In The Rain
4. Body And Soul
5. Touch Of Love
6. Tokyo Air Shaft
7. Thank You, Jimmy
Yoshiaki Miyanoue 宮之上 貴昭 (g)
Jimmy Smith (org)
Kenny Dixon (ds)
Hiroshi Hatsuyama 初山 博 (vib)
Q. Ishikawa 石川 久雄 (ts)
Yuzo Yamaguchi 山口 雄三 (b)
Produced by Shigeru Kurabayashi 倉林 茂
Engineer : Haruo Okada 岡田 治男
Recorded at AOI Studio on September 26, 29 1981
ライブハウスというと都心にあると思いがちだが、最近では郊外にも多い。自宅の近くにあるライブハウスには一度は行ってみたいと思うが、きっかけがないとなかなか出向く機会がない。先日も書いた気がするが、やはり誰か知っているメンバーが出ている時でないと。
先日、そんなライブハウスにギターの宮之上貴昭が出るというので行ってみた。自宅からは車で10分足らずの武蔵境のフォンタナ。駅からは少し離れているが、同じ町内といっても良い距離だ。今回一緒のメンバーはトロンボーンの駒野逸美。このコンビは以前別の所でも聴いたこともあり、内容も勝手知った演奏だったので初物の楽しみはなかったが。
最初に演奏した曲が、宮ノ上のオリジナルで、ジミースミスと共演したアルバムで演奏したSmokin’ in the rainでスタート。スタンダード中心にジャズの名曲やオリジナルも交えていたが、宮之上の曲はどれも演奏スタイル同様メロディアスでスインギーだ。途中、ボーカルの飛び入りもあったが、持参した譜面も不要と、絶妙の歌伴も聴けて楽しいセッションであった。

この宮之上とジミースミスのアルバムというと宮之上がデビューしてまだ間もない1981年、ジミースミスが来日した時に録音したアルバムだ。ギターとオルガンというと相性がいい組み合わせだが、曲によってはヴァイブやテナーも加わってさらに彩を加えている。
ジミースミスとウェスモンゴメリーというとアルバムDynamic Duoが有名だが、ウェス信奉者の宮之上にとっては、願ったりかなったりの共演で、オリジナルのデュオにどこまで迫れるかといった感じであったろう。
このようなセッションにはエピソードが付き物だが、最近の自身のフェースブックでもその出来事を記事にされていたので、以下に転載させて頂く。
〜〜 以下転載 〜〜
「ジミー・スミスに捧ぐ」
ジャズオルガンの神様ジミー・スミスが亡くなって
今月で8年になるんですね。
わたしが28歳の時にジミー・スミスとのレコーディングが決まり、
彼の来日歓迎パーティがあるとのことで、ディレクターと大阪に飛んだ。
しかし神様はこのパーティで演奏するギャラのトラブルか、
待てども暮らせども会場に来ない。(*_*;
さらに待つこと1時間半。
ようやく会場に現れたジミースミスはものすごく恐い表情。
しかしオルガンに座ると夢にまで描いたジミーサウンド炸裂!!
でも2曲ほど短く弾き切るとすぐにステージを離れて休憩した。
そんな中、今でいうKYなディレクターがジミーに近づいて
「This is Japanese Wes Montgomery,Yoshiaki Miyanoue」
Σ(゜Д゜)
ジミーはわたしに向かってこう言いました
「I like Wes, I love Wes, but I don't like copy!」
ひぇ~~(*_*;
これから一緒にステージに上がるというのに何ということを!!
※当時のわたしは今よりずっとウェス色強烈でした(汗)
ジミーは「You like Wes...hum, You must be know this tune」
そう言っていきなり「Baby it's cold outside」を弾きはじめました。
わたしは初めて演奏する曲でしたけど、
ウェスとジミーのレコードで聴いたことはあります。
テーマでコード進行を頭に叩き込み、
思いっきりウェスのように演奏しました。
だってそれしかできなかったんですから。
演奏途中からジミーの顔は笑顔に変わり、
ステージを終えると熱烈なハグをされました。
(一体ウェスのコピーはDon't like、何だったんでしょう)
〜〜 以上転載終わり〜〜
この頃は、このような来日大物ミュージシャンとの共演アルバムが良く作られたが、若手でも動じることなく素晴らしい演奏が多く残されている。
ここでも二回り近く年上の大先輩であり超有名スターのジミースミスの胸を借りる共演だが、全体は宮之上ペースで、ジミースミスは脇役ゲストといった感じだ。というのも、宮ノ上の物おじしない余裕のプレーは、下積み時代は横田基地のクラブで演奏し、アメリカで武者修行をしてからデビューをしたという経験が生きていたからだと思う。
この手の共演だとスタンダード曲が多いが、ここではSmokin’ in the rainだけでなく宮之上のオリジナル曲が中心。ジミースミスのオルガンだけでなく、ヴァイブとテナーを曲によって適宜加えているが、これも2人の演奏に実によくブレンドされアルバムとしての纏まりもある。
最後は、今回のレコーディングに付き合ってくれたジミーに謝意を表して、ギターとベースで自らのリズムギターをオーバーダビングして「サンキュー・ジミー」で締める。
演奏はジミースミスのオルガンに合わせてブルージーな黒っぽい感じが基本だが、ジャケットの白地のデザインに合わせたような洗練されたサウンドでもある。
昔はこんなデモツールもありました。↓
1. Fried Cornbread
2. Georgia On My Mind
3. Smokin’ In The Rain
4. Body And Soul
5. Touch Of Love
6. Tokyo Air Shaft
7. Thank You, Jimmy
Yoshiaki Miyanoue 宮之上 貴昭 (g)
Jimmy Smith (org)
Kenny Dixon (ds)
Hiroshi Hatsuyama 初山 博 (vib)
Q. Ishikawa 石川 久雄 (ts)
Yuzo Yamaguchi 山口 雄三 (b)
Produced by Shigeru Kurabayashi 倉林 茂
Engineer : Haruo Okada 岡田 治男
Recorded at AOI Studio on September 26, 29 1981