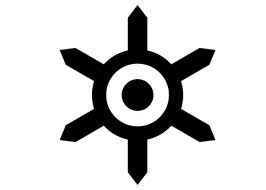(COREDO日本橋)

(日本橋)
東京駅から歩いて、日本橋にやってきたら、
日本橋の東側に出た。
(日本橋)の信号の向こう左角に、COREDO日本橋がある。
ここは昔、白木屋デパートがあった所。
東急デパートの五島慶太が白木屋を買収したが、
売れ行き不振のため閉店、300年に及ぶデパート業から退いて、
今はCOREDO日本橋になっていて、
テナントが沢山入っている。
ビルディングを見ると船の帆のようで、横浜ミナトミライのホテルや、
ドバイのホテルに良く似た建物だ。
話はさかのぼるが、あまりにも強引な手口で、白木屋を買収したので、
当時、五島慶太のことを、もじって強盗慶太といったくらいである。
現在のCOREDO日本橋も、中に入っているテナントは、
儲かっているのか儲かっていないのか、解からないくらい、
普段の日のせいかもしれないが、お客様が入っていなかった。
しかし外界は、普段の日だというのに、人が沢山出ている。
さすが江戸の中心地と言う感じがする。
日本橋と言うだけで、観光に来ているのだろうか?
そう言うボクも東京見物をしているのだから・・・
(普段の日だと言うのに人出が多い、左手は日本橋三越)

そのCOREDO日本橋のビルの手前の信号を左折すると、
目指す「日本橋」がある。
写真では、「日本橋」の文字が二階の高速道路にかかっていて、
川のうえに架かっている本物の「日本橋」の橋は、この道路の下にある。
なんだか奇妙な感じもするが、これが東京という所だ。
ボクが東京へ始めてきた時、下宿先が世田谷であった。
友人が前もって探しておいてくれたもので、
ボクは何しろ東京は始めて。
(渋谷から「上町」方面行きの玉電に乗って、「松陰神社前」駅で降りろ。
そこから公衆電話で連絡をくれ。)
友人が言ったことを頼りに、渋谷で電車を探した。
電車は確かハチ公前から乗ったように思うが、
路面電車であるはずなのに、
乗車場所が二階にあったのには驚いた。
それから思えば日本橋の文字が、二階部分の高速道路にあるのは、
別におかしくも何でもない。
この「日本橋」の文字は、徳川幕府最後の将軍、
徳川慶喜が書いたものだそうだ。
(二階の高速道路に日本橋の文字はある)

「日本橋」の橋から西に向かい(日本橋)の信号までは、
国道一号線、つまり、東海道と甲州道中につながっている。
近づくと、日本橋の文字の向こう側が、目指す日光・奥州道中である。
詳しく言えば、奥州道中、日光道中、中山道が日本橋を基点に、
並んで進む。
三本の道があるような言い方になったが、
道路は一つで、中山道は直進であるが、
日光道中と奥州道中は約100m先、
(室町三丁目)信号を右折する事になる。
日光道中と奥州道中は、宇都宮まで同じ道を進み、
宇都宮で分岐して、左へ行けば日光へ、右へ行くと奥州白河へ行く。
今回、こうしてボクは奥州へ向っていくことになる。
(室町三丁目の信号)

さて、日本橋であるが、欄干の両側には奇妙な彫刻が置いてある。
西側の欄干には、「うん」と口をつぐんだ獅子が妙なマークを足で押さえ、
東側には「あ」と口を開いた獅子が、
これまた同じ妙なマークを足で押さえつけている。
東西の欄干にある獅子像は、神社やお寺の本堂前にある「阿吽」の狛犬像で、
足で押さえているのは、東京都になる前の東京市のシンボルマークである。
(「阿吽」の獅子像 東側、東京市のシンボル・マークを持っている)

(西側の獅子像)

つまり、東京に入るということは、
世間のあらゆる森羅万象の間を潜り抜けて入る場所、
寺院で言えば本堂、神社で言えば神殿、
人間社会で言えば超金持ちから超貧乏人がいる東京、
政治家が言う極楽社会に入るという事のようだ。
狛犬が足で押さえている元東京市マークは、
現在、東京都水道局が使用しているらしく、
マンホールの蓋にデザインされているのを、よく見かける。
(東京市マーク)
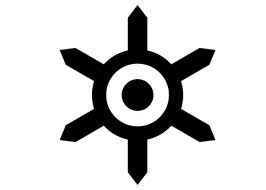
(水道局のマーク)

(水道局のマーク2)

(水道局のマーク3)