
西湘バイパスが邪魔しているので、歩きだと海に出るにはその下をくぐらなくてはなりません。当然のことながら、くぐって初めて海が出現するわけです。車を優先すると、とんでもない光景になることは、日本橋などと同じ。車窓からの眺めの素晴らしい海沿いのバイパスを走るのは気持ちいいものですが、住んでいる人にとっては 結構迷惑なものかもしれないな、と思いました。


連休にしては人出の少なすぎる静かな海岸の風景です。この辺の海は、途中から急に深くなり危険なので遊泳禁止だそうですが、自分達は慣れているから、ヘッチャラでよく泳いだもんだ、と昔の地元の子供たちが話していました。

波打ち際に大きな魚の屍が・・・

夫が昔住んでいた家の辺りにも連れて行ってもらいました。同級生の、地元への定着率が割と高いらしく、ここは〇〇ちゃんの家だ、と私に教えてくれながら歩き回り、町内会の神酒所でも同級生の一人と会い、缶ビールを頂いちゃいました。
そこで幼なじみ男衆4人をパチリ。ウフフ・・・それぞれ様々な年の重ね方で面白い。
出世した誰々は線路の反対側のお屋敷町へ引っ越した、と話していましたが、ちょっと寂びれた海側も私の目には、味わいがある、と映りました。

ドアではなく、引き戸をガラガラと開けてから「こんにちわ~」って言っていた時代、ありましたよね。鍵を掛けないで住める家って、もはやダンボールハウスしかないのでしょうか。

魚屋さんの看板がいいカンジ。下の写真の家などは、隣が空き地になっていたので、奥行きの木造部分が全部見れました。中へ入って階段を昇ってみたくなります。



某天皇陛下が小田原を訪れた時腹痛におそわれ、この(画像上)内科医院で診療を受けたと知り得たのは、私が写真を撮っていたから。門構えと洋風な窓が対照的だし、表札に内科医院の字がなければ、個人宅にしか見えませんものね。
あれっ、ここ新宿って地名なのね、と言うと地元の一人が、「シンシュク」と読むんだ、と教えてくれました。箱根駅伝のときの通過地点なんです。紙垂の付いた榊を持って、急ぎ足で歩いていた男性。信号待ちのときがシャッターチャンス!と同時に青に変わりました。本当は「新宿」を撮りたかったんですけどね。

小田原のお祭りも、昔のような活気はすでになく、映画館などがあった国際通り(左下)など、今は「シャッター通り」と呼ばれているとか。
国道一号沿いの小さな蒲鉾屋(右下)の前を通ったとき、地元の一人が、ここのは全部手作りで、結構美味しいんだよね、と言うので入ってみました。お勧めの商品が売り切れだったので、別の袋入りさつま揚げを自宅と土産用に購入。手頃な値段で美味しかったですが、とっくに食べちゃったから画像なし。佐倉蒲鉾店だったと思います。


ここは何の店だと思う?と聞かれ、雑貨屋かなぁ、と思ったけど・・

「本屋」さんでした!
「御感の藤」は小田原城址公園の南入口のところにあります。昔、大正天皇を感嘆させたということからこの名前がついたとのこと。花房が一メートルにもなるそうですが、枝振りのわりには華奢な印象を受けました。


お堀のむこうに見えるのは郷土文化館と別館の松永記念館。城内には他にも歴史見聞館や小田原城ミューゼ、報徳二宮神社、そして小田原城などがあり、見どころいっぱいです。約20年ほど前に家族全員で遊びに来たときは、小学校がまだこの城内にありました。木造二階建てが印象的な、今思えばレトロで実に格好いい学校でした。
全国的にも珍しく、その校舎が小田原城址二の丸にあったことで、
歴史保存区域内での建設許可が下りなかった事から、1992年本町
小学校との合併まで木造校舎(1928年新築)のままで利用されて
いた。(webより)


城内にあった小学校に通学するには「学橋」を渡ります。卒業生の一人曰く、
「学橋を毎日渡って登校していたけど、学んだって記憶はないなぁ・・・」
今になって、通った学校がお城の敷地内だったことを、たとえ学んだ記憶がなかろうと、少し誇らしく思えるのかもしれませんね。

学橋を渡ると二の丸広場。その先には歴史見聞館があり、そこが小学校講堂を利用したことを知りました。植え込みに咲いていた花は牡丹?とてもきれいだったのでパチリ。


バス停も、ういろう本店も、こんな風なんですけど、本当のお城(小田原城)は、以前行っているので今回はパス。

小田原を離れるその時まで、4人ずっと一緒だったので、地元の人しか知り得ない色々な話しを聞きながら散策することが出来ました。事前に調べておいたカフェとかなどには全く行ける気配ではなかったし(笑)言い出せなかったです!が、ひとあじ違った滞在のしかたは、滅多にあることではないので面白かったかも、と思いましょう。













































































































 最後に一つだけでいいから公開されている旧家を見たい、と、主張し、大橋家住宅を見学することに。自分はいいから、と、友人は入り口のところで待っていました。ここでも入館料が必要ですが、払ってまで見たくない人もいるのです。
最後に一つだけでいいから公開されている旧家を見たい、と、主張し、大橋家住宅を見学することに。自分はいいから、と、友人は入り口のところで待っていました。ここでも入館料が必要ですが、払ってまで見たくない人もいるのです。


















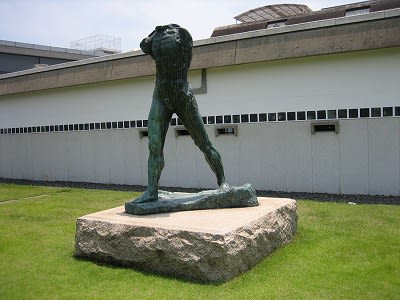
 やっとお昼ごはんの時間で~す。場所は友人が昔、宿泊したという旅館くらしき内のレストランで、花咲き海鮮寿司をいただきました。岡山名物ままかり(サッパというニシン科の魚)も入っているし、何よりお手頃価格のお手軽ランチです。
やっとお昼ごはんの時間で~す。場所は友人が昔、宿泊したという旅館くらしき内のレストランで、花咲き海鮮寿司をいただきました。岡山名物ままかり(サッパというニシン科の魚)も入っているし、何よりお手頃価格のお手軽ランチです。





 古代より神の島として崇められてきたという宮島に到着です。
古代より神の島として崇められてきたという宮島に到着です。 可愛いのでおいでおいでをしたら近寄ってきて、いきなり手に持っていた(宮島の地図の書かれた)一枚の紙をムシャムシャと食べ始めたんです。びっくりしてすぐに取り返しましたがゲンコツ大ほどはかじられました!お腹が空いているのかしら。それにしてもあちこち鹿だらけ。で、地面をよく見るとコロコロした糞がいっぱい。
可愛いのでおいでおいでをしたら近寄ってきて、いきなり手に持っていた(宮島の地図の書かれた)一枚の紙をムシャムシャと食べ始めたんです。びっくりしてすぐに取り返しましたがゲンコツ大ほどはかじられました!お腹が空いているのかしら。それにしてもあちこち鹿だらけ。で、地面をよく見るとコロコロした糞がいっぱい。




 御朱印をいただくとき、値段が表示されてなく、お志でけっこうです、と言われ困った!いつもなら窓口に300円とか書かれているのに、志となると300円はケチくさいかな、それとも気持ちだけでいいなら100円でもいいのかな、と一瞬あたまの中を忙しくセコい考えが一巡。財布をのぞくと小銭がなく、千円を渡して、じゃ500円でお願いします、と言っている私。
御朱印をいただくとき、値段が表示されてなく、お志でけっこうです、と言われ困った!いつもなら窓口に300円とか書かれているのに、志となると300円はケチくさいかな、それとも気持ちだけでいいなら100円でもいいのかな、と一瞬あたまの中を忙しくセコい考えが一巡。財布をのぞくと小銭がなく、千円を渡して、じゃ500円でお願いします、と言っている私。














