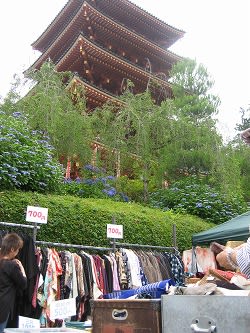ビッグサイトで開催中のイベントに行って来ました。
長かった猛暑から、土砂降りの日を境に一気に秋の気配が感じられる日でしたが、日中はそれでもまだ暑い。ビッグサイトって、電車でも車でも、どちらで行こうと会場までテクテク歩かなきゃならないんですよね。歩く人の身になって建てていない、と同行者に文句を言いながら会場に向かいました。

東展示棟の奥の駐車場を利用しましたが、その前は海。遠くに見える建設中の橋は臨海大橋です。来年開通予定のようですが、第二湾岸としてわが市まで繋がるようになるのでしょうか?早く繋がってくれないと、加齢で更に視力も衰え、運転出来なくなるんですけどね~。
この日はグルメ&ダイニングスタイルショーとギフトショーが目当てでしたが、バイヤーなど、その職種の関係者が多いなかで、私は一体何しに来たんだろう~?って気分にさせられました。

それでもグルメ会場では色々試食・試飲したり、開発中の食品もあったりと、それなりに面白かったです。祖父江町の銀杏コロッケ、土佐の鰹カツとか、青森のリンゴサブレー、山形の柿酢など、いったいどれほど試食したかしら?圧巻だったのは日本全国美酒鑑評会での日本酒の試飲でした!ずらりと並んだ日本酒(冷酒、お燗、個性派の3部門)の中から選んで付属のスポイトで吸い上げ、カップに入れて試飲します。人気のお酒(というか値段の高いもの)はスポイトの先がお酒に届かない。試飲後に用紙に書き込んで鑑評するわけですが、飲み逃げしました。(笑)あ、車で来たんだっけ。きゃっ!と思ったけどあとの祭り。まぁ、何時間もいたから問題なかったけど。
会場は撮影禁止となっていましたが、写真を撮らないとこんなに忘れるもんだ、と、自分の記憶力低下にショックを覚えました。そんな中でも、金平糖入りのカラフルなジェムシュガーが、なぜかとても印象に残りました。私、コーヒーはシュガーレスなんですけどね。

次はギフトショーの会場へ。私がショップを持つとしたら、を頭に描きながら、バイヤーになったつもりで見ている自分。だって会場内ではすぐに、小売店のかたですか?など訊ねられるんですもの。晴海が見本市の会場として使われていた時代から、時々親と一緒に来ていました。こういう場所、好きな方なんですね、きっと。
上代の〇〇掛けで・・など、あちこちから聞こえ、ますますバイヤー気分。お店やさん(ごっこ)、楽しいぃ~!って小学生じゃあるまいし。雑貨、アンティーク風、ハワイアン、玩具、アクセサリー、布、クラフトなど、試作品も含めてみれるのが見本市の楽しさかもしれません。試作のものはアンケートなど書くと何かもらえたり、でしたけど、思考錯誤しながら新商品を創り出しているんだな~、と、良くわかりました。

10日が最終日となりますが・・・もうその日になってしまいました!
会場が広く、東棟を見るだけで精一杯。西棟まで足をのばせませんでした。歩き疲れて筋肉痛に・・。いや、まてよ、そんなわけないよね、と良く考えた結果、前日の体操が原因だ、と気が付きました。
暑すぎた夏の日々、家にいる事が多く運動不足=体重増加、だったのでラジオ体操でもやってみようか、と12時のNHK第二のラジオ放送に併せて体を動かしたからのようでした。ラジオ体操で筋肉痛だなんて恥ずかしすぎですね。けど、少し続けてみようかな。恐怖の「食欲の秋」到来ですもん。


















 お腹がグーグー鳴りっぱなし、なのに、見たい寄りたいところだらけ。一昔前、両親とその親族の全15名で御宿に二泊した際、立ち寄って遊んだ鴨川シーワールドの前を通ったときは懐かしかったです。それは父が計画した初めての大家族旅行でした。今は亡き父の にこやかな姿が、つい浮かんできてしまいます。
お腹がグーグー鳴りっぱなし、なのに、見たい寄りたいところだらけ。一昔前、両親とその親族の全15名で御宿に二泊した際、立ち寄って遊んだ鴨川シーワールドの前を通ったときは懐かしかったです。それは父が計画した初めての大家族旅行でした。今は亡き父の にこやかな姿が、つい浮かんできてしまいます。






































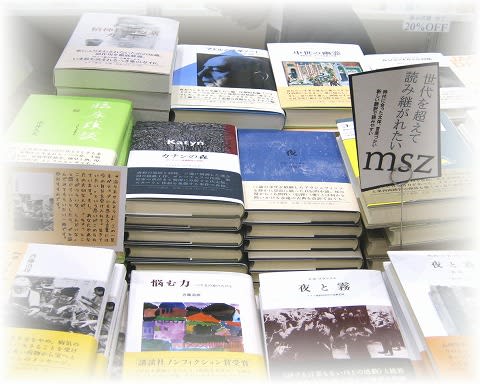




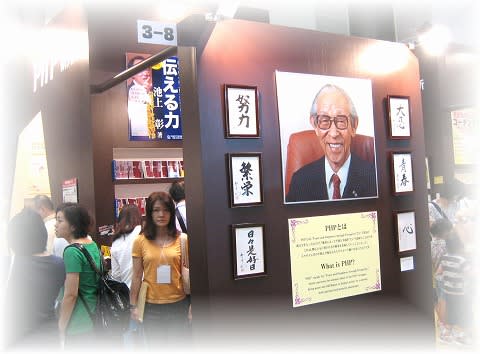






























 れ
れ  い!
い!