 土曜日は運動会でした
土曜日は運動会でした弁当も朝5字半起きでつくる

ごはんものが多くなっちゃったけど
*のりまき(ごぼう、たまごやき、きゅうり)
*天むす
*かぼちゃのサラダ
*とりのからあげ
*ゆでたまご、ブロッコリー、にんじん、たこさんウィンナー
*野沢菜の漬け物
なんだかいつも同じメニューになってしまう。。。
うちの通う保育園の運動会は、むかしながらの運動会。
おじいちゃんやおばあちゃん、兄弟もみんな来て
お昼はゴザを広げてお弁当を食べる。
家族が出る競技も多い。
運動会の準備も役員(親)たちが先生といっしょにやる。
うちは父ちゃんが会長だからすごい大変でしたが。
年長組は障害物リレーのときに逆上がりをするんだけれど
とうぜん出来ない子もいる。そうするとリレーの相手がとっさに
逆上がりを手伝ったりする。毎年見られる光景だけど
いつ見てもちょっと泣ける。
でももうこの運動会に来ることはないんだな、と思うと
秋の風がひゅーと吹くようなさみしさを感じます。
刻々と時間はながれているんだな。

次の日、前日の弁当の残りのからあげを
おそらくひとりでぜんぶ食べてしまい、胃もたれして
テラスでじーっと動かないタマ。















 ←取っ手ははずしてある状態。
←取っ手ははずしてある状態。
 ←知人宅から本もたくさん借りました。でもどこから読んでいいのかわからない!
←知人宅から本もたくさん借りました。でもどこから読んでいいのかわからない! 遊びにきました。お隣の子。
遊びにきました。お隣の子。


 ←晴れ舞台を待つおしりかじり虫のかぶり物(うしろ姿)。
←晴れ舞台を待つおしりかじり虫のかぶり物(うしろ姿)。



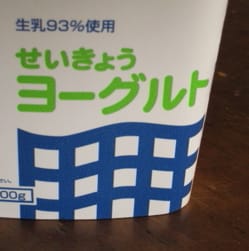
 袋の中身は粘土。日向ぼっこ中。
袋の中身は粘土。日向ぼっこ中。 だから気をゆるすと粘土も凍る。
だから気をゆるすと粘土も凍る。