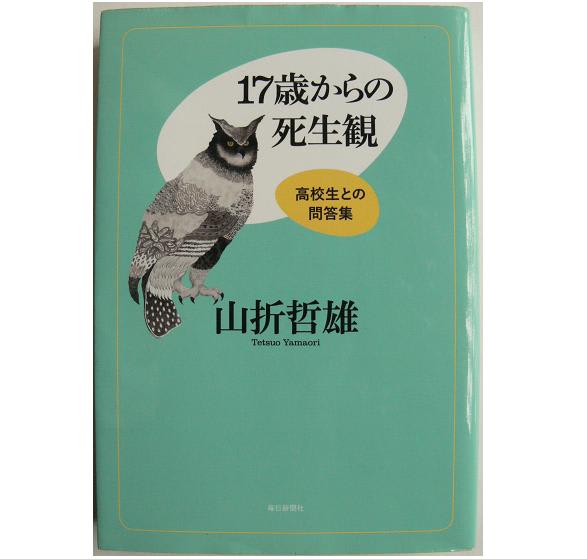
<『17歳からの死生観』表紙(山折哲雄著、毎日新聞社)>
山折哲雄氏が次のようなことを語っていた。
中学2年生の(昭和20年)8月10日、200mぐらい先でダダダダ、ダダダダダと機銃掃射された経験がある。そのときの恐怖感といったらなかった。そして艦載機が去って後花巻の街が燃え始めた。
その折、私の家(=専念寺)が焼けてしまうと火災の被害がさらに拡大するということで、消防団の方々がやって来て寺の周辺を全部破壊し、空き地を作った。そのおかげで、うちの寺は焼け残った。ところが、150mぐらいしか離れていない宮澤賢治の生家はこの花巻空襲で焼けてしまった。
これが、その後の私の心の傷になっている。
<『17歳からの死生観』(山折哲雄著、毎日新聞社)より>
と。そうか山折氏にはそういう心の傷があったたんだ、と初めて知った。宮澤賢治に対するこだわりの大きな理由はそこにあったのだと私(投稿者)は独り勝手に合点してしまった。
そういえばかつて、山折氏は五木寛之とのある雑誌の対談で
花巻あたりでは日が照れば不作なしで、農民たちは喜ぶはずです。むしろ、夏に気温が上がらないことの方が恐ろしい。実は、ヒドリというのは方言で「日取り」、日雇い仕事のことなんです。「雨ニモマケズ」が書かれた昭和六年頃、不作のために土木の仕事をやったり、他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました。そういう人々はいわば人別帳の世界を離れて、一種のアウトロー、戸籍のない境遇になってしまいます。今、派遣切りなど非正規雇用の人々の生活の問題がクローズアップされていますが、状況はまさしく重なるのです。
<『文藝春秋』3月号 「不況と親鸞;他力の時代が来た」より>
と言っているというが、山折氏がそう言い切って本当にいいのものかなと他人事ながら心配していた。 今の時代と重ねてみるこの見方は是としても、昭和6年前後の稗貫郡や紫波郡一帯に引き続いた旱害・冷害に鑑みれば果たして「ヒドリ=日取り」と言い切れるのだろうかと。あるいはまた”他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました”と言い切っているが、実態はやや異なっていたのではなかろうかと。
続きの
 ”花巻空襲罹災区域”へ移る。
”花巻空襲罹災区域”へ移る。
前の
 ”光太郎と戦争責任”に戻る。
”光太郎と戦争責任”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。
山折哲雄氏が次のようなことを語っていた。
中学2年生の(昭和20年)8月10日、200mぐらい先でダダダダ、ダダダダダと機銃掃射された経験がある。そのときの恐怖感といったらなかった。そして艦載機が去って後花巻の街が燃え始めた。
その折、私の家(=専念寺)が焼けてしまうと火災の被害がさらに拡大するということで、消防団の方々がやって来て寺の周辺を全部破壊し、空き地を作った。そのおかげで、うちの寺は焼け残った。ところが、150mぐらいしか離れていない宮澤賢治の生家はこの花巻空襲で焼けてしまった。
これが、その後の私の心の傷になっている。
<『17歳からの死生観』(山折哲雄著、毎日新聞社)より>
と。そうか山折氏にはそういう心の傷があったたんだ、と初めて知った。宮澤賢治に対するこだわりの大きな理由はそこにあったのだと私(投稿者)は独り勝手に合点してしまった。
そういえばかつて、山折氏は五木寛之とのある雑誌の対談で
花巻あたりでは日が照れば不作なしで、農民たちは喜ぶはずです。むしろ、夏に気温が上がらないことの方が恐ろしい。実は、ヒドリというのは方言で「日取り」、日雇い仕事のことなんです。「雨ニモマケズ」が書かれた昭和六年頃、不作のために土木の仕事をやったり、他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました。そういう人々はいわば人別帳の世界を離れて、一種のアウトロー、戸籍のない境遇になってしまいます。今、派遣切りなど非正規雇用の人々の生活の問題がクローズアップされていますが、状況はまさしく重なるのです。
<『文藝春秋』3月号 「不況と親鸞;他力の時代が来た」より>
と言っているというが、山折氏がそう言い切って本当にいいのものかなと他人事ながら心配していた。 今の時代と重ねてみるこの見方は是としても、昭和6年前後の稗貫郡や紫波郡一帯に引き続いた旱害・冷害に鑑みれば果たして「ヒドリ=日取り」と言い切れるのだろうかと。あるいはまた”他県に出稼ぎに行く農民が大量に発生していました”と言い切っているが、実態はやや異なっていたのではなかろうかと。
続きの
 ”花巻空襲罹災区域”へ移る。
”花巻空襲罹災区域”へ移る。前の
 ”光太郎と戦争責任”に戻る。
”光太郎と戦争責任”に戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます