「暗黒星雲のかなたへ」の後SFに戻る気はなく、山本周五郎の「虚空遍歴」を読み出したのですが、なんだか主人公の可哀想さに耐えられず途中で挫折し….SFである本書を手に取りました。
さて本作‘12年ローカス誌オールタイムベスト19位と米国で評価の高い作品のようです。
wikipediaをみると“終末戦争後の世界を描いた小説としては最高の評価を与えられている。”(最近wikipediaに頼っていて安直ですが…)作品のようです。
1959年発刊。
著者のウォルター・ミラー・ジュニアは寡作な作家で本人単独で書いた作品としては本作が唯一の長編とのこと。
アメリカ人には珍しいカソリックで第二次世界大戦中イタリアの修道院の爆撃作戦に参加した体験などが本書を書く動機にもなっているようです。
現在絶版となっておりamazonでもプレミアがついていて「入手できないかなぁ」と思っていたのですが、ブックオフ錦糸町店で発見できてラッキーでした。

内容(裏表紙記載)
最終核戦争の結果、一切の科学知識が失われ、文明は中世以前の段階にまで後退した。だがその時、一人の男が災禍を逃れた数少ない文献の保存につとめるべく修道院を設立した。そして30世紀をすぎる頃、廃墟の中から再建が始まろうとしている。今度の文明こそは、自滅することなく繁栄の道を歩めるだろうか?孤高の記録保管所が見守る遠未来の地球文明史。ヒューゴー賞受賞巨編。
内容紹介及び題名からマッチョな教会をめぐるマッチョな作品かなぁと思っていたのですが、しっとりとした雰因気の、「名作」らしい名作という感じの作品でした。
原題が“A Canticle for Leibowitz”直訳すると「リーボウィッツのための聖歌」という感じでしょうか?
まぁこれもピンとこない題名ですが、読後に見ればこちらの題名の方がしっくりきます。
。
各編独立した三部構成になっていて、第一部は20世紀に起きた最終戦争から600年後の2500年代、第二部は3174年、第三部は3781年を舞台にしていて時代時代の「リーボウィッツ修道院」を中心にした年代記となっています。
第一部 人アレ
文明は中世以前の段階まで衰退しており、リーボウィッツ修道院の修行僧が核シェルターからの遺物を見つけたことにまつわる話を軸に展開します。
この修行僧は発見された遺物である「固定子、巻線型式 73-A、位相3、部品番号6、毎分1800回転、5馬力、A級、リス籠型界磁」の図面を宗教的な抽象図としてなにがなんだかわからないながらも15年かけて金箔やらで飾り立てながら愚直に筆写します。
その筆写した図面は結局なんの役にも立たずに盗賊に奪われるわけですが…。
この修行僧の「愚直」さがなんともいい。
禅の世界では庭をひたすら掃き続けて悟りを開いた僧などという例がよくいわれますがまさにそんな感じですね。
宗教的な話というのはどの宗教でも似てくるんでしょうかねぇ。
「2500年」の話ということで語られていますが、意図的に「中世的」世界が描かれています、第二部・第三部を読んだ後に第一部を思い出すとなんとも味わい深く感じました。
第二部 光アレ
第一部から600年以上経ち、「中世以前」であった世界も徐々に成長していきます。
科学技術も徐々に「復興」されてきて最初の歴史からいえば「ルネッサンス」的な世界になってきています。
(先行文明があるだけにルネッサンス時期より科学技術は進んでいますが)
科学技術だけでなく政治的にも覇権を唱える国も出てきて中央集権的国家が成立しつつあったりします。
話としては「科学者」の象徴であるファーデントロット博士と精神世界の象徴リーボウィッツ修道院長の「からみ」を中心に進んでいきますが最後は「20世紀の間違い…というか自滅への道を人間は踏み出してくのか?」と暗示しています。
人の生活を豊かかつ便利にしていく科学技術ですが精神の成長が伴わないとまた悲劇が起こるのか?悩ましいですね。
第三部 汝ガ意志ノママニ
第二部からまた600年たち…。
科学技術は恒星間飛行も実現するところまで進歩しています。
20世紀を超える進歩をしているわけですが、第二部で暗示されたそれを使用する人間の「精神」は進歩がなく、世界中に大国が跋扈し再び核戦争の危機が訪れます。
なまじ20世紀より化学技術も進歩しているので今度こそ本当に人類は滅亡しそうになってきます。
本部最後の方で、治る見込みのない患者に「安楽死」を薦める医師と、生を全うするべしという「宗教者」リーボウィッツ修道院長が議論したりしていますが、この辺の議論は科学技術と違い38世紀になっても全然進歩していない。
人間って...。
と考えさせられました。
ラストで神的存在が修道院長の前に現れますが、この辺はキリスト教に詳しくない私としてはピンときませんでした。
第一部から第三部まで通して「道化役」的謎の老ユダヤ人(同一人物かどうかも定かではない)が出てきますが、その存在も話をミステリアスにするのに効いていました。
最後まで謎の人物でしたが….どういう存在なんだろう?
(これもキリスト教に詳しいと分かるのかもしれませんが…。)
「SF」という分野と独立した短編形式の話をつなげて長い時間を経過させる様式とは相性がいいんでしょうか?
名作が多い気がします。
アシモフの「ファウンデーション」三部作、「わたしはロボット」もそうですし、他にも「火星年代記」「幼年期の終わり」「都市」もそんな感じの名作ですね。
本作もそのような流れを汲んだ1950年代的SFの終盤に現れた名作の一つという分類もできるかもしれません。
私はこのような形式に弱くけっこう感動してしまい、読後しばしなんとも整理できない感情が湧いてきて大変でした。
「結局中世的な世界が人間の「精神」の成長度合いからすると一番いいのかもしれない…。」
「人類の幸せとは?」
というような極めて青臭い感情です。(笑)
古典的SFは文明論を語るものが多いですが、まさにそのような意味での名作な気がしました。
その辺、「ニューウェーブ」やら「サイバーパンク」の立場から見ると古臭いのかもしれませんが…。
私は1950年代SF好きですねぇ。
第三部で修道院長にキリスト者として「自殺」「安楽死」にあれほど反対させていた著者のウォルター・ミラー・ジュニアですが、1996年に銃で自殺したようです。
この辺もなんとも....。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
さて本作‘12年ローカス誌オールタイムベスト19位と米国で評価の高い作品のようです。
wikipediaをみると“終末戦争後の世界を描いた小説としては最高の評価を与えられている。”(最近wikipediaに頼っていて安直ですが…)作品のようです。
1959年発刊。
著者のウォルター・ミラー・ジュニアは寡作な作家で本人単独で書いた作品としては本作が唯一の長編とのこと。
アメリカ人には珍しいカソリックで第二次世界大戦中イタリアの修道院の爆撃作戦に参加した体験などが本書を書く動機にもなっているようです。
現在絶版となっておりamazonでもプレミアがついていて「入手できないかなぁ」と思っていたのですが、ブックオフ錦糸町店で発見できてラッキーでした。

内容(裏表紙記載)
最終核戦争の結果、一切の科学知識が失われ、文明は中世以前の段階にまで後退した。だがその時、一人の男が災禍を逃れた数少ない文献の保存につとめるべく修道院を設立した。そして30世紀をすぎる頃、廃墟の中から再建が始まろうとしている。今度の文明こそは、自滅することなく繁栄の道を歩めるだろうか?孤高の記録保管所が見守る遠未来の地球文明史。ヒューゴー賞受賞巨編。
内容紹介及び題名からマッチョな教会をめぐるマッチョな作品かなぁと思っていたのですが、しっとりとした雰因気の、「名作」らしい名作という感じの作品でした。
原題が“A Canticle for Leibowitz”直訳すると「リーボウィッツのための聖歌」という感じでしょうか?
まぁこれもピンとこない題名ですが、読後に見ればこちらの題名の方がしっくりきます。
。
各編独立した三部構成になっていて、第一部は20世紀に起きた最終戦争から600年後の2500年代、第二部は3174年、第三部は3781年を舞台にしていて時代時代の「リーボウィッツ修道院」を中心にした年代記となっています。
第一部 人アレ
文明は中世以前の段階まで衰退しており、リーボウィッツ修道院の修行僧が核シェルターからの遺物を見つけたことにまつわる話を軸に展開します。
この修行僧は発見された遺物である「固定子、巻線型式 73-A、位相3、部品番号6、毎分1800回転、5馬力、A級、リス籠型界磁」の図面を宗教的な抽象図としてなにがなんだかわからないながらも15年かけて金箔やらで飾り立てながら愚直に筆写します。
その筆写した図面は結局なんの役にも立たずに盗賊に奪われるわけですが…。
この修行僧の「愚直」さがなんともいい。
禅の世界では庭をひたすら掃き続けて悟りを開いた僧などという例がよくいわれますがまさにそんな感じですね。
宗教的な話というのはどの宗教でも似てくるんでしょうかねぇ。
「2500年」の話ということで語られていますが、意図的に「中世的」世界が描かれています、第二部・第三部を読んだ後に第一部を思い出すとなんとも味わい深く感じました。
第二部 光アレ
第一部から600年以上経ち、「中世以前」であった世界も徐々に成長していきます。
科学技術も徐々に「復興」されてきて最初の歴史からいえば「ルネッサンス」的な世界になってきています。
(先行文明があるだけにルネッサンス時期より科学技術は進んでいますが)
科学技術だけでなく政治的にも覇権を唱える国も出てきて中央集権的国家が成立しつつあったりします。
話としては「科学者」の象徴であるファーデントロット博士と精神世界の象徴リーボウィッツ修道院長の「からみ」を中心に進んでいきますが最後は「20世紀の間違い…というか自滅への道を人間は踏み出してくのか?」と暗示しています。
人の生活を豊かかつ便利にしていく科学技術ですが精神の成長が伴わないとまた悲劇が起こるのか?悩ましいですね。
第三部 汝ガ意志ノママニ
第二部からまた600年たち…。
科学技術は恒星間飛行も実現するところまで進歩しています。
20世紀を超える進歩をしているわけですが、第二部で暗示されたそれを使用する人間の「精神」は進歩がなく、世界中に大国が跋扈し再び核戦争の危機が訪れます。
なまじ20世紀より化学技術も進歩しているので今度こそ本当に人類は滅亡しそうになってきます。
本部最後の方で、治る見込みのない患者に「安楽死」を薦める医師と、生を全うするべしという「宗教者」リーボウィッツ修道院長が議論したりしていますが、この辺の議論は科学技術と違い38世紀になっても全然進歩していない。
人間って...。
と考えさせられました。
ラストで神的存在が修道院長の前に現れますが、この辺はキリスト教に詳しくない私としてはピンときませんでした。
第一部から第三部まで通して「道化役」的謎の老ユダヤ人(同一人物かどうかも定かではない)が出てきますが、その存在も話をミステリアスにするのに効いていました。
最後まで謎の人物でしたが….どういう存在なんだろう?
(これもキリスト教に詳しいと分かるのかもしれませんが…。)
「SF」という分野と独立した短編形式の話をつなげて長い時間を経過させる様式とは相性がいいんでしょうか?
名作が多い気がします。
アシモフの「ファウンデーション」三部作、「わたしはロボット」もそうですし、他にも「火星年代記」「幼年期の終わり」「都市」もそんな感じの名作ですね。
本作もそのような流れを汲んだ1950年代的SFの終盤に現れた名作の一つという分類もできるかもしれません。
私はこのような形式に弱くけっこう感動してしまい、読後しばしなんとも整理できない感情が湧いてきて大変でした。
「結局中世的な世界が人間の「精神」の成長度合いからすると一番いいのかもしれない…。」
「人類の幸せとは?」
というような極めて青臭い感情です。(笑)
古典的SFは文明論を語るものが多いですが、まさにそのような意味での名作な気がしました。
その辺、「ニューウェーブ」やら「サイバーパンク」の立場から見ると古臭いのかもしれませんが…。
私は1950年代SF好きですねぇ。
第三部で修道院長にキリスト者として「自殺」「安楽死」にあれほど反対させていた著者のウォルター・ミラー・ジュニアですが、1996年に銃で自殺したようです。
この辺もなんとも....。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










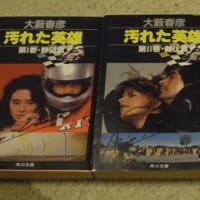
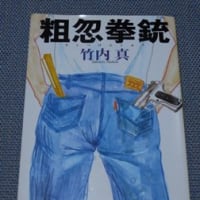
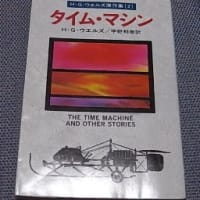
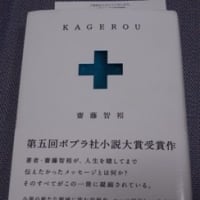
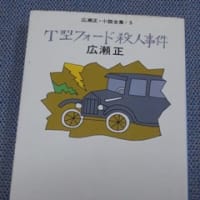
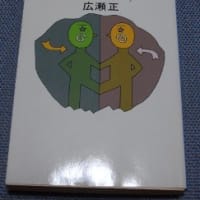


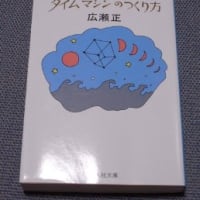
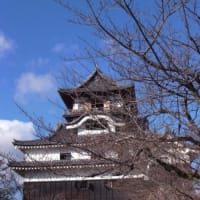
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます