「神様はつらい」を読むために図書館で借りた「世界SF全集24」収録3編のうち最後に読んだ1編です。
本作の著者アチアードナ・グロモアも日本ではほぼ無名の方のようです。
当時の早川書房よく発掘しましたねぇ、余程ロシアSFに強い人がいたんでしょうかねぇ。
グロモアは女性SF作家、1916年生まれ第二次大戦中はゲシュタポに占領されたキエフで地下活動に参加、ゲシュタポに捕えられ死の収容所へ送られる途中で脱走という激しい経験の持ち主。
評論家としても活動、キエフでの地下活動をテーマにした作品などを発表していて、SFは本作は1963年の作品で著者としての三作目のSFとのこと。(解説より)
なお翻訳の出来は(私感ですが..)「クムビ」>「自己との決闘」>「神様はつらい」というところです。
ただ作品としての評価(これまた私感) 「神様はつらい」=「自己との決闘」>「クムビ」という感じです。
内容紹介(これまた私の独断)
舞台はフランスパリ、無職で辛い生活を送る元大学生アルベールと元船員のロジェ、敏腕新聞記者ライモンは天才神経生理学者アンリ・ロラン教授が自宅で極秘で行う研究に引き込まれることになる。ライモン・ロジェはロラン教授の美貌の妻ルイザにも惹かれていく。ロラン教授の実験は生物学的に人間の脳や各部分を成長させた「人間のようなもの」を各種研究や実用業務に使っていこうという研究であった。
検体それぞれはある分野ではすぐれた能力を持つが、機会と違い高度な人間的感情ももつが、それゆえにライバル研究者シャンフォルの半導体で電子的に作っロボットと比べて著しく安定感を欠いていた。
ロラン教授は助手セント・イブと奇跡的に生物学的に脳を発達させる手法を発見したのだが体系化することができず、セント・イブを実験の段階で死なせてしまった罪悪感もあり意識を明確にするが副作用の強いシアルー5を大量摂取し弱りきり、死が近づいていた。そんななかロラン教授の創造した「人間のようなもの」がとった行動は破局を招く。
「フランケンシュタインのようなもの」の生物学的 創造を現代(当時の)に置き換えて思考実験をした作品です。
その生物学的アプローチと物理学、電子的アプローチ=ロボット及び電子頭脳と比較する形になっています。
のちの半導体技術の発展など考えると、当時としてはなかなか斬新なアイディアだったのではないでしょうか?
ロラン教授の創造した「もの」たちの巻き起こす騒動やら苦悩やらがコメディタッチでもあり悲劇的でもありなんとも楽しめました。
かなり好きな作品です。
ロラン教授の美貌の妻ルイザをめぐるライモンとロジェの鞘当てなどは紋切型でこの辺めぐるラストの処理もありがちではあるのですが....。
ハッピーエンドに終わらないところが「クムビ」と違いクールです。
それにしても女性作家なのに「ルイザ」に対する扱いがなんとも厳しいような....。
著者は女性ながら「地下活動」をした人ですから、善良な「主婦」「淑女」的存在に厳しい面があったんでしょうかねぇ。
話の整理があまいとか場面が転換しすぎというような欠点はあるかとも思いましたが全体的にモダンな感じの良作かと思いました。
お薦めです。
↓クールじゃなくてもっとやさしく~という方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
本作の著者アチアードナ・グロモアも日本ではほぼ無名の方のようです。
当時の早川書房よく発掘しましたねぇ、余程ロシアSFに強い人がいたんでしょうかねぇ。
グロモアは女性SF作家、1916年生まれ第二次大戦中はゲシュタポに占領されたキエフで地下活動に参加、ゲシュタポに捕えられ死の収容所へ送られる途中で脱走という激しい経験の持ち主。
評論家としても活動、キエフでの地下活動をテーマにした作品などを発表していて、SFは本作は1963年の作品で著者としての三作目のSFとのこと。(解説より)
なお翻訳の出来は(私感ですが..)「クムビ」>「自己との決闘」>「神様はつらい」というところです。
ただ作品としての評価(これまた私感) 「神様はつらい」=「自己との決闘」>「クムビ」という感じです。
内容紹介(これまた私の独断)
舞台はフランスパリ、無職で辛い生活を送る元大学生アルベールと元船員のロジェ、敏腕新聞記者ライモンは天才神経生理学者アンリ・ロラン教授が自宅で極秘で行う研究に引き込まれることになる。ライモン・ロジェはロラン教授の美貌の妻ルイザにも惹かれていく。ロラン教授の実験は生物学的に人間の脳や各部分を成長させた「人間のようなもの」を各種研究や実用業務に使っていこうという研究であった。
検体それぞれはある分野ではすぐれた能力を持つが、機会と違い高度な人間的感情ももつが、それゆえにライバル研究者シャンフォルの半導体で電子的に作っロボットと比べて著しく安定感を欠いていた。
ロラン教授は助手セント・イブと奇跡的に生物学的に脳を発達させる手法を発見したのだが体系化することができず、セント・イブを実験の段階で死なせてしまった罪悪感もあり意識を明確にするが副作用の強いシアルー5を大量摂取し弱りきり、死が近づいていた。そんななかロラン教授の創造した「人間のようなもの」がとった行動は破局を招く。
「フランケンシュタインのようなもの」の生物学的 創造を現代(当時の)に置き換えて思考実験をした作品です。
その生物学的アプローチと物理学、電子的アプローチ=ロボット及び電子頭脳と比較する形になっています。
のちの半導体技術の発展など考えると、当時としてはなかなか斬新なアイディアだったのではないでしょうか?
ロラン教授の創造した「もの」たちの巻き起こす騒動やら苦悩やらがコメディタッチでもあり悲劇的でもありなんとも楽しめました。
かなり好きな作品です。
ロラン教授の美貌の妻ルイザをめぐるライモンとロジェの鞘当てなどは紋切型でこの辺めぐるラストの処理もありがちではあるのですが....。
ハッピーエンドに終わらないところが「クムビ」と違いクールです。
それにしても女性作家なのに「ルイザ」に対する扱いがなんとも厳しいような....。
著者は女性ながら「地下活動」をした人ですから、善良な「主婦」「淑女」的存在に厳しい面があったんでしょうかねぇ。
話の整理があまいとか場面が転換しすぎというような欠点はあるかとも思いましたが全体的にモダンな感じの良作かと思いました。
お薦めです。
↓クールじゃなくてもっとやさしく~という方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










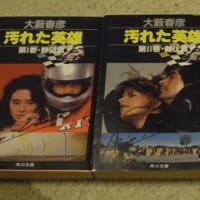
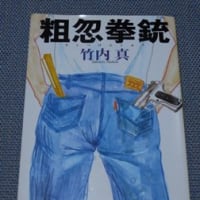
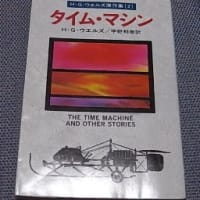
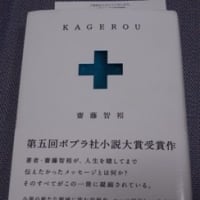
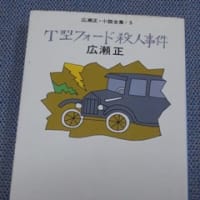
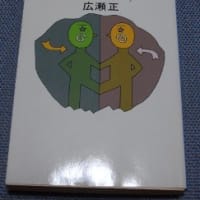


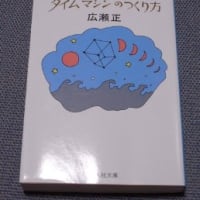
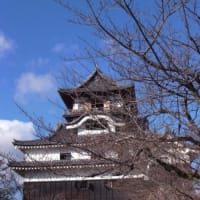






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます