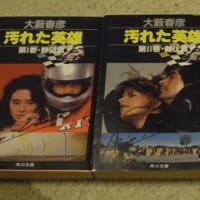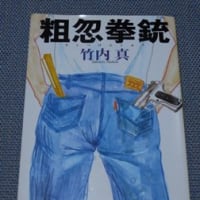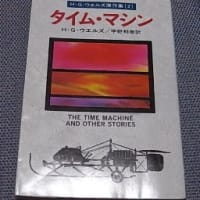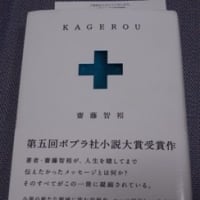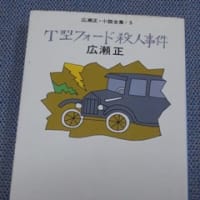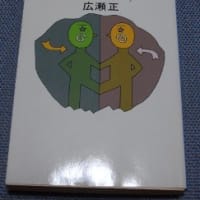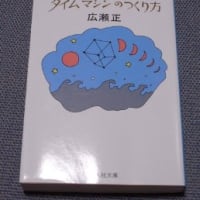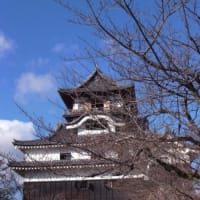「大地は永遠に」に続き、'12年ローカス誌オールタイムベスト71位の本書を手に取りました。
また本作は'06年SFマガジン海外長編45位にもなっております、1930年刊。
ほぼ日本では忘れられていたステーブルドンの処女作である本書を国書刊行会が2004年に刊行したものです。
当時話題になったのか2006年のSFマガジンの海外長編ベストではランクインしていますね。
現在絶版のためこれまたアマゾンで古本を入手しました。
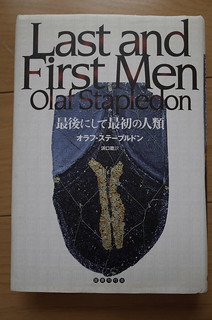
ステーブルドンは英国の人。
1886年生まれ、日本では明治19年、本書は1930年(昭和5年)刊行、著者44歳にしての処女作となります。
それまでは第一次世界大戦へ救急部隊員として従軍、その後大学で哲学の博士号を取得、哲学・英文学・心理学の講師などをしていたようです。
SFの父であるH.G.ウェルズが1866年生まれ、世代は違いますが、本作上梓後の1930年代から40年代に交流があったようです。
時代ですねえ
内容 (「BOOK」データベースより)
数度の大戦争を経験した人類は、24世紀、ついに世界国家を実現、高度な科学文明を築くが、核エネルギーの暴発が地球のほぼ全域を焦土と化してしまう。わずかに生き残り、世界再建を果たした人類を襲う火星人の侵略、生物兵器に端を発した疫病の蔓延。度重なる災禍によって肉体的、精神的に退行した人類は、しかし再び進化の階梯を登り始め、地球を脱出して金星や海王星に移住を開始する…。20億年に及ぶ人類の未来史を驚異の神話的想像力で描いて、アーサー・C.クラークらに決定的な影響を与えた伝説的名作。
とりあえずの感想「人間」を描くのが小説だとしたら本書は小説ではないように感じました。
「人類」はこれでもかというくらい描いていますが…。
特定の人物は断片的にしか描かれていませんので特定の「人間」はまったく描かれていません。
人類の破滅、破滅からの再生、進化や自らの操作による人類の形態の変化についてこれでもかと思考実験しています。
最終的にが20億年後まで描いています...スケールもでかい。
この辺のテーマのSFは今後どんな作品を読んでも既視感感じてしまうのではないかというくらいです、長編何冊分のアイディアがあることやら…。
小説というよりも思考実験を楽しむ作品といえるでしょう。
1930年発刊の作品としては第1期人類から「最後の人類」となる第18期人類までの描写はかなり科学的です。
第1期人類が絶滅寸前になり、少数から盛り返す姿などは、ミトコンドリアイブ説で唱えられる「かなり少数の集団」から人類が全世界に拡散して行ったモデルに対応している感じです。
火星人も出てきますが、非人類型のこんな感じの火星人ならまか「いるかもなぁ」と思わせます。
金星のテラフォーミングは現代の金星に関する知識から見ると無理があるような気もしますが手法はかなり科学的です。
人間の体の方も環境に合わせて変えてますしねぇ。
そこだけ取ってもアイディアだけ取れば「レッド・マーズ」など最近のテラフォーミングSFと比べても遜色ない気がします。
「人間」の自己改変も遺伝子をいじって目的に合わせていくという視点ではヴォルコシガン・サガシリーズでもよく描かれています。
時間軸も人類は進化は猿人からホモ・サピエンスまで数百万年(現代の説、1930年時点の説だと数十万年??)ですから本作の数百万から数千万年、数億年スパンであれば「人類が生き残れば」が前提ですが、こんなこともありうるかもなぁなどと思いました。
著者の経歴見ると哲学、歴史と文系なようですが、当時の素養として理系の素養も相当身につけていたんでしょうねぇ。
邦訳タイトルだけ見ると「最後の人類が最初の人類にとって代わるのか?」というイメージでしたが(原題:"Last and First Men")「最後の人類」=第18期人類が第1期人類=我々に向けたメッセージという形になっています。
第一期人類の章ではヨーロッパの没落、アメリカと並ぶ中国の台頭と軋轢などを予言的に描いています。
最終的にアメリカ化、物質万能となった人類が化石燃料枯渇とともに衰退します。
物質に根ざした文明が第2世代ですでに崩れてしまう様は「大地は永遠に」に通じるものを感じました。
衰退した人類が再び興隆するまで10万年単位の時間がかかり、せっかく栄えても戦争でほとんどを失い数十人の北極に潜伏していた潜水艦の乗組員から2種に分かれて行き、片方の側から第二期人類が生まれます。
教養的でない集団の群の末裔はペットとして連れて行った「猿」が主人となって、人類が家畜となっています。(この辺猿の惑星的)
この家畜人類と第二期人類が遭遇し、家畜人類の病原菌が第二期人類に悪さをしなどという話もなかなか科学的です。
このペースで第18期までいくと全然話が進まないので...。
かいつまんで話すと、人類は何回も病気やら環境の激変にさらされ滅亡しながらもなんとか「人類」として続いていき、それなりの「叡智」を獲得するのですが....。
最後(太陽自体最後を迎える)の叡智を獲得したかに見える第18期人類でさえも太陽の放射線の影響による病でおかしくなってしまいます。
そこにどんな教訓を持つかは人それぞれかと思いますが、賢くもあり愚かな人間に対する「愛情」もしくは「諦念」のようなものは感じました。
あまりに賢すぎてもまぁ面白くないですしねぇ...。
なお進化のイメージとしては海王星に唯一の脊髄動物として移住した第9期人類の末裔が数億年の間にイルカやハチドリ、草食性・肉食性人類と分化していくイメージが「すげぇ」と思いました....。
そもそも「人類」なのか???という感じですが...遺伝子としての人類と「知性」としての人類を考えさせられました。
その中でも「兎」のような人類から第10期人類が進化しその流れの第18期人類が第1期人類とも記憶を共有する...雄大なイメージですね。
↓肉食人類に食われるのは...という方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
また本作は'06年SFマガジン海外長編45位にもなっております、1930年刊。
ほぼ日本では忘れられていたステーブルドンの処女作である本書を国書刊行会が2004年に刊行したものです。
当時話題になったのか2006年のSFマガジンの海外長編ベストではランクインしていますね。
現在絶版のためこれまたアマゾンで古本を入手しました。
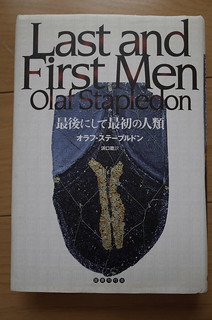
ステーブルドンは英国の人。
1886年生まれ、日本では明治19年、本書は1930年(昭和5年)刊行、著者44歳にしての処女作となります。
それまでは第一次世界大戦へ救急部隊員として従軍、その後大学で哲学の博士号を取得、哲学・英文学・心理学の講師などをしていたようです。
SFの父であるH.G.ウェルズが1866年生まれ、世代は違いますが、本作上梓後の1930年代から40年代に交流があったようです。
時代ですねえ
内容 (「BOOK」データベースより)
数度の大戦争を経験した人類は、24世紀、ついに世界国家を実現、高度な科学文明を築くが、核エネルギーの暴発が地球のほぼ全域を焦土と化してしまう。わずかに生き残り、世界再建を果たした人類を襲う火星人の侵略、生物兵器に端を発した疫病の蔓延。度重なる災禍によって肉体的、精神的に退行した人類は、しかし再び進化の階梯を登り始め、地球を脱出して金星や海王星に移住を開始する…。20億年に及ぶ人類の未来史を驚異の神話的想像力で描いて、アーサー・C.クラークらに決定的な影響を与えた伝説的名作。
とりあえずの感想「人間」を描くのが小説だとしたら本書は小説ではないように感じました。
「人類」はこれでもかというくらい描いていますが…。
特定の人物は断片的にしか描かれていませんので特定の「人間」はまったく描かれていません。
人類の破滅、破滅からの再生、進化や自らの操作による人類の形態の変化についてこれでもかと思考実験しています。
最終的にが20億年後まで描いています...スケールもでかい。
この辺のテーマのSFは今後どんな作品を読んでも既視感感じてしまうのではないかというくらいです、長編何冊分のアイディアがあることやら…。
小説というよりも思考実験を楽しむ作品といえるでしょう。
1930年発刊の作品としては第1期人類から「最後の人類」となる第18期人類までの描写はかなり科学的です。
第1期人類が絶滅寸前になり、少数から盛り返す姿などは、ミトコンドリアイブ説で唱えられる「かなり少数の集団」から人類が全世界に拡散して行ったモデルに対応している感じです。
火星人も出てきますが、非人類型のこんな感じの火星人ならまか「いるかもなぁ」と思わせます。
金星のテラフォーミングは現代の金星に関する知識から見ると無理があるような気もしますが手法はかなり科学的です。
人間の体の方も環境に合わせて変えてますしねぇ。
そこだけ取ってもアイディアだけ取れば「レッド・マーズ」など最近のテラフォーミングSFと比べても遜色ない気がします。
「人間」の自己改変も遺伝子をいじって目的に合わせていくという視点ではヴォルコシガン・サガシリーズでもよく描かれています。
時間軸も人類は進化は猿人からホモ・サピエンスまで数百万年(現代の説、1930年時点の説だと数十万年??)ですから本作の数百万から数千万年、数億年スパンであれば「人類が生き残れば」が前提ですが、こんなこともありうるかもなぁなどと思いました。
著者の経歴見ると哲学、歴史と文系なようですが、当時の素養として理系の素養も相当身につけていたんでしょうねぇ。
邦訳タイトルだけ見ると「最後の人類が最初の人類にとって代わるのか?」というイメージでしたが(原題:"Last and First Men")「最後の人類」=第18期人類が第1期人類=我々に向けたメッセージという形になっています。
第一期人類の章ではヨーロッパの没落、アメリカと並ぶ中国の台頭と軋轢などを予言的に描いています。
最終的にアメリカ化、物質万能となった人類が化石燃料枯渇とともに衰退します。
物質に根ざした文明が第2世代ですでに崩れてしまう様は「大地は永遠に」に通じるものを感じました。
衰退した人類が再び興隆するまで10万年単位の時間がかかり、せっかく栄えても戦争でほとんどを失い数十人の北極に潜伏していた潜水艦の乗組員から2種に分かれて行き、片方の側から第二期人類が生まれます。
教養的でない集団の群の末裔はペットとして連れて行った「猿」が主人となって、人類が家畜となっています。(この辺猿の惑星的)
この家畜人類と第二期人類が遭遇し、家畜人類の病原菌が第二期人類に悪さをしなどという話もなかなか科学的です。
このペースで第18期までいくと全然話が進まないので...。
かいつまんで話すと、人類は何回も病気やら環境の激変にさらされ滅亡しながらもなんとか「人類」として続いていき、それなりの「叡智」を獲得するのですが....。
最後(太陽自体最後を迎える)の叡智を獲得したかに見える第18期人類でさえも太陽の放射線の影響による病でおかしくなってしまいます。
そこにどんな教訓を持つかは人それぞれかと思いますが、賢くもあり愚かな人間に対する「愛情」もしくは「諦念」のようなものは感じました。
あまりに賢すぎてもまぁ面白くないですしねぇ...。
なお進化のイメージとしては海王星に唯一の脊髄動物として移住した第9期人類の末裔が数億年の間にイルカやハチドリ、草食性・肉食性人類と分化していくイメージが「すげぇ」と思いました....。
そもそも「人類」なのか???という感じですが...遺伝子としての人類と「知性」としての人類を考えさせられました。
その中でも「兎」のような人類から第10期人類が進化しその流れの第18期人類が第1期人類とも記憶を共有する...雄大なイメージですね。
↓肉食人類に食われるのは...という方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。