「オリエント急行の殺人」を読んで「ミステリーもいいなぁ」という気になり、数年前に入手していた本書を読みました。
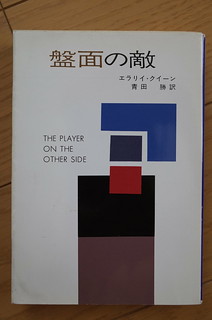 本書入手の動機は、本作がエラリイ・クイーンのプロット担当ダネイのプロットで「人間以上」などで有名なSF作家であるシオドア・スタージョンが書いた作品らしいため。(wikipedia参照)
本書入手の動機は、本作がエラリイ・クイーンのプロット担当ダネイのプロットで「人間以上」などで有名なSF作家であるシオドア・スタージョンが書いた作品らしいため。(wikipedia参照)
1958年の「最後の一撃」以降のクイーン作品は執筆担当のリーの衰えのため他の作家に委ねるスタイルになっていたようです。
とはいっても本作はエラリイ・クイーンの大ファンである北村薫氏が本書のタイトルをもじって「盤上の敵」として一書著すなどもしており、この時期のクイーン作品としては評価の高い作品のようです、1963年刊行。
日本では一般的に初期の国名シリーズや当初バーナビー・ロス名義で発表された「X・Y・Zの悲劇」の方がポピュラーなようですが、海外では後期クィーンの作品の評価が高く架空の町ライツヴィルを舞台にした「災厄の町」(1942年)(日本では「配達されない3通の手紙」として映画化されています)など第三期の作品の評価が高いようです。
が、上記書いてから英米のベスト(1990英国推理作家協会・1995年アメリカ探偵作家協会ベスト)確認したら、エラリイ・クイーンが1作もランクインしていません。(ブログ見直したら私も気づいていたようですが…それほど問題にしていなかった)
‘
日本では'12年週刊文春海外ミステリーベスト100で「Yの悲劇」が2位にランクインしている他、前記合わせて6作ランクインしている人気作家なのに….。
エラリイ・クイーン・ミステリ・マガジンを発行する等、編集者・アンソロジストとしてのクィーンは評価が高いようですが…英米では作家としての評価はそれほど高くないのでしょうか?
でも’12年週刊文春国内ミステリーベストに西村京太郎が入っていないようなものなのかもしれません。
また本書のように60年以降は代筆させたりしているのでその辺も評価されないところなのかもしれませんね。
内容紹介(裏表紙記載)
四つの奇怪な城と庭園とから成るヨーク館で発生した残虐な殺人-富豪の莫大な遺産の相続権をもつ甥のロバートが花崗岩のブロックで殺害されたのだ。エラリィは父親から事件の詳細を聞くや、俄然気負いたった。殺人の方法も奇怪ではあるが、以前からヨーク館には犯人からとおぼしき奇妙なカードが送り付けれれてきていたのだ。果たして犯人の真の目的は? 狡智にたけた犯人からの挑戦を敢然と受けて立つクィーン父子の活躍!
本作読んでの感想、実行犯及び仕掛けは初期の段階で読者には明示されているので、本格ミステリーというよりサスペンスのような作品。
「オリエント急行の殺人」とは異なり、ちょいと現代のミステリーを読みなれている人なら真犯人も物語の手前からあたりがつくのではないでしょうか?
国名シリーズでは颯爽とした生意気な若造エラリイ(以下は作者でなく作中の「名探偵」エラリィ・クイーンを指します)がやさぐれた中年男となって(ちょっとニート入っている)のを楽しむ作品という感じです。
やさぐれ名探偵と個性的なヨーク亭の人々との掛け合いは国名シリーズでの謎解きマシーンのようなクィーンと比べて人間的で楽しめます。
殺人事件の謎よりも捜査が進むにつれ各登場人物のかかえる「謎」が明かされていく過程の方が楽しめました。
「科学捜査」が進んで「恐るべき犯人」VS「名探偵」という構図が成立しない中で、「これぞ恐るべき犯人」と意気込んだエラリイの捜査の終盤までの空回り感もなんとも皮肉です…。
警察がしらみつぶしに探した真犯人から実行犯への指示メッセージを見つけるところで何とか「名探偵」としてのエラリイの対面を立ててはいますが…。
「科学捜査」が進んだ60年代ならこれくらいは警察が見つけられそうな気がするのですが….。
「名探偵」が生きにくい時代に名探偵ものにしなきゃいけない設定ではこんな感じになるのでしょうか?
ミステリーが密室トリックやアリバイ崩しのようなパズル的「謎解き」だけでなく、プロット自体、状況全体に含まれるなにやら異常な仕掛けを解決していくような方向に進化していっているのをキャッチアップした作品なのでしょう。
メイントリックは現代から見たらそれほど意外というものではないですが、その異常な状況で関係者が振り回されるのを楽しむ作品なのでしょう。
文章はスタージョンが書いたとのことですが、クイーン父子のやりとりなど他のクィーン作品と違和感なく、ダネイのプロットを丁寧に処理し、まだ存命のリーの助言も仰いだというのが推察できます。
記憶がなく知能的に「?」なヨーク家の下男、ヘンリー・ウォルトの怪しげな雰囲気がスタージョンぽかったかなぁ?というくらいでした。
「エラリイ・クイーン」していたんでしょうね。
↓人に書かせるなんてダメじゃんという方も、そんなの関係ネーという方も、よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
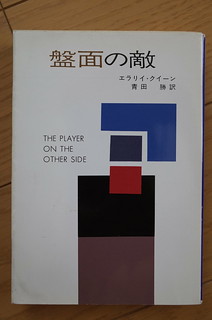 本書入手の動機は、本作がエラリイ・クイーンのプロット担当ダネイのプロットで「人間以上」などで有名なSF作家であるシオドア・スタージョンが書いた作品らしいため。(wikipedia参照)
本書入手の動機は、本作がエラリイ・クイーンのプロット担当ダネイのプロットで「人間以上」などで有名なSF作家であるシオドア・スタージョンが書いた作品らしいため。(wikipedia参照)1958年の「最後の一撃」以降のクイーン作品は執筆担当のリーの衰えのため他の作家に委ねるスタイルになっていたようです。
とはいっても本作はエラリイ・クイーンの大ファンである北村薫氏が本書のタイトルをもじって「盤上の敵」として一書著すなどもしており、この時期のクイーン作品としては評価の高い作品のようです、1963年刊行。
日本では一般的に初期の国名シリーズや当初バーナビー・ロス名義で発表された「X・Y・Zの悲劇」の方がポピュラーなようですが、海外では後期クィーンの作品の評価が高く架空の町ライツヴィルを舞台にした「災厄の町」(1942年)(日本では「配達されない3通の手紙」として映画化されています)など第三期の作品の評価が高いようです。
が、上記書いてから英米のベスト(1990英国推理作家協会・1995年アメリカ探偵作家協会ベスト)確認したら、エラリイ・クイーンが1作もランクインしていません。(ブログ見直したら私も気づいていたようですが…それほど問題にしていなかった)
‘
日本では'12年週刊文春海外ミステリーベスト100で「Yの悲劇」が2位にランクインしている他、前記合わせて6作ランクインしている人気作家なのに….。
エラリイ・クイーン・ミステリ・マガジンを発行する等、編集者・アンソロジストとしてのクィーンは評価が高いようですが…英米では作家としての評価はそれほど高くないのでしょうか?
でも’12年週刊文春国内ミステリーベストに西村京太郎が入っていないようなものなのかもしれません。
また本書のように60年以降は代筆させたりしているのでその辺も評価されないところなのかもしれませんね。
内容紹介(裏表紙記載)
四つの奇怪な城と庭園とから成るヨーク館で発生した残虐な殺人-富豪の莫大な遺産の相続権をもつ甥のロバートが花崗岩のブロックで殺害されたのだ。エラリィは父親から事件の詳細を聞くや、俄然気負いたった。殺人の方法も奇怪ではあるが、以前からヨーク館には犯人からとおぼしき奇妙なカードが送り付けれれてきていたのだ。果たして犯人の真の目的は? 狡智にたけた犯人からの挑戦を敢然と受けて立つクィーン父子の活躍!
本作読んでの感想、実行犯及び仕掛けは初期の段階で読者には明示されているので、本格ミステリーというよりサスペンスのような作品。
「オリエント急行の殺人」とは異なり、ちょいと現代のミステリーを読みなれている人なら真犯人も物語の手前からあたりがつくのではないでしょうか?
国名シリーズでは颯爽とした生意気な若造エラリイ(以下は作者でなく作中の「名探偵」エラリィ・クイーンを指します)がやさぐれた中年男となって(ちょっとニート入っている)のを楽しむ作品という感じです。
やさぐれ名探偵と個性的なヨーク亭の人々との掛け合いは国名シリーズでの謎解きマシーンのようなクィーンと比べて人間的で楽しめます。
殺人事件の謎よりも捜査が進むにつれ各登場人物のかかえる「謎」が明かされていく過程の方が楽しめました。
「科学捜査」が進んで「恐るべき犯人」VS「名探偵」という構図が成立しない中で、「これぞ恐るべき犯人」と意気込んだエラリイの捜査の終盤までの空回り感もなんとも皮肉です…。
警察がしらみつぶしに探した真犯人から実行犯への指示メッセージを見つけるところで何とか「名探偵」としてのエラリイの対面を立ててはいますが…。
「科学捜査」が進んだ60年代ならこれくらいは警察が見つけられそうな気がするのですが….。
「名探偵」が生きにくい時代に名探偵ものにしなきゃいけない設定ではこんな感じになるのでしょうか?
ミステリーが密室トリックやアリバイ崩しのようなパズル的「謎解き」だけでなく、プロット自体、状況全体に含まれるなにやら異常な仕掛けを解決していくような方向に進化していっているのをキャッチアップした作品なのでしょう。
メイントリックは現代から見たらそれほど意外というものではないですが、その異常な状況で関係者が振り回されるのを楽しむ作品なのでしょう。
文章はスタージョンが書いたとのことですが、クイーン父子のやりとりなど他のクィーン作品と違和感なく、ダネイのプロットを丁寧に処理し、まだ存命のリーの助言も仰いだというのが推察できます。
記憶がなく知能的に「?」なヨーク家の下男、ヘンリー・ウォルトの怪しげな雰囲気がスタージョンぽかったかなぁ?というくらいでした。
「エラリイ・クイーン」していたんでしょうね。
↓人に書かせるなんてダメじゃんという方も、そんなの関係ネーという方も、よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。













