南北戦争は「世界最大の内乱」と言われることがあります。その世界最大の戦争が終わって4年後のことです。大陸横断鉄道が開通しました。北部が圧倒的に優勢になったアメリカは莫大な富を生みだすことになります。蒸気機関車のように轟音を立てて、いま、資本主義が華々しく開花しようとしていたのです。
「鉄道はアメリカで最初に現われた大企業であり、後に巨大な産業的企業の財政を処理し、それを管理してゆく上で唯一の利用可能な手本となった。また、鉄道の発起人、融資者、経営者たちは、巨額の投資や複雑な管理様式を必要とする民間事業体を設立し、その財政をまかない、それを経営した最初の実業家たちであった。アメリカの実業家は他の国々の実業家に先んじて新しい方法を開拓した。それは、アメリカの鉄道が公企業ではなく民間企業であったためであろう。また、鉄道網や個々の鉄道が大規模なものであったためでもある。1875年までに、アメリカのひとつの鉄道会社、“ペンシルバニア鉄道” だけで当時のフランスの鉄道の二分の一、イギリスの鉄道の三分の一以上の営業距離をもっていた(「アメリカ史の新観点」/ C.V.ウッドワード・編)」。
鉄道の民間企業による経営は莫大な富を経営者たちにもたらし、農民との格差はおそろしく開きました。カネがマモンのように崇められる時代、「金ピカ時代」といわれる社会をもたらしました。稼いだ者が勝ち組というような、怖しい思想が広まります。「社会ダーウィニズム」です。
「純粋に生物学の理論であったダーウィンの進化論が社会に適用され、自由競争の結果、適者が勝ち残り、不適者は脱落してゆくのが自然淘汰の結果であるとする、ソシアル・ダーウィニズムの考えが時代の潮流となった(「物語・アメリカの歴史」/ 猿谷要・著)」。
失業してゆく者、倒産の憂き目に遭う経営者、彼らは淘汰されるべき「不適者」であるので、今日とは違い、何のセーフティ・ネットの保護も受けることはありませんでした。極端な市場原理主義とも言うべき「自由放任主義」、政府は市場に一切介入しないという方針ですが、当時の共和党は自由市場主義の方針を採っていましたから、独占的な資本家たちは企業連合(カルテル)や企業合同(トラスト)などを積極的に推し進め、政界にも食い込んで行くようになります。政界もまた産業界を利用して、癒着が常態化しました。今の中国のさらなる過激版とでも言えるでしょうか。
「こうして産業界は急激に膨張し、政界は腐敗して汚職が続出する。南北戦争での北軍の英雄グラント将軍は1869年から1877年まで二期にわたり大統領職に就いたが、彼の周辺は汚職にまみれ、今では(引用元の本は1991年初版発行。2006年現在では史上最悪の大統領はジョージ・W・ブッシュでしょう)史上最低の大統領と評価されている。グラントの在任中の1873年マーク・トウェインはチャールズ・ウォーナーとの共著で『金ぴか時代』という小説を発表したが、そのなかには議員やロビイストたちが、いかにカネで簡単に買われるかが、実に露骨なまでに描かれている。後にこの小説のタイトルは、南北戦争後から19世紀末までの物質万能、趣味俗悪、政治腐敗などを象徴するようになった。
「アメリカはかつて、ヨーロッパの束縛から逃れて神の国を実現しようとしたのではなかったろうか。アメリカはかつて『すべての人は生まれながらに平等である』と宣言して独立したはずではなかったろうか。アメリカはかつて天から与えられた使命に感じて西へ向かった人々の国ではなかったろうか。そういう人たちの無垢な精神は、どこへいったのだろうか(上掲書)」。
「かつて天から与えられた使命に感じて西へ向かった」というのはこういうことです。アメリカ合衆国は領土を大陸全般に広げてゆくのですが、その際に、インディアンへのジェノサイドやメキシコ異教国への軍事侵攻という手段を使うのでした。その行為を正当化するために言われたのが、「マニフェスト・デスティニー(明白な使命)」という標語でした。デモクラシーを広めてゆくための、神から与えられた明白な使命であり、合衆国民はそのために選ばれたのだという意味です。「この選民思想による使命感は、やがて西部全域でインディアンが抵抗できなくなるまで虐殺し、さらに太平洋の島々に及び、アジアにも広がろうとする(上掲書)」。インディアンやメキシコ人への侵略行為が無慈悲なピューリタニズムの押しつけであったことを示すシャーマン将軍のことばが残されています。彼は征服したニューメキシコを去るにあたり、ネイティブ・アメリカンたちにこのように言ったのでした。
「私は、今後の10年間にこのテリトリーから、日干しの泥で作られた家が一掃されることを期待しています。どうかあなた方が、レンガ造りの傾斜した屋根を持つ家の建て方を学ばれるよう望んでいます(つまりヨーロッパ・スタイルの家)。私たちヤンキーは、平らな屋根も泥を使った屋根も大嫌いなのです(「アメリカ・過去と現在の間」/ 古矢旬・著)」。
そういうわけで、猿谷要・東京女子大学名誉教授は、上記の最後の文章、「そういう人たちの無垢な精神は、どこへいったのだろうか」という問いかけに対し、このように応じておられます。
「実は、そう考えること自体に誤りがあったのだ。歴史家A.M.シュレシンジャーはこう書いている。『我々は(アメリカの白人)、アメリカ史の一時期に、“無垢の終焉” という語句を不用意に当てはめる。これは致命的間違いというよりは、好意的な修飾である。国は何度、その無垢を失うことができるのか。カルヴァンとタキトゥスで育った人々が無垢でいられるはずがない。侵略、征服、虐殺の上に建設された国家で無垢なものなどなかった。黒人を組織的に奴隷にし、インディアンを虐殺した国民で無垢なものは何もなかった。革命によって成立し、その後、内乱によって引き裂かれた国家で無垢なものはなかった。憲法は、人間は無垢だとは当然、仮定しなかった(「アメリカ史のサイクル」/ A.M.シュレシンジャー・著)』(上掲書)」。
今日のネオコンのブッシュ政権の勢力にも、このような流れが脈々と引き継がれているのでしょう。それはおいおいご紹介してゆきます。
さて、話を戻して、これまで、南北戦争後のアメリカ社会の物質主義化を少しご紹介しました。資本主義、重工業の発達には、合理的、科学的な考え方に立脚した思考があります。それは生物進化論という生物学の理論を、社会のありようにまで強引に適用させたことにも見られます。そしてそういう合理主義は、福音主義キリスト教の、原理主義的な宗教観とは相容れないものでした。こんな時代の流れのなかで、アメリカのキリスト教はどのように自らの占める位置を確保し、さらに拡大をも図ってゆくのでしょうか。ここでアメリカのキリスト教は大々的に「信仰復興運動」の大キャンペーンを張ることになるのです。
--------------------------------------
南北戦争の終結と奴隷解放は、反奴隷制を共通の信条とすることで保たれてきた北部福音派の一体性を大きく揺るがせる結果となった。ときあたかも近代的産業主義が勃興し、科学的合理的な世界観が北部都市を中心に急激な広がりを見せ始めていた。それは信仰の世界に危機が訪れたことを意味する。危機の一因は、キリスト教界の内部に発するリベラルな聖書解釈の動向にあった。
聖書を (神から与えられた霊的預言的な文書としてではなく) 歴史的文書資料として見直し、科学的な思考や歴史学的な思考にもとづいて再解釈し、聖書の神話的、非科学的部分を画定すべきであると主張するこのリベラルな動向が、聖書主義、回心(エホバの証人で言うところの「転向」)、キリストの再臨などを絶対視する保守的な福音主義の基盤を大きく掘り崩しつつあったのである。
しかし、なんといってもこの時期の福音主義的信仰にとって最大の危機は、チャールズ・ダーウィンが提唱した進化論によってもたらされた。それは、自然現象を観察と実験にもとづく科学の対象とし、そこから自然世界を科学的に再構成するという科学革命のひとつの到達点にほかならなかった。それは生物学上の革命でありながら、そのような科学の一分野をはるかに超える社会的衝撃をもたらした。
人類を含め全宇宙の万物を神の被造物とする聖書の一字一句を真実と考え、これを信仰の基礎におく福音主義者たちにとって、生命のないところから生命が発し、与えられた自然の環境との何億年にもわたる交渉と適応の過程を経てさまざまな種が生まれ、滅びてきたとする進化論は、彼らの信仰の根本を破壊しかねない衝撃であった。
進化論の登場により、それに対する福音主義キリスト教徒たちの硬い抵抗が引き起こされて、「近代主義と原理主義」という、以後今日まで一世紀半にわたりアメリカ・プロテスタンティズムを二分する非妥協的対立軸が形成されたのであった。
世紀転換期、進化論に対する保守的な福音主義者たちからの激しい抵抗が繰り返された。その主だった人々は、1895年ナイアガラに集い、危機に直面したキリスト者が信ずるべき「根本主義五原則」を採択する。五原則とは、
1. 聖書の言葉の隅々まですべてが真実であるという「聖書の逐語的な無謬性」、
2. イエスは神であるという「イエスの神性」、
3. 処女からキリストが生まれたという「処女降誕」、
4. キリストは人類の罪を背負って十字架についたとする「代償的贖罪論」、
5. 人間の罪が劫罰のなかで焼き尽くされるときにキリストが再び降臨するという「キリストの肉体的復活と身体的再臨」…からなる。
ここに示された神学的立場から見るならば、現状における人間社会は、罪に汚れ、破滅に向かって進みつつある「前千年王国」の段階にある。キリストの再臨がいつあってもおかしくない今、すべてのキリスト者は悔い改め、信仰を堅くすべきであると主張するこの前千年王国説は、「天啓的歴史観」に立脚していた。イギリスで同じような危機感のもとで信仰復興を行った「プリマス兄弟団」によってアメリカに持ち込まれたこの神学思想は、聖書のうちでも、とりわけ預言的な性格の強い「ダニエル書」や「黙示録」のメッセージを重視し、古代から現在にいたるまでの種々の歴史的事件はつとに聖書に預言されていたという注解を行いながら、終末におけるキリストの再臨を待ち望むというものであった。それは福音主義者の現世的戦闘性を生みだすこととなった。
その影響は遠く、中東情勢を語るときにハルマゲドンに言及する現代のTV福音伝道師の言説にまで及んでいる。この危急のとき、手をこまねいていたら、われわれキリスト者は堕落したまま千年王国を迎えなければならない。眼前の戦いこそが、まさにキリスト者にとっての最終的な戦いであるという。この終末論的思考が、現代の原理主義に独特の熱狂的で好戦的な色合いを添えているのである。
(「アメリカ 過去と現在の間」/ 古矢旬・著)
--------------------------------------
福音主義キリスト教徒は、だから、「近代化」を精神的に受け入れることができなかった人たちです。19世紀末までには古典物理学が完成され、欧米の人たちはそれまで神がかりに思われた自然現象を合理的に説明できるようになっていました。そのころには物理学はもはやこれ以上の進展はないと言われてさえいました。最後の難問である「光」の研究が物理学の新たな進展をもたらしたのですが、時代は合理主義の精神が広く受け入れられるようになり、物質文明が毒々しい花を咲かせはじめたのでした。しかし、同時に合理主義、科学的な精神は宗教的な因習や偏見を打破し、人間の生きかたに活路を開いたのも事実です。それだからこそ、アメリカのキリスト教徒は、自分たちの信仰にとって時代の精神が「危機」と受け止めるようになったのです。
もちろん、キリスト教徒の中にも、科学的・合理的批判を受け入れ、聖書のある部分を神話的創作として認めても、そのあと残る部分に立脚して信仰を立てていこうとする派もありました。「近代化」には人間の生活に便利と快適を提供する一面もあり、そういった側面は採用していくほうがよいとする一派です。こうした人たちは「熱狂的で戦闘的」な態度を持ちませんでした。ところが、もっとも保守的なキリスト教徒たち、「近代科学の手法による歴史的事実の発見や、社会認識の発展にかかわりなく、聖書の字句すべてを額面どおりに(上掲書)」事実と見なし、エホバの証人のように「神の霊的なメッセージ」として受けとめ、聖書と相容れない科学的な知見、それがもたらす進んだ社会認識のほうを否定してしまう派があり、彼らは戦闘的な態度を有するようになるのです。これはかなり目立つわけです。20世紀末でさえ、中絶手術を行う医療機関に爆弾を仕掛けるという、文字通りのテロ行為が行われているのです、アメリカでは。女性がローライズのジーンズの着用を禁ずる法が成立した州もあります。
このような頑迷固陋のキリスト教徒たちが団結し、根本主義五原則を採択し声明として打ち出すのです。宗教感情というものの怖ろしさをうかがわせる出来事ですよね。ピューリタニズムというものは、アメリカの白人市民の深層心理に焼き付けられていたようです。こういうのはたいてい、家庭での教育、躾がもたらすものです。エホバの証人の創始者である、チャールズ・テイズ・ラッセルもそうです。
「チャールズの両親はキリスト教世界の諸教会の信条を心から信じており,彼にもそれを受け入れてもらうことを目標に子育てを行ないました。そのため,チャールズ少年は,神は愛であると教えられましたが,同時に,神は人間を元々不滅のものとして創造し,救いが予定されている人々以外の全員をとこしえの責め苦に遭わせるために火の燃える場所を準備されたと教えられました。そのような考えは,十代のチャールズ少年の誠実な心を不快にさせました。
「自分の力を使って人間を創造しておきながら,その人間がとこしえの責め苦に遭うのを予知し,予定しているような神には知恵も公正も愛もあるはずがない。その規準は多くの人間の規準よりも低いことになる」と,チャールズは考えました。しかし,若き日のラッセルは無神論者ではありませんでした。ただ,一般に理解されている諸教会の教えを受け入れることができなかったのです。「そのような信条の各々には真理の要素が幾らか含まれていたものの,それらの信条は全体として人を惑わすものであり,神の言葉と矛盾していることを私は徐々に悟るようになった」と,彼は説明しています。
(「ふれ告げる」/ ものみの塔聖書冊子教会・作←「作」というのは、この本の記述にはかなりの潤色があるらしいのです。ニューヨーク本部の執筆委員が、そのことに心を痛めて脱会したという情報が、JWIC で報告されています)」。
ラッセルの両親は、ラッセルにも「キリスト教世界の諸教理を受け入れてもらうことを目標に子育てを行った」ようですが、ラッセルは期待通りになる反面、教理への自然な疑問をも抱くようになります。ですが、親の教えへの忠実さは越えることができず、キリスト教徒として、もうすこし受け入れやすい解釈を探し求めていたようです。こういうのって、19世紀後半における標準的なアメリカ人労働者の精神だったのでしょうか。こういう人たちが、近代的合理主義や科学精神、物質文明に対して戦闘的に抗うようになったのです。その意識下にあるものは変化への怖れでしょうか、それとも時代の流れに置き去りにされてゆくことへの不満があったのでしょうか。原理主義的なキリスト教の有りようを古矢教授はさらにこう述べておられます。
-------------------------------------------
20世紀冒頭のキリスト教における「根本主義」「原理主義」の背後には、アメリカ・キリスト教に初めから内在していた近代科学や個人主義的リベラリズムに対する根本的な不信感の流れをうかがうことができる。さらにいえば、原理主義とは、近代や科学の「攻勢」に対して信仰という領域をどのようにして防衛するかという課題に対する、アメリカの福音主義的立場からするひとつの回答であった。
一個の人間存在のレベルで見るならば、この課題は自らの霊的存在にかかわる信仰の部分と、世俗的存在にかかわる合理的知的な部分とをどのように両立させながら、ひとりの人間としての人格的統合を保つか、という問題となる。信仰と科学の矛盾を解決することは、人間が一貫した人格を取り戻すことを意味する。両者が引き裂かれたままでは、宗教は存立しえない。どうすればこの知識偏重の世俗社会の中で、真の霊性を取り戻すことができるか、霊的存在としての人間を回復できるか、これが近代世界においてまじめなキリスト教徒が考え続けてきた問題であった。したがって、この矛盾のなかで一貫して、過激に信仰の優位を説き続けてきた原理主義者を肯定的に評価する、主流のプロテスタント宗教者も少なくはない。彼らこそは、人間が科学や知識のみではよりよく生きえないというメッセージを執拗に発し続けてきたのである。
むろん、信仰と知の対立は、アメリカだけに現われた現象ではなかった。しかし、ヨーロッパの場合ならば、問題を引き受け、対立の前線に立つのは何よりもまず、地域の共同体や伝統的信仰組織たる教会や専門の聖職者であったといえよう。逆に人間の流動性の高い人工国家アメリカにおいては、それらの土着の共同体的な緩衝組織は、きわめて脆弱であった。それだけに、個人に大幅な信仰の自由、教派選択の自由が許され、多元的な宗教世界が展開されたとはいえる。
しかし、それは同時に、近代(科学的合理的精神)の侵食によって信仰が衰えるとき、個人が信仰復興の前線を担うことを求められることを意味してもいた。信仰復興のメッセージが、既成の教会や教派を飛び越えて、野外大集会を媒介として直接信徒に届けられ、個人的回心体験を梯子にして個々人を再度組織化してゆくというかたちの信仰復興運動が、アメリカに繰り返されてきた理由はまさにそこにある。
そしてその場合、説教師が届けるメッセージはそれ自体きわめて反近代的、反科学的、反進化論的であり、保守的、復古的な福音主義であり、しかし音信を伝達する手段は大衆説得の効率性を重視し、大衆集会であろうと、ラジオであろうと、TVであろうと、いかなる近代的テクノロジーが積極的に活用されるのである。
(「アメリカ 過去と現在の間」/ 古矢旬・著)
-------------------------------------------
堅苦しい文章ですね。ちょっとかみ砕いておきます。
アメリカのキリスト教には、近代化や個人主義(全体・共同体のための “個人” ではなく、“個人” の尊重と個人の権益を保障するための “全体、集団” という考えかた)への不信感がありました。信仰による自分の在りかた、信仰による人との結びつきを重視する傾向がありました。信仰、神、不謬の聖書というものがなければ、自分という存在は立ちえない、とする考えかたです。ですから、かれらは、近代のもたらす科学の成果や、合理主義的な考えかたにもとづく社会の有りようには徹底的に反感・嫌悪を表しました。それらが、とくに進化論や聖書の高等批判が信仰の土台を切り崩すからです。
しかし、テクノロジーの進歩や合理主義の精神は、世俗的な暮らしを豊かにするものであることは否定できません。これはとても魅力的です。しかし「豊かさ」という魅力は同時に信仰の基礎を破壊するのです。そして信仰が破壊されれば、彼らのアイデンティティも崩壊するのです、彼らにとっては。教派によっては、聖書から神話と画定された部分を除いても、残る部分から信仰は打ち立てることができるとするものもありましたが、原理主義的な態度は、近代化、科学精神、合理主義といったものを全く否定する方法で、世俗生活の利便よりも、信仰のほうを重視するのです。彼らの主張はこうです。
「人間は、科学やより明快になった知識ではよりよく生きられない。霊的価値観(宗教的価値観、という意味に受け取って間違いではないです)によってのみ、それが可能であり、アメリカはこのイデオロギーによって特徴づけられる」。
こうして彼らは、近代社会、科学的合理的精神への不信感を露骨に表し、否定するのです。わたしは、エホバの証人の輸血拒否や、そのまえに主張されていた予防接種禁止などの医療テクノロジーへの否定的態度には、こういったアメリカ社会に内在していた原理主義的なキリスト教の精神を受け継いでいると強く感じます。なぜなら、近代化や科学技術や合理主義への同様の反感はヨーロッパにもあったのですが、ヨーロッパでは伝統的な教会組織が対応するわけです。しかし、アメリカでは伝統的教会組織の影響力が脆弱でした(注:国家というものはみな「人工的」ですが、ここで「人工的」とあえて表現されているのは、アメリカが封建主義という経験を克服して国民国家をつくり上げたのではなく、初めから、封建主義の経験を持たずに、ピューリタンたちの思惑によって、国民国家として成立した国であるという意味です)。
だから、個人個人が近代化の流れになかで信仰をいかに守り、つまり自分たちのアイデンティティを守るかという問題に対処する。「個人的な回心体験が重視される(上掲書)」、つまり個人が対応するのだから、専門の聖職者のような歴史的評価、統一された神学による検討などふまえずに、信仰が語られる。そうすると個人的見解の色濃い教理が語られるようになる→トンデモ教理が登場する可能性も高くなる…エホバの証人のように…。現に、かれらの送り出すメッセージは「きわめて反近代的、反科学的、反進化論的であり、保守的、復古的な福音主義(上掲書)」だったのです。
この点なんて、エホバの証人は忠実に受け継いでいますよね。「純潔」を守りましょうなんていう言葉が生きているのはおそらくエホバの証人社会だけではないでしょうか。現実には、いろんな男性と交際する機会が多いほど、よりマッチするパートナーを見つけやすいのです。人を見る目もできますしね。実際、抱かれてみてあとでなんとなく不快に感じたということで、自分の本当の気持に気がついたりするということがあるのです。科学への不信というのもエホバの証人の特徴です。科学者による捏造事件などはしばしば取り上げられる話題です。だから科学に信頼をおいてはいけないというわけです。商業主義というのもやり玉に挙げられます。この点も、近代的な社会への反感が受け継がれているといえるのではないでしょうか。とくに伝統的宗教への敵意はエホバの証人の場合、凄まじい。「好戦的」という点では、エホバの証人は裁判を頻繁に起こします。輸血拒否というトンデモ教理を、信教の自由という個人的な権利の問題にすりかえて騒ぎ立てます。立憲国家ならどこでも信教の自由は保障しようとします。しかも法は宗教道徳の合理性にはタッチしません。どんな教理であれ、宗教を選択し、奉じるのは個人の権利であり、国家は介入しないのが大原則であるからです。それをいいことにトンデモ教理を正当化するのです。
一方で、音信の伝達には最新の技術が駆使されるという点もエホバの証人の特徴です。ラジオも使用されていましたし、エホバの証人はラジオ局を持っていたのです。聖書講演を吹き込んだレコードを訪問先で聞かせるということも行われていました。最近になると、電話回線を使用して、大会を全国で同時に開催するということも行います。エホバの証人はまさにアメリカの宗教だといえるのではないでしょうか。
以下、次回に続きます。
「鉄道はアメリカで最初に現われた大企業であり、後に巨大な産業的企業の財政を処理し、それを管理してゆく上で唯一の利用可能な手本となった。また、鉄道の発起人、融資者、経営者たちは、巨額の投資や複雑な管理様式を必要とする民間事業体を設立し、その財政をまかない、それを経営した最初の実業家たちであった。アメリカの実業家は他の国々の実業家に先んじて新しい方法を開拓した。それは、アメリカの鉄道が公企業ではなく民間企業であったためであろう。また、鉄道網や個々の鉄道が大規模なものであったためでもある。1875年までに、アメリカのひとつの鉄道会社、“ペンシルバニア鉄道” だけで当時のフランスの鉄道の二分の一、イギリスの鉄道の三分の一以上の営業距離をもっていた(「アメリカ史の新観点」/ C.V.ウッドワード・編)」。
鉄道の民間企業による経営は莫大な富を経営者たちにもたらし、農民との格差はおそろしく開きました。カネがマモンのように崇められる時代、「金ピカ時代」といわれる社会をもたらしました。稼いだ者が勝ち組というような、怖しい思想が広まります。「社会ダーウィニズム」です。
「純粋に生物学の理論であったダーウィンの進化論が社会に適用され、自由競争の結果、適者が勝ち残り、不適者は脱落してゆくのが自然淘汰の結果であるとする、ソシアル・ダーウィニズムの考えが時代の潮流となった(「物語・アメリカの歴史」/ 猿谷要・著)」。
失業してゆく者、倒産の憂き目に遭う経営者、彼らは淘汰されるべき「不適者」であるので、今日とは違い、何のセーフティ・ネットの保護も受けることはありませんでした。極端な市場原理主義とも言うべき「自由放任主義」、政府は市場に一切介入しないという方針ですが、当時の共和党は自由市場主義の方針を採っていましたから、独占的な資本家たちは企業連合(カルテル)や企業合同(トラスト)などを積極的に推し進め、政界にも食い込んで行くようになります。政界もまた産業界を利用して、癒着が常態化しました。今の中国のさらなる過激版とでも言えるでしょうか。
「こうして産業界は急激に膨張し、政界は腐敗して汚職が続出する。南北戦争での北軍の英雄グラント将軍は1869年から1877年まで二期にわたり大統領職に就いたが、彼の周辺は汚職にまみれ、今では(引用元の本は1991年初版発行。2006年現在では史上最悪の大統領はジョージ・W・ブッシュでしょう)史上最低の大統領と評価されている。グラントの在任中の1873年マーク・トウェインはチャールズ・ウォーナーとの共著で『金ぴか時代』という小説を発表したが、そのなかには議員やロビイストたちが、いかにカネで簡単に買われるかが、実に露骨なまでに描かれている。後にこの小説のタイトルは、南北戦争後から19世紀末までの物質万能、趣味俗悪、政治腐敗などを象徴するようになった。
「アメリカはかつて、ヨーロッパの束縛から逃れて神の国を実現しようとしたのではなかったろうか。アメリカはかつて『すべての人は生まれながらに平等である』と宣言して独立したはずではなかったろうか。アメリカはかつて天から与えられた使命に感じて西へ向かった人々の国ではなかったろうか。そういう人たちの無垢な精神は、どこへいったのだろうか(上掲書)」。
「かつて天から与えられた使命に感じて西へ向かった」というのはこういうことです。アメリカ合衆国は領土を大陸全般に広げてゆくのですが、その際に、インディアンへのジェノサイドやメキシコ異教国への軍事侵攻という手段を使うのでした。その行為を正当化するために言われたのが、「マニフェスト・デスティニー(明白な使命)」という標語でした。デモクラシーを広めてゆくための、神から与えられた明白な使命であり、合衆国民はそのために選ばれたのだという意味です。「この選民思想による使命感は、やがて西部全域でインディアンが抵抗できなくなるまで虐殺し、さらに太平洋の島々に及び、アジアにも広がろうとする(上掲書)」。インディアンやメキシコ人への侵略行為が無慈悲なピューリタニズムの押しつけであったことを示すシャーマン将軍のことばが残されています。彼は征服したニューメキシコを去るにあたり、ネイティブ・アメリカンたちにこのように言ったのでした。
「私は、今後の10年間にこのテリトリーから、日干しの泥で作られた家が一掃されることを期待しています。どうかあなた方が、レンガ造りの傾斜した屋根を持つ家の建て方を学ばれるよう望んでいます(つまりヨーロッパ・スタイルの家)。私たちヤンキーは、平らな屋根も泥を使った屋根も大嫌いなのです(「アメリカ・過去と現在の間」/ 古矢旬・著)」。
そういうわけで、猿谷要・東京女子大学名誉教授は、上記の最後の文章、「そういう人たちの無垢な精神は、どこへいったのだろうか」という問いかけに対し、このように応じておられます。
「実は、そう考えること自体に誤りがあったのだ。歴史家A.M.シュレシンジャーはこう書いている。『我々は(アメリカの白人)、アメリカ史の一時期に、“無垢の終焉” という語句を不用意に当てはめる。これは致命的間違いというよりは、好意的な修飾である。国は何度、その無垢を失うことができるのか。カルヴァンとタキトゥスで育った人々が無垢でいられるはずがない。侵略、征服、虐殺の上に建設された国家で無垢なものなどなかった。黒人を組織的に奴隷にし、インディアンを虐殺した国民で無垢なものは何もなかった。革命によって成立し、その後、内乱によって引き裂かれた国家で無垢なものはなかった。憲法は、人間は無垢だとは当然、仮定しなかった(「アメリカ史のサイクル」/ A.M.シュレシンジャー・著)』(上掲書)」。
今日のネオコンのブッシュ政権の勢力にも、このような流れが脈々と引き継がれているのでしょう。それはおいおいご紹介してゆきます。
さて、話を戻して、これまで、南北戦争後のアメリカ社会の物質主義化を少しご紹介しました。資本主義、重工業の発達には、合理的、科学的な考え方に立脚した思考があります。それは生物進化論という生物学の理論を、社会のありようにまで強引に適用させたことにも見られます。そしてそういう合理主義は、福音主義キリスト教の、原理主義的な宗教観とは相容れないものでした。こんな時代の流れのなかで、アメリカのキリスト教はどのように自らの占める位置を確保し、さらに拡大をも図ってゆくのでしょうか。ここでアメリカのキリスト教は大々的に「信仰復興運動」の大キャンペーンを張ることになるのです。
--------------------------------------
南北戦争の終結と奴隷解放は、反奴隷制を共通の信条とすることで保たれてきた北部福音派の一体性を大きく揺るがせる結果となった。ときあたかも近代的産業主義が勃興し、科学的合理的な世界観が北部都市を中心に急激な広がりを見せ始めていた。それは信仰の世界に危機が訪れたことを意味する。危機の一因は、キリスト教界の内部に発するリベラルな聖書解釈の動向にあった。
聖書を (神から与えられた霊的預言的な文書としてではなく) 歴史的文書資料として見直し、科学的な思考や歴史学的な思考にもとづいて再解釈し、聖書の神話的、非科学的部分を画定すべきであると主張するこのリベラルな動向が、聖書主義、回心(エホバの証人で言うところの「転向」)、キリストの再臨などを絶対視する保守的な福音主義の基盤を大きく掘り崩しつつあったのである。
しかし、なんといってもこの時期の福音主義的信仰にとって最大の危機は、チャールズ・ダーウィンが提唱した進化論によってもたらされた。それは、自然現象を観察と実験にもとづく科学の対象とし、そこから自然世界を科学的に再構成するという科学革命のひとつの到達点にほかならなかった。それは生物学上の革命でありながら、そのような科学の一分野をはるかに超える社会的衝撃をもたらした。
人類を含め全宇宙の万物を神の被造物とする聖書の一字一句を真実と考え、これを信仰の基礎におく福音主義者たちにとって、生命のないところから生命が発し、与えられた自然の環境との何億年にもわたる交渉と適応の過程を経てさまざまな種が生まれ、滅びてきたとする進化論は、彼らの信仰の根本を破壊しかねない衝撃であった。
進化論の登場により、それに対する福音主義キリスト教徒たちの硬い抵抗が引き起こされて、「近代主義と原理主義」という、以後今日まで一世紀半にわたりアメリカ・プロテスタンティズムを二分する非妥協的対立軸が形成されたのであった。
世紀転換期、進化論に対する保守的な福音主義者たちからの激しい抵抗が繰り返された。その主だった人々は、1895年ナイアガラに集い、危機に直面したキリスト者が信ずるべき「根本主義五原則」を採択する。五原則とは、
1. 聖書の言葉の隅々まですべてが真実であるという「聖書の逐語的な無謬性」、
2. イエスは神であるという「イエスの神性」、
3. 処女からキリストが生まれたという「処女降誕」、
4. キリストは人類の罪を背負って十字架についたとする「代償的贖罪論」、
5. 人間の罪が劫罰のなかで焼き尽くされるときにキリストが再び降臨するという「キリストの肉体的復活と身体的再臨」…からなる。
ここに示された神学的立場から見るならば、現状における人間社会は、罪に汚れ、破滅に向かって進みつつある「前千年王国」の段階にある。キリストの再臨がいつあってもおかしくない今、すべてのキリスト者は悔い改め、信仰を堅くすべきであると主張するこの前千年王国説は、「天啓的歴史観」に立脚していた。イギリスで同じような危機感のもとで信仰復興を行った「プリマス兄弟団」によってアメリカに持ち込まれたこの神学思想は、聖書のうちでも、とりわけ預言的な性格の強い「ダニエル書」や「黙示録」のメッセージを重視し、古代から現在にいたるまでの種々の歴史的事件はつとに聖書に預言されていたという注解を行いながら、終末におけるキリストの再臨を待ち望むというものであった。それは福音主義者の現世的戦闘性を生みだすこととなった。
その影響は遠く、中東情勢を語るときにハルマゲドンに言及する現代のTV福音伝道師の言説にまで及んでいる。この危急のとき、手をこまねいていたら、われわれキリスト者は堕落したまま千年王国を迎えなければならない。眼前の戦いこそが、まさにキリスト者にとっての最終的な戦いであるという。この終末論的思考が、現代の原理主義に独特の熱狂的で好戦的な色合いを添えているのである。
(「アメリカ 過去と現在の間」/ 古矢旬・著)
--------------------------------------
福音主義キリスト教徒は、だから、「近代化」を精神的に受け入れることができなかった人たちです。19世紀末までには古典物理学が完成され、欧米の人たちはそれまで神がかりに思われた自然現象を合理的に説明できるようになっていました。そのころには物理学はもはやこれ以上の進展はないと言われてさえいました。最後の難問である「光」の研究が物理学の新たな進展をもたらしたのですが、時代は合理主義の精神が広く受け入れられるようになり、物質文明が毒々しい花を咲かせはじめたのでした。しかし、同時に合理主義、科学的な精神は宗教的な因習や偏見を打破し、人間の生きかたに活路を開いたのも事実です。それだからこそ、アメリカのキリスト教徒は、自分たちの信仰にとって時代の精神が「危機」と受け止めるようになったのです。
もちろん、キリスト教徒の中にも、科学的・合理的批判を受け入れ、聖書のある部分を神話的創作として認めても、そのあと残る部分に立脚して信仰を立てていこうとする派もありました。「近代化」には人間の生活に便利と快適を提供する一面もあり、そういった側面は採用していくほうがよいとする一派です。こうした人たちは「熱狂的で戦闘的」な態度を持ちませんでした。ところが、もっとも保守的なキリスト教徒たち、「近代科学の手法による歴史的事実の発見や、社会認識の発展にかかわりなく、聖書の字句すべてを額面どおりに(上掲書)」事実と見なし、エホバの証人のように「神の霊的なメッセージ」として受けとめ、聖書と相容れない科学的な知見、それがもたらす進んだ社会認識のほうを否定してしまう派があり、彼らは戦闘的な態度を有するようになるのです。これはかなり目立つわけです。20世紀末でさえ、中絶手術を行う医療機関に爆弾を仕掛けるという、文字通りのテロ行為が行われているのです、アメリカでは。女性がローライズのジーンズの着用を禁ずる法が成立した州もあります。
このような頑迷固陋のキリスト教徒たちが団結し、根本主義五原則を採択し声明として打ち出すのです。宗教感情というものの怖ろしさをうかがわせる出来事ですよね。ピューリタニズムというものは、アメリカの白人市民の深層心理に焼き付けられていたようです。こういうのはたいてい、家庭での教育、躾がもたらすものです。エホバの証人の創始者である、チャールズ・テイズ・ラッセルもそうです。
「チャールズの両親はキリスト教世界の諸教会の信条を心から信じており,彼にもそれを受け入れてもらうことを目標に子育てを行ないました。そのため,チャールズ少年は,神は愛であると教えられましたが,同時に,神は人間を元々不滅のものとして創造し,救いが予定されている人々以外の全員をとこしえの責め苦に遭わせるために火の燃える場所を準備されたと教えられました。そのような考えは,十代のチャールズ少年の誠実な心を不快にさせました。
「自分の力を使って人間を創造しておきながら,その人間がとこしえの責め苦に遭うのを予知し,予定しているような神には知恵も公正も愛もあるはずがない。その規準は多くの人間の規準よりも低いことになる」と,チャールズは考えました。しかし,若き日のラッセルは無神論者ではありませんでした。ただ,一般に理解されている諸教会の教えを受け入れることができなかったのです。「そのような信条の各々には真理の要素が幾らか含まれていたものの,それらの信条は全体として人を惑わすものであり,神の言葉と矛盾していることを私は徐々に悟るようになった」と,彼は説明しています。
(「ふれ告げる」/ ものみの塔聖書冊子教会・作←「作」というのは、この本の記述にはかなりの潤色があるらしいのです。ニューヨーク本部の執筆委員が、そのことに心を痛めて脱会したという情報が、JWIC で報告されています)」。
ラッセルの両親は、ラッセルにも「キリスト教世界の諸教理を受け入れてもらうことを目標に子育てを行った」ようですが、ラッセルは期待通りになる反面、教理への自然な疑問をも抱くようになります。ですが、親の教えへの忠実さは越えることができず、キリスト教徒として、もうすこし受け入れやすい解釈を探し求めていたようです。こういうのって、19世紀後半における標準的なアメリカ人労働者の精神だったのでしょうか。こういう人たちが、近代的合理主義や科学精神、物質文明に対して戦闘的に抗うようになったのです。その意識下にあるものは変化への怖れでしょうか、それとも時代の流れに置き去りにされてゆくことへの不満があったのでしょうか。原理主義的なキリスト教の有りようを古矢教授はさらにこう述べておられます。
-------------------------------------------
20世紀冒頭のキリスト教における「根本主義」「原理主義」の背後には、アメリカ・キリスト教に初めから内在していた近代科学や個人主義的リベラリズムに対する根本的な不信感の流れをうかがうことができる。さらにいえば、原理主義とは、近代や科学の「攻勢」に対して信仰という領域をどのようにして防衛するかという課題に対する、アメリカの福音主義的立場からするひとつの回答であった。
一個の人間存在のレベルで見るならば、この課題は自らの霊的存在にかかわる信仰の部分と、世俗的存在にかかわる合理的知的な部分とをどのように両立させながら、ひとりの人間としての人格的統合を保つか、という問題となる。信仰と科学の矛盾を解決することは、人間が一貫した人格を取り戻すことを意味する。両者が引き裂かれたままでは、宗教は存立しえない。どうすればこの知識偏重の世俗社会の中で、真の霊性を取り戻すことができるか、霊的存在としての人間を回復できるか、これが近代世界においてまじめなキリスト教徒が考え続けてきた問題であった。したがって、この矛盾のなかで一貫して、過激に信仰の優位を説き続けてきた原理主義者を肯定的に評価する、主流のプロテスタント宗教者も少なくはない。彼らこそは、人間が科学や知識のみではよりよく生きえないというメッセージを執拗に発し続けてきたのである。
むろん、信仰と知の対立は、アメリカだけに現われた現象ではなかった。しかし、ヨーロッパの場合ならば、問題を引き受け、対立の前線に立つのは何よりもまず、地域の共同体や伝統的信仰組織たる教会や専門の聖職者であったといえよう。逆に人間の流動性の高い人工国家アメリカにおいては、それらの土着の共同体的な緩衝組織は、きわめて脆弱であった。それだけに、個人に大幅な信仰の自由、教派選択の自由が許され、多元的な宗教世界が展開されたとはいえる。
しかし、それは同時に、近代(科学的合理的精神)の侵食によって信仰が衰えるとき、個人が信仰復興の前線を担うことを求められることを意味してもいた。信仰復興のメッセージが、既成の教会や教派を飛び越えて、野外大集会を媒介として直接信徒に届けられ、個人的回心体験を梯子にして個々人を再度組織化してゆくというかたちの信仰復興運動が、アメリカに繰り返されてきた理由はまさにそこにある。
そしてその場合、説教師が届けるメッセージはそれ自体きわめて反近代的、反科学的、反進化論的であり、保守的、復古的な福音主義であり、しかし音信を伝達する手段は大衆説得の効率性を重視し、大衆集会であろうと、ラジオであろうと、TVであろうと、いかなる近代的テクノロジーが積極的に活用されるのである。
(「アメリカ 過去と現在の間」/ 古矢旬・著)
-------------------------------------------
堅苦しい文章ですね。ちょっとかみ砕いておきます。
アメリカのキリスト教には、近代化や個人主義(全体・共同体のための “個人” ではなく、“個人” の尊重と個人の権益を保障するための “全体、集団” という考えかた)への不信感がありました。信仰による自分の在りかた、信仰による人との結びつきを重視する傾向がありました。信仰、神、不謬の聖書というものがなければ、自分という存在は立ちえない、とする考えかたです。ですから、かれらは、近代のもたらす科学の成果や、合理主義的な考えかたにもとづく社会の有りようには徹底的に反感・嫌悪を表しました。それらが、とくに進化論や聖書の高等批判が信仰の土台を切り崩すからです。
しかし、テクノロジーの進歩や合理主義の精神は、世俗的な暮らしを豊かにするものであることは否定できません。これはとても魅力的です。しかし「豊かさ」という魅力は同時に信仰の基礎を破壊するのです。そして信仰が破壊されれば、彼らのアイデンティティも崩壊するのです、彼らにとっては。教派によっては、聖書から神話と画定された部分を除いても、残る部分から信仰は打ち立てることができるとするものもありましたが、原理主義的な態度は、近代化、科学精神、合理主義といったものを全く否定する方法で、世俗生活の利便よりも、信仰のほうを重視するのです。彼らの主張はこうです。
「人間は、科学やより明快になった知識ではよりよく生きられない。霊的価値観(宗教的価値観、という意味に受け取って間違いではないです)によってのみ、それが可能であり、アメリカはこのイデオロギーによって特徴づけられる」。
こうして彼らは、近代社会、科学的合理的精神への不信感を露骨に表し、否定するのです。わたしは、エホバの証人の輸血拒否や、そのまえに主張されていた予防接種禁止などの医療テクノロジーへの否定的態度には、こういったアメリカ社会に内在していた原理主義的なキリスト教の精神を受け継いでいると強く感じます。なぜなら、近代化や科学技術や合理主義への同様の反感はヨーロッパにもあったのですが、ヨーロッパでは伝統的な教会組織が対応するわけです。しかし、アメリカでは伝統的教会組織の影響力が脆弱でした(注:国家というものはみな「人工的」ですが、ここで「人工的」とあえて表現されているのは、アメリカが封建主義という経験を克服して国民国家をつくり上げたのではなく、初めから、封建主義の経験を持たずに、ピューリタンたちの思惑によって、国民国家として成立した国であるという意味です)。
だから、個人個人が近代化の流れになかで信仰をいかに守り、つまり自分たちのアイデンティティを守るかという問題に対処する。「個人的な回心体験が重視される(上掲書)」、つまり個人が対応するのだから、専門の聖職者のような歴史的評価、統一された神学による検討などふまえずに、信仰が語られる。そうすると個人的見解の色濃い教理が語られるようになる→トンデモ教理が登場する可能性も高くなる…エホバの証人のように…。現に、かれらの送り出すメッセージは「きわめて反近代的、反科学的、反進化論的であり、保守的、復古的な福音主義(上掲書)」だったのです。
この点なんて、エホバの証人は忠実に受け継いでいますよね。「純潔」を守りましょうなんていう言葉が生きているのはおそらくエホバの証人社会だけではないでしょうか。現実には、いろんな男性と交際する機会が多いほど、よりマッチするパートナーを見つけやすいのです。人を見る目もできますしね。実際、抱かれてみてあとでなんとなく不快に感じたということで、自分の本当の気持に気がついたりするということがあるのです。科学への不信というのもエホバの証人の特徴です。科学者による捏造事件などはしばしば取り上げられる話題です。だから科学に信頼をおいてはいけないというわけです。商業主義というのもやり玉に挙げられます。この点も、近代的な社会への反感が受け継がれているといえるのではないでしょうか。とくに伝統的宗教への敵意はエホバの証人の場合、凄まじい。「好戦的」という点では、エホバの証人は裁判を頻繁に起こします。輸血拒否というトンデモ教理を、信教の自由という個人的な権利の問題にすりかえて騒ぎ立てます。立憲国家ならどこでも信教の自由は保障しようとします。しかも法は宗教道徳の合理性にはタッチしません。どんな教理であれ、宗教を選択し、奉じるのは個人の権利であり、国家は介入しないのが大原則であるからです。それをいいことにトンデモ教理を正当化するのです。
一方で、音信の伝達には最新の技術が駆使されるという点もエホバの証人の特徴です。ラジオも使用されていましたし、エホバの証人はラジオ局を持っていたのです。聖書講演を吹き込んだレコードを訪問先で聞かせるということも行われていました。最近になると、電話回線を使用して、大会を全国で同時に開催するということも行います。エホバの証人はまさにアメリカの宗教だといえるのではないでしょうか。
以下、次回に続きます。














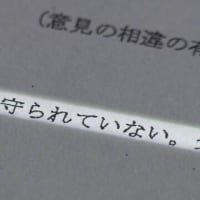
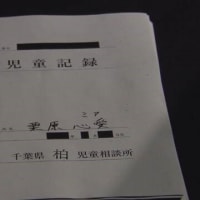







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます