◆「利息」は経済社会にとって非合理なもの - 利息取得の禁止で「近代」は終焉を迎える - 投稿者 あっしら 日時 2002 年 10 月 12 日
通貨を貸して、貸した通貨額+利息(通貨額)を得るということがどういうことかを考えてみます。
● 利息の源泉
通貨自体が新たな通貨を生み出すことはありません。
借りた通貨を元手に生産活動か商業活動を行って、他者から元手以上の通貨を稼がなければ、自分の生活費+利息に相当する通貨を手に入れることはできません。
借りた通貨ではなく元々所有している通貨を使って生産活動か商業活動を行う人と競争関係にある場合、無借金の人は自分の生活費だけを稼げばいいのに対し、借金をしている人はそれに加えて利息分も稼がなければなりません。
具体的に言えば、無借金の人は小麦を10万円で販売すればいいのに、借金の人は小麦を11万円で販売しなければならないことになります。
10万円で売っているものを11万円で買う人は物不足でもない限りいないはずです。
ですから、借金をした人が投機に成功した場合を除けば、債務が履行できなくなり、担保の土地などを取られるか、債務奴隷になるというのが普通です。
共同体を考えたとき、生産手段を失った人や債務奴隷が増大したらどうなるでしょう。
これまで農具や衣服を生産した人が活動できなくなったり、これまで小麦を仕入れてくれた人がいなくなったりします。
これでは、共同体の再生産構造は揺らいでしまいます。
宗教や法は、共同体(国家)という複数の人々(家族)の関係性や活動を規定するものですから、共同体の再生産構造がおかしくなる行為を禁止するのは極めて自然な判断です。
※ 商業利潤
商業利潤も、商業自体が利潤を生むわけではありません。
商業活動で仕入れ額<販売額になるのは、輸送費(昔の商人は輸送業も兼務)と生産者の販売活動の代理(生産者の利益の分配)と考えるほうが論理的です。
● 金持ちが金貸しに揃って走ったら
利息取得を許したら、余裕の通貨をたっぷり持っている人が金貸し業に走ることを考えれます。
なぜなら、自分が汗水垂らす活動をしなくても、ひとがそのような活動を行った成果を利息によって手に入れることができるからです。
金貸し業がはびこる経済社会が、長期に維持できると考えるのは無理なことで、金貸しに通貨や資産が集まってしまうことでその経済社会は終焉を迎えるはずです。
● ユダヤ教の利息取得禁止とイスラムの利息取得禁止
ユダヤ教(旧約聖書)では、同胞からの利息取得を禁止しています。
これは、同胞以外すなわち外部共同体からであれば利息を取得してもいいということになります。
金貸し活動が欧州で反ユダヤ意識を醸成した主要な要因ですが、共同体経済論理に照らせば、ユダヤ教の教えは合理的な判断と言えます。
外部共同体からの利息取得は、近代風に言えば、経常収支を構成する所得収支に該当します。ですから、共同体の通貨幣的“富”が増加するので、その通貨が共同体内で使われれば全体が潤うことになります。
イスラムは、誰に対しても利息を取得することを禁止していますから、利息の流入による特定共同体の繁栄を認めていないことになります。
これが、ウンマ(世界性を持つイスラム共同体)のウンマたる所以です。
そして、だからこそ、イスラム世界は「近代」の歴史過程のなかで“没落”していったとも言えます。
● 近代の利息所得
「近代」のすごさは、通貨の供給そのものが利息を取る貸し出しを始源としていることです。
中央銀行が商業銀行に利息付きの貸し出しをすることで通貨が経済社会に顔を出し、商業銀行が各種活動を営む経済主体に同じく利息付きの貸し出しを行うことで、通貨が経済社会に流れ出します。
さらに、銀行の利息取得活動をサポートするために、「信用創造」機能が認められています。
現在の中央銀行であれば、なんら裏付けがないまま紙幣を印刷して貸し出しができます。
それに対する制約は、それによって利息がマイナスになってしまうインフレが起きるとか、商業銀行が借りてくれないという経済状況だけです。
金本位制でも、中央銀行は保有金量の4倍まで紙幣を発行することができました。
もちろん、4倍の紙幣を発行するからといって価値が1/4になるわけではありません。まさに錬金術で、1Kgの金が4kgの金になるのです。
(この恩恵をワールドワイドに受けたのは、パックスブルタニカのなかで絶対的な信用力を誇っていた英国の銀行家なかんずくイングランド銀行だけと言っても過言ではありません)
商業銀行は、預金を活用して「信用創造」を行います。
商業銀行の「信用創造」に対する制約は、預金準備率や自己資本規制と“経済状況”です。
「信用創造」は、同じ通貨を複数の貸し出しに使うということです。
例えば、X銀行が1億円の預金を保有しており、そのうち8千万円をAに貸し出し、AはBにそれを支払い、Bがその8千万円をX銀行に預ける。X銀行は、8千万円のなから6千万円をCに貸し出し、CがDに・・・・・という仕組みで、ひとの通貨1億円で3億、4億という貸し出しができます。(これは、預金準備率により規制の例だとイメージしてください)
自己資本規制であれば、自分の通貨ではない預金を自分の通貨の12倍ほど貸し出しに使うことができます。この規制を逃れてもっと貸し出しをしたいときは、国家への貸し出しである国債を購入すればいいのです。(国債は基本的にリスクゼロとして規制から除外されます)
このように、「中央銀行→商業銀行→経済主体」という過程で、厖大な貸し出しが行われているのが「近代経済システム」です。
不思議なのは、それでも、先進国といわれる国々の国民経済はうまく経済活動が循環して再生産構造が維持されてきたことです。
そのわけは、ユダヤ教と同じで、「外部共同体から利息(利潤)を取得してきた」からです。
厖大な「信用創造」=貸し出しが銀行の利息をマイナスにするようなインフレを招かないためには、供給される財が貿易を通じて外部共同体に流出していく必要があります。
もう一つの方法は、貸し出しを国内ではなく、国際的に行うことです。
貿易黒字は、財の国内供給を少なくしてインフレを抑制しながら通貨的“富”を増加させる方法であり、国際貸し出しは、通貨を外部に流出させてインフレを抑制しながら利息を外部共同体から得て通貨的“富”を増加させるという方法です。
(前者は戦後日本を、後者は戦後米国をイメージすればいいでしょう)
最後の不思議は、厖大な「信用創造」=貸し出しが行われてインフレになるはずの「近代経済システム」に、今、世界的なデフレの波が押し寄せているという現実です。
そのわけは、貸し出しが拡大できない“経済状況”が世界的に生まれているからです。
借り手がいなければ、貸し出しはできません。また、貸し出しをしても返済があてにならないと判断したら、銀行は貸し出しをしません。
銀行家は、元々共同体(国家)のために機能しているのではなく、自己の資本を増殖させるために活動しています。
資本が増殖しない経済条件であれば、信用=貸し出しは一気に収縮します。
その一方で、産業は、競争に打ち勝つために、生産性を上昇させる努力を日々重ねています。生産性の上昇とは、同じ通貨量を投入してより多くの財を生産できるようにすることです。
貸し出しであれ、保有通貨であれ、経済社会に流れている通貨量が減少するなかで財や用役の供給量が増大すれば、デフレになるのは当然のことです。
科学技術の驚異的な発展に支えられた産業の飛躍的成長が、近代の通貨制度と激突する時代を迎えたのです。
(科学技術の驚異的な発展も、利潤追求欲求に支えられたものです)
● 利息取得禁止法で「近代」は終焉を迎える
財の価格が下落傾向を示すデフレは、ことさら悪い経済事象ではありません。
デフレが“悪”と認識されるのは、それが経済活動全体を縮小させ、借り入れ負担を増大させるからです。
経済活動とりわけ産業活動が縮小するのは、G-W-G’という通貨→財→通貨の迂回的な資本増殖活動にとって、デフレは“敵”となる経済事象だからです。
時間経過と共に財の価格が下落しているということは、G>G’になる可能性が高いのですから、わざわざ人を雇ったり財を購入して生産活動を行うより、通貨をそのまま保有していたほうがいいという判断を資本家(経営者)にもたらします。
競争に打ち勝つために、生産性を上昇させる努力を日々重ねる経済システムですから、「近代経済システム」は、根っことして、デフレになる宿命を帯びています。
「信用創造」による“インフレ”が行き詰まったことで、根っことしての“デフレ”が現実しているのが現在の経済状況です。
そうであるが故に、「デフレ不況」の解消策としての金融緩和政策やインフレターゲット政策は無効なのです。
これから確実に襲ってくる「世界同時デフレ不況」は、経済価値観もそうですが、利息取得を目的とした通貨供給を止めることでしか究極的には解消できません。
利息取得禁止法のなかで経済社会が円滑に動くためには、国家(政府)が通貨を発行するかたちに制度を改変する必要があります。
http://sun.ap.teacup.com/souun/164.html
◆晴耕雨読 - 寄生性と知的謀略
http://sun.ap.teacup.com/souun/143.html
◆晴耕雨読 - 世界経済にとって70年代はどういう時代だったのか
http://sun.ap.teacup.com/souun/358.html
◆晴耕雨読 - 80年代以降の金融資本的収穫を支える価値観と経済政策
http://sun.ap.teacup.com/souun/363.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/364.html
◆晴耕雨読 - 「定常状態」あるいは「歴史段階的動態均衡」という経済状況
http://sun.ap.teacup.com/souun/342.html
◆中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ (2007年2月4日3時5分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070204i101.htm
◆国際協力銀、イスラム金融普及へセミナー・現状を紹介 日本経済新聞 2007年1月24日
国際協力銀行(JBIC)は22、23の両日、都内でイスラム金融の現状を紹介するセミナーを開いた。教義に従い資金を調達・運用するイスラム金融を対象にした本格的なセミナーは初めて。同行は、23日のセミナーでマレーシア中央銀行とアジアでのイスラム金融普及に向けて協力する内容の覚書に調印したと明らかにした。
セミナーはイスラム金融の国際監督機関、イスラム金融サービス委員会(IFSB、本部クアラルンプール)などとの共催。講演したマレーシア中央銀行のゼティ総裁は「イスラム金融の規模は世界60カ国以上で5000億ドル(約61兆円)程度にまで増えており、特殊な市場ではなくなった」と指摘。カリームIFSB事務局長は「市場は毎年15%以上拡大しており、需要に供給が追いつかない状況だ」と述べた。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20070124AT2M2301K23012007.html
◆国際協力銀がイスラム金融でマレーシア中央銀と覚書締結 朝日新聞 2007年01月23日
http://www.asahi.com/business/update/0123/142.html
◆【フランス】仏初のイスラム銀行設立へ 2月6日12時0分 NNA
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070206-00000014-nna-int
◆不動産価格、2年以内に上海50%北京30%の下落か 2007/02/03 [中国情報局]
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0203&f=business_0203_001.shtml
◆中国政府要人のバブル発言と株価抑制:調整への懸念 [中国情報局]
上昇を続けた中国株が、足元で大きく調整しています。2月5日、中国株の代表的な指標である上海総合株価指数(上海指数)の終値は2612.54と、5日連続の下落となりました。過去最高を記録した今年1月24日と比べると、上海指数は12%下落したことになります。
昨年11月から今年1月末まで、中国株は急ピッチで上昇を続けていました。昨年11月1日の上海指数(終値)からの上昇率をみると、わずか1カ月後の11月30日に13%の上昇を記録し、年末(12月29日)には44%の上昇、そして過去最高を記録した今年1月24日には60%の上昇となっています。2月に入って上海指数は下落が続いていますが、それでも昨年11月1日からみれば、上海指数は4割以上も上昇していることになります。
中国株が下落する理由として、中国金融当局による株価抑制策が指摘されています。中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会の成思危・副委員長は、英「フィナンシャル・タイムズ」紙に対し「バブルが形成されている。投資家はリスクを心配すべきだ」と発言し、中国株の上昇が「バブル」状態にあることを明言しました。また、その後も成・副委員長は、中国の金融時報に「中国の株式市場には国内外から資金が流入し、過熱状態にある」と寄稿し、中国株の上昇に対する警戒感を隠そうとしていません。成・副委員長のこうした姿勢をみれば、市場が当局による株価抑制策を懸念するのも自然のことと思われます。
ただ、仮に中国の当局者が中国株の上昇に警鐘を鳴らさなくても、中国株の調整は起きても不思議ではなかったと思えます。株式の時価総額を企業利益で割ることで求められるPER(株価収益率)を2月5日時点で比べると、韓国総合株価指数(KOSPI)が13倍、インドNIFTY指数が24倍であるのに対し、上海指数は37倍と、他市場に比べ割高感が強い状況です。仮に上海指数の株価収益率がインドNIFTY指数と同程度まで低下する余地があるならば、上海指数は、足元からさらに3割以上下落しても不思議ではないことになります。
これまで拡大を続けてきた外資企業による中国への直接投資が伸び悩んでいる点も気になるところです。中国商務部が公表した昨年の投資統計によると、日本から中国への直接投資は、前年(2005年)から3割近く減少しています。また日本に次いで中国に投資する韓国の直接投資額は25%程度、米国も6%程度それぞれ減少しています。中国当局は、理由として、中国国内の賃金や土地取得のコストが上昇した点を挙げていますが、仮にこれが真実であれば、中国企業の収益性は、コスト上昇により低下することになり、急ピッチの株価上昇に合理性がなくなります。
国内外の投機資金の流入が今後も続く可能性があることや、08年開催の北京五輪を契機にさらなる経済成長が見込まれることを理由に、長期で考えれば、中国株の上昇は、今後も続くと見込む投資家が(プロアマ問わず)数多くいるようです。ただ、仮に中国株が長期的には上昇するとしても、短期でみた場合、大きな調整を迎える可能性が高まっているのも事実です。中国株に限らないことですが、買えば儲かる、といったシンプルな発想だけで中国株への投資を進めるのは、あまり感心できることではないように思えます。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0207&f=column_0207_006.shtml
【私のコメント】
イスラム教は全ての利息取得を、ユダヤ教は全ての同胞からの利息取得を禁止しているが、これは金利を取得される共同体が破滅的運命を辿ることを経験的に理解していたからなのであろう。「近代経済システム」はこのユダヤ教的利息取得を極限まで押し進めたものであり、「中央銀行→商業銀行→経済主体」という過程で、厖大な貸し出しが行われている。しかし、この貸し出しの増加がもはや限界に達しつつあること、技術革新による物価の下落がデフレによって製造業を破綻させつつあることが「近代経済システム」の行き詰まりを示している。このまま国際金融資本の世界支配が継続すれば、「近代経済システム」は破綻し、「近代経済システム」が世界全体を支配下に置いているが故に、長沼真一郎氏が危惧するとおりに地球文明全体がブラックホール(コラプサー)状態に陥ることであろう。
このような危機から脱出するには、利息取得のない文明が成功できるという実例を作りだしそれを世界に広めるしかない。そこに、現在「イスラム金融」が注目される理由がある。現在のイスラム世界は混乱の中にあり欧州やロシアは混乱の拡大や移民流出を脅威視しているが、その一方で危機に瀕した世界文明(近代経済システム)を救うための数少ない救いでもあるのだ。西欧科学技術とイスラム教社会とイスラム金融を結合させた先進社会をペルシャ湾岸に作り出すことができるかどうかが先進国の運命を握っているとも言える。
1970年代以降の先進国では、サッチャリズムに代表される「国営企業の民営化」「規制緩和」「自由化」「グローバル化」が叫ばれた。しかし、その結果先進国の職場が途上国に奪われて貧困化し、巨大化した多国籍企業に関わる一握りの人々に富が集中する結果をもたらした。また、公共サービスを中心とする国営企業の民営化は国有財産の切り売りやその後の利潤至上主義経営を通じて国際金融資本を富裕化させた。先進国から搾取すること以外に成長を生み出す原動力を国際金融資本は失ってしまったのだ(中国やインドの成長は先進国からの搾取の分け前に過ぎない)。その結果が、国際金融資本が寄生してきた先進国社会の崩壊に繋がることはもはや自明である。また、途上国で繰り返される通貨危機も国際金融資本による搾取の機会に他ならないのだ。
1990年代の世界的な株式バブル、2000年代以降も継続している米英などの不動産バブル、消費者金融バブルは借金を通じたバブル形成であり、もはやバブルを作り出す以外に先進国では銀行貸し出しの増加や経済成長を生み出せないことを示している。そのバブルが崩壊したあとに起きることは、一足早くバブル形成と崩壊を経験した日本の例を見る限り、極端なデフレ不況である可能性が高い。そして、同時に多くの先進諸国では金利が急速に低下してゼロ金利に近い状態に成るであろう。成長が止まり、貸出先が減少するのだから金利も低いのは当たり前である。それは、「利息」が消滅した状態、つまり「近代経済システム」の終わった時代という見方ができる。現在の超低金利状態でも中小企業や消費者向けの金融では高利息の取得が行われているが、それはもはや「金利」ではなく、「債務不履行リスク」の取引と言うべきであろう。1990年代以降の日本はいわば、「科学技術文明とゼロ金利状態の結合」という、寿命を迎えた近代経済システム後の社会像の巨大な実験場と言えるだろう。日本は江戸時代後半に成長の停止を経験しており、この経験に学ぶことが解決策に繋がると想像される。そして、長沼真一郎氏が提唱する「全ての利息取得を禁止するイスラム社会と科学技術文明の結合」という計画もまた同様の実験場と考えられる。江田島孔明氏らの提唱する「親日イスラムとの提携」には私は賛成だが、もはや寿命を迎えた「国際金融資本」との提携には害はあっても利益はないように思われ、賛成しない。
1945年の第二次大戦終了から62年が経過した。戦後生まれのベビーブーム世代が今後続々と定年退職を迎える一方で少子化により新規就職者は減少しており、極端なデフレ不況による失業率上昇が緩和される絶好の機会である。先月末から中国では急激な株価下落が始まっており、地価の暴落も予測されている。また、3月に中国で私有財産保護法が制定されることは共産主義体制の完全な終焉を意味する(この重大なニュースは重大であるが故にあまり取り上げられていないのだろう)が、農民の所有する土地を強制収用して高値で売り払って私腹を肥やしてきた中国の地方自治体政府の役人たちは収益源を失うことになり、大きな打撃を受けることになると想像される。共産主義体制化で不動産バブルや株式バブルが発生するという中国の現状は私有財産保護の不明確さがその原動力であった。世界でほとんど唯一、高度成長を続けてきた中国がそのバブルを崩壊させ始めたことで、「近代経済システム」が終焉することになるだろう。そして、日本やイスラム社会での実験の行方が新たな社会の行方を占うものとなるだろう。もし、日本・イスラムの実験が失敗するならば、国際金融資本の伝統的な解決策である「世界大戦実行による先進国社会の破壊=リセット」が唯一の選択枝となり、世界核戦争が実行されることになるのかもしれない。
通貨を貸して、貸した通貨額+利息(通貨額)を得るということがどういうことかを考えてみます。
● 利息の源泉
通貨自体が新たな通貨を生み出すことはありません。
借りた通貨を元手に生産活動か商業活動を行って、他者から元手以上の通貨を稼がなければ、自分の生活費+利息に相当する通貨を手に入れることはできません。
借りた通貨ではなく元々所有している通貨を使って生産活動か商業活動を行う人と競争関係にある場合、無借金の人は自分の生活費だけを稼げばいいのに対し、借金をしている人はそれに加えて利息分も稼がなければなりません。
具体的に言えば、無借金の人は小麦を10万円で販売すればいいのに、借金の人は小麦を11万円で販売しなければならないことになります。
10万円で売っているものを11万円で買う人は物不足でもない限りいないはずです。
ですから、借金をした人が投機に成功した場合を除けば、債務が履行できなくなり、担保の土地などを取られるか、債務奴隷になるというのが普通です。
共同体を考えたとき、生産手段を失った人や債務奴隷が増大したらどうなるでしょう。
これまで農具や衣服を生産した人が活動できなくなったり、これまで小麦を仕入れてくれた人がいなくなったりします。
これでは、共同体の再生産構造は揺らいでしまいます。
宗教や法は、共同体(国家)という複数の人々(家族)の関係性や活動を規定するものですから、共同体の再生産構造がおかしくなる行為を禁止するのは極めて自然な判断です。
※ 商業利潤
商業利潤も、商業自体が利潤を生むわけではありません。
商業活動で仕入れ額<販売額になるのは、輸送費(昔の商人は輸送業も兼務)と生産者の販売活動の代理(生産者の利益の分配)と考えるほうが論理的です。
● 金持ちが金貸しに揃って走ったら
利息取得を許したら、余裕の通貨をたっぷり持っている人が金貸し業に走ることを考えれます。
なぜなら、自分が汗水垂らす活動をしなくても、ひとがそのような活動を行った成果を利息によって手に入れることができるからです。
金貸し業がはびこる経済社会が、長期に維持できると考えるのは無理なことで、金貸しに通貨や資産が集まってしまうことでその経済社会は終焉を迎えるはずです。
● ユダヤ教の利息取得禁止とイスラムの利息取得禁止
ユダヤ教(旧約聖書)では、同胞からの利息取得を禁止しています。
これは、同胞以外すなわち外部共同体からであれば利息を取得してもいいということになります。
金貸し活動が欧州で反ユダヤ意識を醸成した主要な要因ですが、共同体経済論理に照らせば、ユダヤ教の教えは合理的な判断と言えます。
外部共同体からの利息取得は、近代風に言えば、経常収支を構成する所得収支に該当します。ですから、共同体の通貨幣的“富”が増加するので、その通貨が共同体内で使われれば全体が潤うことになります。
イスラムは、誰に対しても利息を取得することを禁止していますから、利息の流入による特定共同体の繁栄を認めていないことになります。
これが、ウンマ(世界性を持つイスラム共同体)のウンマたる所以です。
そして、だからこそ、イスラム世界は「近代」の歴史過程のなかで“没落”していったとも言えます。
● 近代の利息所得
「近代」のすごさは、通貨の供給そのものが利息を取る貸し出しを始源としていることです。
中央銀行が商業銀行に利息付きの貸し出しをすることで通貨が経済社会に顔を出し、商業銀行が各種活動を営む経済主体に同じく利息付きの貸し出しを行うことで、通貨が経済社会に流れ出します。
さらに、銀行の利息取得活動をサポートするために、「信用創造」機能が認められています。
現在の中央銀行であれば、なんら裏付けがないまま紙幣を印刷して貸し出しができます。
それに対する制約は、それによって利息がマイナスになってしまうインフレが起きるとか、商業銀行が借りてくれないという経済状況だけです。
金本位制でも、中央銀行は保有金量の4倍まで紙幣を発行することができました。
もちろん、4倍の紙幣を発行するからといって価値が1/4になるわけではありません。まさに錬金術で、1Kgの金が4kgの金になるのです。
(この恩恵をワールドワイドに受けたのは、パックスブルタニカのなかで絶対的な信用力を誇っていた英国の銀行家なかんずくイングランド銀行だけと言っても過言ではありません)
商業銀行は、預金を活用して「信用創造」を行います。
商業銀行の「信用創造」に対する制約は、預金準備率や自己資本規制と“経済状況”です。
「信用創造」は、同じ通貨を複数の貸し出しに使うということです。
例えば、X銀行が1億円の預金を保有しており、そのうち8千万円をAに貸し出し、AはBにそれを支払い、Bがその8千万円をX銀行に預ける。X銀行は、8千万円のなから6千万円をCに貸し出し、CがDに・・・・・という仕組みで、ひとの通貨1億円で3億、4億という貸し出しができます。(これは、預金準備率により規制の例だとイメージしてください)
自己資本規制であれば、自分の通貨ではない預金を自分の通貨の12倍ほど貸し出しに使うことができます。この規制を逃れてもっと貸し出しをしたいときは、国家への貸し出しである国債を購入すればいいのです。(国債は基本的にリスクゼロとして規制から除外されます)
このように、「中央銀行→商業銀行→経済主体」という過程で、厖大な貸し出しが行われているのが「近代経済システム」です。
不思議なのは、それでも、先進国といわれる国々の国民経済はうまく経済活動が循環して再生産構造が維持されてきたことです。
そのわけは、ユダヤ教と同じで、「外部共同体から利息(利潤)を取得してきた」からです。
厖大な「信用創造」=貸し出しが銀行の利息をマイナスにするようなインフレを招かないためには、供給される財が貿易を通じて外部共同体に流出していく必要があります。
もう一つの方法は、貸し出しを国内ではなく、国際的に行うことです。
貿易黒字は、財の国内供給を少なくしてインフレを抑制しながら通貨的“富”を増加させる方法であり、国際貸し出しは、通貨を外部に流出させてインフレを抑制しながら利息を外部共同体から得て通貨的“富”を増加させるという方法です。
(前者は戦後日本を、後者は戦後米国をイメージすればいいでしょう)
最後の不思議は、厖大な「信用創造」=貸し出しが行われてインフレになるはずの「近代経済システム」に、今、世界的なデフレの波が押し寄せているという現実です。
そのわけは、貸し出しが拡大できない“経済状況”が世界的に生まれているからです。
借り手がいなければ、貸し出しはできません。また、貸し出しをしても返済があてにならないと判断したら、銀行は貸し出しをしません。
銀行家は、元々共同体(国家)のために機能しているのではなく、自己の資本を増殖させるために活動しています。
資本が増殖しない経済条件であれば、信用=貸し出しは一気に収縮します。
その一方で、産業は、競争に打ち勝つために、生産性を上昇させる努力を日々重ねています。生産性の上昇とは、同じ通貨量を投入してより多くの財を生産できるようにすることです。
貸し出しであれ、保有通貨であれ、経済社会に流れている通貨量が減少するなかで財や用役の供給量が増大すれば、デフレになるのは当然のことです。
科学技術の驚異的な発展に支えられた産業の飛躍的成長が、近代の通貨制度と激突する時代を迎えたのです。
(科学技術の驚異的な発展も、利潤追求欲求に支えられたものです)
● 利息取得禁止法で「近代」は終焉を迎える
財の価格が下落傾向を示すデフレは、ことさら悪い経済事象ではありません。
デフレが“悪”と認識されるのは、それが経済活動全体を縮小させ、借り入れ負担を増大させるからです。
経済活動とりわけ産業活動が縮小するのは、G-W-G’という通貨→財→通貨の迂回的な資本増殖活動にとって、デフレは“敵”となる経済事象だからです。
時間経過と共に財の価格が下落しているということは、G>G’になる可能性が高いのですから、わざわざ人を雇ったり財を購入して生産活動を行うより、通貨をそのまま保有していたほうがいいという判断を資本家(経営者)にもたらします。
競争に打ち勝つために、生産性を上昇させる努力を日々重ねる経済システムですから、「近代経済システム」は、根っことして、デフレになる宿命を帯びています。
「信用創造」による“インフレ”が行き詰まったことで、根っことしての“デフレ”が現実しているのが現在の経済状況です。
そうであるが故に、「デフレ不況」の解消策としての金融緩和政策やインフレターゲット政策は無効なのです。
これから確実に襲ってくる「世界同時デフレ不況」は、経済価値観もそうですが、利息取得を目的とした通貨供給を止めることでしか究極的には解消できません。
利息取得禁止法のなかで経済社会が円滑に動くためには、国家(政府)が通貨を発行するかたちに制度を改変する必要があります。
http://sun.ap.teacup.com/souun/164.html
◆晴耕雨読 - 寄生性と知的謀略
http://sun.ap.teacup.com/souun/143.html
◆晴耕雨読 - 世界経済にとって70年代はどういう時代だったのか
http://sun.ap.teacup.com/souun/358.html
◆晴耕雨読 - 80年代以降の金融資本的収穫を支える価値観と経済政策
http://sun.ap.teacup.com/souun/363.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/364.html
◆晴耕雨読 - 「定常状態」あるいは「歴史段階的動態均衡」という経済状況
http://sun.ap.teacup.com/souun/342.html
◆中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ (2007年2月4日3時5分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070204i101.htm
◆国際協力銀、イスラム金融普及へセミナー・現状を紹介 日本経済新聞 2007年1月24日
国際協力銀行(JBIC)は22、23の両日、都内でイスラム金融の現状を紹介するセミナーを開いた。教義に従い資金を調達・運用するイスラム金融を対象にした本格的なセミナーは初めて。同行は、23日のセミナーでマレーシア中央銀行とアジアでのイスラム金融普及に向けて協力する内容の覚書に調印したと明らかにした。
セミナーはイスラム金融の国際監督機関、イスラム金融サービス委員会(IFSB、本部クアラルンプール)などとの共催。講演したマレーシア中央銀行のゼティ総裁は「イスラム金融の規模は世界60カ国以上で5000億ドル(約61兆円)程度にまで増えており、特殊な市場ではなくなった」と指摘。カリームIFSB事務局長は「市場は毎年15%以上拡大しており、需要に供給が追いつかない状況だ」と述べた。
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20070124AT2M2301K23012007.html
◆国際協力銀がイスラム金融でマレーシア中央銀と覚書締結 朝日新聞 2007年01月23日
http://www.asahi.com/business/update/0123/142.html
◆【フランス】仏初のイスラム銀行設立へ 2月6日12時0分 NNA
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070206-00000014-nna-int
◆不動産価格、2年以内に上海50%北京30%の下落か 2007/02/03 [中国情報局]
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0203&f=business_0203_001.shtml
◆中国政府要人のバブル発言と株価抑制:調整への懸念 [中国情報局]
上昇を続けた中国株が、足元で大きく調整しています。2月5日、中国株の代表的な指標である上海総合株価指数(上海指数)の終値は2612.54と、5日連続の下落となりました。過去最高を記録した今年1月24日と比べると、上海指数は12%下落したことになります。
昨年11月から今年1月末まで、中国株は急ピッチで上昇を続けていました。昨年11月1日の上海指数(終値)からの上昇率をみると、わずか1カ月後の11月30日に13%の上昇を記録し、年末(12月29日)には44%の上昇、そして過去最高を記録した今年1月24日には60%の上昇となっています。2月に入って上海指数は下落が続いていますが、それでも昨年11月1日からみれば、上海指数は4割以上も上昇していることになります。
中国株が下落する理由として、中国金融当局による株価抑制策が指摘されています。中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会の成思危・副委員長は、英「フィナンシャル・タイムズ」紙に対し「バブルが形成されている。投資家はリスクを心配すべきだ」と発言し、中国株の上昇が「バブル」状態にあることを明言しました。また、その後も成・副委員長は、中国の金融時報に「中国の株式市場には国内外から資金が流入し、過熱状態にある」と寄稿し、中国株の上昇に対する警戒感を隠そうとしていません。成・副委員長のこうした姿勢をみれば、市場が当局による株価抑制策を懸念するのも自然のことと思われます。
ただ、仮に中国の当局者が中国株の上昇に警鐘を鳴らさなくても、中国株の調整は起きても不思議ではなかったと思えます。株式の時価総額を企業利益で割ることで求められるPER(株価収益率)を2月5日時点で比べると、韓国総合株価指数(KOSPI)が13倍、インドNIFTY指数が24倍であるのに対し、上海指数は37倍と、他市場に比べ割高感が強い状況です。仮に上海指数の株価収益率がインドNIFTY指数と同程度まで低下する余地があるならば、上海指数は、足元からさらに3割以上下落しても不思議ではないことになります。
これまで拡大を続けてきた外資企業による中国への直接投資が伸び悩んでいる点も気になるところです。中国商務部が公表した昨年の投資統計によると、日本から中国への直接投資は、前年(2005年)から3割近く減少しています。また日本に次いで中国に投資する韓国の直接投資額は25%程度、米国も6%程度それぞれ減少しています。中国当局は、理由として、中国国内の賃金や土地取得のコストが上昇した点を挙げていますが、仮にこれが真実であれば、中国企業の収益性は、コスト上昇により低下することになり、急ピッチの株価上昇に合理性がなくなります。
国内外の投機資金の流入が今後も続く可能性があることや、08年開催の北京五輪を契機にさらなる経済成長が見込まれることを理由に、長期で考えれば、中国株の上昇は、今後も続くと見込む投資家が(プロアマ問わず)数多くいるようです。ただ、仮に中国株が長期的には上昇するとしても、短期でみた場合、大きな調整を迎える可能性が高まっているのも事実です。中国株に限らないことですが、買えば儲かる、といったシンプルな発想だけで中国株への投資を進めるのは、あまり感心できることではないように思えます。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0207&f=column_0207_006.shtml
【私のコメント】
イスラム教は全ての利息取得を、ユダヤ教は全ての同胞からの利息取得を禁止しているが、これは金利を取得される共同体が破滅的運命を辿ることを経験的に理解していたからなのであろう。「近代経済システム」はこのユダヤ教的利息取得を極限まで押し進めたものであり、「中央銀行→商業銀行→経済主体」という過程で、厖大な貸し出しが行われている。しかし、この貸し出しの増加がもはや限界に達しつつあること、技術革新による物価の下落がデフレによって製造業を破綻させつつあることが「近代経済システム」の行き詰まりを示している。このまま国際金融資本の世界支配が継続すれば、「近代経済システム」は破綻し、「近代経済システム」が世界全体を支配下に置いているが故に、長沼真一郎氏が危惧するとおりに地球文明全体がブラックホール(コラプサー)状態に陥ることであろう。
このような危機から脱出するには、利息取得のない文明が成功できるという実例を作りだしそれを世界に広めるしかない。そこに、現在「イスラム金融」が注目される理由がある。現在のイスラム世界は混乱の中にあり欧州やロシアは混乱の拡大や移民流出を脅威視しているが、その一方で危機に瀕した世界文明(近代経済システム)を救うための数少ない救いでもあるのだ。西欧科学技術とイスラム教社会とイスラム金融を結合させた先進社会をペルシャ湾岸に作り出すことができるかどうかが先進国の運命を握っているとも言える。
1970年代以降の先進国では、サッチャリズムに代表される「国営企業の民営化」「規制緩和」「自由化」「グローバル化」が叫ばれた。しかし、その結果先進国の職場が途上国に奪われて貧困化し、巨大化した多国籍企業に関わる一握りの人々に富が集中する結果をもたらした。また、公共サービスを中心とする国営企業の民営化は国有財産の切り売りやその後の利潤至上主義経営を通じて国際金融資本を富裕化させた。先進国から搾取すること以外に成長を生み出す原動力を国際金融資本は失ってしまったのだ(中国やインドの成長は先進国からの搾取の分け前に過ぎない)。その結果が、国際金融資本が寄生してきた先進国社会の崩壊に繋がることはもはや自明である。また、途上国で繰り返される通貨危機も国際金融資本による搾取の機会に他ならないのだ。
1990年代の世界的な株式バブル、2000年代以降も継続している米英などの不動産バブル、消費者金融バブルは借金を通じたバブル形成であり、もはやバブルを作り出す以外に先進国では銀行貸し出しの増加や経済成長を生み出せないことを示している。そのバブルが崩壊したあとに起きることは、一足早くバブル形成と崩壊を経験した日本の例を見る限り、極端なデフレ不況である可能性が高い。そして、同時に多くの先進諸国では金利が急速に低下してゼロ金利に近い状態に成るであろう。成長が止まり、貸出先が減少するのだから金利も低いのは当たり前である。それは、「利息」が消滅した状態、つまり「近代経済システム」の終わった時代という見方ができる。現在の超低金利状態でも中小企業や消費者向けの金融では高利息の取得が行われているが、それはもはや「金利」ではなく、「債務不履行リスク」の取引と言うべきであろう。1990年代以降の日本はいわば、「科学技術文明とゼロ金利状態の結合」という、寿命を迎えた近代経済システム後の社会像の巨大な実験場と言えるだろう。日本は江戸時代後半に成長の停止を経験しており、この経験に学ぶことが解決策に繋がると想像される。そして、長沼真一郎氏が提唱する「全ての利息取得を禁止するイスラム社会と科学技術文明の結合」という計画もまた同様の実験場と考えられる。江田島孔明氏らの提唱する「親日イスラムとの提携」には私は賛成だが、もはや寿命を迎えた「国際金融資本」との提携には害はあっても利益はないように思われ、賛成しない。
1945年の第二次大戦終了から62年が経過した。戦後生まれのベビーブーム世代が今後続々と定年退職を迎える一方で少子化により新規就職者は減少しており、極端なデフレ不況による失業率上昇が緩和される絶好の機会である。先月末から中国では急激な株価下落が始まっており、地価の暴落も予測されている。また、3月に中国で私有財産保護法が制定されることは共産主義体制の完全な終焉を意味する(この重大なニュースは重大であるが故にあまり取り上げられていないのだろう)が、農民の所有する土地を強制収用して高値で売り払って私腹を肥やしてきた中国の地方自治体政府の役人たちは収益源を失うことになり、大きな打撃を受けることになると想像される。共産主義体制化で不動産バブルや株式バブルが発生するという中国の現状は私有財産保護の不明確さがその原動力であった。世界でほとんど唯一、高度成長を続けてきた中国がそのバブルを崩壊させ始めたことで、「近代経済システム」が終焉することになるだろう。そして、日本やイスラム社会での実験の行方が新たな社会の行方を占うものとなるだろう。もし、日本・イスラムの実験が失敗するならば、国際金融資本の伝統的な解決策である「世界大戦実行による先進国社会の破壊=リセット」が唯一の選択枝となり、世界核戦争が実行されることになるのかもしれない。













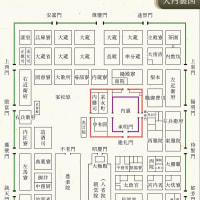





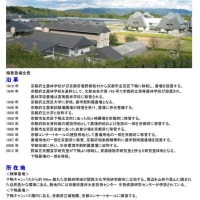
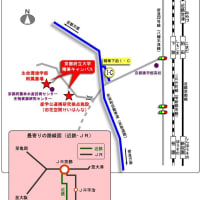
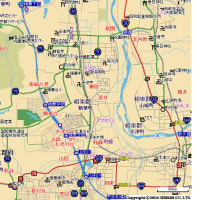






国際金融と反国際金融が正面衝突して世界大戦によって世界が壊滅したとしても新しい循環都市を南海に設置している彼らには「対岸の火事」に過ぎない。
一部の古き血の末裔たる精鋭と新鋭たる日本人の若者たちが参加している。日本それ自体が国際金融と反国際金融によって灰燼と帰し消滅し我らが死滅しても彼らが日本を復興するだろう。
日本に残った第二線戦力でさえこの程度の情報は知らされている。しかし本当の彼らの力は想像を絶する。
隔岸観火(岸を隔てて火を観る)は兵法三十六計の第九計にあたる戦術。
対岸で火事が起きたときは、燃え盛るのをじっと待つのが良い。中国春秋時代に晋の宰相趙盾は宋、衛、陳とともに晋から離反した鄭を攻めた。楚の大臣闘椒は鄭へ救援に向かい、「楚王はこれから諸侯を帰服させるのに、配下の私が諸侯の難儀を見捨てることが出来ようか」と言って、陣を構えて決戦を挑んだ。闘椒の豪勇を知る趙盾は「彼の一族は楚で盛んであるのでやがて滅びる。しばらく驕らせておこう」と言って兵を退いた。果たして後年、闘椒は荘王の謀臣蔿賈を幽閉して殺し、叛乱軍を起こして荘王に鎮圧された。闘椒・蔿賈という優れた武将を二人も一挙に失ってしまった荘王は、以降の重要な戦いでは常に自らが先頭に立って軍を率いねばならなかった。
このように、敵が内側に火種を抱えている場合に、それが燃え盛って敵が自滅するのを待つ戦術を隔岸観火の計と呼ぶ。
後年、荘王が臣下に国事を諮ったところ、誰一人自分よりも優れた意見を出す人物が居なかった。荘王は嘆息して、「どのような時代にも聖人はおり、どのような国にも賢者は乏しくない。真の師を見いだして臣下にすることが出来た者は王となり、友となる資格のある者を臣下に出来れば覇者となれる、と聞いている。私は特別優れているわけでもないのに、その自分に及ぶ者がいないとなれば、楚の国の将来はどうなるのか」と言った。居並ぶ群臣は、返す言葉もなかったという。結局荘王の死後、楚は天下の覇権を晋に奪われることになる。
出典は『呉子』。
過剰な生産力を国家が買い上げていくと。
そうしたら国際金融資本の居場所はなくなってくるかな。
中世から近代への大きなうねりがいろいろとありますが、そのひとつがこの金貸し業の利息が経済の中でシステム化されていく過程にあるというのは、非常に重要なことになります。その中でユダヤ人が生みだした金融資本は、ユダヤ教という宗教からのみ導かれるものではなく、金融資本という行動原理から導かれる、さらにこういった金融資本が「寄生性」、「知的謀略」という行動原理を持つというのは、とてつもなく重要なことに思えます。
米国保守本流につらなる財閥は、(隠れも含めて)ユダヤ系であるかないかという議論より、長年の「伝統的」国際金融資本との「つきあい」から上記の原理によって自ら、国際金融資本となったということになりそうです。トヨタなど日本企業もそうなりつつあるかもしれません。
> 地理的に継承される共同体ではなく価値的つながりを基礎に、地理的に継承されているほかの共同体との経済取引を通じて利益を得ようとする構えを意味します。
米国保守本流につらなる財閥が、これにあてはまる歴史的な事実をみつける必要がありますが、早雲氏の他の記事をヒントにすると、第2次世界大戦前からベトナム戦争ということになるのでしょうか。
> もし、日本・イスラムの実験が失敗するならば、国際金融資本の伝統的な解決策である「世界大戦実行による先進国社会の破壊=リセット」が唯一の選択枝となり、世界核戦争が実行されることになるのかもしれない。
管理人氏の前提条件は関係なく、彼らは実行計画を立てているのではないでしょうか。
世界大戦の場所をどこにするのか、自分たちはどこに避難するのか、いろいろな陰謀を巡らせるのでしょう。
http://tanakanews.com/070206korea.htm
日米安全保障条約が消滅するという議論が盛んですね。
日米安保の終焉 2012年
No. : 330 [返信]
Name : koji
Date : 2007/01/25(Thu) 17:26
URL : http://park1.wakwak.com/~dupuy/sunbbs/index2.html?
2011年に米国が日米安全保障条約の自動更新をしない通告をする。
日付を見る限り江田島氏はアメリカから光の声はイギリスから田中宇氏は中国から情報を得ているのでしょう。たぶん、管理人氏はKGB経由で北野氏から同様の情報を得ている可能性があると思いますがどうなんでしょうか?
「イスラム教は全ての利息取得を、ユダヤ教は全ての同胞からの利息取得を禁止しているが、・・・」
とありますが、イスラム教の国(インドネシア・イラン・イラク・サウジアラビア・・・・・・)での経済社会は全て無利子で運用されているのですか?
たとえば会社の運用資金の借り入れは無利子なのですね。住宅ローンは無利子で元本を分割で払っていくのですね。金貸し業そのものもないのですね。
オイルマネーは、無利子で米国に貸し付けているのですね。初めて知りました。