
シンポジウム「食の伝統と革新、持続可能性、および栄養 - 無形文化遺産としての地中海式食事法と和食」を聞いてきました(2017.11.22)@イタリア文化会館
「第2回世界イタリア料理週間」(2017.11.17~26)のメインイベントが このシンポジウム「食の伝統と革新、持続可能性、および栄養 - 無形文化遺産としての地中海式食事法と和食 -(Tradizione e innovazione per il cibo e la nutrizione sostenibili del futuro: le diete mediterranea e giapponese in quanto "Patrimoni culturali immateriali dell'umanità" dell'UNESCO)」でした
4名のパネリストの方々が学術的観点から様々な貴重なご報告をされ モデレーター(木村純子/法政大学教授)がラストにまとめてくださり その後のビュッフェでは イタリア農業食料林業政策省 そして協賛のBarilla社 Bottega社による素晴らしいイタリア料理とワインが次から次へと...この場で新しい人たちとも出会い 忘れられない貴重な一日となりました:
* * *
紹介文:
2010年に地中海食 2013年に和食がそれぞれユネスコ無形文化遺産に登録されました
これら2つの食事法は異なるものでありながら、様々な点において共通する特徴を有しています
双方とも 脈々と受け継がれてきた天然資源の持続可能な使用法や 生産・加工・保存方法を持ち 長年におよぶ実践と伝統を背景としているのです
本シンポジウムの目的は 学術的なアプローチを通し イタリアと日本両国において食と栄養の文化が持つ重要性に光をあてることです
食の伝統や地域産業を維持しつつ 同時に食品の健全で持続可能な生産を確保するために両国がいかに尽力しているのかについても焦点を当てます
イタリアと日本の食文化や生産への関心を 今後さらに高めていくための鍵は その類似点と相違点を適切に理解することです
各分野の具体的な研究プロジェクトを手がかりに 社会科学と自然科学両方の視点から議論します
* * *
1. 「ユネスコ無形文化遺産の視点から考える地中海式食事法の栄養と環境に与える影響」
カルロ・アルベルト・プラテージ(ローマ第三大学教授、バリラ食品栄養学センター顧問)
イタリアの輸出総額のうち8.7%がイタリアの食材 ただ世界には偽ブランドのイタリア食もある  ← イタリア各州のDOP IGP
← イタリア各州のDOP IGP
なぜイタリア料理は愛されるのか? 1. Tasty 味(2017年の 「世界のレストランBest50」のトップはイタリアのOsteria Francescana) 2. Healthy 健康 3. Convenient 作りやすさ (フランス料理は8割が調理人の腕 イタリア料理は8割が素材) 4. ingrediente telling a story 素材のストーリー性 5. Inexpensive 安さ そして 6. Sosteinible 持続性 これはあまり知られていないが フードガイドピラミッドを示しつつ 環境にやさしいことと身体にやさしいという2つの目的があると示してくださいました ← 地中海食では肉は少なめに(環境負荷が実は高い)と勧めています ← フードガイドピラミッド 2つの目的
← フードガイドピラミッド 2つの目的 ← 食品ごとのCo2の環境負荷
← 食品ごとのCo2の環境負荷
バリラ食品栄養学センターでの研究結果の発表: パスタをゆでる時に水を3割減らせばCo2も8%減る ガスを減らせる鍋も開発されたそうです
輪作の大切さ 農家の収入を落とさずに持続可能な収穫を続けるためのデシジョンサポートシステム テクノロジーによりベストな方法を探る試みが 各方面と協力して進められている 環境影響を3割減らしつつ収穫を3割アップ 等についてご報告いただきました  ← Barillaによる co-innovation for sustainability
← Barillaによる co-innovation for sustainability
このあとのビュッフェでは様々なパスタが続々と... ← Barillaの展示
← Barillaの展示
* * *
2.中村丁次「健康食としての地中海食と和食の類似点および相違点」(神奈川県立保健福祉大学学長)
地中海食は生活習慣病の予防食でもあり 食事 運動 適度なアルコール 禁煙 この4つの要因が守られれば死亡リスクは下がる この食事のモデルとなっているのが地中海食
「地中海食スコア」(9点満点)により 今までは栄養素からのアプローチだけだった健康度の評価を初めて試みた(2008年) ただ最近では 高収入・高学歴の人には心疾患のリスク低下が認められたが 低収入・低学歴の人には認められなかった スローダイエット 丁寧な食事づくりの必要性
和食が2013年 無形文化遺産に登録された その特徴を紹介しつつ 昔の日本は低栄養の貧しい食事で日本人は短命だったが 戦後の食の欧米化が急激に進んだ これ程短期間に変化した例は他の民族にはない 戦後アメリカからミルク 小麦粉が輸入され学校給食が始まり 子どもたちの低栄養が改善された
第二次大戦後の子どもたちの栄養失調が 学校給食導入により4か月後と2年後に改善された当時の貴重な写真も見せていただきました
1960~70年代に 食の西洋化によりメタボが増えたが 1995年からようやく脂肪摂取が減り始めた 極端な西洋化を止めたのは伝統的な食文化と栄養教育だった 給食もパンからコメに変わり 食育などの栄養指導がなされた  ← 1995年からようやく脂肪の摂取量が減り始めた
← 1995年からようやく脂肪の摂取量が減り始めた
地中海食と和食との類似点は 穀物が主食 肉は少なめ 魚介が多くバター等が少ない
相違点は オリーブオイルに対して油が少ない エネルギー比率が30-40%に対して20-30%の低脂肪食
また 虚血性心疾患のリスクは日本が最も低く イタリアも低い位置にあります
参考: 地中海式食事法は こちら
和食が無形文化遺産に は こちら
* * *
3.「海洋生態系における恵みとしての魚」 古谷研(創価大学教授)
このお話はショッキングでした 将来漁業資源がどうなってゆくのか 真剣に取り組まないといけないと思いました
鮭は寿司ネタとしては マグロよりも好まれている(JETRO) 日本よりもイタリアの方が鮭の料理法は多い 今は人工ふ化により養殖が増えた
日本では江戸時代に始まる鮭の養殖の歴史について紹介 遡上するまでに稚魚のうちに食べられる等の困難があり オホーツク海 太平洋 ベーリング海 アラスカ湾へと4年前後かけてもとの海に戻ってくる その間にプランクトンをどこでどれだけ摂取するかの研究結果(ベーリング海が7割) プランクトンに含まれるカロチノイドが鮭の身の赤い色となる 漁獲高の30倍の価格にあたる餌を海から摂取するシャドーコストについて説明 養殖ではオキアミが原料
温暖化によりRCP8.5(代表的濃度経路)のシナリオ 今世紀末までには鮭の生息は困難となる可能性について示唆 2100年にはプランクトンが夏にはかなり減る 近年は養殖が増加
食物連鎖 プランクトンを小さな魚が食べて それを大きな魚が食べて...このサイクルでどれか一つでもリンクが欠けると食物連鎖はストップしてしまう 海には環境・浄化・精神面等でさまざまな役割・機能がある (ちょうど田んぼが お米の栽培だけでなく保水機能があり 洪水等を防ぐのと似ていますね)  ← 海の生態系のどれか一つでも欠けると食物連鎖はストップする
← 海の生態系のどれか一つでも欠けると食物連鎖はストップする
食卓からのメッセージ 水産物は海の多様性の証であり 人類の生存にとって大切であるからこそ 海の恵みを担保してくれる生物多様性は守らなければならない  ← 温暖化が鮭に与える影響の可能性
← 温暖化が鮭に与える影響の可能性
* * *
4.「麹菌(ニホンコウジカビ)と日本の発酵食品」丸山潤一(東京大学准教授)
こちらはとても興味深い研究結果を示していただきました 「麹菌は国菌」であり 日本酒 醤油 味噌 酢 みりん 甘酒 塩麴等様々なものが作られており 「家畜化された微生物」とのこと
さらに化粧品 生ハム 鹿肉などの醤油作りにも応用されるだろうとのことで 近々東京大学では初の甘酒が「日本の伝統的エネルギードリンク」として発売予定とのこと ← 麹菌(Koji-mold)
← 麹菌(Koji-mold)
麹菌はうまみ(Umami)を作り出します 菌糸を伸ばしてゆく貴重な映像も見せていただきました 様々な種類があり ゲノム配列を解読し 麹菌の祖先も示していただきながら 祖先とは違って毒は作られていないことが判明 また雄雌はないが それに近い接合型の特性が発見され 将来は交配を研究とのこと
お酒の神様 坂口教授が発見したoryzae(麹菌)のcell fusion(細胞融合)の貴重な写真も見せていただきました
また麹菌の内部の構造や 水をかけると頭部から中身が浮き出る発見 ビタミンを作るメカニズムも世界で初めて発見されたそうです
東大の甘酒 楽しみですね!
* * *
実は地中海料理と日本食を 無形文化遺産登録の観点から話すのかと思っていたのですが かなり学術的な発表でビックリしました! 木村モデレーターによる総括のあとで ホワイエでビュッフェが始まりました:  ← 豪華なビュッフェ!!
← 豪華なビュッフェ!! ← Barillaの様々なパスタ♪ お米の形のリゾーニ(risoni)も!
← Barillaの様々なパスタ♪ お米の形のリゾーニ(risoni)も! ← dolceは別腹!?
← dolceは別腹!?
大変ビッグなシンポジウムを開催していただきましたイタリア文化会館様 関係者の皆様に心よりお礼申し上げます 同時通訳もとても素晴らしかったです!
開催のお知らせは こちら
* 写真は 会場に展示されていたFoog Guide Pyramid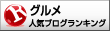 グルメランキング
グルメランキング![]() にほんブログ村
にほんブログ村
























