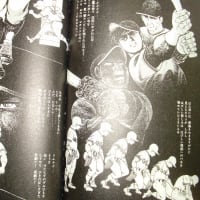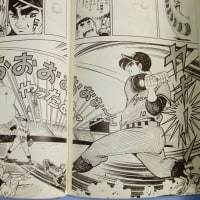今日は「2 悲哀 対 絶対的倦怠感」について話す。
この節は前回言ったことを詳しく掘り下げたような内容となっている。
ポイントは「心理的落ち込み」と「本来の医学的鬱病」の違いを「悲哀」と「絶対的倦怠感」の違いとして把握することにある。
普通、うつと言うと、精神的落ち込みを連想するが、本来の精神医学的な鬱病は単にそのような精神的落ち込みではなく、身体症状を伴った心身的生命エネルギーの減衰である。
そこで、甘く見ていると、自殺に至ることになる。
精神的落ち込みでも自殺するが、心身的生命エネルギーの減衰でも自殺するのである。
とすると、自殺は本来の鬱病の病理の核心にはない付随現象であることが分かる。
自殺は大変な出来事なので、ついそれにばかり着目して、「鬱病になると自殺の率が健常者の24倍になる」という俗説を鵜呑みにすることになる。
実はこの説に裏がある。
精神的落ち込みと医学的鬱病を一緒くたにして、自殺した人は何らかのうつ状態にあった、というバイアスをそのまま通してしまう、素人の悪癖である。
鬱病の病理の本体は自殺に導くような暗い気分、精神的落ち込みではなく、脳の機能障害を基にした心身的生命エネルギーの減衰なのである。
この心身的生命エネルギーの減衰をこの節では「絶対的倦怠感」と表現しているのである。
それに対して、落ち込みの方は「悲哀」と表現している。
この絶対的倦怠感と悲哀を対比して、本来の「鬱病」とにせの「うつ」、いわゆる「落ち込み」を区別しなければならない。
そうだにゃ。全くをもってそうだにゃ。

僕もそう思うにゃ。