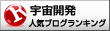書名:宇宙はなぜこのような形なのか
著者:NHK「コズミック フロント」制作班
監修:渡部潤一(国立天文台副台長)
発行:KADOKAWA(角川EPUB選書)
目次:Chapter1 物理学 Physics
宇宙はどのように誕生したのか
ダークマターの謎に挑む
最初の星を探せ
Chapter2 天文学 Astronomy
太陽系の起源を探る
パルサーの発見
ブラックホールは実在した
銀河系の構造
不思議な天体 マゼラン雲
Chapter3 生物学 Biology
土星の衛星 エンケラドス
火星の生命探査
太陽系の外で生命を探す
宇宙に知的生命体はいるか
Chapter4 工学 Engineering
スペースシャトルが切り開いた宇宙
国際宇宙ステーションへの道
月面探査競争
NHK-BSプレミアムで毎週木曜日の午後10時からの宇宙テレビ番組「コズミック フロント」をご覧になったことはあるだろうか。既にご覧になった方は、この番組が書籍になったと考えれば、同書「宇宙はなぜこのような形なのか」(NHK「コズミック フロント」制作班著/渡部潤一<国立天文台副台長>監修/KADOKAWA<角川EPUB選書)>)の内容は、自ずと想像がつくと思う。宇宙テレビ番組「コズミック フロント」は、宇宙に対する最新知識を画像を通して、多くの人が理解するのに打って付けの番組である。特別に宇宙の知識がなくても容易に理解できるように工夫されているので、子供から大人まで誰でも知らず知らずのうちに宇宙の基礎知識が身に付けることができる、貴重なテレビ番組だ。最近放映されたタイトルを挙げてみると、「未踏の宇宙を切りひらけ! NASAジェット推進研究所」 「宇宙でイチバン! 驚異の天体 最も熱く速い星」「宇宙飛行士列伝 奇跡の生還スペシャル~ロシア編~」 「ファーストコンタクト」 「宇宙でイチバン! 宇宙一明るく輝く星」 「バーチャル宇宙ツアー 異形の惑星」 「大逆転! イプシロンロケットの挑戦」 などなど、実に興味深い内容で埋められていることが分かる。例えば「バーチャル宇宙ツアー 異形の惑星」では、最近発見されつつある太陽系外惑星が目の前に現れるのであるから、映像からの情報ほど強いものはない。
しかし、一方では、テレビ映像は、論理立てて知識を吸収しようとすると、自ずと限界があることも事実である。一度知識を整理し直して、一貫性のある知識を手に入れるためには、書籍が一番いい。それを実現したのが同書なのである。通常、宇宙に関する書籍は、専門の天文学者が執筆するケースがほとんどであるが、この場合、知識の正確性では最上なデータが提供されるが、素朴な何故といったような発想には、どうも欠けるきらいがある。この点、同書の著者は、NHK「コズミック フロント」制作班なので、読者の立場に限りなく近い人たちなので、素人にも分かりやすく、最新の宇宙の知識が平易に紹介されているので、宇宙の入門者には打って付けの書籍といえよう。しかも、第一線の研究者である国立天文台副台長の渡部潤一氏が監修者となっているため、内容の正確性も保証されていることもうれしい。その渡部氏は、同書の「はじめに」の中で、「そんな番組から出版物が生まれたなら。誰しもが、そう思うだろう。これだけ、宇宙に関して広く、深く、そして最新の知見を集積した日本放送史上まれに見る金字塔たる科学番組を、活字にしない手はあるまい。・・・本書は、最新の宇宙研究の現場をみなさんにビビッドに提示しつつ、個々の専門分野をフロンティアまで追求した深さ、そして分野全体を俯瞰する広さを併せ持つ、極めてまれな宇宙に関する書籍となっている」と書いている。
同書の全体は、物理学、天文学、生物学、工学の大きく4つに分けられている。「Chapter1 物理学」では、宇宙の誕生から最初の星の誕生であるファーストスター、それに現在の宇宙が形成されるまでを辿る。最近、佐藤勝彦博士らが提唱した、ビックバン以前の宇宙形成の理論であるインフレーション理論が世界の注目を集めているが、これらの最新知識をひとまず得ておきたいという読者にとっては便利である。さらに、かなり知られてきたダークマターについても、やさしく解説されているので、頭に入りやすい。「Chapter2 天文学」では、誰でも知っている小惑星探査機「はやぶさ」の話から始まる。目標は、地球から約3億キロメートルも離れた小惑星イトカワだ。もう知らない人がいないくらいの話ではあるのだが、その意義はと問われて正確に答えられる人は、果たしてどのくらいいるのか。そんな時に同書は威力を発揮する。専門家ではなくとも「はやぶさ」の偉業が良く理解できる。今年中にも「はやぶさ2」は打ち上げられることになっている現在、同書により、「はやぶさ」の果たした成果を整理しておくことは、今後の宇宙探査を知るうえで欠かせない。このほか、我々の銀河系はどのような構造となっているかなどは、最近になり正確に把握できたことも多く、最新知識を整理するには、同書は打って付けと言えよう。
「Chapter3 生物学」は、ある意味では、一番興味がわくところである。火星に生物の痕跡が見つかったといったニュースが飛び交うが、未だはっきりとした証拠はない。さらに、果たして地球以外に知的生命体は存在するのかといった素朴な疑問にもこの章では答えてくれる。それらの中の一番のハイライトは、太陽系以外の惑星が、最近になり続々と発見始めたことだ。つまり、第二の地球探しに世界の関心が集まっている。これらの中には、生命体はおろか、知的生命体がいるかもしれないのだ。現在、我々は、そんな人類史上まれに見る大発見前夜にいるのかもしれない。この章では、そんな知的好奇心を満たしてくれる内容となっている。そして、最後の章である「Chapter4 工学」を迎える。ここでは国際宇宙ステーション(ISS)までの道のりが紹介される。時々、「『ISS』は新しい成果に乏しい」といった批判を言う人がいるが、それは間違えだ。人類は今、“宇宙大航海”時代の入り口に入ったところで、長期間の宇宙滞在自体が、次のステップの足掛かりになるのである。そして、今、火星にばかり人々の関心が集まりがちだが、水面下では月面探査競争も激化していることを、同書の最後で触れている。日本の宇宙政策について考えさせられる個所だ。以上、同書は、宇宙の入門書として、さらには、入門は卒業した人たちの知識の再整理には、最適な宇宙書と言えるだろう。豊富なカラー写真は眺めているだけでわくわくしてくる。(勝 未来)