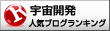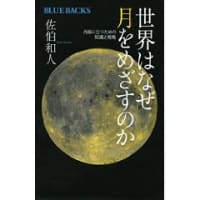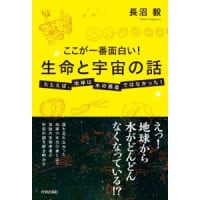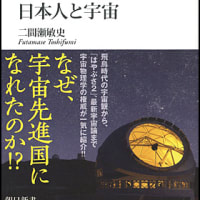書名:世界はなぜ月をめざすのか~月面に立つための知識と戦略~
著者:佐伯和人
発行:講談社(ブルーバックス)
目次 : 序 章 月探査のブーム、ふたたび到来!
第1章 人類の次のフロンティアは月である
第2章 今夜の月が違って見えるはなし
第3章 月がわかる「8つの地形」を見にいこう
第4章 これだけは知っておきたい「月科学の基礎知識」
第5章 「かぐや」があげた画期的な成果
第6章 月の「資源」をどう利用するか
第7章 「月以前」「月以後」のフロンティア
第8章 今後の月科学の大発見を予想する
第9章 宇宙開発における日本の役割とは
終 章 月と地球と人類の未来
日本人にとって月は、太古の昔から和歌などに歌われるなどして、親しみのある天体である。しかし、その誕生からして謎に満ちている。巨大隕石が地球に衝突して、その勢いで岩石が飛び散り、長い時間をかけて現在の形になったというのが一番の有力説だが、まだ確定したわけではない。そもそも、月が無かったなら、地球の姿勢は不安定となり、高温、低温の差が激しく、生物が誕生できたかどうかも怪しくなる。言ってみれば月は、我々人類にとってはなくてはならない貴重な存在なのである。そこで、これまで各国ではロケットを打ち上げ、月探査を行ってきた。それらは、ルナ (旧ソ連)に始まり、アポロ (米国)、かぐや (日本)、嫦娥1号 (中国)、チャンドラヤーン1 (インド)など、数々の実績を挙げてきた。そして、現在行われている月探査は、米国のルナー・リコネサンス・オービター/エルクロスと中国の嫦娥3号である。「世界はなぜ月をめざすのか~月面に立つための知識と戦略~」(佐伯和人著/講談社)は、過去、現在、そして未来にわたって人類と月とのかかわりを、誰でも分かるように解説した書籍である。著者の佐伯和人氏は、専門が惑星地質学・鉱物学で、現在大阪大学の准教授を務め、JAXA月探査機「かぐや」プロジェクトの地形地質カメラグループ共同研究員、次期月探査機「SELENE2」計画着陸地点検討会主席を務めるなど、月探査を語るには最適な立場にある人である。
第1章から第4章までは、月科学の基礎知識を誰でも理解できるように平易に解説されているので、「月とはそもそも何者だ」と考えている読者にとっては、非常に助かる内容である。例えば「月では太陽光線に照らされた昼の側は120℃、太陽光線が当たらない夜の側はマイナス170℃いかという大変な温度差がある。昼の側でも日なたと、岩陰などの日陰は、昼夜の差ほどではないにしても、200℃前後も温度差がある」そうであり、人間が生存するには過酷な環境であることが分かる。月の表面は、レゴリスと呼ばれる細かい砂で覆われている。このレゴリスは、月の石が粉々にくだかれたもので、平均的な粒の直径が100μm弱。数μmしかないような小さな隕石さえ、大気に減速されることなく、最大秒速数十㎞といった高速で月表面の岩石に衝突する。そのような衝突が月の誕生から45億年間続いてきたために、月の表面の岩石は粉々の砕かれのだという。月には川が流れてはいない。ところが川が流れていたような峡谷が月には存在している。これは何故か。このような地形は、水ではなく、マグマによってできたと考えられているそうである。月の海を形成したマグマは、ハワイの火山のマグマよりもサラサラと流動的だと考えられている。そのような、サラサラしたマグマが大量に吹き出すと、まるで水流のように地面を削るという。
第5章では、日本の月探査機「かぐや」があげた画期的成果について詳細な解説が行われている。高度100㎞で、「かぐや」は、1年半以上にわたって、月の極を通る軌道を周回・観測し、2009年6月11日に月の表側に制御落下された。「かぐや」に搭載された多数の観測機器は、それぞれ世界の最先端となるデータを出しており、現在でも解析が続けられているという。日本の宇宙探査機では、「はやぶさ」、それに続き昨年末打ち上げられた「はやぶさ2」が圧倒的に知名度が高いが、月探査機「かぐや」は、最先端の月のデータを地球に送り、そのデータは、現在解析され、月の謎の解明に大きく貢献していおり、その重要度は「はやぶさ」に劣るものではない。特に注目されるのは、「かぐや」が世界で初めて見つけた月面上の縦孔構造。これは月面に空いた、直径50mを超える大孔で、深さも数十mあるという。春山純一博士のグループが、「かぐや」の地形カメラの映像をくまなく探して、3か所の縦孔を見つけたというのだ。月面上の縦孔は、人類が月面に降り立って活動をする際に、重要な役割を果たす。特に月面に降り注ぐ宇宙線の脅威から人体を守るには、縦孔に入ることが最も有効だ。もし、隠れるものがない場合は、月面上に建造物建て、宇宙線から身を守らなければならない。しかし、最初に月面に降り立って、すぐに月面に頑強な建造物を構築すことは非常に困難だ。その点、縦孔があれば、月での活動をスムーズに行うことができる。
同書が、通常の月に関する書籍と異なるのは、月科学の解明の先をさらに一歩進めて、月の「資源」をどう利用するかに関して言及していることであろう。一般に月資源を利用することは、月から鉱物を地球まで運ぶというイメージを持ちやすいが、著者は、それはコストの点からも現実的でなく、月での資源活用を考えるべきだとする。現在、米国が進めている火星に人類を送り込む計画でも、月に一旦降り立ってから月を出発し、彗星に降り立ち、そして彗星から火星を目指す案が検討されていると聞く。火星ばかりでなく、今後、人類が宇宙探査や宇宙開発に挑む場合、月を中継点とすることは、ほぼ間違いないことだろう。そのために月の資源を使ってロケットの燃料をつくり出すことを考えることが重要だとする。言われてみれば確かにそうであろう。そう考えると、各国が月探査を急ぐ理由も分かってくる。今後打ち上げが予定されている月探査機は、ムーンライズ (米国)、嫦娥4号・5号 (中国)、ルナ・グローブ計画 (ロシア)、セレーネ2 (日本)、チャンドラヤーン2(インド)などであるが、筆者は日本の月探査計画を今後急速に強めなければ他国に後れをとると、と次のように警鐘を鳴らす。「月着陸機の周辺を実効支配したからといって、たいした問題でないとおもわれるかもしれません。しかし、まったく逆で、これは大問題です。近年の月探査によって、月の開発すべき『良い場所』が次々と判明していますが、その場所はきわめて限られた面積しかないことも明らかになってきています」。つまり、月開発に最適な場所は限られており、早い者勝ちになるということだ。そう考えると、同書は真っ先に宇宙探査の予算を握っている日本の政治家に読んでもらわねばならない書籍なのかもしれない。(勝 未来)