小さなことだが、最近、ダイヤモンド・オンラインに連載されている更科功さんの漫画コラムを読んで、ダーウィンについて、私自身、ちょっと誤解していたところを正す発見があった。ダーウィンは「進化」について必ずしも「進歩」的な意味あいを持っておらず、従いevolutionという言葉を使っておらず、特定の方向性がない偶然の「変異」による機械論的なものとして、「変更を伴う由来」(Descent with modification)と呼んでいたらしい(Wikipediaによる)。今さらではあるが。
Wikipediaを読み直して総括すると・・・すべての生物は「変異」を持ち、「変異」のうちの一部は親から子へ伝えられ、その「変異」の中には生存と繁殖に有利さをもたらす物があって、限られた資源を生物個体同士が争い、「存在し続けるための努力」(struggle for existence、現在では「生存競争」と訳される)を繰り返すことによって起こる「自然選択」(natural selection)によって、生物の「進化」が引き起こされる、とダーウィンは考えたようだ。ここで「変異」はランダムなもの、とは、「変異」それ自体に進化の方向性を決める力が内在しないと言う意味らしい。後に「自然選択」をわかりやすく説明する語として、社会進化論のハーバート・スペンサーが使っていた「適者生存」を使うようになったということだ(ダーウィンより先にスペンサーが使っていたとは。但し「生存競争」や「適者生存」は誤解を招きやすいために近年では用いられない)。
一方のスペンサーは、「自然選択」説を社会に適用して、最適者生存によって社会は理想的な状態へと発達していくという社会進化論を唱えた。生物は下等から高等へと進歩していくというラマルクを高く評価していたようで、進化に目的や方向性はないと考えるダーウィンとは異なるようだ。
ビジネスの世界で、ダーウィンの言葉としてよく引用されるのが、大きいものや強いものが勝つのではない、変化によく対応するものが生き残るのだ、というものだ。どうやら「弱肉強食」は、ダーウィン(生物学的)やスペンサー(社会学的)の進化論そのものにはなかった考え方で、当時の帝国主義を正当化するために、キリスト教的な優越意識と結びついて特異な発展を遂げた、時代特有の考え方だったのだろう。
ダーウィンがらみで、ついでに発見して興味深かったのが、マルサスの「人口論」の影響だ。ダーウィンの自伝には、以下のような記述があるらしい(Wikipediaから引用);
・・・1838年11月、つまり私が体系的に研究を始めた15ヶ月後に、私はたまたま人口に関するマルサスを気晴らしに読んでいた。動植物の長く継続的な観察から至る所で続く生存のための努力を理解できた。そしてその状況下では好ましい変異は保存され、好ましからぬものは破壊される傾向があることがすぐに私の心に浮かんだ。この結果、新しい種が形成されるだろう。ここで、そして私は機能する理論をついに得た・・・
再びWikipediaをそのまま引用すると、
・・・マルサスは人間の人口は抑制されなければ等比数列的に増加し、すぐに食糧供給を越え破局が起きると主張した。ダーウィンはすぐにこれをド・カンドルの植物の「種の交戦」や野生生物の間の生存のための努力に応用して見直し、種の数がどのようにして大まかには安定するかを説明する準備ができていた・・・
スペンサーも、マルサスの影響を受けたが、その悲観論は無視し、人口の圧力による生存競争は社会全体に利益をもたらすと考えた。何故なら、技術のあるもの、知性や自制心に優れたもの、新しい技術を社会に応用するものが生き残り、それによって社会の進化が達成されるからである。このようにして、彼は「適者生存」を社会科学で利用される専門用語に仕立て上げたとされる。
19世紀後半の帝国主義あるいは植民地主義は、ダーウィンやスペンサーの「適者生存」「優勝劣敗」といった発想を、自己正当化する「強者の論理」として利用した。産業革命によって飛躍的に生産力が増大し、人口が増加し、その人口増加を支えるために資源を求めて更に植民地を拡大する・・・大雑把な話だが、時代がマルサスやダーウィンやスペンサーを生み、彼らの論が次の時代を正当化する根拠を与えるという連鎖の妙(と言っても現代的な目線では手放しで喜べるものではないが)を感じる。
因みに、ダーウィンを育てた母国イギリスよりも先に、アメリカはダーウィンを社会的に受容し(『種の起源』出版の10年後、ケンブリッジ大学が彼に名誉学位を与える10年前の1869年に、アメリカ哲学会は彼を名誉会員に推挙した)、スペンサーは、母国イギリスよりアメリカで遥かに有名だそうである。その後のアメリカの帝国的な発展を見るにつけ、なんだか象徴的なエピソードだと言えないだろうか。
なかなか本題に踏み込めないまま、ちょっと長くなったので、続きは次回・・・
Wikipediaを読み直して総括すると・・・すべての生物は「変異」を持ち、「変異」のうちの一部は親から子へ伝えられ、その「変異」の中には生存と繁殖に有利さをもたらす物があって、限られた資源を生物個体同士が争い、「存在し続けるための努力」(struggle for existence、現在では「生存競争」と訳される)を繰り返すことによって起こる「自然選択」(natural selection)によって、生物の「進化」が引き起こされる、とダーウィンは考えたようだ。ここで「変異」はランダムなもの、とは、「変異」それ自体に進化の方向性を決める力が内在しないと言う意味らしい。後に「自然選択」をわかりやすく説明する語として、社会進化論のハーバート・スペンサーが使っていた「適者生存」を使うようになったということだ(ダーウィンより先にスペンサーが使っていたとは。但し「生存競争」や「適者生存」は誤解を招きやすいために近年では用いられない)。
一方のスペンサーは、「自然選択」説を社会に適用して、最適者生存によって社会は理想的な状態へと発達していくという社会進化論を唱えた。生物は下等から高等へと進歩していくというラマルクを高く評価していたようで、進化に目的や方向性はないと考えるダーウィンとは異なるようだ。
ビジネスの世界で、ダーウィンの言葉としてよく引用されるのが、大きいものや強いものが勝つのではない、変化によく対応するものが生き残るのだ、というものだ。どうやら「弱肉強食」は、ダーウィン(生物学的)やスペンサー(社会学的)の進化論そのものにはなかった考え方で、当時の帝国主義を正当化するために、キリスト教的な優越意識と結びついて特異な発展を遂げた、時代特有の考え方だったのだろう。
ダーウィンがらみで、ついでに発見して興味深かったのが、マルサスの「人口論」の影響だ。ダーウィンの自伝には、以下のような記述があるらしい(Wikipediaから引用);
・・・1838年11月、つまり私が体系的に研究を始めた15ヶ月後に、私はたまたま人口に関するマルサスを気晴らしに読んでいた。動植物の長く継続的な観察から至る所で続く生存のための努力を理解できた。そしてその状況下では好ましい変異は保存され、好ましからぬものは破壊される傾向があることがすぐに私の心に浮かんだ。この結果、新しい種が形成されるだろう。ここで、そして私は機能する理論をついに得た・・・
再びWikipediaをそのまま引用すると、
・・・マルサスは人間の人口は抑制されなければ等比数列的に増加し、すぐに食糧供給を越え破局が起きると主張した。ダーウィンはすぐにこれをド・カンドルの植物の「種の交戦」や野生生物の間の生存のための努力に応用して見直し、種の数がどのようにして大まかには安定するかを説明する準備ができていた・・・
スペンサーも、マルサスの影響を受けたが、その悲観論は無視し、人口の圧力による生存競争は社会全体に利益をもたらすと考えた。何故なら、技術のあるもの、知性や自制心に優れたもの、新しい技術を社会に応用するものが生き残り、それによって社会の進化が達成されるからである。このようにして、彼は「適者生存」を社会科学で利用される専門用語に仕立て上げたとされる。
19世紀後半の帝国主義あるいは植民地主義は、ダーウィンやスペンサーの「適者生存」「優勝劣敗」といった発想を、自己正当化する「強者の論理」として利用した。産業革命によって飛躍的に生産力が増大し、人口が増加し、その人口増加を支えるために資源を求めて更に植民地を拡大する・・・大雑把な話だが、時代がマルサスやダーウィンやスペンサーを生み、彼らの論が次の時代を正当化する根拠を与えるという連鎖の妙(と言っても現代的な目線では手放しで喜べるものではないが)を感じる。
因みに、ダーウィンを育てた母国イギリスよりも先に、アメリカはダーウィンを社会的に受容し(『種の起源』出版の10年後、ケンブリッジ大学が彼に名誉学位を与える10年前の1869年に、アメリカ哲学会は彼を名誉会員に推挙した)、スペンサーは、母国イギリスよりアメリカで遥かに有名だそうである。その後のアメリカの帝国的な発展を見るにつけ、なんだか象徴的なエピソードだと言えないだろうか。
なかなか本題に踏み込めないまま、ちょっと長くなったので、続きは次回・・・














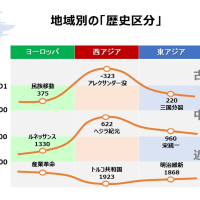




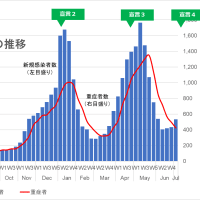






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます