タイトルに惹かれて、「東洋の至宝を世界に売った美術商 -ハウス・オブ・ヤマナカ-」(朽木ゆり子著、新潮社)を読みました。明治から大正・昭和初期に、日本をはじめ中国・韓国などの美術品を扱う東洋美術商として世界的に有名だった山中商会(ヤマナカ&カンパニー)の、知られざる海外進出から、太平洋戦争勃発とともに敵国資産として接収され解体されるに至るまでを描いた、一企業の盛衰の物語です。子供の頃から図画工作や美術が好きで(好きこそものの上手で、主要五教科より余程成績が良かったものです(苦笑))、「なんでも鑑定団」は始まった当初から欠かさず楽しみに見るほどでしたので、どんな歴史の秘めたるロマンがあるのだろうかと興味津々で読み進めました。
しかし案に相違して、エンターテイメント性には乏しい本です。そもそも美術の世界は、芸術家は言うまでもありませんが、せいぜいコレクターや美術史学者までが登場人物で、そこでは美術商は縁の下の力持ちでしかなく、表に出ることは滅多にありません。また、古美術商の商習慣から売買記録は残されていないことが多く、取引実態がよく分からないという事情もあります。そのため、海外渡航が不自由な当時にあって世界を股にかけて活躍した、国際ビジネスマンのはしりのような山中定次郎をはじめとする豪快な人物にスポットライトが当てられ、武勇伝が語られるのがせいぜいでした。著者は、アメリカの美術館やコレクターなどの得意客の手元に残されていた手紙や請求書や領収書、さらにはアメリカ国立公文書館に保存されていた、山中商会がアメリカ政府に接収されたときに押収された大量の資料を丹念に読み解きながら、当時の時代背景ととともに古美術商というひとつの業界史を浮かび上がらせます。いわば学術書の趣で、退屈な場面が多いのは事実です。
そうは言っても、いろいろ発見がありました。
私がアメリカに滞在していたときに、マサチューセッツ州セーラム(魔女裁判で有名)にあるピーボディー・エセックス美術館を訪れ、膨大なモース・コレクションを目にして驚かされたことは忘れられません。エドワード・S・モースは、明治の初めにお雇い外国人(動物学者)として来日し、大森の貝塚を発見したことで有名ですが、「多くの民芸品や陶磁器を収集したほか、多数のスケッチを書き残し」(Wikipedia)、今でこそJALが就航していますが私が駐在していた頃は直行便が飛ばないボストンから更に車を一時間以上走らせなければならない片田舎に、それこそ当時の日本の街角の看板から、たとえば豪華な雛祭りセットなどの民具まで、今はなき日本らしい日本が切り取られ、いわば冷凍保存されていたのですから。ことほどさように、幕末から明治の混乱期に、まだ貧しかった日本の素晴らしい美術工芸品を発見した裕福な欧米人が、カネに飽かせて買い漁って、場合によっては略奪して、持ち帰ったものが、今我々が目にする欧米の有名どころの日本美術コレクションに繋がるものと、一種の植民地史観で当然のように思い込んでいました。
しかし、日本でも有名なフェノロサや岡倉天心や林忠正のほか、フリーア、ハヴマイヤー、ロックフェラーなどの海外のコレクターと良好な関係を構築し、東洋美術を仲介した日本人商人の存在があったとは意外でした。彼らの得意客の中には、メトロポリタン美術館、ボストン美術館、フリーア美術館、シアトル美術館、シカゴ美術館などのアメリカを中心とする著名コレクションを有する美術館のほか、大英博物館まで手広く、また英国王室やスウェーデン王室に連なる人も含まれたそうです。お蔭で、浮世絵のように、当時の輸出品である伊万里陶磁器の包み紙にして捨てられるような庶民のための漫画が見直され芸術品の域に高められるなど、日本の至宝が散逸から逃れ、ある程度まとまった形で、しかも極めて良い保存状態で残されることにもなりました(参考)。
こうした美術工芸品は、とりわけ時代背景との関連が興味深い。
先ずは、さして輸出できる工業製品がない明治初期の日本にあって、生糸や茶のほかに美術工芸品が、輸出に向いているものとして奨励されたというのは、なんとなく理解されるところです。1862年のロンドン万博で初代駐日英国公使ラザフォード・オルコックのコレクションが展示され評判を呼ぶと、流れを探るため、ウィーン万博(1873年)やフィラデルフィア万博(1876)では日本政府自らが出品し、日本ブームを巻き起こします。そうした波を捉えたのが山中商会で、波に乗るだけでなく、折しも経済力をつけ贅沢品を求め始めたアメリカの好奇心を満足させるべく、市場を開拓して行ったと言えるかも知れません。最初は異国趣味だったことでしょう。しかしほどなく日本の美意識の高さと確かな技術に驚嘆し惹かれて行ったであろうことは間違いありません。
ところが明治も後半になると、質の高い日本の美術工芸品が国外に出回ることは稀になります。日本が経済力をつけるにつれ、社寺や旧家が経済的に困窮して資産処分するような事態もなくなり、逆に日本人自身が茶道具を中心とした美術品蒐集に目覚め、価格が高騰し始めたという事情もあります。その後も、関東大震災とそれに続く昭和金融恐慌で美術品を手放す例がありましたが、1900年代後半以降、とりわけ清朝崩壊に伴う政情不安で中国の美術品が大量に出回るようになると、東洋美術の中に占める日本美術と中国美術の比重は逆転します。
「東洋の至宝を世界に売った美術商」というタイトルからは、一見、こうした美術商を糾弾する思いが込められているかのように思われますが、著者は、日陰者の存在の美術商に同情的であり、それまで余り知られていなかった東洋美術の普及を陰で支え、いわば戦前のアメリカとの間で民間の文化外交を担ったといったような積極的な価値を認めています。伝統的な芸術の世界は経済的な擁護者(パトロン)の存在が重要であり、古美術の世界も、経済的な強者(強国)に買い占められる運命にあり、美術商の商売は、結果としてそんな国家間の関係に翻弄される運命を辿ります。実証的に山中商会のビジネスを追いかける著者の目は、飽くまでも暖かい。美術史の裏面を知ることが出来る好著と思います。
(参考)「写楽」 http://blog.goo.ne.jp/mitakawind/d/20110506
しかし案に相違して、エンターテイメント性には乏しい本です。そもそも美術の世界は、芸術家は言うまでもありませんが、せいぜいコレクターや美術史学者までが登場人物で、そこでは美術商は縁の下の力持ちでしかなく、表に出ることは滅多にありません。また、古美術商の商習慣から売買記録は残されていないことが多く、取引実態がよく分からないという事情もあります。そのため、海外渡航が不自由な当時にあって世界を股にかけて活躍した、国際ビジネスマンのはしりのような山中定次郎をはじめとする豪快な人物にスポットライトが当てられ、武勇伝が語られるのがせいぜいでした。著者は、アメリカの美術館やコレクターなどの得意客の手元に残されていた手紙や請求書や領収書、さらにはアメリカ国立公文書館に保存されていた、山中商会がアメリカ政府に接収されたときに押収された大量の資料を丹念に読み解きながら、当時の時代背景ととともに古美術商というひとつの業界史を浮かび上がらせます。いわば学術書の趣で、退屈な場面が多いのは事実です。
そうは言っても、いろいろ発見がありました。
私がアメリカに滞在していたときに、マサチューセッツ州セーラム(魔女裁判で有名)にあるピーボディー・エセックス美術館を訪れ、膨大なモース・コレクションを目にして驚かされたことは忘れられません。エドワード・S・モースは、明治の初めにお雇い外国人(動物学者)として来日し、大森の貝塚を発見したことで有名ですが、「多くの民芸品や陶磁器を収集したほか、多数のスケッチを書き残し」(Wikipedia)、今でこそJALが就航していますが私が駐在していた頃は直行便が飛ばないボストンから更に車を一時間以上走らせなければならない片田舎に、それこそ当時の日本の街角の看板から、たとえば豪華な雛祭りセットなどの民具まで、今はなき日本らしい日本が切り取られ、いわば冷凍保存されていたのですから。ことほどさように、幕末から明治の混乱期に、まだ貧しかった日本の素晴らしい美術工芸品を発見した裕福な欧米人が、カネに飽かせて買い漁って、場合によっては略奪して、持ち帰ったものが、今我々が目にする欧米の有名どころの日本美術コレクションに繋がるものと、一種の植民地史観で当然のように思い込んでいました。
しかし、日本でも有名なフェノロサや岡倉天心や林忠正のほか、フリーア、ハヴマイヤー、ロックフェラーなどの海外のコレクターと良好な関係を構築し、東洋美術を仲介した日本人商人の存在があったとは意外でした。彼らの得意客の中には、メトロポリタン美術館、ボストン美術館、フリーア美術館、シアトル美術館、シカゴ美術館などのアメリカを中心とする著名コレクションを有する美術館のほか、大英博物館まで手広く、また英国王室やスウェーデン王室に連なる人も含まれたそうです。お蔭で、浮世絵のように、当時の輸出品である伊万里陶磁器の包み紙にして捨てられるような庶民のための漫画が見直され芸術品の域に高められるなど、日本の至宝が散逸から逃れ、ある程度まとまった形で、しかも極めて良い保存状態で残されることにもなりました(参考)。
こうした美術工芸品は、とりわけ時代背景との関連が興味深い。
先ずは、さして輸出できる工業製品がない明治初期の日本にあって、生糸や茶のほかに美術工芸品が、輸出に向いているものとして奨励されたというのは、なんとなく理解されるところです。1862年のロンドン万博で初代駐日英国公使ラザフォード・オルコックのコレクションが展示され評判を呼ぶと、流れを探るため、ウィーン万博(1873年)やフィラデルフィア万博(1876)では日本政府自らが出品し、日本ブームを巻き起こします。そうした波を捉えたのが山中商会で、波に乗るだけでなく、折しも経済力をつけ贅沢品を求め始めたアメリカの好奇心を満足させるべく、市場を開拓して行ったと言えるかも知れません。最初は異国趣味だったことでしょう。しかしほどなく日本の美意識の高さと確かな技術に驚嘆し惹かれて行ったであろうことは間違いありません。
ところが明治も後半になると、質の高い日本の美術工芸品が国外に出回ることは稀になります。日本が経済力をつけるにつれ、社寺や旧家が経済的に困窮して資産処分するような事態もなくなり、逆に日本人自身が茶道具を中心とした美術品蒐集に目覚め、価格が高騰し始めたという事情もあります。その後も、関東大震災とそれに続く昭和金融恐慌で美術品を手放す例がありましたが、1900年代後半以降、とりわけ清朝崩壊に伴う政情不安で中国の美術品が大量に出回るようになると、東洋美術の中に占める日本美術と中国美術の比重は逆転します。
「東洋の至宝を世界に売った美術商」というタイトルからは、一見、こうした美術商を糾弾する思いが込められているかのように思われますが、著者は、日陰者の存在の美術商に同情的であり、それまで余り知られていなかった東洋美術の普及を陰で支え、いわば戦前のアメリカとの間で民間の文化外交を担ったといったような積極的な価値を認めています。伝統的な芸術の世界は経済的な擁護者(パトロン)の存在が重要であり、古美術の世界も、経済的な強者(強国)に買い占められる運命にあり、美術商の商売は、結果としてそんな国家間の関係に翻弄される運命を辿ります。実証的に山中商会のビジネスを追いかける著者の目は、飽くまでも暖かい。美術史の裏面を知ることが出来る好著と思います。
(参考)「写楽」 http://blog.goo.ne.jp/mitakawind/d/20110506



















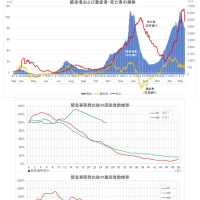






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます