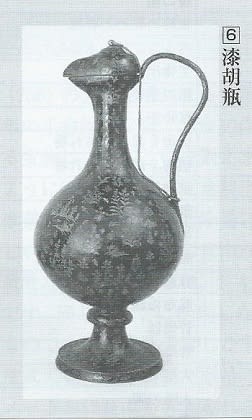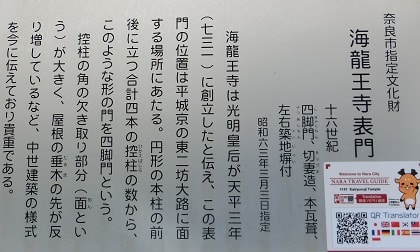奈良の世界遺産・春日大社
春日大社では年間に2200回以上の祭りが行われていますが、中でも至高最高の式典が「式年造替」です。
「式年造替」は「遷宮」のように神さまがお引越しされるのではなく、本殿の位置は変えずに建て替え、修復を行うもので、創建以来20年に一度行われてきました。
6日夜、春日大社で営まれた「正遷宮」は、暗闇に包まれる境内で、ご神体は、新しくなった本殿へゆっくりと戻されました。7日は「正遷宮」が無事終わったことを祝う神事「奉幣祭」が営まれました。
11月11日~13日、13時頃から本殿特別参拝が行われました。
大勢の方がすでに参拝の為並んでおられます。
若宮社の方から、御間道(おあいみち、御本社と若宮社の間の道)の方へ進みます。


御間道は、 850年以上も神官や崇敬者が往復した道で、本社と若宮の間を百度千度万度と往還する祈祷も盛んでした。
この道沿いには、古い石燈籠が立ち並びます。 康暦2年(1380年)の燈籠を始め室町時代から江戸初期の燈籠が多く、古くから信仰の道であったことを物語っています。
東側は、御蓋山の神聖な森で、道の中ほどに、御蓋山山頂の本宮神社の遥拝所のしるしとして小さな鳥居が立っています。 真昼にも濃い影が落ち、石燈籠と共に森厳な景観を形作っています。

灯籠の奥の森には、殆どが竹柏(なぎ)の木だけという純林が多く見られ、極めて稀であるとして大正12年に天然記念物に指定されました。
竹柏は暖かいところに自生する木ですから、春日大社にあるものは、古くに献木されたものが、 鹿も食べないところから繁茂して樹林を形成したのだと考えられています。
鎌倉時代には、すでに繁茂していたことが記録から類推され、実際樹齢が850年と考えられる木も確認されています。 春日社では古くから榊の代わりに神事に用いられた神聖な木でもあるそうです。
南門をはいり、回廊から本殿へと進みます。




「正面は撮らないでくださーい」と。



本殿背面から



春日大社を後にして近鉄奈良方面へ向かいます。
春日大社では年間に2200回以上の祭りが行われていますが、中でも至高最高の式典が「式年造替」です。
「式年造替」は「遷宮」のように神さまがお引越しされるのではなく、本殿の位置は変えずに建て替え、修復を行うもので、創建以来20年に一度行われてきました。
6日夜、春日大社で営まれた「正遷宮」は、暗闇に包まれる境内で、ご神体は、新しくなった本殿へゆっくりと戻されました。7日は「正遷宮」が無事終わったことを祝う神事「奉幣祭」が営まれました。
11月11日~13日、13時頃から本殿特別参拝が行われました。
一の鳥居



伏鹿手水所(ふせしかのてみずしょ)




伏鹿手水所(ふせしかのてみずしょ)

大勢の方がすでに参拝の為並んでおられます。
若宮社の方へ進み・・・。

若宮社を右に見て・・・。

写真中央あたりに、八ツ房藤
若宮社本殿北側の竹柏(なぎ)に巻きつく藤で、屋根を覆うように花をつけます。八ツ藤とも言われる濃い紫の八重咲きの藤で、花の時期も通常の藤より1週間から10日ほど遅く、例年は5月初旬から半ば頃です。
若宮の大楠

幹周が約11.5mあって、奈良県下で1、2を争う巨樹です。江戸時代の半ばに大雪のため上部が折れたことが知られ、今のような樹形になったと考えられています。かなりの老木でもあり、千歳楠という別名もあるそうです。

若宮社を右に見て・・・。

写真中央あたりに、八ツ房藤
若宮社本殿北側の竹柏(なぎ)に巻きつく藤で、屋根を覆うように花をつけます。八ツ藤とも言われる濃い紫の八重咲きの藤で、花の時期も通常の藤より1週間から10日ほど遅く、例年は5月初旬から半ば頃です。
若宮の大楠

幹周が約11.5mあって、奈良県下で1、2を争う巨樹です。江戸時代の半ばに大雪のため上部が折れたことが知られ、今のような樹形になったと考えられています。かなりの老木でもあり、千歳楠という別名もあるそうです。
若宮社の方から、御間道(おあいみち、御本社と若宮社の間の道)の方へ進みます。


御間道は、 850年以上も神官や崇敬者が往復した道で、本社と若宮の間を百度千度万度と往還する祈祷も盛んでした。
この道沿いには、古い石燈籠が立ち並びます。 康暦2年(1380年)の燈籠を始め室町時代から江戸初期の燈籠が多く、古くから信仰の道であったことを物語っています。
東側は、御蓋山の神聖な森で、道の中ほどに、御蓋山山頂の本宮神社の遥拝所のしるしとして小さな鳥居が立っています。 真昼にも濃い影が落ち、石燈籠と共に森厳な景観を形作っています。

灯籠の奥の森には、殆どが竹柏(なぎ)の木だけという純林が多く見られ、極めて稀であるとして大正12年に天然記念物に指定されました。
竹柏は暖かいところに自生する木ですから、春日大社にあるものは、古くに献木されたものが、 鹿も食べないところから繁茂して樹林を形成したのだと考えられています。
鎌倉時代には、すでに繁茂していたことが記録から類推され、実際樹齢が850年と考えられる木も確認されています。 春日社では古くから榊の代わりに神事に用いられた神聖な木でもあるそうです。
南門をはいり、回廊から本殿へと進みます。




「正面は撮らないでくださーい」と。



本殿背面から



春日大社を後にして近鉄奈良方面へ向かいます。
鹿のいる風景


交差点にも



交差点にも

説明は春日大社ホームページより。