夫が1週間行っていたダーチャから帰って来た。
収穫時なので大根いっぱい、キュウリ、セイヨウカブ、それに何年ぶりかで見るトリトマ、トラノオ。

セイヨウカブ(これは「黄金カブ ゴールド」という品種)は日本のカブとどうちがうのかな?と種を買って、夫に播いて育ててもらったもの。けっこう上手くできたみたい。
ロシアでは、古来カブは第2のパンといわれるくらい日常的な食べ物でした。栽培がかんたん、すぐ収穫できて収穫量も多く、寒さに強く、冷害でも穀物ほど影響を受けない、保存がきくなど、寒いロシアになくてはならない野菜でした。「カブより安い」といったらただ同然のたとえで、農民たちはこれなしには生きてゆけませんでした。
18世紀までカブは今のジャガイモの役割を果たしていたのです。それがジャガイモが一般的になるにしたがって、カブは忘れ去られていったのでした。
カブはめずらしい野菜になってしまって、前にも書きましたが、おばあさんに「大きなかぶ」を毎晩読んでもらっている子供たちがカブを見たこともないということになりました。
でも最近カブは「体にいい」とあちこちで見直されています。日本人と一緒でロシア人も「体にいい(パレーズニー)」ものが大好き。これからカブは復活してゆくと思います。
ロシアのカブ、ごらんになりますか。
Googleの画像一覧 今はいろんなカブがありますね。




明日です!!

開催するかどうかは、八王子いぬ親会のHPで午前8時までにお知らせします。
参加犬プロフィールはHPの一番下にあります。












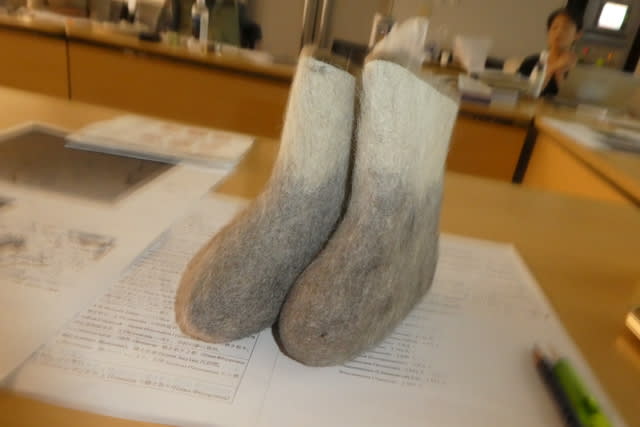


 さらにもう最近では紹介する二人の名前を思い出せないOさんのエピソードではなぐさめられないほどの物忘れぶりなのです。
さらにもう最近では紹介する二人の名前を思い出せないOさんのエピソードではなぐさめられないほどの物忘れぶりなのです。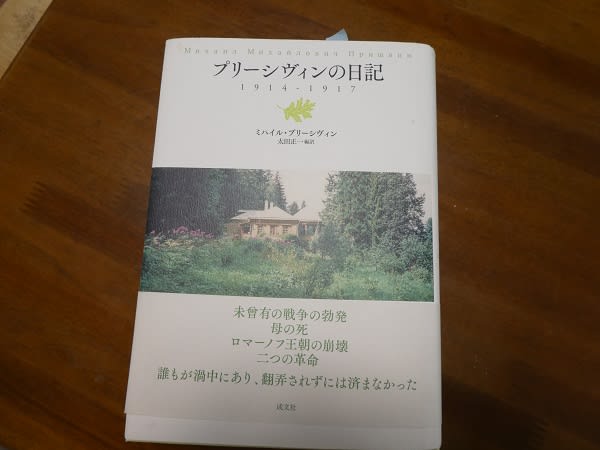


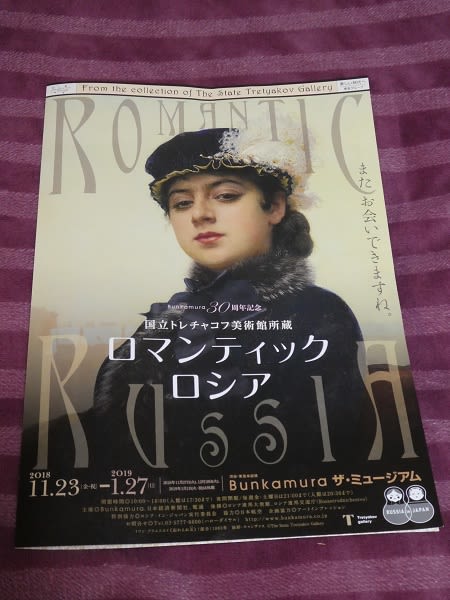









 大丈夫!! ベールイはポルチーニです。
大丈夫!! ベールイはポルチーニです。



