Information
『そこに言葉も浮かんでいた』(新日本出版社)『アゲイン アゲイン』(あかね書房)『わくわくもりのはいくえん はる おともだちできるかな』『みちのく山のゆなな』(国土社)『ファミリーマップ』、エンタメシリーズ『家守神』1~5巻、『おはようの声』幼年童話『ヘビくんブランコくん』『オンチの葉っぱららららら♪』、短編集『友だちの木』・歴史物語『アテルイ 坂上田村麻呂と交えたエミシの勇士』他、好評発売中です。各種ご依頼は、左側のメッセージからお願いいたします。
 木蓮 もう少し。
木蓮 もう少し。 我が家の杏。この写真は数日前。今は満開です。電線があるのと庭が狭いので、二年に一度くらいはかなり枝を伐っています。これ、伐らずにいたら、見事な木になってるだろうな。うちの木だからわかるけど、梅との見分けはぱっとできません。外を歩いていて、あ、杏だと思うことなく、みんな梅と思ってますから・・。枝ぶりが違うんですけどね。
我が家の杏。この写真は数日前。今は満開です。電線があるのと庭が狭いので、二年に一度くらいはかなり枝を伐っています。これ、伐らずにいたら、見事な木になってるだろうな。うちの木だからわかるけど、梅との見分けはぱっとできません。外を歩いていて、あ、杏だと思うことなく、みんな梅と思ってますから・・。枝ぶりが違うんですけどね。
 未来屋書店多賀城店様
未来屋書店多賀城店様 岩手県陸前高田市では、10年前7万本の松の木が流されました。その木で作られた数珠です。
岩手県陸前高田市では、10年前7万本の松の木が流されました。その木で作られた数珠です。 2012年7月撮影の一本松。この後枯れてしまい、今はレプリカです。一本松と書いただけで、陸前高田とわかっていただけるでしょうか。陸前高田とだけ書いて、岩手県とわかっていただけるでしょうか。ふと思い、加筆します。私自身が九州や四国のことを○○県から書いていただかないと、わからないからです。
2012年7月撮影の一本松。この後枯れてしまい、今はレプリカです。一本松と書いただけで、陸前高田とわかっていただけるでしょうか。陸前高田とだけ書いて、岩手県とわかっていただけるでしょうか。ふと思い、加筆します。私自身が九州や四国のことを○○県から書いていただかないと、わからないからです。 同日。陸前高田市にて。
同日。陸前高田市にて。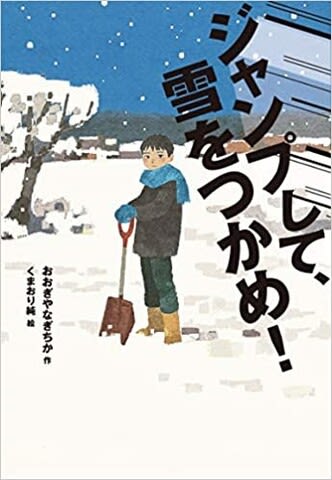

 半月くらい前の虹です。
半月くらい前の虹です。


