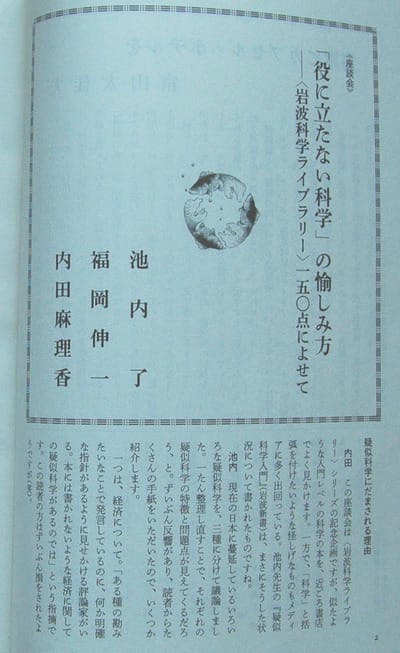11月13日の金曜日は映画館に「沈まぬ太陽」を観に行ったので、文科省関係の事業仕分け作業の様子をニコニコ動画 行政刷新会議 事業仕分けにアップロードされた音声記録でいくつか聴いてみた。
私は行政刷新会議「事業仕分け」なんて鳩山内閣のマッチポンプのようなものと思っているので、予算を削る作業をセレモニー化するだけに終わるのではないかと想像したが、これまでのところ予想通りの展開のようである。私が関心を持った科学技術関連予算は文部科学省の管轄なので、まず文科省の担当者が事業の要点を説明し、引き続いてなぜか財務省主計官が意見を述べてから仕分け人と呼ばれる評価者がいろいろと質問したり議論をするかたちで作業が進む。そして最後に仕分け人が評決内容を評価シートに記入し、取りまとめ役がその結果を集計して評価を定める手順となっている。例年なら概算要求が出てから各省庁担当者と財務省主計官が折衝して削減案が練られていくのだろうが、この事業仕分けでは主計官が黒子役に退き仕分け人が表に出た形になっている。見方によれば仕分け人一同が主計官の仕事を分担したと言える。
マッチポンプという意識がつい頭にあるものだから、説明者と仕分け人のやりとりも聞き流すという感じであったが、噛み合わないやり取りが多すぎたように思った。お互いに話し方が下手なのである。その一つとして「次世代スーパーコンピューティング技術の推進((独)理化学研究所)」を取り上げると、多分説明者の一人だと思うが、仕分け人に何を聞かれても「世界一」、「世界最先端」、「最高性能」を繰り返すだけのように私は感じてしまった。世界一速いスーパーコンピューターがとにかく欲しいと強調すればするほど、子どもが玩具が欲しいと駄々をこねているのと同じように聞こえてくるのである。そして国民に夢を与えるなんて宣う。この説明者は研究者を自称していたようであるが、こういう説明者しかこの場に連れてこられない文科省・理研は相当の世間音痴だなと思った。これまでもおそらく中身が空疎な言葉を並べるたてるだけで大型予算を獲得してきたものだから、そのノリでこの仕分けに臨んだのであろう、とはげすの勘ぐりである。
下手すると予算を取り上げられてしまうかも知れないという事態の認識が説明する側にあったのか無かったのか、もう少し説得力のある説明を練ってくるべきであったのに、説明者は防戦一方であったように感じた。しかも世界一を目指して当初はNEC、日立、富士通とわが国のコンピューター製造大手三社が共同開発することになっていたのに、経営状況の悪化を理由にNECと日立がこの5月に脱落してしまったというのである。その結果、当初のベクトル・スカラー複合型からスカラー単独システムへの基本システムの変換を余儀なくされたので、脱落したNECには損害賠償の請求を準備中という。このような大きな状況の変化、なかんずく基本的枠組みが大きく変更されたのであれば、いったん立ち止まって計画全体を見直すべきではないかと素人(国民)はつい考えてしまう。しかしこれまで設計段階ですでに546億円を投入しており、完成までには更に700億円近くかかるが、いよいよ製造段階の契約に入るのでさしずめ来年度には268億円が必要だと強調するのみである。もう動き出したから止まれないだけでは八ッ場ダムに道路建設と同じである。
なぜ世界最高速のスーパーコンピューターが必要なのかについて、説明者の一人がスーパーコンピューターの能力を最大限引き出すソフトを開発するとして、ライフサイエンスでナノレベルのシミュレーションを挙げていたが、私には違和感があった。普通ならある実験をするためにこのような装置が必要であるからと装置開発を申請するのに、最高速コンピューターが出来たからその能力を最大限発揮するソフトを開発するというのだから、これは本末転倒ではないのかと思った。なにはともあれ世界最高速ありきなのである。
文科省が説明に科学者を連れてきて、これが科学にとって重要なのでこの事業をやりますと説明するのがお決まりの手法である、と仕分け人の一人が説明の矛盾を突いていた。それは大いに結構、このような意見がひいては科学技術研究への予算の出し方の基本理念に今後の民主党の科学技術政策立案の過程でまとまっていって欲しいものである。ところがその先行きが不透明な現状では、行政刷新会議が事業仕分け場に連れてきた科学者が説明者に意見を述べること自体、意識するしないにかかわらず財務省主計官の代弁者というか手先のように見えてきたのが奇妙であった。これでは文科相の連れてきた科学者と行政刷新会議の連れてきた科学者による両省庁の代理戦争ではないか。
科学者仕分け人が主計官の手先と言われたくないのであれば、この仕分け会議において予算の削減に手を貸すのではなく、立ち止まり考えるための時間を与えるべくまずは凍結の意思表示をすべきなのではなかろうか。結果的には、来年度の予算計上の見送りに限りなく近い縮減となった。
科学研究費補助金制度についても同じ思いをしたが、機会があれば述べようと思う。
私は行政刷新会議「事業仕分け」なんて鳩山内閣のマッチポンプのようなものと思っているので、予算を削る作業をセレモニー化するだけに終わるのではないかと想像したが、これまでのところ予想通りの展開のようである。私が関心を持った科学技術関連予算は文部科学省の管轄なので、まず文科省の担当者が事業の要点を説明し、引き続いてなぜか財務省主計官が意見を述べてから仕分け人と呼ばれる評価者がいろいろと質問したり議論をするかたちで作業が進む。そして最後に仕分け人が評決内容を評価シートに記入し、取りまとめ役がその結果を集計して評価を定める手順となっている。例年なら概算要求が出てから各省庁担当者と財務省主計官が折衝して削減案が練られていくのだろうが、この事業仕分けでは主計官が黒子役に退き仕分け人が表に出た形になっている。見方によれば仕分け人一同が主計官の仕事を分担したと言える。
マッチポンプという意識がつい頭にあるものだから、説明者と仕分け人のやりとりも聞き流すという感じであったが、噛み合わないやり取りが多すぎたように思った。お互いに話し方が下手なのである。その一つとして「次世代スーパーコンピューティング技術の推進((独)理化学研究所)」を取り上げると、多分説明者の一人だと思うが、仕分け人に何を聞かれても「世界一」、「世界最先端」、「最高性能」を繰り返すだけのように私は感じてしまった。世界一速いスーパーコンピューターがとにかく欲しいと強調すればするほど、子どもが玩具が欲しいと駄々をこねているのと同じように聞こえてくるのである。そして国民に夢を与えるなんて宣う。この説明者は研究者を自称していたようであるが、こういう説明者しかこの場に連れてこられない文科省・理研は相当の世間音痴だなと思った。これまでもおそらく中身が空疎な言葉を並べるたてるだけで大型予算を獲得してきたものだから、そのノリでこの仕分けに臨んだのであろう、とはげすの勘ぐりである。
下手すると予算を取り上げられてしまうかも知れないという事態の認識が説明する側にあったのか無かったのか、もう少し説得力のある説明を練ってくるべきであったのに、説明者は防戦一方であったように感じた。しかも世界一を目指して当初はNEC、日立、富士通とわが国のコンピューター製造大手三社が共同開発することになっていたのに、経営状況の悪化を理由にNECと日立がこの5月に脱落してしまったというのである。その結果、当初のベクトル・スカラー複合型からスカラー単独システムへの基本システムの変換を余儀なくされたので、脱落したNECには損害賠償の請求を準備中という。このような大きな状況の変化、なかんずく基本的枠組みが大きく変更されたのであれば、いったん立ち止まって計画全体を見直すべきではないかと素人(国民)はつい考えてしまう。しかしこれまで設計段階ですでに546億円を投入しており、完成までには更に700億円近くかかるが、いよいよ製造段階の契約に入るのでさしずめ来年度には268億円が必要だと強調するのみである。もう動き出したから止まれないだけでは八ッ場ダムに道路建設と同じである。
なぜ世界最高速のスーパーコンピューターが必要なのかについて、説明者の一人がスーパーコンピューターの能力を最大限引き出すソフトを開発するとして、ライフサイエンスでナノレベルのシミュレーションを挙げていたが、私には違和感があった。普通ならある実験をするためにこのような装置が必要であるからと装置開発を申請するのに、最高速コンピューターが出来たからその能力を最大限発揮するソフトを開発するというのだから、これは本末転倒ではないのかと思った。なにはともあれ世界最高速ありきなのである。
文科省が説明に科学者を連れてきて、これが科学にとって重要なのでこの事業をやりますと説明するのがお決まりの手法である、と仕分け人の一人が説明の矛盾を突いていた。それは大いに結構、このような意見がひいては科学技術研究への予算の出し方の基本理念に今後の民主党の科学技術政策立案の過程でまとまっていって欲しいものである。ところがその先行きが不透明な現状では、行政刷新会議が事業仕分け場に連れてきた科学者が説明者に意見を述べること自体、意識するしないにかかわらず財務省主計官の代弁者というか手先のように見えてきたのが奇妙であった。これでは文科相の連れてきた科学者と行政刷新会議の連れてきた科学者による両省庁の代理戦争ではないか。
科学者仕分け人が主計官の手先と言われたくないのであれば、この仕分け会議において予算の削減に手を貸すのではなく、立ち止まり考えるための時間を与えるべくまずは凍結の意思表示をすべきなのではなかろうか。結果的には、来年度の予算計上の見送りに限りなく近い縮減となった。
科学研究費補助金制度についても同じ思いをしたが、機会があれば述べようと思う。