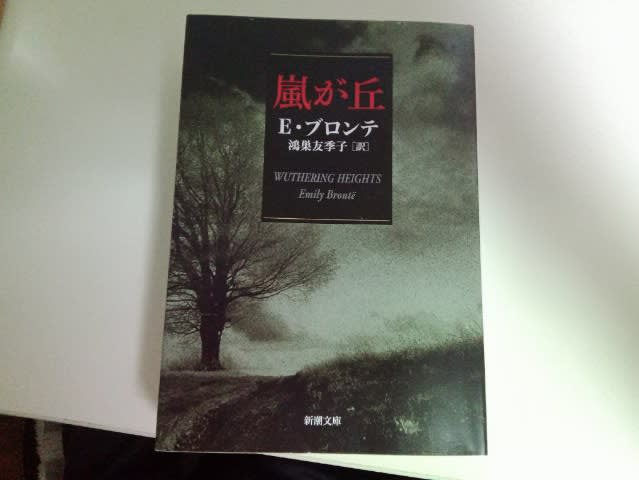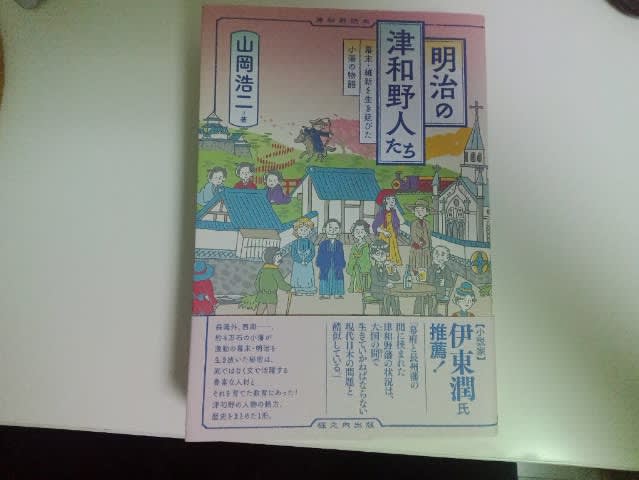全8篇からなるモームの短編集。多分全部初めて読む作品。
結構どれも良かったが、私が好きなのは最初の2作「アンティーブの三人の太った女」と「征服されざる者」。
前者は仲良しの三人女性が一緒にダイエットやブリッジをしながら生活しているところに一人のスレンダーな女性がやってきて一騒動。三人が食事制限をしているところを尻目に痩せた女性はお構いなしに美味しいものを食べる。そんな姿を目の当たりにすると三人のストレスはマックスでお互いの不満をぶつけ合う。
最後はスレンダー女性が去って再び仲良しになるが、短い作品の中で女性の醜い部分がありありと出てとても面白い。実にモームだなと思える作品であった。軽妙さの中にも鋭さがある。
後者の作品は一転してフォークナーばりのヘビーさがある。
戦争中にドイツ兵がフランス人女性を襲い子どもを身ごもることになる。最初は軽い気持ちだったドイツ兵も次第にフランス人女性への愛を表現するようになる。資産的な誠意も見せることで女性の家族は結婚を受け入れるように言うが、女性の方は頑なに拒み続ける。
最後は生まれた子ども殺すところでお終い。後味は悪いが、こういう話は好きだ。
重い話ではあるが、笑ってしまったところもある。捕虜になって収容所に入っていた女性のフィアンセが、食事が少ないことを契機に暴動が発生して、その結果殺されることとなった。そのことを知ったドイツ兵が「収容所をなんだと思っているんだ。リッツホテルか?」と言う。こういうツッコミも好きだ。