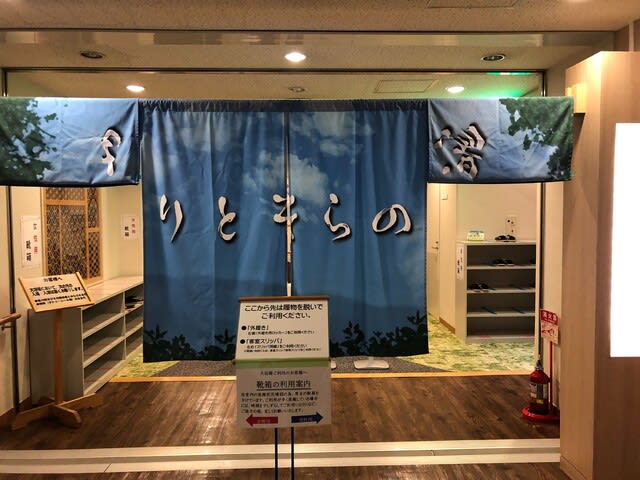10月29日(土)、30日(日)は、温泉観光士の養成講座。会場は吉祥寺の杏林大学、自宅から2時間もかかった。初日のプログラムは、温泉地学、温泉化学、温泉生物学、温泉工学、そして温泉歴史学・文化論であった。


講師は大学の先生が多い。これ以上は望めないような豪華な顔ぶれだ。各科目、一言コメントをする。温泉地学:水源、熱源、水の流路の学問だ。温泉は日本海側に多く、太平洋側に少ない理由がわかった。
温泉化学:当初予定の先生がコロナになり、ピンチヒッターの講師、話の内容が資料と全然一致していない。話は面白いんだが、資料が手元になく、覚えられない。
温泉生物学:微生物やジリオネラ菌、この方も資料にないパワポが多く、話を聴いても記憶に残らない。
温泉工学:温泉調査や採掘、設備、浴槽の管理、安全管理など。資料に則って、話していただき、よく理解できた。会場からの質問も多数受けてくれた。
温泉歴史学・文化論:古事記、日本書紀の時代から、江戸時代、そして明治大正の温泉の特性について、話は面白い。

何名かの講師は、最初の頁に話を膨らませ、時間を取る。そして半分以上過ぎたあたりで、時間がないのに気が付いて、駆け足になる。最後の5分で1頁分を粗く話す。
実は私も研修講師、この経験がある。資料に書いてある事柄を話すと、頭が連鎖反応で、次々に話が出て来る。そして、ああ、話し過ぎた、と反省する。
今日はこのくらい、明日もあり、最後は試験もあるという。資格試験らしい。大学祭もやっていたが、寒いのでパス。明日に続く・・