ぼくは本屋のおやじさん / 早川義夫 ちくま文庫
絵を描く日常 OF MY LIFE ART / 玉村豊男 東京書籍
カラスの教科書 / 松原始 雷鳥社
あるようなないような / 川上弘美 中央公論新社
返品のない月曜日 ボクの取次日記 / 井狩春夫 ちくま文庫
旅をする木 / 星野道夫 文春文庫
花咲か / 岩崎京子 石風社
黒いハンカチ / 小沼丹 創元推理文庫
桜の首飾り / 千早茜 実業之日本社
夜の木の下で / 湯本香樹美 新潮社
番外「アルケミスト『錬金術師ニコラ・フラメル』他」シリーズ6巻 マイケル・スコット 橋下恵 訳 理論社
「えどさがし」畠中恵 新潮文庫
 「今年の10冊」、2004年から初めて11回目になりました。
「今年の10冊」、2004年から初めて11回目になりました。
今年は2014年12月27日迄に読み終えた148冊の本の集計記録の「凄く面白かった本(☆印)」と「面白かった本(○印)」の中から選んで読んだ順に並べてみました。(再読物は一応除外)
☆印10個 ○印21個 ×印は0個 ・・・☆印がちょうど10冊。なので番外に○印から2つ選びました。
並んだ10冊を見てみると、今まで読んだことのない作家さんのが多いことが判ります。
早川義夫さんは元「ジャックス」の一員でありソロでも活動しているミュージシャンですが、ある時期音楽をすっぱりやめて本屋さんをやっていました。
その頃の書店日記、これがなんとも言えず面白かった。
息子に借りて読んだ本だったけど、手元において読み返したくて買いました。
そういえば単行本は殆ど図書館で借りて読んでいるけど、特に気に入った本は書店で買い直しています。
玉村豊男さんてグルメなエッセイストとしてしか知らなかったけど、素敵な植物画を描く画家でもあることを初めて知りました。
小沼丹さんの「黒いハンカチ」はなんと昭和32年に「新婦人」という雑誌に連載されていた推理小説。
それが実にエンターテインメントでその時代の雰囲気もしっかりと描かれているのに語り口も含めて全然古くない、しかも主人公の女性のキャラクター作りが秀逸!
驚きとともにぱっと☆印をつけてました。
岩崎京子、千早茜のおふたりも初、良い作家さんに出会えました。
今年つくづく感じたのは、私はここ数年川上弘美さんのエッセイや小説が本当に好きなんだなぁということ。
何気なく読んでいてもどれもつい○印をつけてしまう。
特にエッセイは”こんな風に気持ちを表現出来たらなんて素敵なんだろう”と思いながら読んでいる・・なんだかとっても羨ましくて憧れる。
久しぶりに読んだ湯本香樹美さんの新作「夜の木の下で」(2014/11/27発売)。
5つの短編が入った作品集、その中の1つ「焼却炉」である物語仲間を発見。
舞台はとある女子校、どこか閉鎖的な学校という入れ物の中で揺れる「クラスメイト」というそれぞれの位置づけ。
その中で唐突に(と感じられるのだけど)カナちゃんが呟いた、主人公のユリには「符丁かなにかのような、人の名と思われるもの」と思えたある本の題名。
え、もしかして?と思い、その先のページに「焼却炉でカナちゃんがつぶやいたのは架空の国の名で、全部で7冊のシリーズだった。」に、やっぱり!と頷き。
話しの終りにユリが引いた一節「わたしはけものだ。そしてとりわけアナグマなのだ・・・」に、あぁこの作者さんは一体いつこの物語に出逢ったのだろう、知りたい..と思いました。
物を作り出す人たちの中で、子どもの頃に読んだその話しが残り続けていることが多いことに時々びっくりする。
映画監督だったり、イラストレーターだったり作家さんであったり、様々なアーティスト・・
話し自体は多分大人になってから初めて読む人にはそれほど面白い物ではないかもしれない、「指輪物語」や「ゲド戦記」の緻密なストーリーとは違い、本当にごく普通の子どもたちが主人公の児童文学だから。
私は小学1年生のクリスマスに第1巻を貰って、それから毎年1冊ずつクリスマスか誕生日の時に貰ったように覚えています。
でも6年生の時には全巻揃ってたから、2冊買って貰った年があるのかな。
挿絵のペン画がとても好きで、絵を描きたいって思ったのはおそらくそこからだし、ペン画の作品が好きなのも幼少期の児童文学作品の影響が強い。
その他にも懐かしく不思議な出会いを本を読むたびに感じています。
だから本が好き。
そして今回1番大事にしたいのは星野道夫さんの「旅をする木」
若くして亡くなられたことが哀しいけれど、残された言葉の数々が心に滲みます。
皆さんの『思い出に残る本』ありますか?
《過去記録はこちら》
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
絵を描く日常 OF MY LIFE ART / 玉村豊男 東京書籍
カラスの教科書 / 松原始 雷鳥社
あるようなないような / 川上弘美 中央公論新社
返品のない月曜日 ボクの取次日記 / 井狩春夫 ちくま文庫
旅をする木 / 星野道夫 文春文庫
花咲か / 岩崎京子 石風社
黒いハンカチ / 小沼丹 創元推理文庫
桜の首飾り / 千早茜 実業之日本社
夜の木の下で / 湯本香樹美 新潮社
番外「アルケミスト『錬金術師ニコラ・フラメル』他」シリーズ6巻 マイケル・スコット 橋下恵 訳 理論社
「えどさがし」畠中恵 新潮文庫
 「今年の10冊」、2004年から初めて11回目になりました。
「今年の10冊」、2004年から初めて11回目になりました。今年は2014年12月27日迄に読み終えた148冊の本の集計記録の「凄く面白かった本(☆印)」と「面白かった本(○印)」の中から選んで読んだ順に並べてみました。(再読物は一応除外)
☆印10個 ○印21個 ×印は0個 ・・・☆印がちょうど10冊。なので番外に○印から2つ選びました。
並んだ10冊を見てみると、今まで読んだことのない作家さんのが多いことが判ります。
早川義夫さんは元「ジャックス」の一員でありソロでも活動しているミュージシャンですが、ある時期音楽をすっぱりやめて本屋さんをやっていました。
その頃の書店日記、これがなんとも言えず面白かった。
息子に借りて読んだ本だったけど、手元において読み返したくて買いました。
そういえば単行本は殆ど図書館で借りて読んでいるけど、特に気に入った本は書店で買い直しています。
玉村豊男さんてグルメなエッセイストとしてしか知らなかったけど、素敵な植物画を描く画家でもあることを初めて知りました。
小沼丹さんの「黒いハンカチ」はなんと昭和32年に「新婦人」という雑誌に連載されていた推理小説。
それが実にエンターテインメントでその時代の雰囲気もしっかりと描かれているのに語り口も含めて全然古くない、しかも主人公の女性のキャラクター作りが秀逸!
驚きとともにぱっと☆印をつけてました。
岩崎京子、千早茜のおふたりも初、良い作家さんに出会えました。
今年つくづく感じたのは、私はここ数年川上弘美さんのエッセイや小説が本当に好きなんだなぁということ。
何気なく読んでいてもどれもつい○印をつけてしまう。
特にエッセイは”こんな風に気持ちを表現出来たらなんて素敵なんだろう”と思いながら読んでいる・・なんだかとっても羨ましくて憧れる。
久しぶりに読んだ湯本香樹美さんの新作「夜の木の下で」(2014/11/27発売)。
5つの短編が入った作品集、その中の1つ「焼却炉」である物語仲間を発見。
舞台はとある女子校、どこか閉鎖的な学校という入れ物の中で揺れる「クラスメイト」というそれぞれの位置づけ。
その中で唐突に(と感じられるのだけど)カナちゃんが呟いた、主人公のユリには「符丁かなにかのような、人の名と思われるもの」と思えたある本の題名。
え、もしかして?と思い、その先のページに「焼却炉でカナちゃんがつぶやいたのは架空の国の名で、全部で7冊のシリーズだった。」に、やっぱり!と頷き。
話しの終りにユリが引いた一節「わたしはけものだ。そしてとりわけアナグマなのだ・・・」に、あぁこの作者さんは一体いつこの物語に出逢ったのだろう、知りたい..と思いました。
物を作り出す人たちの中で、子どもの頃に読んだその話しが残り続けていることが多いことに時々びっくりする。
映画監督だったり、イラストレーターだったり作家さんであったり、様々なアーティスト・・
話し自体は多分大人になってから初めて読む人にはそれほど面白い物ではないかもしれない、「指輪物語」や「ゲド戦記」の緻密なストーリーとは違い、本当にごく普通の子どもたちが主人公の児童文学だから。
私は小学1年生のクリスマスに第1巻を貰って、それから毎年1冊ずつクリスマスか誕生日の時に貰ったように覚えています。
でも6年生の時には全巻揃ってたから、2冊買って貰った年があるのかな。
挿絵のペン画がとても好きで、絵を描きたいって思ったのはおそらくそこからだし、ペン画の作品が好きなのも幼少期の児童文学作品の影響が強い。
その他にも懐かしく不思議な出会いを本を読むたびに感じています。
だから本が好き。
そして今回1番大事にしたいのは星野道夫さんの「旅をする木」
若くして亡くなられたことが哀しいけれど、残された言葉の数々が心に滲みます。
皆さんの『思い出に残る本』ありますか?
《過去記録はこちら》
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年












 おはなしぐるんぱクリスマスおはなし会
おはなしぐるんぱクリスマスおはなし会 《プログラム》
《プログラム》


 にワクワクしてもらえたかな・・?
にワクワクしてもらえたかな・・? 小さなお土産を渡してバイバイ。
小さなお土産を渡してバイバイ。
 また来年♪
また来年♪






 今年は証拠写真が撮れた!
今年は証拠写真が撮れた!
 車が轢いてくれるまで何度もトライしてたハシボソガラス。
車が轢いてくれるまで何度もトライしてたハシボソガラス。









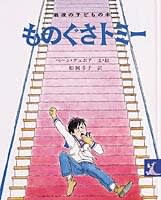
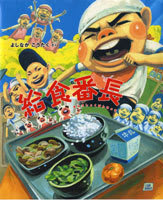
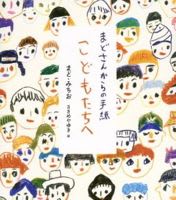
 はらっぱ便り
はらっぱ便り







 さて恒例の問いかけです「あなたの(心に残った)今年の1冊、または作家さんは?」
さて恒例の問いかけです「あなたの(心に残った)今年の1冊、または作家さんは?」







 これだ!(笑)
これだ!(笑)










 はらっぱ便り
はらっぱ便り





