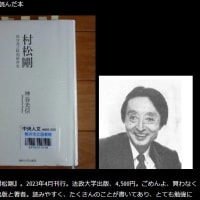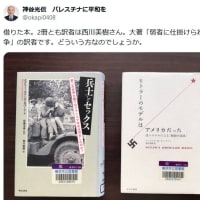横浜・港の見える丘公園からの見晴らし。
このあたりフランス山といって、1863年から1875年まで、フランス軍が駐屯した。 すこしはなれたところにはイギリス軍が駐屯した。
1863年の4月に幕府は朝廷に対し「攘夷は5月10日までにやる」と約束。そして5月9日には英国に生麦事件の賠償金を払っている。その際、幕府は英仏に横浜への駐兵を認めた。攘夷どころか、外国軍の国内駐屯を認めたのである。
これも、生麦事件を受けての徳川幕府の英仏への現実策としての妥協。
■マルクス主義系の歴史学者石井寛治は、この英仏駐兵について;
小栗忠順は、文久3年(1863)4月に、幕兵を率いて上京、京都を軍事的に制圧したうえで、朝廷に和親開国の勅旨をださせ、上洛したまま損尊攘派の人質になった感のある将軍家茂をつれもどすクーデターを計画したが、反対され歩兵奉行を罷免されている。同計画の背後には、英仏両国公使による援助の申し出があった。
同様な計画は、同年5-6月に、老中小笠原長道の卒兵上洛として具体化され、英仏両国公使の協力を得てイギリスからチャーターした汽船2隻と幕船をあわせて4隻の船に1600名の大軍がのり、大阪へ向かった。この軍勢は将軍の命で上洛を阻まれ、クーデターは失敗する。しかし、英仏両国公使への見返りとして幕府が両国にあたえた横浜居留地のための駐兵権はそのままのこり、英仏両国軍隊はこののち横浜山手に常時駐屯することとなった。
尊攘派を一掃して幕府中心の体制を再建することが、これら失敗したクーデターのねらいであったが、そのために必要とあらば国家主権を一部失ってでも外国の助けを借りるというのが彼らの姿勢であった。因循開国派の幕府の姿勢の中には、その意味できわめて危険なものがひそんでいたのである。 石井寛治 日本の歴史⑫ 開国と維新
■近代日本の外交史の印象としての「現実策を取る玄人と理想主義に燃える素人の相克」の視点で考えた場合、戦後日本で理想主義に燃える素人の役割は左翼によって担われてきた。その典型例が上記である。なぜなら、政権党の自由民主党/LDP(本名、放埓衆愚(democrazy)党)は占領憲法を墨守し、占領国との保護国条約である安保条約を結び、まさに国家主権の源泉である交戦権を放棄して、快楽主義の実現に邁進してきたからである。でもそれは、「現実策を取る玄人」政治としてみなされ、今日に至っている。一方、左翼がサヨであるのは、交戦権の回復を声高に主張しないからにほかならない。


▼そして、1863年、運命の5月10日、幕府はどうせなにもしないだろうと踏んでか、長州は下関で外国船に砲撃。その年の7月、鹿児島湾で薩摩と英海軍が交戦。
1941年にさかのぼること78年前に、第一次 米英撃滅 大作戦となる。